【著者インタビュー】木皿 泉『さざなみのよる』
木皿泉は『野ブタ。をプロデュース』など、数々の人気作品の脚本を手掛ける、和泉務氏と妻鹿年季子氏による夫婦ユニット。今回は小説『さざなみのよる』について、おふたりに対談形式で語っていただきました!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
「死」は日常の中にあるからこの世は明るく切なく楽しいのだ――人気脚本家夫妻による感動の物語
『さざなみのよる』
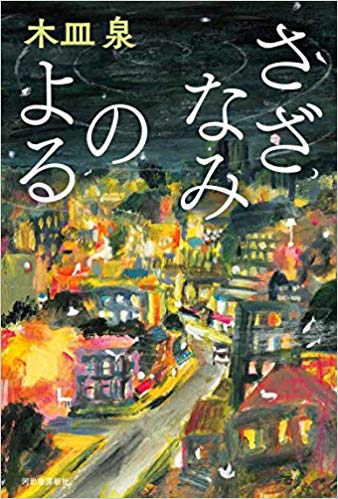
河出書房新社 1400円+税
装丁/野中深月
装画/荒井良二
木皿 泉

●きざら・いずみ NHK漫才コンクール入賞後、構成作家となった1952年神戸市生まれの和泉務と、商社勤務を経て脚本デビューした57年西宮市生まれの妻鹿年季子が90年に『やっぱり猫が好き』で合作開始。『すいか』(向田邦子賞、ギャラクシー賞)『野ブタ。をプロデュース』『セクシーボイスアンドロボ』『Q10』等で支持を獲得。04年和泉が脳出血で倒れ、07年結婚。初小説『昨夜のカレー、明日のパン』(14年本屋大賞2位)や戯曲でも活躍。神戸市在住。共にO型。
「あること」と「ないこと」がパラレルに同居する世界に、私たちは生きている
一昨年と昨年のお正月。和泉務氏と妻鹿年季子氏による人気脚本家ユニット、木皿泉作 『富士ファミリー』(NHK)が放送された。
富士山麓のコンビニとは名ばかりの雑貨屋を舞台に、同家の三姉妹(薬師丸ひろ子、小泉今日子、ミムラ)や片桐はいり演じる〈笑子ばあさん〉らの日常を描くドラマだ。帯に〈小国ナスミ、享年43〉とある本書『さざなみのよる』は、ドラマ作品では冒頭で既に亡くなり、幽霊となっている次女ナスミの死から始まる。
妻鹿「小説の方は家族から一人の時間に戻る、夜のイメージがあったんです」
和泉「よるは寄るとも読めるしな。寄せては返す波のように、昼と夜、生と死が、全部連環していくんです」
東京で結婚後、癌に冒され、笑子が作るおはぎが名物の実家に夫と戻ったナスミは、その間、様々な印象や言葉を周囲に残していた。そうした一見脈絡のない欠片の集積が彼女の実体を刻み、ナスミというヒト型をした空白や不在という名の存在が、ここには確実に「ある」。
*
妻鹿「あれ、なぜドラマではナスミを幽霊にしたんだっけ?」
和泉「ぼくらが考えるナスミ役の小泉さんは、遠くで見守ってるくらいの出方が一番好きなんやと思う。笑子ばあさんだけに見えるナスミの幽霊は、ここにはいないけど、どこかにはおるんや」
妻鹿「今回の小説は、独立した作品として読めますし、ナスミの死にこんな背景があったなんて、書くまで私たちも全然知らなかったんですよ(笑い)。片桐はいりさんは、ドラマの方を、おせちみたいだと言っていた。その各90分の重箱に詰め切れなかったタッパの中の御馳走を、物語の行間を一つ一つ埋めるようにして書いたのが、この小説でした」
互いをトムちゃん、ときちゃんと呼び合う木皿夫妻。実際の作業の流れは、まず設定等々を二人で決め、妻ときちゃんが一通り脚本化。それを膨大な読書量を誇る元漫才作家のトムちゃんがブラッシュアップし、どちらがどこを書いたかわからない作品ができ上がる寸法だ。
第1話では死の床にいるナスミ本人、第2話以降はナスミの姉〈鷹子〉や妹〈月美〉、ナスミの夫〈日出男〉らが話者を順に務める。日出男と後にできちゃった結婚する〈愛子〉とナスミとの意外な関係や、東京時代の元同僚〈加藤由香里〉が託されたある伝言など、故人の知られざる横顔が語られてゆく。
改めて気づかされるのは、口もガラも悪いナスミが、ここぞという時に頼りになる人物だったこと。愛子にしろ由香里にしろ、彼女の一言に背中を押されるのだが、その言葉自体、ナスミが誰かから手渡されたものだった。
妻鹿「つまりそこも連環で、ナスミ一人の手柄じゃないんですよね。日本人は死者を妙に美化するけど、むしろその方が人をバカにしているし、ダメなところはダメなまま、悼めばいいと思うんです。
いいところも悪いところも、まるごと受けとめることで、亡くなった人が本当に生きていたんだという実感が持てるんじゃないかなと思う。限られた命を生きたっていう。そういう生きている実感を持ちにくい今の時代、万人受けする価値観なんてないから、『生きてよし』ということだけでも伝わるよう、いろんな価値観のフックを地道にバラ撒いていくしかないかなと思う」
和泉「忍者の撒き菱やな」
妻鹿「それを誰かが不意に踏んでくれて、『イテテ』と気付くみたいなね(笑い)」
働くことは相手がいてこそ光を放つ
夫妻自身、夫の脳出血や妻の鬱病など、幾多の困難を乗り越えてきただけに、日常を肯定し、笑いに変える態度には説得力がある。
妻鹿「病気の時より若い頃の方が大変だった。長く生きるだけ損だって、本気で思っていたんですよ。トムちゃんは違うけどね」
和泉「そんなん、考えてもムダやから、考えへん」
妻鹿「それでもぐちぐち言いながらもみんな生きてゆくわけで、日常って一体何だと、いつも考えていた。やっぱり一番の転機はトムちゃんと会ったことかな。以前は誰かのためにご飯を作るなんて苦痛にしか思えなかったけど、そうかプロセスなんだと。相手がいて、働くことこそが光を放つと、気づけたんです」
例えば第7話。妹の死後、看護師づてに一通の手紙を鷹子は受け取り、それを託した〈佐山〉なる男に37年前、ナスミが誘拐されかけた事実を知る。
病院で偶然再会した彼に、ナスミは〈なんで私を殺さなかったんですか〉と声をかける。かつて借金苦から犯行に加担した彼は、ナスミが口にしたある童謡が自分を思い留まらせてくれたと手紙の中で告白する。〈お茶をのみにきてください/はい、こんにちは/いろいろお世話になりました/はい、さようなら〉
そのナスミが死んだことをまだ知らない彼の手紙はさらにこう続く。〈あなたには、これから何人も何人も会う人がいて、あなたと別れを告げる人が、それと同じ数だけいる〉〈私はちゃんと「さようなら」を言い、次の人につなぐのが、人生というゲームの絶対に守らねばならないルールではないかと、そう思ったのです〉
妻鹿「それも生きる理由の一つかもしれません。これが最後と思って人と別れたり、映画を一度きりのつもりで見たり、人生はサヨナラの塊な気がします」
和泉「哲学も元は死を受け入れる練習らしいしな」
妻鹿「そう思ってはいても日常は続くし、別れがあっても忙しくて悲しみは棚上げにされがち。そうやって、あったことはどんどん忘れ去られてゆく。でも、あったんですよね。人は死に、形あるものは壊れますが、それがあった事実はあり続ける」
和泉「つまり生存はなくなっても、存在はあるんです」
妻鹿「そう。人は死んでも死にきりじゃない。叶わなかった願いや届かなかった思いも全部そこにあって、常に『あること』と『ないこと』がパラレルに同居する世界に、私たちは生きている」
ドラマと本書の関係性もそう。ナスミの死で始まる物語は、その前後に連綿と続く時間の一部でしかなく、登場人物の数だけ縦横に広がる木皿ワールドに、私たちはとりあえずは明日を生きるための、ちょっぴり甘くて苦い栄養をもらうのだ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2018年6.8号より)
初出:P+D MAGAZINE(2018/09/03)

