【著者インタビュー】酒井順子『家族終了』/この国の家族は、どう変わっていくのか
『負け犬の遠吠え』など、いまを生きる人々の生の声を的確にすくい取ってきた酒井順子氏が、日本の「家族終了」について考察した話題作!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
事実婚や同性婚、「おひとりさま」比率も上昇中! 「普通」なんてどこにもない連帯のあり方を考察する全18章
『家族終了』
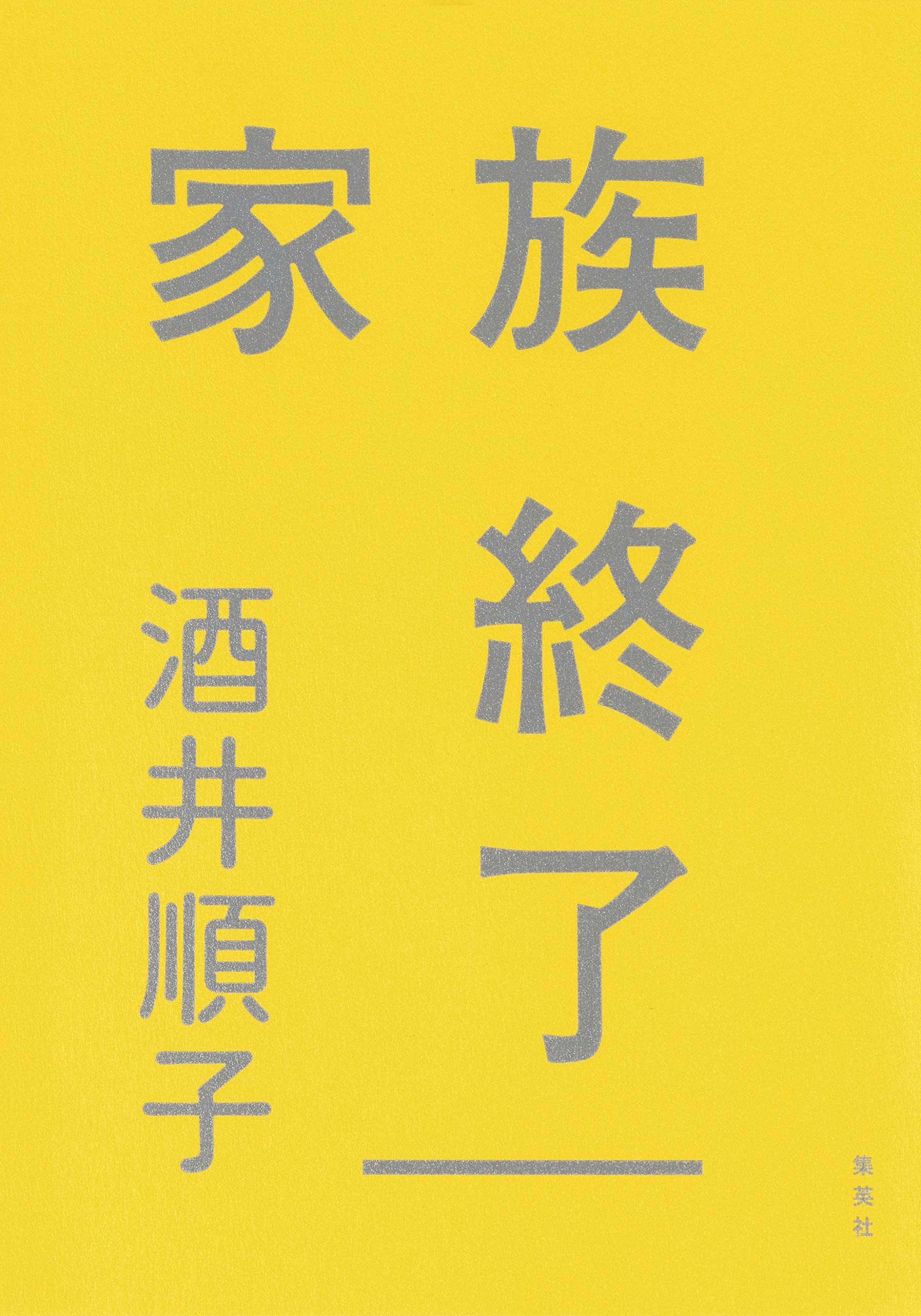
1400円+税
集英社
装丁/寄藤文平+鈴木千佳子
酒井順子

●さかい・じゅんこ 1966年東京生まれ。高校在学中からコラムニストとして雑誌『Olive』等で活躍し、大学卒業後、広告会社勤務を経て独立。03年発表のベストセラー『負け犬の遠吠え』で婦人公論文芸賞、講談社エッセイ賞をW受賞し、「負け犬」は04年の流行語に。著書は他に『女子と鉄道』『ユーミンの罪』『地震と独身』『裏が、幸せ。』『子の無い人生』『男尊女子』『百年の女「婦人公論」が見た大正、昭和、平成』『駄目な世代』等。158㌢、O型。
いろんな家族形態を自由に選択しながら助け合っていける世の中になればいい
30代で父を、40代で母を亡くし、2年前、3歳上の兄までがこの世を去った。
そもそも家族には親兄弟等の〈生育家族〉と、結婚や出産による〈創設家族〉があると言い、現在同居中のパートナーとも事実婚を選択した酒井順子氏(52)は、この生育家族の死をもって、『家族終了』を宣言する。
〈ではそれが悲しかったり寂しかったり無念だったりするかといえば、「別にそうでもない」のでした。そうなってしまったものは、もう仕方がない。名家であるわけでもなければ、特殊な技能や看板を受け継ぐ家でもないのであるからして、消えていってもどうということは無いなぁ、と〉
そして彼女は、〈日本では、このような感覚を持つ人が少なからぬ数で存在しています〉と続け、家族を作り、〈イエ〉を維持する営みがどう変わりつつあるのか、この国の家族終了について、さらに観察と考察を進める。
*
私事だが、筆者は人前で泣ける人より泣けない人、むしろつらい時こそ
「終了という言葉が強すぎたのか、皆さん、心配して下さるんですけど、本人は意外と大丈夫なんですよ。今思えば『このままいくと終了しそうだ』と気づいた時の方が悶々としていて、独身だったり子供がいなかったりする人の多くがその予感を共有していると思う。
ただ、どんなに理想的な家族も永遠ではありえないし、自分の終わった家族と世の中の家族全般の流れをリンクさせながら、今回は“普通の家族”とは何かについて考えてみました」
未婚、子なしの30代女子の現実を綴った『負け犬の遠吠え』や『ユーミンの罪』など、自由を謳歌する一方、かえって生き難くもなった同時代人の生の声を的確にすくい取ってきた酒井氏。昨年は『婦人公論』のバックナンバー約1400冊を読み解き、明治から昭和の女性の意識の変遷を追った『百年の女』を上梓。その延長上に本書もあるという。
「昭和41年生まれの私は、昭和ヒト桁世代の父と戦後教育を受けた母、明治生まれの祖母と兄の5人家族で育ち、家族観は世代ごとに違って当たり前でした。
特に母は他に好きな人ができて家を出たこともあるくらい奔放な人で、なのに帰ってきた理由が、〈おばあちゃんが可哀想になった〉なんですよ。子供のためではなくて。死ぬまで女だったあの母にすら〈姑は看取らねば〉という感覚が残っていることに私は仰天したものですが、どんな家族も時代の影響を受けてはいます。特に私は子供がいないせいか、今時の親子関係に驚かされることが多くて」
例えば昨年1月、草津白根山噴火のニュースに釘付けだった山好きな酒井氏は、ゴンドラの中で救助を待つ男性客の一言に思わず耳を疑う。〈電話の相手は、自分の父親であり、今どのような状況かを切羽詰まった様子で話した後、彼は、「パパ、愛してるよ!」と言ったのです〉(「パパ、愛してる」)。
だがそんな時、違和感を違和感のままにしないのが、時代の観察者・酒井順子だ。さっそく周囲のママたちに意見を聞くと、昨今は大学の部活ですら親がかりで、引退式で〈僕が感謝をしたい人は……、お母さんです〉と言って〈熱いハグ〉を交わす親子も珍しくないとか。そして、〈友達化〉した父と息子や〈ママっ子男子〉の存在に一々驚く方がおかしいのだと、腹を立てる前に自らを省みるのである。
「その驚きやムカツキで、口に糊しているわけですね(笑い)。当の母親たちも公の場であり得ないと言う人がいる一方、〈ハグくらい、当然〉と言う人もいて、ママっ子もパパっ子も今や当たり前。私が学生の頃は親が試合の応援に来ること自体ありえなかったけれど、それも時代の変化であり、自分にも子供がいたら同じことをしていたのでしょう(笑い)」
家族内の上下関係は消えつつある、今。むしろ〈これが本来の人の道なのかも〉と酒井氏は書く。
〈私は、親に対して何ら、これといった愛情表現をしてきませんでした〉〈母親はほとんど突然死くらいの状態だったのですが〉〈耳元で勇気をふりしぼって小声で囁いたのは、「ありがとね」の一言〉〈嗚呼、親に「愛してるよ!」と叫ぶことができる人、親をハグすることができる人に幸いあれ〉と。
他人同士だから優しくなれる
「うちは今風の仲良し家族では全くなかったし、もし生まれ変わったら京塚昌子さんみたいな肉じゃが系の母親のいる家に生まれたいと思います(笑い)。
でも父や母のことを嫌いではなかったし、我が家だけが特殊かといったら、どんな家庭も特殊と言えば特殊なんですよね。にもかかわらず人は普通の家族を求め、手に入らない場合は飲み屋のママや、甥や姪といった代替家族に愛情が向かう。たぶんそれは
特に非婚化や少子高齢化が進む今、家族は〈贅沢品〉になりつつあり、歌舞伎界や皇室が注目を集めるのも、その継承の物語が既に虚構に近いからではないかと。
「何々屋に誰が嫁いだとか、眞子様のお相手がどうといった話は、皆の大好物。ただし自分が“家”の中に取り込まれるのは嫌で他人事だから楽しめるんです。
昔の家制度は誰かの我慢の上に成立したわけで、もうそんな我慢ができる人は少なくなっています。国は家族による介護や看取りを美徳のように推奨しますが、他人同士だから優しくなれる側面もあると思うし、老後を過ごす相手も血縁や婚姻関係に限る必要はないと思う。
私もこの本を書いていて気づかされたのですが、性愛抜きのカップルとか、〈セックスが介在しない家族〉がいてもいいんですよね。現に女友達と幸せそうに暮らしている友人がいるし、性別も人数も、いろんな家族形態を自由に選択しながら助け合っていける世の中になればいいなあと。男女の法律婚のみが正しい型、という考えのままでは、一人で生きる人は増える一方。子供がいるから安心というわけでもない。家族もトランスフォームしていくのではないでしょうか」
そう言って制度や法整備の必要にも言及する酒井氏。どんな形であれ、家族にはやっぱりいてほしいからだ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2019年6.7号より)
初出:P+D MAGAZINE(2019/12/13)

