【花火、扇風機、プール教室…】「子どものころの夏休み」を思い出す小説4選

大人になると、扇風機の回る部屋で昼寝をしたり、虫採りに行ったり、プール教室に通ったり……、といった子どもの頃の夏休みの思い出が、いっそう懐かしく感じられるもの。そんな「子ども時代の夏」を描いた名作小説を4作品ご紹介します。
夏がくると、小学生の頃の夏休みを懐かしく思い返す方も多いのではないでしょうか。友人たちと海へ泳ぎに行ったり、扇風機の回る部屋で昼寝をしたりといったノスタルジックな記憶は、うんざりするほどの猛暑日にも汗水を垂らして働かなければいけない私たち大人の心を、いつでも少しだけ癒やしてくれるものです。
今回は、そんな「子どもの頃の夏」をテーマにした名作小説を、現代小説を中心に4作品ご紹介します。
『海辺の町』(江國香織)
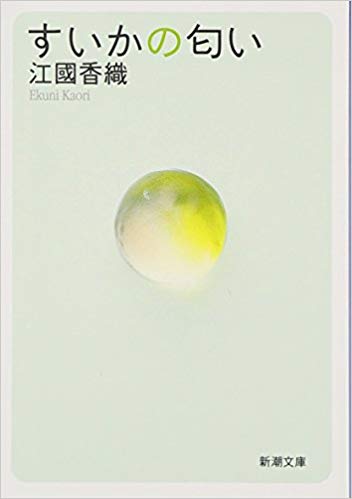
『海辺の町』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101339163/
『すいかの匂い』は、江國香織による短編小説集です。11人の少女を主人公とする11話の作品はそれぞれ、忘れられないひと夏の記憶についての回想という形をとっています。
そのうちの1篇である『海辺の町』は、11歳の「私」が短いあいだ暮らした、とある海辺の町での夏の出来事を綴った物語です。「私」は離婚したばかりの母とともに海辺の町のアパートの2階に間借りをしており、窓を開けると潮風が流れてくる部屋で夏休みを過ごしています。
本作の魅力のひとつは、夏を感じさせる、とても些細でありながら美しい風景についての描写です。
ときどき海に行った。坂道を下っていくと、海は錆びた物干し竿の匂いがした。以前住んでいた都心のアパートの、サッシ窓と狭いベランダ。そのベランダ一杯にシーツを干したときの匂い。白いシーツの向う側に立ち、はためく布に顔を寄せて匂いを嗅ぐ。(中略)あのときの匂いだ。母にみつかると叱られた。窒息したらどうするの、と、本気で怒った声に耳を叩かれる。
海に続く坂の途中に、ござや浮き輪を売っている店があった。一度父と散歩に行って、つばの広い、ごわごわと肌ざわりの悪い麦わら帽子を買ってもらった。(中略)帽子にはクリーム色のりぼんがついていて、風が吹くとびらびら揺れる。中に顔をうずめると、埃の匂いがした。
『海辺の町』では、「私」がその町で暮らしたひと夏のあいだに見た風景についての記憶や、近所のおばさんやプール教室の講師といった人物と交わした会話が、最初から最後まで淡々と綴られます。本書の収録作品には奇妙でどこか不気味なストーリーも少なくない中、この作品の静けさ、起伏のなさはむしろ異質なものとして、読者の印象に強く残ります。
なにげない物語ではありますが、江國香織らしいロマンティックかつ緻密な情景描写を存分に味わえるとともに、読後には心地のよいさみしさを感じられるような1作です。
『夏の庭 The Friends』(湯本香樹実)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101315116/
『夏の庭 The Friends』は、湯本香樹実による長編小説です。1992年の発表以来、10数か国で翻訳され出版され続けている本作は、現代児童文学の代表であるとともに、小学生・中学生にとっての夏休みの課題図書の定番としても広く知られています。
本作のストーリーは、小学6年生の「僕」が、河辺という同級生に「近所でひとり暮らしをしているおじいさんが死ぬところを目撃しよう」と奇妙な提案を受けるところから始まります。「僕」と河辺、そして同じく同級生の山下という3人組は、夏がくるとともにおじいさんの生活の見張りを始めます。
おじいさんは庭を片づけている。古新聞のつまった袋や、ゴミや、漬物桶や、片っぽだけになってしまったゲタやらを、せっせと集めては玄関の前に少しずつ積み上げていく。はげ頭に太陽がかんかん照りつけている。
このところ、すごく暑い日が続いていた。(中略)新聞にはぎっしり人で埋まった砂浜の写真や、閉め切ったクルマの中の子どもが暑さのために死んだとか、冷房病の対策とか、そんなことばかりがくりかえし、くりかえし載っていた。まるで同じ日が永遠に続くみたいに。
子どもたちは猛暑の中で必死におじいさんを観察し続けますが、おじいさんは子どもたちの振る舞いの幼さを逆手にとったように彼らをからかい始め、庭での洗濯物干しやゴミ出しを彼らに命じるようになります。やがて、そのような交流を通して、おじいさんと「僕」たちはすっかり親しくなってしまいます。
本書の魅力は、塾での夏期講習や部活の合宿、蝉の鳴く森の散策といったノスタルジックな風景描写はもちろん、ひと夏の些細な冒険を通じて少しずつたくましく、少年から青年への階段を上っていく子どもたちの姿。夏がくるたびに本棚から取り出し、何度でも読み返したくなるような永遠の名作です。
『子供の墓』(阿部昭)

「子供の墓」収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4122067219/
『子供の墓』は、情感豊かな小説の名手として知られる小説家・阿部昭による「少年」をテーマとしたアンソロジー、『天使が見たもの』に収録されている短編小説です。
本作のストーリーは、主人公である父親と3歳になる彼の息子が、ある夏に近所の尼寺へ散歩がてら墓参りに行くというとてもシンプルなもの。しかしながら、父と兄を亡くし漠然とした喪失感を抱えている主人公と、まだ死というものを理解していない無邪気な彼の息子の対比が美しくも切ない情景と共に描き出され、静かに読者の胸を打ちます。
主人公は焼けつくような太陽の下、息子の手を引いて町を歩きながら、自分が生まれる前の世界や、いつか必ず自分たちにも訪れる死について思いを馳せます。まばゆい夏の路上を“死の国の無人の街路”のようだと感じながら、物語の最後、主人公たちは遠くに小学校の見える坂道までたどり着きます。
坂の下は、小学校だった。夏休みで、ここにも人気のない、白い幻のような校舎。壁の時計は針が止まったままだ。鉄柵の扉は固く閉ざされていて、誰も中に入ることはできない。(中略)堀のむこうに、満水のプールが見えるが、子供の目からは届かなかった。父親は、子供を荷台に立たせ、両手で自分の肩につかまらせて、プールを見せてやった。
「見える?」
「見える。」
「プールは何色?」
「白。」
「水は?」
「青。」
特別なことはなにも起きないささやかな物語でありながら、読後にはひりひりとした余韻が残る本作。夏という季節と「死」の親和性について考えさせられるような、幻想的な雰囲気をたたえた短編です。
『花火、七月の夜』(澁澤龍彦)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4309411495/
『花火、七月の夜』は、澁澤龍彦による自らの少年時代の回顧をテーマとした作品集、『私の少年時代』の中に収録されている私小説です。本作では、少年時代に鎌倉の家で遊んだ線香花火にまつわる思い出が、格調高く幻想的な文章とともに綴られます。
マッチで火をつけると、まず火薬をふくんだ花火の先端が、熟したような火の玉になって、ぐらぐら煮立ってでもいるかのように、かすかに震え出すのである。手で一心に支えていると、みずからの重みに堪え切れなくなって、そのまま流星のように地面に落ちてしまい、私たちをがっかりさせることもある。
しかし、熟した火の玉の重みによく堪えた線香花火は、やがて私たちの期待に応えて、庭さきの薄暗がりのなかに、華麗な火花の抽象模様を繰りひろげはじめる。
火花が消えても、夜の闇のなかに、まだ黄色っぽい松葉やしだれ柳の残像が、ぼんやりと残っているような気がする。あたりには煙硝の匂いがただよって、なにか一つの事件が終ったという感じがする。
読んでいるだけで、こちらにまで手持ち花火が終わったあとの煙の匂いが伝わってくるような名文です。本作の中で「夏がいちばん好き」と語っているように、澁澤は、夏という季節に強い思い入れがあったようです。
『私の少年時代』では他にも、夏休みに避暑地で星の観察をしたときの思い出(『星の思い出』)や、虫採りをした日のこと(『私の昆虫記』)などが軽やかな筆致で綴られます。美しい文章の中で存分に子ども時代のノスタルジーに浸りたいという気分のとき、特におすすめの1冊です。
(合わせて読みたい:【澁澤龍彦の生涯】破天荒なシュールレアリスト)
おわりに
社会人になると、暇を持て余すほどに長い休暇というのはなかなか取れないもの。中には、「夏休み」という響きにさえ懐かしさを感じる、という方もいるかもしれません。
今回ご紹介した小説の中で描かれる夏休みは、どれもばらばらな時代・場所でありながら、かつてどこかで体験したような懐かしさで私たちの心を震わせます。“あの頃の夏”にトリップしたくなったときや夏を待ち遠しく感じる気持ちを忘れそうになったとき、ぜひ、この4作のページを開いてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2019/08/09)

