戦争、震災、闘病生活──「非常事態」の中で書かれた日記文学3選

日々状況が変わりゆくコロナ禍を受け、書き手が日記をつけることの意味が見直されつつあります。今回はかつて文豪と呼ばれた作家たちが“非常時”にも淡々と書き続けた、日記文学の傑作を3作品ご紹介します。
刻一刻と状況が移り変わるコロナ禍を受け、いま、プロ・アマチュアを問わず、書き手が“日記をつける”ことの意義が見直されつつあります。これまでに経験したことのないような怒涛の日々を記録すべく、自分のノートやブログ上で日記を書き始めてみたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
かつて同じように、戦時下や震災直後、闘病生活中といった壮絶な環境の中でも、筆を折らずに淡々と日々を記録し続けた文豪たちがいました。今回はそんな“非常事態”とも言える環境下で書かれた文豪たちによる日記文学・随筆の名作を、3作品ご紹介します。
『断腸亭日乗』(永井荷風)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/400310420X/
『断腸亭日乗』は、小説家・永井荷風による日記集です。「断腸亭」とは、腸の持病にちなんで荷風が自身の邸宅につけた名前に由来しています。荷風は大学の教職を辞して「断腸亭」に移り住んだ1917年からこの日記を綴り始め、79歳で亡くなる直前まで、42年間にわたって書くことをやめませんでした。
五月初一。(旧三月十八日)晴れて風甚冷なり。小説執筆。
五月廿五日。晴又陰。今日も亦老鶯の鳴くを聞く。扇骨木の花白し。晡下大石医院に徃く。帰途銀座にて女給愛子に出会ひ真砂屋にて夕飯を食してわかる。燈下小説執筆。深更驟雨あり。(昭和9年)
……などと、街の噂や目にした風景、会った人々といった日々の些細なできごとから世相への批判、時には関係を持った女性たちの実名までが季節感豊かな文章で仔細に記録され続けた『断腸亭日乗』。昭和16年の太平洋戦争開戦時には、このような文章が残っています。
開戦布告と共に街上電車其他到処に掲示せられし広告文を見るに、屠れ英米我等の敵だ進め一億火の玉だとあり。或人戲にこれをもじり、むかし米英我等の師困る億兆火の車とかきて、路傍の共同便処に貼りしと云ふ。現代人のつくる広告文には鉄だ力だ国力だ何だかだとダの字にて調子を取るくせあり。
寔 に是駄句駄字と謂ふ可し。晡下向嶋より玉の井を歩む。両処とも客足平日に異らずといふ。金兵衛に飯して初更にかへる。
開戦布告のポスターを見て、“鉄だ力だ国力だ”などと“ダの字”で調子をとるような広告文は“駄句駄字”だと痛烈な批評をする荷風。さらりとこのような国勢批判をしたかと思えば、次に続く文章では何事もなかったかのように(当時日本有数の私娼街であった)“玉の井を歩む”と書いてしまうところに、徹底的な個人主義と自由主義を生涯貫き通した彼らしさが表れています。
特に読みごたえがあるのは、昭和20年3月、空襲によって自宅が焼失してしまった日の日記です。
三月九日。 天氣快晴。夜半空襲あり。翌曉四時に至りわが偏奇館燒亡す。火は初長埀坂の半程より起り、西北の風にあふられ忽市兵衛町二丁目表通りに延燒す。予は枕頭の窓火光を受けてあかるくなり、隣人の叫ぶ聲唯ならぬに驚き日誌及草稿を入れたる手革包を掲げて庭に出でたり。谷町邊にも火の手上るを見る。又遠く北方の空にも火光の反映するあり。火粉は烈風に舞ひ粉々として庭上に落つ。(中略)予は風の方向と火の手とを見計り逃ぐべき路の方角をも
稍 知ることを得たれば、麻布の地を去るに臨み二十六年住なれし偏奇館の燒け落るさまを心の行くかぎり眺飽かさむものと、再び田中氏邸の門前に歩み戻りぬ。
燃えている自宅の様子を見ながら、慌てたり嘆いたりするのではなく“焼け落ちるさまを心ゆくかぎり眺め飽かそう”とする荷風の堂々とした様子には、思わず読者のほうが驚かされてしまいます。激動期の世相や、空襲によって姿を変えてゆく東京の風景を、揺らぐことのない静かな筆致で捉え続けた荷風の日記には、淡々としているからこそ、得も言われぬ凄みがあります。
(あわせて読みたい:【生誕140周年・没後60年】永井荷風のおすすめ作品4選)
『病牀六尺』(正岡子規)

出典:http://amzn.asia/6HloyN7
『病牀六尺』は、若くして結核を患った俳人・正岡子規が、臥床生活を送りながらも死の2日前まで書き続けた随筆集です。
子規は23歳のときに結核による
病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである。僅かに手を延ばして畳に触れる事はあるが、蒲団の外へまで足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて五分も一寸も体の動けない事がある。苦痛、煩悶、号泣、麻痺剤、僅かに一条の活路を死路の内に求めて少しの安楽を貪る
果敢 なさ、それでも生きて居ればいひたい事はいひたいもので、毎日見るものは新聞雑誌に限つて居れど、それさへ読めないで苦しんで居る時も多いが、読めば腹の立つ事、癪にさはる事、たまには何となく嬉しくてために病苦を忘るるやうな事がないでもない。
……という書き出しのとおり、子規は病による苦痛や無気力に屈服することなく、“生きていれば言いたいことは言いたい”という精神で画評や時評、同時代の俳人たちとの交流などを淡々と記し続けました。
特筆すべきは、子規自身の病状に対する凄絶な描写です。
支那や朝鮮では今でも拷問をするさうだが、自分はきのふ以来昼夜の別なく、五体すきなしといふ拷問を受けた。誠に話にならぬ苦しさである。(九月十二日)
人間の苦痛はよほど極度へまで想像せられるが、しかしそんなに極度にまで想像したやうな苦痛が自分のこの身の上に来るとはちよつと想像せられぬ事である。(九月十三日)
子規はこのように自分の病状を詳細に記録し続けながらも、同時に、死の直前まで俳句や随筆の創作を欠かしませんでした。自分の体が思い通りに動かなくなってゆくという想像を絶するような苦痛に苛まれてもなお、強靭な精神力を失わなかった子規。その文章は、どのような過酷な環境の中でも人間は強く高潔でいることができる、というひとつの証明のようにも感じられます。
『震災日記より』(寺田寅彦)
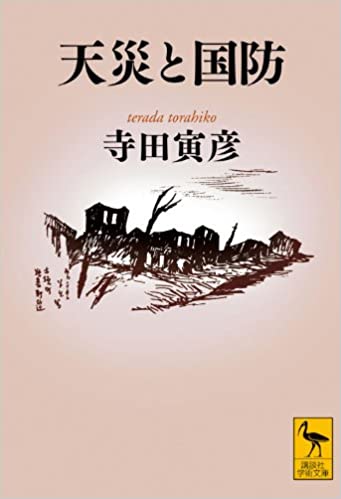
『震災日記より』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062920573/
『震災日記より』は、戦前の物理学者・随筆家である寺田寅彦が自らの日記に綴った関東大震災の記録です。寺田は自然科学や地球物理学の分野で功績を残した科学者でありながら、その豊富な知識を活かし、優れた随筆も多く遺しました。
『震災日記より』は非常に短い随筆ですが、寺田が経験した震災時の衝撃と実感が詳細に書き表されています。1923年9月1日、関東大震災当日の日記は以下のように綴られています。
T君と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品画「I崎の女」に対するそのモデルの良人からの撤回要求問題の話を聞いているうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけている両足の
蹠 を下から木槌で急速に乱打するように感じた。多分その前に来たはずの弱い初期微動を気が付かずに直ちに主要動を感じたのだろうという気がして、それにしても妙に短週期の振動だと思っているうちにいよいよ本当の主要動が急激に襲って来た。同時に、これは自分の全く経験のない異常の大地震であると知った。
同じ食卓にいた人々は大抵最初の最大主要動で吾勝ちに立上がって出口の方へ駆出して行ったが、自分等の筋向いにいた中年の夫婦はその時はまだ立たなかった。しかもその夫人がビフテキを食っていたのが、少なくも見たところ平然と肉片を口に運んでいたのがハッキリ印象に残っている。しかし二度目の最大動が来たときは一人残らず出てしまって場内はがらんとしてしまった。
このあと、喫茶店の外に出て東京の街を歩いた寺田は、柱がすっかり倒壊した神社や火事を起こして燃えている家屋を目にするうちに、事態の深刻さに気づきます。
無事な日の続いているうちに突然に起った著しい変化を充分にリアライズするには存外手数が掛かる。
という一文は、東日本大震災やコロナ禍を経験した私たちにとっては深く頷けるものではないでしょうか。
『震災日記より』は、地震や津波といった天災についての寺田の論考をまとめた書籍『天災と国防』に収録されています。寺田は表題作となっている随筆『天災と国防』において、関東大震災や三陸沖地震、函館の大火といった天災を立て続けに経験した日本国家の対応の不十分さを批判し、国際環境に対する安全保障と同様に、自然に対する安全保障も必要であると説いています。
国際的のいわゆる「非常時」は、少なくも現在においては、無形な実証のないものであるが、これらの天変地異の「非常時」は最も具体的な眼前の事実としてその惨状を暴露しているのである。
悪い年回りはむしろいつかは回って来るのが自然の鉄則であると覚悟を定めて、良い年回りの間に充分の用意をしておかなければならないということは、実に明白すぎるほど明白なことであるが、またこれほど万人がきれいに忘れがちなこともまれである。もっともこれを忘れているおかげで今日を楽しむことができるのだという人があるかもしれないのであるが、それは個人めいめいの哲学に任せるとして、少なくも一国の為政の枢機に参与する人々だけは、この健忘症に対する診療を常々怠らないようにしてもらいたいと思う次第である。
科学者、そして一生活者としての実感を持って書かれた『天災と国防』は、まさにいま読むべき価値のある1冊。非常事態において、日々をどのような心持ちで過ごせばいいかわからないという方にとっては、特に手を伸ばしていただきたい名著です。
おわりに
名前どおりの“緊急事態”の只中において、コロナ禍以前の日常は恋しいものではありますが、時間を巻き戻さない限り、まったく同じ日々が戻ってくることはありません。これまでに人類が経験してきた数多の天災や疫病の歴史のように、私たちはこの“非日常”をいずれは“日常”として受け入れる覚悟を持つ必要がありそうです。
個人がどのような気持ちで日々と向き合えばいいのかわからなくなりそうになってしまったとき、その助けとなるものが文学です。壮絶な環境の中でも自身の毎日を淡々と綴り続けた文豪たちの日記をいま読み返すことは、一筋の光になるかもしれません。
初出:P+D MAGAZINE(2020/05/13)

