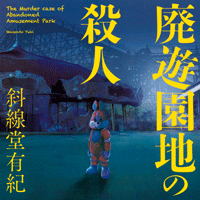今月のイチオシ本 【ミステリー小説】

冒頭で、渋谷を混乱に陥れた女性ゲームクリエイターが自ら命を絶つ、『虹を待つ彼女』(第三十六回横溝正史ミステリ大賞受賞作/二〇一六年)。人工知能による作曲アプリが普及した作曲家なき世界で、それでも作曲を求め続けた友人の自死の謎を追う、『電気じかけのクジラは歌う』(二〇一九年)。逸木裕の作品には、こうした「自殺」が影を落とす物語がこれまでにもあったが、『銀色の国』では真正面からこの深刻なテーマに挑んでいる。
NPO法人で自殺防止に取り組むも、必ずしも止めることができない無力感を抱えている田宮晃佑のもとに、悲しい報せが届く。現在の活動を始めるきっかけとなった人物──市川博之の自殺だった。現場となったホテルの部屋にはVR用のゴーグルが残されており、田宮はある恐ろしい企みの可能性に気がつき、高校時代の同級生である城間宙に相談を持ち掛ける。
この田宮のパートを軸に進んでいく本作において、同じく重要な役割を果たすふたりの人物がいる。習い事やバイトをはじめ、とにかく逃げ出してしまう〝逃げ癖〟に囚われた人生を送ってきた二十四歳の小林詩織。そしてツイッターに「死にたい」と書き込み、常習的に足の甲にカッターを走らせる浪人生の外丸くるみだ。このふたりが深く関わることになる謎の自助グループ〈銀色の国〉に、田宮たちが迫ることになる。
生きるよりも死を強く求める者、その死を防ごうとする者、近しいひとの死を背負って生きる者、死を弄ぶ者、死を与えようとする者──こうした登場人物たちを通じて次第に浮かび上がる、現代的悪意のおぞましさには誰もが言葉を失い、なかには現実の痛ましい事件を重ねる向きもあるだろう。しかし本作の主題は、テクノロジーの進化と悪用の警告ではない。むしろ黒幕との対峙の先にこそ、最大の読みどころが用意されている。
〈銀色の国〉は、確かにそら恐ろしい虚構と映るかもしれない。しかし、そこにさえも生きることに背を向けていた心を振り向かせる一条の光は差し込む。その希望を、しかと見届けていただきたい。