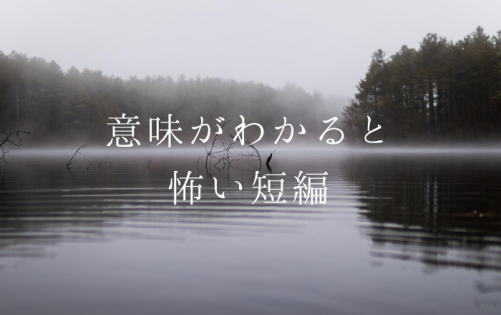【あれ? なんか変】真夏に読みたい、“意味がわかると怖い”短編3選
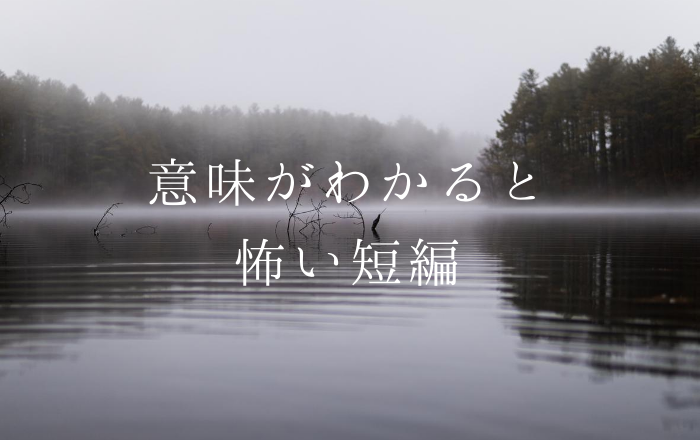
物語の最後になって初めてそこに隠されていた意味に気づき、一気に背筋が寒くなる……。今回はそんな、夏の暑さが和らぐような“意味がわかると怖い”短編小説の名作を、3作品ご紹介します。
蒸し暑い日が続くと、背筋が冷たくなるような怖い話が読みたくなる──という方も多いのではないでしょうか。
幽霊・妖怪が登場する怪談やサイコホラーなど、怖い話にもさまざまなジャンルがありますが、中でも「え、もしかしてこの話って……?」と、“意味がわかった瞬間”にゾッとするようなストーリーは、特に怖いものです。
今回は、名だたる作家たちの短編作品の中から、そんな“意味がわかると怖い”話を3作品、選りすぐってご紹介します。
(※本記事には短編作品のネタバレが含まれますので、ご注意ください)
星新一『暑さ』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101098018/
最初にご紹介するのは、ショート・ショートの神様、星新一による『暑さ』という短編。
主人公の男がある暑い日、交番に駆け込み、巡査に「罪を犯しそうで怖いから、私を逮捕してくれませんか」と奇妙なお願いをするところから物語は始まります。
巡査は不思議に思いながらも、交番で男の話を聞くことにします。男は子どもの頃から暑さに弱く、暑いと頭がぼんやりしとにかくイライラしてきて、なにかしなくては、という衝動に駆られるのだと言います。
子どもの頃は、アリを踏み潰して殺すのがストレスのはけ口だった、と男は語ります。アリを潰すと男の暑さに対するいらだちは消え、清々しい気持ちになったと言うのです。
しかしその翌年の夏、暑さに耐えられなくなった男はアリでは物足りなくなり、カナブンを殺しました。その翌年の夏はカブトムシを殺し、また次の年には、ついに犬を殺したのだと男は言います。
同じ年の秋、生き物に愛情を持つことができれば自分の衝動は解消されるのではと考えた男は、ペットとして猿を飼い始めました。しかし男はその次の年にあたる昨年の夏、ついにそのペットの猿まで殺してしまったのです。このままでは取り返しのつかないことになる、もう自分を逮捕してほしい──。男の切実な訴えに対し、巡査は「事件を起こしたわけではないから、逮捕はできない」と困ったように言います。
諦めた男が帰ろうとしたとき、巡査が不意に男に尋ねます。
「家族はあるんだろう」
「ええ、昨年の秋に結婚して……」
たったひと言で男が予感していた“衝動”の正体がわかってしまう、鮮やかで恐ろしい、夏にぴったりのショート・ショートです。
阿刀田高『迷路』
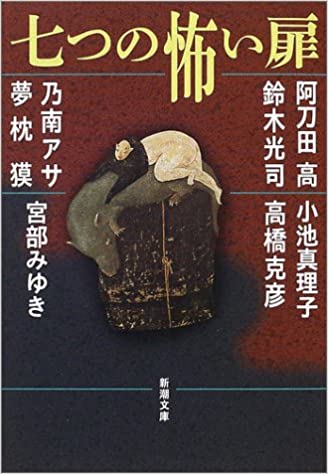
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101255253/
奇妙な味(読後に後味の悪さを残すという特色を持った推理小説のジャンル)の短編小説の名手である阿刀田高。彼による思わずゾッとするような短編のひとつに、『迷路』という作品があります。
物語の主人公は、昌司という青年。昌司は自分の幼い頃から現在に至るまでのある記憶を語ろうとしますが、語ることが夢なのか現実なのかがわからず、彼の頭はいつもどこか「薄ぼんやり」していると言います。
昌司は幼い頃、実家の庭にある井戸の上に降り積もった雪をかぶせ、落とし穴を作ったことがある、と回想します。そこに友人の女の子を呼ぶと、女の子は落とし穴に落ちてあっけなく死んでしまいました。
昌司は“あれは夢だ”と自分に言い聞かせ、春になったら井戸を見てみようと決めます。やがて春がきて井戸の中を覗き込むと、なぜかそこに女の子の死体はありませんでした。昌司は、やはり女の子が井戸に落ちてしまったのは夢だったのだ、と考えます。
大人になった昌司は、小さなことで恋人と口論になり、彼女を殺してしまいます。死体の隠し場所に困った昌司は、井戸の中に恋人を投げ込み、そこに蓋をしました。しばらくして蓋をとり中を覗いてみると、なぜかまた、そこには死体がありませんでした。昌司は、この井戸は死体を入れてもそれを消してくれる不思議な井戸なのかもしれない、と考え始めます。
それから数年が経ち、老いた昌司の母が寝たきりになってしまいます。昌司は介護に嫌気が差し、ためらいなく母を殺します。死体はもちろん井戸に投げ込むのですが、なぜか、数日経っても井戸の中から死体はなくなりません。血と水で溶けて膨張した死体は、お化けのように井戸からこちらを見続けています。もうそろそろ消える頃だ、と昌司が何度思って蓋を開けても、やはり母の死体は消えないのです。
物語は、
母ちゃんが死んでしまったら、だれも体を張ってまで昌司の不始末を救ってくれる人などあろうはずもないのに……
という一行で終わります。シンプルでありながら背筋が凍るような、一級のホラーです。
シャーリイ・ジャクスン『くじ』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4151823018/
1940年代から1960年代にかけてアメリカで人気を博した作家、シャーリイ・ジャクスン。『ずっとお城で暮らしてる』、『たたり』といった代表作を持ち、恐怖小説の帝王とも呼ばれる彼女の有名な短編小説のひとつに、『くじ』があります。
本作は、
からりと晴れて、暖かく明るい陽射しも澄んだ、夏らしい日となった。花は一面に咲き乱れ、草は青々と繁っている。
という爽やかな描写で幕を開けます。読み進めていくと、ここは300人ほどが暮らす小さな村で、村人たちはある“くじ”を引くために広場に集っている──ということがわかります。
どうやらこのくじは年に一度開催されている、村に代々伝わる伝統のようで、人々はほんの2時間ほどで終わるというくじ引きの儀式を終わらせるために、子どもから大人まで皆、家から出てきたところなのでした。
くじ引きを運営するのは、市民活動に熱を注いでいるサマーズ氏です。サマーズ氏が村に古くから伝わる“黒い箱”を準備し、箱の中に入っている紙切れが十分にかき回されるのを、村の人たちは黙って見ています。
はじめは家族単位でくじ引きがおこなわれ、丸印のついた紙をビル・ハッチンスンという男が引き当てました。ビルの妻であるハッチンスン夫人は、「うちの人がくじを選ぶのに十分な時間をくれなかったじゃないか。こんなのずるいよ」と反発しますが、それがルールだから、と村の人々は聞き入れません。
2回目のくじ引きは、ビルが丸印を引き当てたため、ハッチンスン家の5人によっておこなわれました。幼い娘と息子の3人がくじに外れたことがわかると、周囲でそれを見ていた村の人々から安堵のため息が漏れます。ビルも外れを引き、今度丸印を引き当てたのは、ハッチンスン夫人でした。
「さっさと終わらせるとしよう」というサマーズ氏の号令を聞いて、村の人々は両手に石を握ります。その石のひとつはすでに、ハッチンスン夫人のこめかみをかすめ始めていました。このくじは、石で打つ村人を決めるためのものだったのです。そして本作は、
「ずるいよ。まちがってるよ」ハッチンスン夫人は悲鳴をあげた。そこに村人たちが殺到した。
という一行で幕を下ろします。
毎年ひとりずつ、石を投げつける村人をくじで決めるというこの伝統がなぜいまもなお続いているのか、なんのためにおこなわれているのか、作中では一切説明はされません。
しかし、ハッチンスン夫人は1度目のくじ引きが終わったあと、すでに嫁いだ自分のふたりの娘にもくじを引かせようとして「娘はその夫の一族として引くルールだとわかっているだろう」とサマーズ氏に諭されるなど、どこか利己的で、村の人たちからも敬遠されている人物であるように思えます。
繰り返し読むほどに、ハッチンスン夫人が当たりくじを引いてしまったのは必然だったのではないか、そうであるとしたら、このくじは本当に無作為に誰かひとりに当たるように作られているのか? ──といったことが頭をよぎる、たまらなく後味の悪い名作です。
おわりに
“意味がわかると怖い”話は、インターネットの掲示板上などでも人気を集め、さまざまな作家の作品を下敷きにした派生作品や、オリジナルの怪談なども多数生まれているジャンルです。しかし、小説家たちによる短編をあらためて味わっていただくと、その鮮やかさにはっとする方も多いのではないでしょうか。
今回は3作品のあらすじをご紹介しましたが、結末を知ってから原作を読んでも、伏線の張り巡らせ方やちょっとした描写の不穏さ・恐ろしさに驚くはずです。暑い夏、短編の名手たちによるホラーの凄みを、ぜひ味わってみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2020/08/29)