【名作推理小説5選】この「叙述トリック」がすごい!

先入観を巧みに利用し、読者をミスリードへと導く小説技法のひとつ「叙述トリック」。今回はそんな叙述トリックが際立つミステリ小説・サスペンス小説の名作を、5作品ご紹介します。
ミステリファンの方のなかには、推理小説やサスペンスを読み進める醍醐味のひとつに「叙述トリック」を挙げる方も多いのではないでしょうか。「叙述トリック」とは、読者の先入観を利用し、巧みな仕掛けを用いてミスリードへと導いていく小説技法のこと。女性だと思っていた語り手が男性だった、被害者だと思っていた人物が加害者だった──といった意外なオチが、「叙述トリック」の典型的な一例です。
今回は、そんな「叙述トリック」を堪能することができるミステリ小説を、古典的名作やミステリファンに人気の高い作品を中心に5作品ご紹介します。
(※以下の紹介には、作品の核心に関わる部分のネタバレが含まれるものがあります)
『アクロイド殺し』(アガサ・クリスティー)
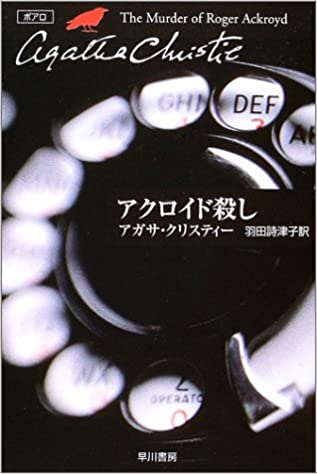
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4151300031/
【ここがすごい!】
・「叙述トリック」が広く認知されるきっかけとなった一作
・ミステリの女王による、推理小説史に残る名作
・江戸川乱歩も賛辞を贈った文章の巧みさ
アガサ・クリスティーによる『アクロイド殺し』は、1926年に発表されたミステリの古典的名作です。名探偵エルキュール・ポアロシリーズの3作目にあたる本作では、同シリーズで通常ポアロの友人として記録係を務めているヘイスティングス大尉に代わり、医師であるジェイムズ・シェパードという人物が語り手となってストーリーが進行します。
かつて夫を殺してしまったことで何者かから恐喝を受けていたフェラーズ夫人という人物の不審死、そしてフェラーズ夫人と再婚予定だった富豪のロジャー・アクロイドが刺殺された事件の真相を巡って、探偵ポアロが活躍する本作。語り手であるシェパード医師は、ポアロから事件にまつわる手記の存在を指摘され、
そんなにすぐに見せてくれといわれても、心の準備ができていなかった。頭を絞って、ある細かい部分を思いだそうとした。
と何かを隠しているような素振りを見せます。勘のいい方であればもうおわかりだと思いますが、この事件の犯人は、語り手であるシェパード医師。彼は事件にまつわる語りのなかで嘘はついていないものの、彼にとって都合の悪い部分は曖昧にし、あえて多くを書かないという形をとっています。これこそが本作で用いられている叙述トリックなのです。
語り手が犯人だなんてありがち……と思われた方もいるかもしれませんが、本作が書かれた1920年代には、まだミステリにおいて「叙述トリック」(さらに本作で言えば、読者が物語の語り手の言うことを鵜呑みにできないという「信頼できない語り手」の手法)は一般的なものではありませんでした。『アクロイド殺し』のインパクトは大きく、当時のミステリ界では「この手法がフェアであるか?」という論争が盛り上がり、ヴァン・ダインやエラリー・クイーンなど著名な作家らによってさまざまな意見が交わされたという記録があります。日本では江戸川乱歩がフェアであるという立場をとり、
この作では、記録者は少しも嘘を書いていない。ただ一ヵ所ちょっと記述をはぶいたところがあるだけで、全体としては真実を書いている。それでいて、記録者が犯人なのだから、その書き方には非常な技術を要する。クリスティは、それを巧みにやってのけた。
(江戸川乱歩・松本清張『推理小説作法 あなたもきっと書きたくなる』より)
と本作を賛えています。現在では『アクロイド殺し』は、ミステリ史上に残る古典的名作としてよく知られています。
(あわせて読みたい:【実例つき】“信頼できない語り手”ってなんだ? 小説用語を徹底解説)
『幻の女』(ウイリアム・アイリッシュ)
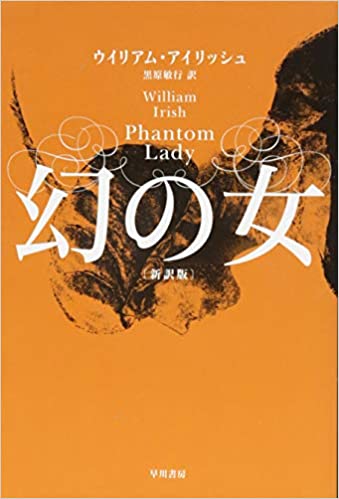
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4150705542/
【ここがすごい!】
・誰も見ていない“幻の女”を巡る、魅力的すぎる謎
・“サスペンスの詩人”による詩的で美しい文体
・「死刑執行日の〇〇日前」という恐怖のカウントダウン
『幻の女』は、ヒッチコックによって映画化された短編小説『裏窓』などの代表作を持つアメリカの作家・ウイリアム・アイリッシュによる長編小説です。ウイリアム・アイリッシュは犯罪を巡る人間の心理や恐怖を巧みに描くサスペンス作家として知られており、その詩的な文体から“サスペンスの詩人”の異名を持ちます。本作の書き出しである、
夜は若く、彼も若かったが、夜の空気は甘いのに、彼の気分は苦かった。むこうからやってくる彼の顔が不機嫌なのは、かなり離れたところからでもわかった。それは鬱積してくすぶりつづけ、時に何時間も続くことがある、あのしつこい怒りのせいだった。(中略)
五月の夕べ、今まさにデートの時間が始まろうとしていた。三十歳前の、街の半分が、髪を撫でつけ、財布に資金をしこみ、意気揚々と待ち合わせの場所へ向かっていた。これまた三十歳前の、街の残り半分は、顔に白粉をはたき、特別の服を着こんで、待ち合わせの場所に向かってうきうきと歩を運んでいた。どちらを向いても、街の半分と街の半分が落ち合っていた。
という文章は非常に有名。この書き出しを読んだだけでも、デートの待ち合わせをする人々だらけの浮かれた街でひとり、不機嫌な様子でいる“彼”の心情がよく伝わってくるはずです。
本作の主人公はこの“彼”ことスコット・ヘンダーソン。スコットは既婚者でありながら他に愛する女性ができてしまい、妻のマーセラに離婚を申し出ていました。しかしマーセラに話し合いを拒否されたスコットは、思わず家を飛び出し、バーで出会ったオレンジ色の異様な帽子をかぶった女性と食事を共にします。家に帰ったスコットを待ち受けていたのはなんと、スコットのネクタイを使って絞殺されていたマーセラの遺体と、刑事・バージェスでした。
スコットは無実を証明するため、その夜は異様な帽子の女性と一緒にいたということを主張しますが、なんと彼らを目撃していたはずのバーテンダーらは皆、口を揃えて「スコットはひとりだった。女は見ていない」と言うのです。無実を証明できなければ死刑になってしまうスコットを救うため、彼らの証言に違和感を覚えたバージェス刑事とスコットの友人ジャックが、それぞれ独自に捜査を始めます。
事件の真犯人は誰なのか? そして“幻の女”は本当に存在したのか? ──という魅力的な謎が、死刑執行日までのカウントダウンという緊張感をかきたてる仕掛けつきで展開されていきます。トリックの詳細なネタバレにはここでは触れませんが、「叙述トリックもの」と知って読んでもなお驚く結末であるはずです。
『歯と爪』(ビル・S・バリンジャー)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4488163041/
【ここがすごい!】
・結末部分はまさかの「袋とじ」
・主人公が復讐者、殺人者、そして被害者?
・ある天才奇術師を巡って繰り広げられる、奇想天外なストーリー
『歯と爪』は、1955年にアメリカの作家ビル・S・バリンジャーによって発表された長編小説です。主人公は、リュウ・マウンテンという名の天才奇術師。本作のプロローグには、
生前、彼は奇術師だった――ハリー・フーディニやサーストンと同じような手品師、魔術師で、その方面ではすばらしい才能をもっていた。ただ、早死にしたため、ハリーやサーストンほど有名にならなかっただけだ。だが彼は、これらの名人すら試みなかったような一大奇術をやってのけた。
まず第一に彼は、ある殺人犯人に対して復讐をなしとげた。
第二に彼は殺人を犯した。
そして第三に彼は、その謀略工作のなかで自分も殺されたのである。
という、不可解な文章が並びます。読者は、リュウが復讐者であり、殺人者でありながら自らも殺された人物(被害者)である──という大きな謎を念頭に置いて物語を読み進めることになるのです。ストーリーは、アイシャム・レディックという運転手が殺され、その遺体が見つからないという奇妙な殺人事件の裁判記録と、リュウとその妻の暮らしを描いたラブストーリーが交互に挿入されることで展開していきます。このふたつの物語がどのように関わってくるのか、そして冒頭の“謎”がどのように解き明かされるのか──というのが本作の肝。読み進めていくと、プロローグのなかで著者が仕掛けた巧妙な叙述トリックに読者は気づくはずです。
本作の仕掛けとしてもうひとつ特筆すべきは、本の結末部分が“袋とじ”になっているという点。しかも本作の出版当初は、“袋とじ部分を開封していなければ返品可能”という触れ込みで発売されるなど、そのユニークな販促方法でも話題を呼びました。読者は絶対に結末を知りたくなるはずだ、という著者の自信が伝わってくるトリッキーな仕掛けですが、60年以上の時代を経たいま読んでもなお、「そうきたか……!」と唸ってしまうような結末が待っています。
『「アリス・ミラー城」殺人事件』(北山猛邦)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062761467/
【ここがすごい!】
・シンプルながらも騙されてしまう叙述トリック
・探偵たちがひとりずつ消えていく、ハラハラするストーリー
・絶対に予想のできない“すごい動機”
『「アリス・ミラー城」殺人事件』は、『「クロック城」殺人事件」』など“城”シリーズの代表作を持つ、北山猛邦による長編ミステリ小説です。本作のストーリーは、『鏡の国のアリス』の世界を思わせるアリス・ミラー城という城に集められた探偵たちが、まるでチェスの駒のように次々と殺されていく──というもの。ミステリ好きであれば思わず前のめりになってしまうような、王道かつ魅力的な舞台設定です。
舞台となるアリス・ミラー城は、酸性雨が降り続ける東北の孤島・江利ヵ島に建つ古城。この城に8名の探偵たちが「1週間の滞在のうちに、城に眠るアリス・ミラーという名の鏡を探し出してほしい」という名目で招待されます。さらに、アリス・ミラーを手に入れることができるのは、最後まで生き残った人物のみという不穏なルールも提示されます。
翌日、探偵のひとりである、
本作の最大の特長は叙述トリックを用いたその意外な結末ですが、もうひとつ、真犯人による“動機”も驚くべきもの。怨念や復讐ではなく、“死体”そのものが必要だったという殺人の動機の真相には、思わずエーッと声を上げたくなるはずです。
(あわせて読みたい:【この動機がひどい!】ミステリ小説の「ヤバい動機」4選)
『葉桜の季節に君を想うということ』(歌野晶午)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167733013/
【ここがすごい!】
・絶対に2回読みたくなる、まさかすぎるどんでん返し
・巧妙に散りばめられた細かい伏線の数々
・意外すぎる、けれど感動させられてしまうラブストーリー
『葉桜の季節に君を想うということ』は、ミステリ作家の歌野晶午による長編小説です。本作は第57回日本推理作家協会賞、第4回本格ミステリ大賞、「このミステリーがすごい!」2004年版の第1位など、2004年のあらゆるミステリ大賞を受賞した名作として知られています。
主人公は、なんでも屋ならぬ“なんでもやってやろう屋”を自称する男・成瀬将虎。彼は強い性欲と体力を持つ人物で、さまざまな女性と寝てはジムで汗を流す──という生活をしていました。ある日、ジムで出会った高校の後輩・清に誘われ、清が密かに思いを寄せている愛子という女性に会いに行くと、すこし前に愛子の「おじいちゃん」が交通事故で亡くなったのだという話を聞きます。その後、愛子は「おじいちゃん」は保険金目当てにひき逃げされたのではないか、その事件には悪徳会社である蓬莱倶楽部という企業が関わっているのではないか──と疑いを抱き、探偵もできるという将虎に事件の真相を突き止めてほしいと依頼します。
同じ頃、将虎は電車に飛び込み自殺をしようとしていたさくらという女性に出会い、すんでのところで彼女を救出します。お互いのことを知るうち、次第に惹かれ合っていくふたり。しかし、将虎が引き受けた愛子の「おじいちゃん」の殺人事件の謎を解き明かしていくうち、さくらと蓬莱倶楽部との繋がりが浮かび上がってくる──という不穏な展開を見せていきます。
本作の最大の読みどころは、なんと言ってもその巧みすぎる叙述トリック。
射精したあとは動きたくない。相手の体に覆いかぶさったまま、押し寄せてくる眠気を素直に受け入れたい。
俺の愛車はミニ。BMWの手に渡った新生ミニではなく、オースチン・ローバーのミニ・メイフェア。89年製の車体はあちこちがたがきていて、クーラーの機嫌もきわめて悪い。
といった、将虎のキャラクターや行動にまつわる描写から受ける先入観を利用したトリックはあまりにも予想外なはず。読み終えたあと最初のページに戻り、散りばめられた伏線をもう一度確かめたくなること請け合いの1冊です。
おわりに
小説が“読者を騙す”という形をとる叙述トリック。叙述トリックを巡っては、上記でもご紹介した『アクロイド殺し』にまつわる論争が盛り上がったように、現在でも「それはアンフェアなのでは」という指摘がされることもたびたびあります。しかし、『アクロイド殺し』の叙述トリックがアンフェアだという意見を批判した推理小説家・翻訳家のドロシー・L・セイヤーズは、彼女が編纂したミステリのアンソロジー『Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror』のなかで、このようにも述べています。
the reader’s job to keep his wits about him, and, like the perfect detective, to suspect everbody.
(訳:読者の仕事は、機知を働かせ、完璧な探偵のようにあらゆる人物を疑うことだ)
“完璧な探偵”のようにあらゆる人物を疑う──というのはなかなか難しいことですが、そういった姿勢で謎に臨むことこそがミステリ小説を読む上での楽しみだという読者も少なくないのではないでしょうか。鮮やかに騙される快感、そして記述のなかのわずかな違和感に気づく快感を味わいたい方には、今回ご紹介した5作品はどれもとてもおすすめです。
初出:P+D MAGAZINE(2021/06/23)

