主人公がひたむきに生きるピュアな世界。三浦しをんのおすすめ小説5選

リアリティのある舞台をエンタテインメントに紡ぎ上げる名手・三浦しをん。作品の舞台は枚挙にいとまがないほどですが、見渡すと「ある特殊な世界で、ひたむきに生きる人たち」というテーマが見えてきます。ひたむきに生きる主人公の姿が胸を打つ作品が多い、三浦しをんのおすすめ作品5選を紹介します。
今や押しも押されぬ人気作家の三浦しをん。その多岐に渡る作品群に驚かされます。
三浦しをんは、リアリティのある舞台をエンタテインメントに紡ぎ上げる名手です。作品の舞台は枚挙にいとまがないほどですが、見渡すと「ある特殊な世界で、ひたむきに生きる人たち」というテーマが見えてきます。
世の多くの人は、無名よりは有名になりたい、苦労よりは楽をしたい、お金はないよりあるほうがいい、と思うでしょう。しかし三浦しをんの作品に登場する主人公たちは、そうした価値観を逆走するかのごとく、ひたむきに自己の世界と向き合っています。そこまで彼らを夢中にさせるものは何なのか? 当然のごとく、読者はその「閉じた世界」に興味を惹かれていきます。三浦しをんは一種の“触媒”として、知られざる(だからこそ面白い)世界にスポットを当て続けています。
今回はそんな三浦しをんのおすすめ作品5選をお届けします。
『愛なき世界』×生物科学研究室

https://www.amazon.co.jp/dp/4120051129
舞台は日本でもトップクラスの国立大学の生物科研究室。大学の向かいに位置し、教授や学生たちの行きつけの食堂「円服亭」の見習い・
本村と会ってから、藤丸には世界がこれまでとは違って見える。料理で使う野菜はよりうつくしく輝きを帯び、なんということもない都会の風景のあちこちにある緑が目にとまる。なんてたくさんの植物が、地球上で生きているんだろう。さびしさをふと忘れるほどに。
藤丸は、後悔はしていなかった。藤丸に新しい世界を見せてくれたひと。植物に恋する女の子に、恋をしたことを。
登場する生物科松田研究室の面々は、とにかく「変人」ばかり。私生活もそっちのけで植物研究にいそしみ、常識からはややズレた言動や行動を繰り返します。
恋人とデートする暇があったら、一粒でも多く(研究対象である)「シロイヌナズナ」の種をとりたい 、と切に願う本村にも、最初はユーモアしか感じません。けれども読み進めるうち、彼らの研究や人生に対する真摯な姿勢に打たれ、藤丸と同じく、深淵な「植物」の世界に引き込まれていきます。
恋のライバルが常に人類だとはかぎらない。
本村に二度告白し、二回ともふられた藤丸はそう達観するまでになりますが、本村との絆は切れるどころか深まっていきます。本村は、彼の支えに心から感謝し、だからこそ今まで以上に自分の信じる「研究」に強く取り組まねばならないと決意を新たにします。そんな彼女を尊敬し、今の形のままでいいからつながり続けたいと願う藤丸。不器用すぎるふたりの姿は、いつしか、「愛がある」 、「愛がない」という言葉では括れない、純粋な「愛」のかたちをあらわしていきます。「植物」を追究することで、彼らは研究や修行などの言葉だけではとらえられない、“普遍”という大きな存在に触れたのです。
研究に限らず何かを突き詰める事は孤独な道です。厳しさの中で生きる人だけが受け取ることのできる、確かな幸せや希望、人との繋がりの温かさがあることもまた真実。そう教えてくれる作品です。
『風が強く吹いている』×箱根駅伝
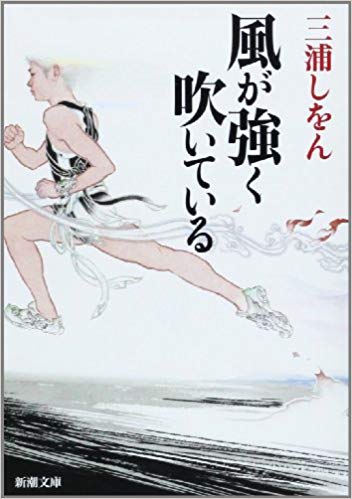
https://www.amazon.co.jp/dp/4101167583
陸上界のホープとして期待されていた
走りとは力だ。スピードではなく、一人のままでだれかとつながれる強さだ。
ハイジさんが、それを俺に教えた。(中略)好みも生きてきた環境もスピードもちがうもの同士が、走るというさびしい行為を通して、一瞬だけ触れあい、つながる喜び。
(中略)
走りはもう、走を傷つけない。走を排除したり、孤立させたりしない。走がすべてをかけて求めたものは、走を裏切らなかった。走るという行為は、走の思いに応えて強さを返した。呼べば振り向き、近づいてきてくれる大切な友人のように、走りは走のかたわらに寄り添う。征服し、ねじ伏せるべき敵としてではなく、いつまでもともにあり、走を支える力となって。
2006年、『まほろ駅前多田便利軒』で、第135回直木賞を受賞したことをきっかけに、より幅広い世代へ知られる作家となった三浦しをん。
同年に刊行された本作は、「箱根駅伝」という胸が熱くなるテーマを取り上げ、作者の確かな筆力を広く知らしめる快作となりました。
正月の風物詩である箱根駅伝。その裏には、言葉では語り尽くせないほどの汗と涙のドラマがあります。 主人公の 天才ランナー・走と、彼の才能を見いだす清瀬との運命的な出会い。
学生寮・竹青荘の住人を巻き込み、ほぼ素人の集団が1年で箱根駅伝出場をめざす、というあらすじからは、ライバル校の妨害のようなわかりやすい「障害」がもっとストーリーにからんでくるのかと思いがちですが、最大の敵は、走ること、そして自分自身を信じられるかどうか――――とても孤独な、自分との戦いだ、ということがテーマに据えられています。
また、男子学生寮で繰り広げられる友情とバカ騒ぎ、淡い恋が全編にちりばめられ、クスリと笑わせられながら、彼らとともに1年を過ごした後は、クライマックスの箱根本戦でタスキをつなぐ10人のモノローグが、もはや涙なしに読めないほど。
「走る」という選択は、誰ともわかちあえない、孤独な道を行くこと。だからこそ、孤独な者同士で、同じ夢を見ることに意味があり、意義があるのだと、走は気づきます。
走るという「一番好きなこと」に裏切られ、傷心のまま周りの全てに疑心暗鬼になっていた走。ハイジや仲間との出会いが、彼にもう一度、「走り」に真正面から向き合う勇気を与えるのです。かつての竹青荘の住人が、そして私たちがそうであるように、傷つくことを恐れ「こんなもんだろう」と日々に対して不感症になることなく、“生きる”ことにがっぷり四つに組むことの尊さと喜び――爽やかな青春の息吹とともに、重厚で鮮やかな感動を与えてくれる作品です。
『仏果を得ず』×文楽

https://www.amazon.co.jp/dp/4575514446
「文楽」はユネスコの世界文化遺産にも登録されている、大阪発祥の古典芸能・人形浄瑠璃文楽のことです。
主人公の健は、学生時代に 修学旅行で見学したことをきっかけに独特の美の世界に魅せられ、体ひとつで伝統の世界に飛び込みます。修行はもちろん厳しく、激昂した師匠からはモノが飛んでくることだって日常茶飯事。芸の道に邁進しようとすればするほど、日常さまざまな欲望にふりまわされて上手くいかなくなり、太夫としての自分の将来に不安を覚えていきます。
「きみは、自分にどれくらい時間が残っていると思う」
質問の意味がよくわからず、健は兎一郎の顔を正面から見た。兎一郎は目に苦い陰を宿し、淡々とつづけた。
「たいした病気も怪我もせず、存分に長生きしたとしても、あと六十年といったところだぞ。たった六十年だ。それだけの時間で、義太夫の神髄にたどりつく自信があるのか。(後略)」
三浦しをんの文楽熱は有名で、足繁く劇場に足を運ぶほどだと聞きます。そんな作者の、文楽という芸能への愛情と期待がこもった作品。 敷居の高いイメージのある伝統芸能の世界を、魅力ある主人公・健の視点で鮮やかに語ります。
ものになるまで数十年を要する厳しい修行の道で、恋やプライド、焦りに翻弄される現代っ子の苦悩があちこちにちりばめられています。それでもこの道を辞められないのはどうしてか。身近な人や師匠たちに、「認めてもらう」ことばかりにやっきになっていた健は、一見修行とは関係のないように思えた様々の出来事を通し、一番大事にしなければならないものに気づきます。
“うまく”やろうとしても無駄、等身大の自分でしか語ることはできない。遠回りに見えた道が、実は一番の近道。そう認めることでふっきれた健は、昨日までとは違う、成長した自分自身に気づくのです。
伝統、という枕詞から想像されるものとは裏腹に、清々しいほどの実力社会である文楽の世界は、憧れにも似た清涼感を読む者に与えてくれます。自分にも、他人にも、嘘をつけない世界で生きることは、並大抵なことではありません。だからこそ、どんなにささやかな一歩であっても、「成長」の手応えは何ものにもかえがたい幸せを自分に与えてくれるのです。自分にとことん向き合ってこそ周囲の評価がついてくる、そんな当たり前で見過ごされがちな教訓とともに、伝統芸能の知られざる魅力に目を開かせてくれる作品です。
『神去なあなあ日常』×林業
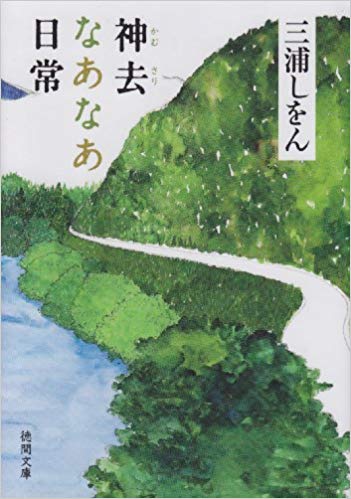
https://www.amazon.co.jp/dp/4198936048
高校卒業後、半ば強制的に林業の「若手育成プログラム」に放り込まれた、横浜育ちの平野勇気。三重県に位置する「神去村」では、ケータイなし、女の子なし、自由なし……。初めてだらけの異世界に怯え、不満たらたらだった勇気は、居候先のヨキ、そして神去村の住人との小さな衝突を繰り返しながら、林業、家族、時を経てつながれてゆくものといった、それまで考えてもみなかった大きな存在に気づき、素直さを取り戻し成長していきます。
「巌さんは、山がこわくならなかったですか」
「なんでや」
「神隠しに遭ったんでしょう?一歩間違えれば、家に戻れなかったかもしれないじゃないですか」
(中略)
「神隠しに遭うても遭わんでも、山はこわいもんや。(中略)けど俺は、山から離れたいとは思ったことない。山の神さんに祝福してもろた身なんやから、山で生きて山で死ぬのはあたりまえや」
すげえ。山仕事は仕事じゃなく、生きかたそのものです、って感じだ。こんなこと言う大人、俺のまわりにはいなかった。巌さんの口調がまた、淡々としてるんだよな。かっこいい。
2014年に映像化された三浦しをんの人気作品で、2012年に続編『神去なあなあ夜話』が刊行されています。
主人公は、18歳の平野勇気。要領よく生きることと女の子のことしか考えられないのに、突然、名前も聞いたことのない三重県の小さな村、それも「林業」という過酷な世界に放り込まれることになり、戸惑いと苛立ちを隠せません。隙をついて逃げ出してやる、最初はそんなことばかり考えている勇気ですが、神去村の面々とのやりとりでペースを崩され、いつのまにか、彼らとの距離を縮めていきます。
タイトルにもある「なあなあ」は彼らの言葉で「あせらず行こう」というようなニュアンスで、作中、頻繁に使われます。穏やかで、率直で、どこまでものんびり。勇気がそんな彼らにじりじりして喧嘩を売っても、ひょいとかわされてしまいます。「これだから田舎は!」的に最初は虚勢を張っていた勇気も、しだいに、彼らの包容力、しなやかな強さに気づき、やがて憧れるようにさえなります。
神去村の住人にとって全てである「山」そのもののように、泰然と、飄々と、自らの生活と家族とを守っていく。現代の感覚からすればささやかすぎる生の営みが、とがった10代の青年にもまぶしく感じられるほどに、「幸せ」の本質を突いていること。勇気の目を通して村の四季を感じていくうちに、私の人生も「なあなあ」でいいわぁ、そんな不思議で温かい気持ちに気づかされます。
『舟を編む』×辞書編集部
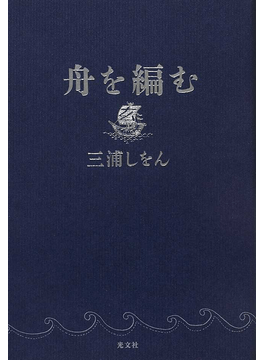
https://www.amazon.co.jp/dp/4334927769
玄武書房の辞書編集部の荒木は、定年を間近にして後継者選びに焦っていました 。監修者の松本先生とともにあたためてきた見果てぬ夢、新版「
馬締の不器用な恋と仕事への熱意を軸に、辞書にすべてをかける大人たちの神々しいまでの情熱とドラマが描かれています。
いったいどうしたら、なにかに夢中になれるのだろう。これしかないと思い定めて、ひとつのことに邁進できるのだろう。西岡にはわからなかった。
(中略)
学生時代の友人たちは、なにかにのめりこむのを、むしろ敬遠する傾向があった。西岡も、がっつく姿勢を見せるのは格好悪いと思っている。
(中略)
なぜそこまで打ち込めるのか、謎としか言えない。見苦しいとさえ思うときがある。だけどもし俺に、まじめにとっての辞書にあたるようなものがあったら。西岡はつい、そう夢想してしまうのだった。
きっと、いまとはまったく異なる形の世界が目に映るのだろう。胸苦しいほどの輝きを帯びた世界が。
2012年、第9回本屋大賞を受賞した作品で、 2013年の映画化も大きな話題を呼んだ、三浦しをんの代表作ともいえる一冊です。
「辞書」という、誰もが一度は手にする身近なものが、一体どのように作られているか。本書は、知られざる辞書作りの驚愕の裏側にスポットを当てた、「ことば」とのあくなき戦いを繰り広げる人々の物語です。
辞書作りとは、まさに一大プロジェクト。主人公の馬締を中心とし、一度は刊行不可能かと思われた新辞書「大渡海」は、多くの人を巻き込みながら、膨大な時間と作業の積み重ねの上に完成を目指します。
辞書は、「ことば」でできている。言葉があればなんでもできるようでいて、実は、気持ちをそのまま表すことは難しい。誰しもが大切な人との間で、そんなもどかしさを感じます。だからこそ「ことば」を、辞書作りをなおざりになど出来ない――――。主人公の馬締は、度重なる苦境の中で決意を新たにしていきます。
本作で爽快なのは、「巻き込む力」。馬締をはじめ、辞書編集の仕事に打ち込む人の周囲は、例外なく、その熱量にほだされるように情熱を取り戻し、「辞書」を通して自らの人生をもポジティブに変えていきます。だからこそ、馬締の情熱に遠く及ばない人でも、本書を読むことで、何かに心から打ち込むことでしか得られない喜びを分かち合いたいと願うのかもしれません。
おわりに
こうして見ると、特殊な舞台を通しての群像劇を得意とする三浦しをんが、実はその中で「孤独」というテーマを深く掘り下げている のではないかということに気づきます。
人生こんなものだとうそぶく前に、せめて一度くらい、自分が愛してやまないものをとことん突き詰めてみようじゃないか――――、上記に挙げた作品のどれかひとつにも触れれば、きっとそう思えることでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2018/12/17)

