【『三匹の蟹』など】小説家・大庭みな子のおすすめ作品

デビュー作『三匹の蟹』で芥川賞を受賞し、生涯に渡って精力的な執筆活動を続けた作家・大庭みな子。初期の傑作短編集や評伝『津田梅子』など、大庭みな子の魅力を知ることのできるおすすめの作品を、4作品紹介します。
『三匹の蟹』で第11回群像新人文学賞、第59回芥川賞を受賞して彗星のごとくデビューし、生涯に渡って小説や随筆を執筆し続けた作家・大庭みな子。
1960年代、「内向の世代」に属する小説家として注目を集めた大庭の作品は、現代のフェミニズムや多文化共生といった思想に通ずる要素も多く持っており、いまあらためて読んでも新鮮に感じられるはずです。今回は、そんな大庭みな子のおすすめ作品のあらすじと読みどころをご紹介します。
『三匹の蟹』
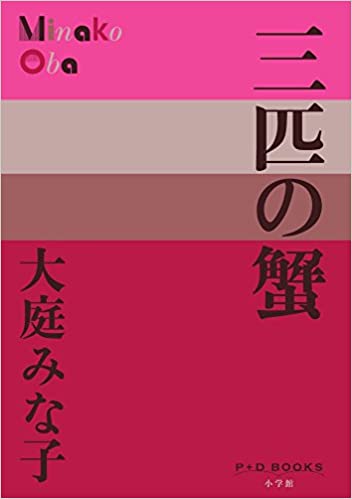
出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352340
『三匹の蟹』は、大庭のデビュー作である短編小説です。大庭は本作を発表した1968年、家族の仕事の都合によってアラスカに移住し、そこで生活をしている最中でした。本作は、自身のアラスカ体験を下敷きに、由梨という日本人女性の視点から海外での市民生活を描いた作品です。
主人公の由梨は、夫・武と10歳の娘・梨恵と3人でアラスカに暮らしている主婦。由梨は芯の強い人物ではあるものの、インテリで高圧的なところのある武に女性として見下され、抑圧された日々を送っていました。
あるとき、由梨は武の友人たちを招いて自宅でおこなうブリッジ・パーティーのために、軽食やお菓子の準備をすることになります。由梨は、進歩的なリベラルを装いつつも、その実はひどく女性蔑視的な招待客たちと、周囲の男性たちに媚びることで社交の場を盛り上げようとするその妻たちに嫌悪感を抱いていました。
“由梨はお菓子の粉を混ぜ合わせながら、胃の奥の方で微かな痛みを感じた。彼女は機械的に卵を割りほぐし、バターをこね合わせ、ベーキングパウダーや塩をふり入れながらまるで悪阻の時みたいに生唾が喉元まで上ってくるのを感じた。(中略)
「ママはね、誰にも本当のことを言えないから、時には梨恵にほんとうのことを言いたくなるのよ。たとえばサーシャが大嫌いだとか。お菓子なんか、吐きそうになるほど嫌いなのに作らなきゃならないとか。でも、そういうことをひとに言わないのよ。ママが、変なことを言ったら、ママは馬鹿だなあ、と思って黙って聞いておくだけにするのよ。ママは馬鹿かも知れないけれど、可哀そうなんだから、時には親切にするのよ」(中略)
武が酒の瓶をおろしながら、口をへの字に歪げて言った。
「そういうことを子供に言うものじゃない。君は大人の癖に耐えるということを知らん。いいか、梨恵、ひとは誰でも耐えなくちゃならんのだ」”
気分が悪く、耐えられなくなった由梨は、急用ができたと招待客たちに嘘をつき、ひとり家を抜け出します。由梨は夜の遊園地まで車を走らせ、そこで桃色のシャツを着た男と出会い、やがてひと晩の関係を持つのでした。桃色のシャツの男は、自身のルーツを
“「僕は四分の一、エスキモーで、四分の一、トリンギットで、四分の一、スウェーデンで、四分の一、ポーランドだ」”
と語ります。人種としてマイノリティである男と由梨は、どちらも言いようのない疎外感や空虚さを抱え、それに苦しんでいるように見えます。
発表当時、本作は海外に暮らす女性の先進的な価値観や役割からの解放を描いたものとして、大きな注目を集めました。現代の私たちの目から見ると、海外の男性と不倫する妻──というのはある種のステレオタイプにも見えるかもしれませんが、本作が描いた疎外されてしまう人々の孤独感は、決して古びていません。
『がらくた博物館』

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352438
『がらくた博物館』は、大庭が1975年に発表した作品集です。「犬屋敷の女」「よろず修繕屋の妻」「すぐりの島」という、アラスカを彷彿とさせる土地を舞台とした3篇の連作から成る本作は、第14回女流文学賞も受賞しています。
「犬屋敷の女」の主人公は、4頭のシベリア犬と暮らす女、マリヤ・アンドレエヴナ。マリヤは色の黒い、ロシア生まれの大女で、親友のアヤという日本人女性といつも一緒にいます。
“アヤという日本人の女が親友で、しょっ中連れだって歩いていたが、大女のマリヤがのっしのっしと歩くと、小女のアヤが走るようにちょこちょことその後を追って歩くのである。二人は年中深刻な顔付きで何やらひそひそと喋り、突然突拍子もない大きな声で笑ったり、どんとテーブルを叩いたりする。また、二人で雨の中で薄汚れたネッカチーフをかぶり、首から空缶をぶらさげてきのこや野いちごを採ったり、海辺の尖った岩に腰かけて、柳の枝に糸をつけて魚を釣っていたりした。”
マリヤやアヤ、そしてアヤの夫であるよろず修繕屋のラスといった風変わりな人物は、常に街のお喋りな人々の話題の中心でした。彼女たちが住む辺境の地は、つい数十年前までロシアの植民地だった街。“みんなその祖先に流れ者の血を持っているので、流れ者に対して寛容であり、理解もあった”と語り手は言います。
本作は、そんな“流れ者”の住人たちが奇妙な連帯感でゆるやかに繋がる様子を、ユーモラスでありながら哀愁も感じさせるエピソードを交えて描きます。
“考えてみると、ロシア女のマリヤにしろ、日本女のアヤにしろ、またスペインの男カルロスにしても、そろいもそろって、典型的なロシア人とか日本人とかいうのとは、似ても似つかぬ人間たちなのではないかと思われる。だから一人や二人の人間を見て、あれがロシア人だとか、あれが日本人だとか、あれがアメリカ人だとか判断を下すのは大して意味のない場合が多い。
もし強いて人間を分類したいのであれば、反逆的な人間とか、服従の好きな人間とか、威張るのが好きな人間とか、自由を求めずにはいられない人間とか、幻を追う人間とか、いうふうに分けたほうがずっとよい。”
という言葉はそのまま、大庭の人間観を反映しているようです。どこか奇妙で愛着の湧くキャラクターたちによる、極上の人間ドラマを味わえる1作です。
『幽霊達の復活祭』
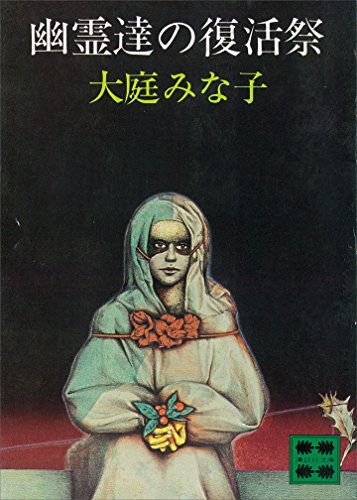
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07FMNMH4C/
『幽霊達の復活祭』は、大庭による初期短編を集めた作品集です。月夜の晩に礼拝堂で執りおこなわれた復活祭を祝うパーティーの様子を描く表題作を始め、奇妙で幻想的な作品や、耽美的な作品が多く収録されています。
本書の収録作のひとつである『首のない鹿』は、浜に打ち上がった鯨の血で真っ赤に染まった海の中、男と女が舟に乗って沖に出ていくというシーンから始まります。男は仕事でポスターのデザインをしており、展覧会で落選したポスターを地下室の壁一面に貼ることを習慣にしていました。あるとき、男が地下室に降りていくと、そこには落選した“首のない鹿”のポスターにもたれかかり、ひげの男とキスをしている女がいました。
“それは首のない鹿が狂気のようになって歩きまわっているポスターである。鹿の脚元には鶏が四つくらいの肉片につきさかれていて、羽や脚や首がついたまま、桃色の血のしたたる肉片がまだ暖かなゆげを立てていた。首から胸にかけてひきさかれた部分には、赤いとさかや、老婆の閉じた瞼を想わせる眼が淋しげについていた。足から胸にかけてひきさかれた部分は腹の内側に黄色い卵をいくつも数珠つながりにくっつけ、褐色のひび割れた鱗に蔽われた枯枝のような脚を宙にひきつらせてころがっていた。”
男の視界の中で、そのポスターの中の光景は、いつしか目の前の現実の風景へとシームレスに接続していきます。
“とれた鹿の首は地下室の一番隅っこにころがっていた。大きな哀しげな瑪瑙色のうるんだ眼には無数の蛆虫がゆっくりと這いまわっていた。長い睫の間で首をもたげてじっとこちらをうかがっている蛆虫もいた。首の無い鹿は飢餓状態で、まるで駝鳥のようにせかせかと歩きまわって、頭のない首の附根を、鶏の肉片の上に、あたかもその匂いをかぐようにさしのべているのだが、口がないので食べられないのである。”
男が女に対して覚えた嫌悪感に重なるように、どこまでもグロテスクかつ、緻密な描写が続いていきます。大庭が綴る情景描写の妙と奇想を存分に味わうことのできる作品集です。
『津田梅子』

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352376
『津田梅子』は、大庭が1991年に発表し、同年の読売文学賞を受賞した評伝です。津田梅子は、津田塾大学を創設し、日本の女子教育の近代化に生涯を捧げた女性。2024年から発行される予定の5000円札紙幣にも肖像が採用されたことで、いま再び注目が高まっている人物です。
本書は、津田塾大学の倉庫から後年に見つかった津田と留学先の里親アデリン・ランマンとの往復書簡を手がかりに、津田の人物像や思想を解き明かしていこうとする1冊です。
アメリカ留学からの帰国直後の津田の手紙には、日本人の家族や友人たちが、海外の文化や風土に染まった津田を好奇と尊敬の目で見てくるさまがありありと書かれています。大庭は、
“わたしは二十年ほど前、日本人が戦後という言葉から脱け出そうとする頃、日本を出て、十一年のアメリカ滞在の後、高度成長のさ中にある日本に帰って来たときのことを梅子の手紙に重ねて思い浮かべている。
軽蔑と好奇心の混ざり合ったじろじろとした眼で頭のてっぺんから爪先まで眺められ、何か言ったりしたりすれば、アメリカにいた人だから仕方がない、といった顔付きで、相手が妙な含み笑いをしたときのことなどを。”
と、津田と自らの姿をところどころで重ねながら、彼女の生き様を紐解いていこうとします。
大庭は津田の手紙を評して、
“それは、歴史書には書かれていない日本の近代、明治の内面、いや当時、そこに生きていた人びとの姿と心が綾になって織り出される、梅子という女性の肉眼を通して映し出されたセピア色のフィルム、といった趣があった。”
と綴っています。津田が成し遂げた偉業が理解できるのはもちろん、ひとりの少女、そして大人の女性として明治の時代を生きていた津田の内面を覗くことのできる、資料的価値も高い1冊です。
おわりに
『三匹の蟹』でセンセーショナルなデビューを果たして以来、芥川賞以外にも野間文芸賞や谷崎潤一郎賞などさまざまな文学賞を受賞し、生涯に渡って精力的な執筆活動を続けた作家・大庭みな子。
その先駆性は当時から文学界の注目の的でしたが、彼女の作品が持つ奇想・幻想の魅力や、抑圧から解放された女性の描き方は、現代の私たちの目にも決して色あせては見えないはずです。今回ご紹介した4冊の本を手がかりに、その唯一無二の魅力を味わってみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2022/05/02)

