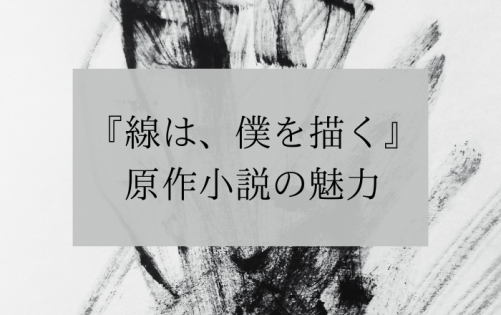【横浜流星主演で映画化】青春小説『線は、僕を描く』の魅力
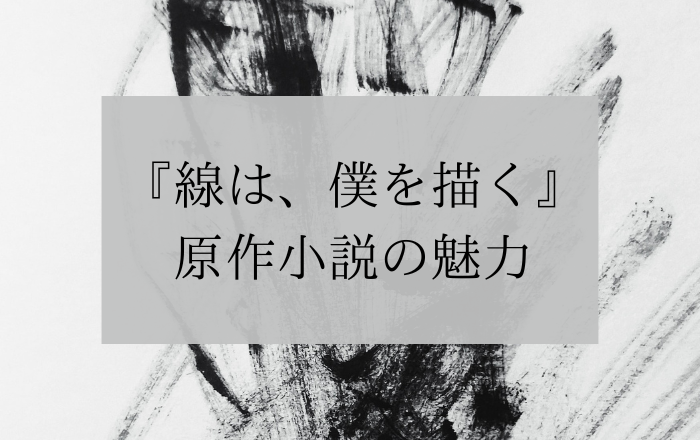
孤独を抱えた青年が“白と黒の芸術”である水墨画に出合い、徐々にその心を癒やしてゆく青春小説『線は、僕を描く』(砥上裕將作)。本作は人気俳優の横浜流星主演で映画化され、2022年10月21日から全国公開されます。映画化をきっかけに本作を読んでみたくなった方に向け、『線は、僕を描く』のあらすじと読みどころを紹介します。
水墨画の世界に足を踏み入れたひとりの青年の成長を描く青春小説、『線は、僕を描く』。本作は、画家・
『線は、僕を描く』は、水墨画という多くの人にとって馴染みが薄いであろう世界を鮮やかに描き出し、発表直後から話題を集めた作品です。2020年には第17回本屋大賞の候補作となり、コミック化(作画・堀内厚徳)もされました。
そんな『線は、僕を描く』が2022年、小泉徳宏監督で映画化され、10月21日から全国公開されます。人気俳優の横浜流星主演ということもあり、本作はいま、一層注目されています。
今回は、そんな『線は、僕を描く』のあらすじと読みどころを詳しく紹介します。
【『線は、僕を描く』のあらすじ】“水墨画”の世界に魅入られていく青年の成長を描く

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4065137594/
本作の主人公は、大学1年生の青山霜介。高校時代に交通事故で両親を失った霜介はそれ以来、“真っ白な部屋に自分だけがいる”かのような、深い喪失感を抱えて生きていました。両親の死をきっかけに無口で無気力な性格になってしまった霜介は、一時は食事もほとんどとれないほど衰弱していましたが、最低限の生活を送ることができる程度には回復し、大学に通い始めたばかりでした。
そんな彼はある日、大学で唯一できた友人・古前から、“展示会の飾りつけ”のアルバイトをしないかと誘われます。詳しい内容を聞かず会場に行ってみると、それは展示会用の特大パネルを運ぶという、かなりの力仕事でした。同級生たちはその仕事の過酷さに次々と逃げ出してしまいますが、霜介は持ち前の責任感の強さから逃げ出すことができず、どうにかパネル運びをこなします。
パネル運びが一段落したとき、霜介は、会場の控室に入っていこうとする小柄な老人に出会います。「一緒に展示を見ていかないか」と彼に誘われ、作品が運び込まれたあとの会場を見た霜介は、自分が運んでいたパネルが、水墨画を展示するためのものであったことに気づくのでした。
僕がとくに目を惹かれたのは、花や草木の絵だった。
真っ白い画面の中に封じ込められた花や草木は、ほかには何もないからこそ花のみずみずしさや、草木の生命感を表しているように思えた。
シンプルなものにどうしてこんなにも目が留まるのだろう、と自分でも不思議なほど余白の多い簡単そうな絵に惹かれた。
生まれて初めて水墨画を鑑賞した霜介は強く心を動かされ、老人に尋ねられるがまま、率直に絵の感想を述べていきます。その感想を聞いた老人は“プロの水墨画家顔負けの凄い目を持っている”と霜介に告げ、突如、霜介を自分の内弟子にしたいと言い出しました。なんと彼は、美術に関心のない者でもその名を聞いたことがあるような有名水墨画家、篠田湖山だったのです。
突然の申し出に戸惑う霜介。しかし霜介は湖山やその兄弟子たちから水墨画を学ぶにつれ、白と黒だけで紡がれる世界に魅了されていきます。霜介は湖山のもとで水墨画の技術を会得することを決意し、技術を磨いていくのでした。
【作品の魅力1】丁寧な描写を通じ、“水墨画”の世界に触れられる

本作の第一の魅力はやはり、水墨画という、多くの読者にとって馴染みがないであろう芸術の歴史や背景、技術習得の難しさを非常に丁寧かつ生き生きと描いている点にあります。
主人公の霜介は、湖山に出会った当初、日本画家といえば葛飾北斎や雪舟しか知らない程度の美術初心者でした。彼の視点で描かれる水墨画への感想は、初心者ならではの戸惑いと驚きに満ちています。
立ち止まったのは、大きく華麗な薔薇の絵だった。五輪の薔薇が上から下に並んでいる掛け軸だ。
墨一色で描かれた花びらの中には漆の光のような微妙なグラデーションがあり、花は黒光りしていた。対照的に葉っぱは薄墨で繊細に描かれており、漆黒の花を際立たせていた。花と葉の濃度の微妙な違いが、架空の色彩を絵の中に生んでいるのだ。
僕が驚いたのは、その真っ黒なはずの花が真っ赤に見えたことだ。
燃えるような赤をその黒は感じさせた。なぜそう感じるのかは、まったく分からなかった。ただ、この絵は白のためだけでなく、いまある赤のためだけに描かれたような気がした。
本作の著者・砥上は、実際に自身も大学時代に水墨画に出合い、水墨画の大家である絵師との交流を通じてその世界へ入っていったと過去のインタビューなどで語っています。水墨画に関する事前知識がない読者でも、霜介と同じ視点に立ってその面白さを少しずつ知っていくことができる構成となっています。
【作品の魅力2】秀才絵師と主人公との距離が近づいていく描写のみずみずしさ

本作は芸術をテーマにした作品であると同時に、優れた青春恋愛小説でもあります。
主人公の霜介は、初めて湖山に会った水墨画の展覧会で、パネル搬入のリーダーを務めていた湖山の弟子・西濱に、
「たぶん、アイドルみたいなものすごい美少女が会場に登場するけれど、サインとか求めたらだめだよ? あと話しかけられても、口説いたらだめ。すっごく、怖いから」
と告げられます。午後、実際に会場に現れたその美少女・
振り袖の華やかさに劣らない煌びやかな容姿で、そこにいるだけでその空間が価値を生む宝石のような存在だ。僕と同じくらいの年なのだろうか。いや、美しすぎて年齢もよく分からない。
僕はさっきからいぶかしげな目で睨まれている。西濱さんが言っていた怖い美女というのはこの人のことなのだ。確かに恐ろしい。美しさというのはある種の『凄み』なのだと僕はそのとき知った。男性にとってのケンカの強さみたいなものかもしれない。腕っぷしの強そうな男にやたらと話しかけないことと同じで、ふだんなら間違っても声を掛けない。
千瑛は、湖山に「内弟子にしようと思う」と名指しされた霜介に苛立ちを募らせ、「こんなひょろひょろで弱っちそうな人、まったく気に入らない」と言い放ちます。さらには、湖山が主催している水墨画の賞・湖山賞の審査でもし自分が霜介に負けたら、門派を去ると宣戦布告します。
はじめは最悪かのように見えたふたりの関係でしたが、燃えるような絵を描く千瑛のひたむきさに、霜介は次第に強い信頼感を抱いていきます。霜介と千瑛の関係性の深まりも、本作の大きな読みどころです。
【作品の魅力3】一度は“真っ白”になってしまった主人公の孤独と回復を描く

本作は、若い絵師たちの成長だけでなく、孤独に慣れた霜介の心が徐々に癒えてゆくまでを丁寧に描く作品でもあります。
前述の通り、霜介は両親を事故で亡くして以来、自分ひとりだけが“真っ白な部屋”にいるかのような喪失感を抱えながら暮らしていました。
現実から逃げ出すように眠りについた。しばらくすると、僕は何もない真っ白な部屋の中にいた。入り口も出口も、おまけに遠近感さえない。真っ白な部屋だ。(中略)
いつもの場所だ。この部屋で僕はずっと独りでいる。
しかし、霜介の強い孤独を象徴するような“真っ白”という感覚はそのまま、彼が白と黒の線のみによって構成される水墨画に魅了された理由でもありました。千瑛をはじめとする若い絵師たちや湖山との関わりを通じ、霜介はやがて、水墨画とは命そのものを描く芸術だという真理にたどり着きます。
たった一輪の菊でさえ、もう二度と同じ菊に巡り合うことはないのだ。たった一瞬ここにあって二度と巡り合うこともなく、枯れて、失われていく。あるとき、ふいにそこにいて、次の瞬間には引き留めることさえできずに消えていく。僕はそのことを誰よりもよく知っているはずだった。命の輝きと陰りが、一輪の花の中にはそのまま現れているのだ。
僕の心が、小さな感動の前に立ち止まった。
僕が生まれたことと、僕が見送った命と、僕が思っているこの束の間の時間の中で、僕にできることは、ただこうして愛おしむことだけのようにも思えた。
自らの命や、森羅万象の命そのものに触れようとする想いが絵に換わったもの、それが水墨画だ。
目の前にあるものの姿かたちを精巧に描くのではなく、そのものの命が燃えていた一瞬を切り取って絵画にする芸術こそが水墨画なのだという境地に至った霜介は、それまで自分を縛りつけていた孤独から一歩外へ足を踏み出し、力強い“線”を描いていくための勇気を持ち始めます。霜介のダイナミックな変化も、本作を彩る大きな魅力です。
おわりに
水墨画をテーマにした小説と聞くと、難解で玄人好みの文芸作品を思い浮かべる方も少なくないかもしれません。しかし本作は、孤独を抱えた青年の成長という王道のストーリーをシンプルで美しい文体で描き切った、子どもから大人までが楽しめる小説となっています。
水墨画に関心がある方はもちろん、みずみずしい青春小説を読みたい方にも一推しの作品です。映画化を機に原作小説が気になったという方もぜひ、気軽な気持ちで手にとってみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2022/10/21)