あの『007』シリーズ原作者は元スパイ!? イギリスの華麗なるスパイ小説を大特集!

『007』シリーズの原作者であるイアン・フレミングや、『第三の男』で知られるグレアム・グリーンなど、イギリスの有名スパイ小説家には戦時中、実際に諜報活動に従事した作家がたくさんいることをご存知ですか?この記事では、そんな華麗なるスパイの世界を時代背景とともに解説します!
ヘアスタイルからつま先まで、ビシッときまったスーツ姿に、そこから繰り出される隠し道具の数々。そのクールな所作から、女性にはモテモテ……。
この人物像を聞いて、イギリスの生んだ名物スパイ、ジェイムズ・ボンドの姿を思い浮かべた人は多いはず。
2012年のロンドンオリンピック開幕式では、白のスーツを身にまとい、エリザベス女王とスカイダイビングをするなどというド派手な演出でも話題を呼びましたが、イギリスが生んだスパイキャラクターはジェイムズ・ボンドだけではありません。
2014年公開の映画『キングスマン』は、表向きは高級テーラーでありながらも、どこの国にも属さない最強スパイ機関を舞台にしています。亡き父親がスパイだったことを知った主人公が自らも一人前のエージェントを目指し、成長していく姿を描いたこの作品は続編製作が決定するなど多くのファンからの支持を獲得しています。
実はこの「スパイ」という職業、イギリスでは「小説家」という職業とも深ーい関係があったことをご存知ですか? 今回は、スパイだった小説家や、名作スパイ小説の紹介を通じて、20世紀のイギリスにおける「スパイ像」に迫ります!
あの小説家も元スパイ!?オックスフォード、ケンブリッジが生んだ俊英たち

英語では「諜報機関・諜報部員」のことを「インテリジェンス(intelligence=知性)」と呼ぶことからも明らかな通り、優れた知性の持ち主でない限りスパイ活動は務まりません。実際、現代に至るまで、イギリスの諜報機関である「MI6(Military Intelligence 6/軍事情報活動第6部)」で働く諜報部員は、オックスフォード大学やケンブリッジ大学などの卒業生がそのほとんどを占めています。
そして、銃前・銃後での総力戦が繰り広げられた20世紀の2つの世界大戦では、小説家たちもトリッキーな働きをしていました。古くは第一次世界大戦の際に、作家であるアーノルド・ベネットが対フランス用のプロパガンダ部隊の責任者として招聘され、アーサー・コナン・ドイルやラドヤード・キプリングなどの同時代を代表する大作家たちもまた宣伝印刷物の発行を通じてプロパガンダ活動の一端を担うなど、〈戦争〉をめぐる情報統制に従事したのです。
▶︎過去記事:『ジャングル・ブック』が映画化!原作者のラドヤード・キプリングってどんな人?

第一次世界大戦中、対独戦争の遂行のために国債購入を呼びかけるプロパガンダ・ポスター(1915)
小説家と言えば、「嘘をつくのが仕事」と言っても過言ではありません。プロパガンダや工作活動を通じた情報操作を行うには、彼らほど適任の人物はいないでしょう。元スパイの小説家と言えば、 『007』シリーズの原作者イアン・フレミングが有名ですが、その他にも『月と6ペンス』などの代表作で知られるサマセット・モームや、後に紹介する『第三の男』のグレアム・グリーン、女流作家のミュリエル・スパークなども世界大戦の折に諜報活動に従事した経歴を持つことで知られています。
実際、ミュリエル・スパークの短編集、『バン、バン! はい死んだ』の木村政則氏によるあとがきには、次のような驚きのエピソードが紹介されています。
スパークは、対ドイツ情報操作「ブラック・プロパガンダ」に携わった。ドイツの最新情報に基づいてまことしやかなニュースを作り、それをあたかもドイツの放送であるかのように流す。ドイツ人の士気の低下を狙った心理戦である。スパークの仕事は、「スクランブラー」と呼ばれる緑色の特殊な電話機を通じて得たドイツの情報をタイプにまとめて、指揮官のセフトン・デルマーに渡すことだった。
ミュリエル・スパーク『バン、バン! はい死んだ』(木村政則訳)
訳者あとがきより
「お話」を創作し、流通させ、信じ込ませる。この一連の仕事が、創作活動にも活かされたことは想像に難くありません。
「スパイ」はエリートの仕事
なぜ、イギリスにはスパイだった作家がこれほどまでに沢山いるのでしょうか? その背景には、イギリスの知的エリート階級にとって、語学力や文章表現力、頭脳労働が評価される諜報部員という仕事は、有事の際に戦闘に関わらなくてすむため人気だったという理由もあるようです。
実際、第二次世界大戦前から1950年代にかけてのケンブリッジには、「ケンブリッジ・ファイヴ」と呼ばれる旧ソ連の二重スパイ集団が実在し、イギリスの国営放送であるBBCや、外務省、さらには王室顧問などの錚々たる地位で暗躍していたことが発覚したことでイギリス社会に大きなショックを呼びました。
このケンブリッジ・ファイヴのうちの一人であるガイ・バージェスの青春時代を題材にした映画『アナザー・カントリー』は、同性愛者であることによってエリートコースの梯子を外された若者が、世界を騙して生きることを決意するまでの経緯をルパート・エヴェレットの妖艶な魅力で実写化した傑作。知的エリート階級からスパイになり、さらには祖国を裏切るに至るまでのストーリーには、20世紀前半のイギリス特有の時代状況が関わっていることがわかる映画になっています。
これだけは読んでおきたい!入門編にぴったりのスパイ小説5選
イアン・フレミング『カジノ・ロワイヤル』(1953)
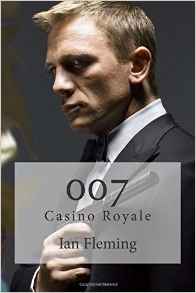
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/1512398314
『007』シリーズといえば、やはり映画のイメージが強いことでしょう。ジェームズ・ボンドを演じるためにはスーツを着こなし、スタイリッシュなアクションを決めることを求められますが、ショーン・コネリーやダニエル・クレイグなど、演じる俳優は変わっても、ファンからは常に愛される存在であることに変わりはありません。 そんな『007』の原作者であるイアン・フレミングですが、彼自身がハンサム・ガイであり、イギリスの名門・イートン校を不純異性交遊に問われて退学させられたという「プレイボーイ」な一面も持ち合わせていたのです。
ジャーナリストとしてキャリアをスタートしたフレミングはモスクワに特派員として派遣され、第二次世界大戦の折には海軍省で諜報活動に従事。1940年にフランスが降伏した際にはアルバニア国王などを含む避難民を数々の宝石類とともに脱出させる大作戦を成功させるなど、まさにジェームズ・ボンドそのものと言っていいほどの活躍を残しています。
秘密道具の使い方から暗号解釈、さらには爆発物の取り扱いに至るまで、スパイ実務を通じてしか得られないノウハウを蓄積したフレミングは戦後、「あらゆるスパイ小説にとどめを刺す」べく、シリーズ第1作となる『カジノ・ロワイヤル』を執筆します。
この初版がイギリス本国では1ヶ月の間に売り切れ、その後、第2版、第3版と飛ぶように版を重ねるうちにアメリカ上陸まで果たすなど、スパイ小説ブームの火付け役となりました。
1962年に公開された映画化第1作の『007 ドクター・ノオ』は米ソの宇宙開発競争など時事性を帯びた作品であり、こちらも人気を博しました。人々の注目を集めるエンタメ要素に溢れた007シリーズは、次作の公開に向けファンの間では内容の予想が早くも始まるなど、今後も注目を集め続けるシリーズといえます。
ジョン・バカン『三十九階段』(1915)
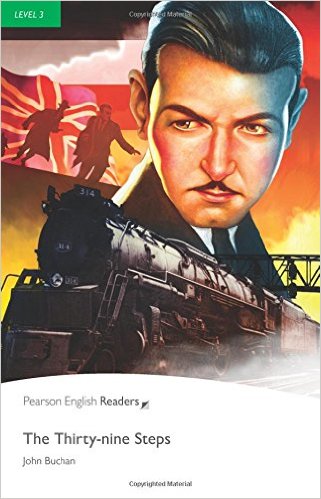
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/1405862343
そんなフレミングの青春時代に大きな影響を与えた作家が、20世紀前半のイギリスにスパイ小説ブームを巻き起こしたジョン・バカンです。秘書として政治キャリアをスタートさせた傍ら、著作活動も行なっていたバカンは、第1次世界大戦が勃発した際には『タイムズ』紙のフランス特派員としてイギリスの戦果をプロパガンダ的に宣伝する任務に就きました。
その後、1935年にはカナダ総督を務めるまで、政治エリートとしてのキャリアを歩み続けたバカンでしたが、彼の最初の大ヒット作となったのがアルフレッド・ヒッチコック監督による映画『三十九夜』の元ともなったスパイ小説、『三十九階段』です。
バカン自身の華々しい政治キャリアと、その八面六臂の貢献ぶりとは裏腹に、この小説の主人公として登場するスパイ、リチャード・ハネイは「大英帝国でいちばん退屈している男」として描かれています。ロンドンという大都会で退屈な日常に
そんなハネイは、ひょんなことをきっかけに大掛かりな陰謀事件に巻き込まれ、生死を分ける身の危険にさらされることによって「退屈病」からの復活を遂げます。『三十九階段』を金字塔とする通俗的な娯楽小説・冒険小説のスタイルを、バカン自身は“ショッカー”と呼びましたが、作中で愛国者として活躍するハネイのキャラクター造形には、バカン自身の国際政治への嗅覚と同時に、プロパガンダを通じて大衆に刺激と高揚感を与えるという戦略性が込められていたのかもしれません。
グレアム・グリーン『第三の男』(1949)
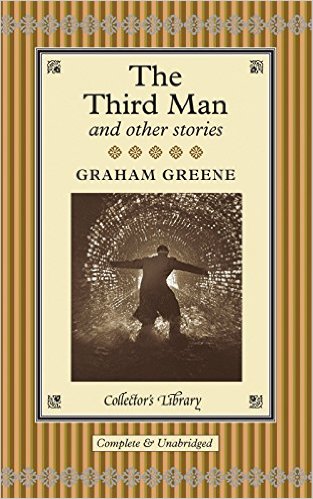
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/190736031X
スパイ出身の大作家と言えば、第二次世界大戦の際にMI6の正式メンバーとなったグレアム・グリーンを忘れてはいけません。学生時代からバカンのスパイ小説に心酔し、オックスフォード在籍時にはドイツ人伯爵を相手どった〈二重スパイごっこ〉に興じるなど、若くして諜報活動に対して並々ならぬ関心を抱いていたグリーンは、MI6に採用されてからはアフリカでの工作活動に従事するなど、本格的なスパイ活動にのめり込んでいきます。
戦後、グリーンはスパイとしての実体験を『恐怖省』などの創作に活かすことになりますが、諜報活動に従事していたからこそ持つ想像力がもっとも縦横無尽に発揮された作品といえば、『第三の男』を差し置いて他にないでしょう。映画脚本となることを前提に物語が作られたこの小説では、友人ハリーに招かれて第二次世界大戦後のウィーンを訪れた作家、ロロ・マーティンズが、友人の死の真相を追ううちに、大きな陰謀にたどり着く様がイギリス人刑事の視点から描かれます。
ソ連、アメリカ、フランス、イギリスによる分割統治を受けていたオーストリアの複雑な政治状況や、真相究明を阻む様々な妨害活動などのリアルさは、スパイとして国際政治の裏舞台で暗躍したグリーンだからこそ獲得できた要素でしょう。
ちなみに、『1984年』『動物農場』などで知られるジョージ・オーウェルといった同世代作家と同じく、青春時代にソビエトの共産主義に憧れたグリーンは、その生涯を通じて親共産主義・反米の立場を貫きました。一口に「スパイ小説」と言っても、一般的にイアン・フレミングは大衆小説家、グリーンは純文学の作家として分類されますが、そうした政治観もまた同時代のフレミングとは大きく異なっているポイントです。
スパイ小説は国際政治を舞台にしているだけに、作家自身の政治観を読み比べてみるのも面白いかもしれませんね。
ジョセフ・コンラッド『密偵』(1907)
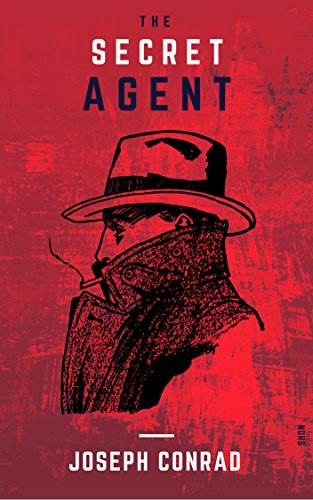
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01HJ116SM
作家としてのキャリアを開始させる前には船乗りだったジョセフ・コンラッドは、『闇の奥』や『ロード・ジム』など、多くの海洋小説によって文学史に名を残した文豪です。そんなコンラッドは、南米の架空の小国を舞台にした『ノストローモ』などの政治的フィクションも執筆していますが、彼の同時代の文化状況・政治状況を広く見渡す視野が、世紀末の大都市・ロンドンを舞台に集約されたのが、この『密偵』です。
「密偵」と言っても、危険分子の集団に潜入捜査するスパイたちの活躍が描かれる小説ではなく、1894年のグリニッジ天文台爆破事件をモデルに執筆されたこの作品は、テロに直接的・間接的に携わったアナーキストたちの心理描写に力点を置いています。
その読みどころは何と言っても、知的障害を抱えた息子をテロの実行メンバーとした父親、マッドサイエンティスト的な爆弾魔である「教授」など、一癖も二癖もあるキャラクターたちの〈エゴ〉と〈自己正当化〉の数々がもたらす大きな悲劇。
この『密偵』を通じて、19世紀末から20世紀初頭にかけてのイギリスにおけるアナーキストへの恐怖、海外から侵入する「見えざる敵」に対しての不安感をうかがい知ることができますが、コンラッド自身もまた、ポーランドから政治亡命した作家であったことを考えあわせれば、さらに深い読書体験が味わえるかもしれません。
G. K. チェスタトン『木曜日だった男』(1905)
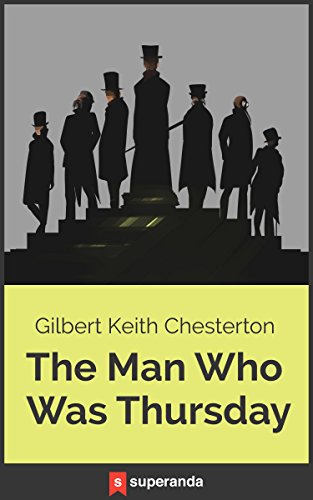
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZRN5FW
『ブラウン神父』シリーズの作者であり、イギリス推理作家クラブ(The Detection Club)の初代会長を務めるなど、ミステリー作家としても知られるG. K. チェスタトンは、イギリスの保守主義を代表する論者としても名を馳せた人物。
そんなチェスタトンが書いた『木曜日だった男』ですが、タイトルもさながら、内容はもっとはちゃめちゃなスパイ小説です。「日曜日(Sunday)」というコードネームの議長が率いる過激なアナーキストたちの秘密結社への潜入調査を任されることになった詩人が、「木曜日(Thursday)」という名を組織から与えられた後、それぞれ曜日の名を冠した結社メンバーたちと渡りあうことになるのだが……というのが全体の筋書き。しかしその展開は、謎が謎を呼び、未解決のクエスチョンマークがさらに大きくなっていくようで、ページをめくる読者は皆、狐につままれたような気分に陥ることでしょう。
さて、保守主義者であるチェスタトンが国家転覆を企む「アナーキスト」の暗躍する小説を描くとなれば、通俗的なステレオタイプに基づいた、いかにも“危険人物”然としたキャラクターが登場すると思われるかもしれません。しかし、ラストシーンでは“まさかの人情オチ!?”とでも言いたくなるような暖かな視線がアナーキストに注がれることになるのです。これは、「芸術家は総じてアナーキストである」という19世紀末イギリスに流布した通念と、20世紀の犯罪小説ブームの両方を逆手にとったチェスタトン流のパロディーだったのかもしれません。
全体的にナンセンスかつドタバタ劇的なユーモアに溢れる『木曜日だった男』。哲学的でもあり、宗教的でもあり、芸術論のようでもある記述が要所要所に混じることによって、文章家・チェスタトンの計り知れない力量と、イギリス小説を読む愉しみの両方を味わえる大傑作となっています。一味ちがうスパイ小説を読みたいあなたは是非ご一読を!
まとめ
イギリス文学とスパイとの深い関係について紹介してきましたが、お楽しみいただけましたでしょうか?
スパイ小説が現実の国際政治と強いつながりを持っているように、それを執筆した小説家もまた、同時代の政治状況と無縁ではありません。皆さんも、小説を読む際にはその作品が発表された当時の時代背景や、作家自身のエピソードについても掘り下げてみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2016/09/28)

