国際的な視野から地球の未来を描く 多和田葉子おすすめ4選

1993年、『犬婿入り』で第108回芥川賞を受賞した多和田葉子は、長年ドイツに住み、日独2ヵ国語で小説を発表し、世界的に評価の高い作家です。そんな著者のおすすめ作品を紹介します。
『雪の練習生』東西冷戦時代、人間に蹂躙 されたホッキョクグマの生の哀しみと愛おしさ

https://www.amazon.co.jp/dp/4101255814
本作の語り手は、ホッキョクグマの「わたし」。旧ソ連で生まれ、かつては共産主義国の威信をかけたサーカス団で、玉や三輪車を乗りこなす花形団員でしたが、腰をいためて引退しました。本来なら、用済みの動物はすぐに射殺されるところですが、そのまま生かされ、今はサーカス団の事務方の手伝いをしています。「わたし」は、自分が現役時代、いかに調教されたかという自叙伝を書きます。自叙伝は評判になり、海外でも翻訳されます。
(冷戦)当時、サーカスで動物を使うことは人権侵害になるので、サーカスに動物を出させない運動が西側では盛り上がっていた。特に社会主義圏では動物が迫害されていると信じられていた。いきり立つ西側のジャーナリストたちは、わたしの書いた文章を虐待の証拠として取り上げた。
図らずも、母国にとって不利益な情報を提供してしまった「わたし」は、ソ連にいられず、西ドイツに亡命します。しかし、そこでもモスクワ出身と言うと一部の人から迫害されたため、さらにカナダへ逃れ、当地で娘のホッキョクグマ「トスカ」を出産します。
曲芸が上手なトスカは、やがて東ドイツの国営サーカス団に入団します。ある時、東側のソ連の視察団が訪ねて来ることになり、ソ連の影響下にある東ドイツでは、トスカが西側のカナダ産であることを憂慮しますが、トスカにしてみれば、それは些末なことでした。
そもそもホッキョクグマにナショナル・アイデンティティはない。グリーンランドで妊娠し、カナダで出産、ソ連で育児というのが常識で、国籍もパスポートもなく、亡命さえしないで、いつの間にか国境を越えてしまう。
やがて、トスカは息子「クヌート」を出産し、クヌートは西ドイツの動物園に引き取られて人間の手で育てられます。西ドイツの人達は、「トスカは社会主義国で過酷な調教を受けたストレスで、育児放棄した」と、まことしやかに言いますが、トスカにすれば、それは的外れ。「強い子に育ってほしかったから、あえて別の動物のもとへ里子に出したのだ。人間の思い込みを、勝手に動物に投影されるのは迷惑だ」と内心では思っています。
ベルリンの壁崩壊後のドイツで、クヌートはその愛らしい姿から動物園のマスコットにされ、地球温暖化防止のための環境大使に任命されます。人間たちは、「地球温暖化が進めば、北極の氷が解けて、ホッキョクグマの数が減少するから、そのために一役買ってほしい」と言いますが、クヌートは皮肉にも故郷の北極を見たことがないのです。
人間のエゴに振り回される動物の姿は、そのまま、国策に翻弄される民衆の姿の暗喩とも読めます。事実、著者は、「東西ドイツが統一された今なお、東と西の間には見えない境界線が残っている」と述べています。(2021年11月25日収録の芥川賞作家・石沢麻依との対談「ドイツと日本のはざまにて」より)
『献灯使 』2度目の原発事故が起きた近未来の日本の姿とは
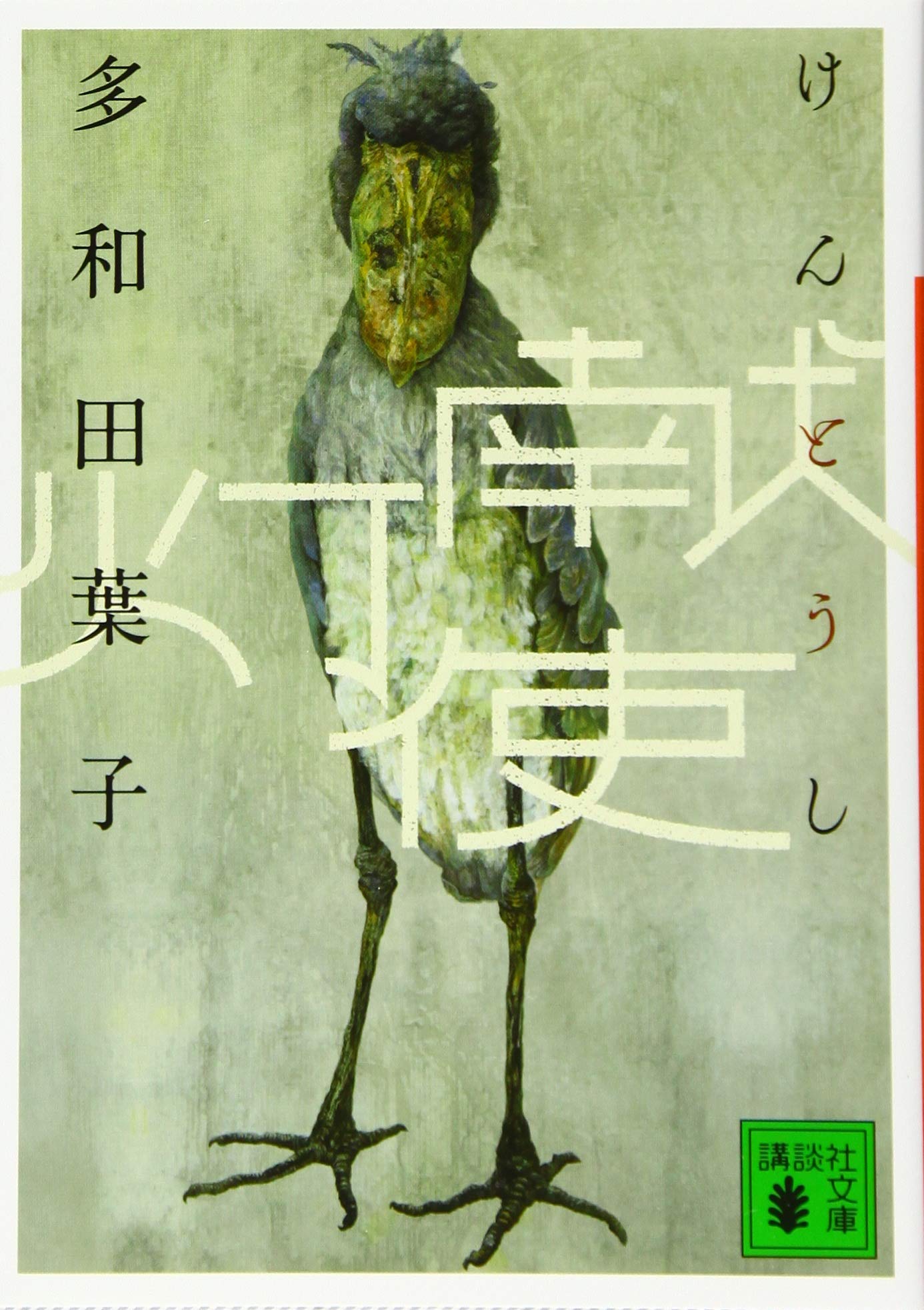
https://www.amazon.co.jp/dp/406293728X/
舞台は、そう遠くない未来の日本。太平洋大地震という巨大地震が首都近郊を襲い、2011年の東日本大震災の福島の原発事故に続き、2度目の原発事故が起こったという設定です。「福島の事故のとき、原発を止めておけばよかったのに、なぜ再稼働したのか」と、日本に批判的な諸外国は、放射能の汚染を恐れ、日本との交易や行き来を忌避してしまい、日本は鎖国状態になっています。日本に密航した海外の冒険家は、本国で、日本の惨状を以下のように報告します。
2011年、福島で被曝した当時、百歳を越えていた人たちは今も健在で1人も亡くなっていない。どうやら死ぬ能力を放射性物質によって奪われてしまったようなのである。2011年に子供だった人たちは次々に病気になり、働くことができないだけでなく、介護が必要なのだ。毎日浴びる放射能は微量でも、細胞が活発に分裂していけば、あっという間に百倍、千倍に増えてしまう。だから年が若ければ若いほど危険なのだ。
問題なのは、このことが日本人には一切知らされていないこと。財政破綻のため民営化された新政府は、国民にとって不都合な真実を隠蔽し、日本人が海外に渡航することや、海外の人と情報のやりとりすることを禁止しています。
都内の仮設住宅で105歳の曽祖父と暮らす「無名」と呼ばれる10代の少年は、小さい頃から虚弱体質です。歯が脆いので固い物は咀嚼できず、胃腸が弱いので肉や魚を消化できません。学校まで歩く体力がないので、車いすが手放せず、すでに白髪頭。曽祖父はひ孫がなぜこうした状態なのかと涙を流します。
そんな中、子どもたちの体調の異変を不審に思った大人たちは、極秘で組織を発足させます。それは、無名たちを「遣唐使」ならぬ「献灯使」として、海外の国際医療センターに被験者として送り出し、真相を解明してもらう組織でした。
本作は、2018年、全米図書賞(翻訳文学部門)を受賞していますが、著者は、「近未来のことを書いたつもりではなく、自分としてはすでに日本で起こり始めていることを書いた」と述べています。(『群像』2017年10月号より)
装画と挿画は、日本画家の堀江
『地球にちりばめられて』日本も日本語も消滅した遠い未来。元日本人はいかに生きるか

https://www.amazon.co.jp/dp/4065238153/
本作の時代設定は、はるか遠い未来。Hirukoという名の日本人女性は、スウェーデンに留学中に、何らかの理由で日本が消滅したと知らされ、母国へ帰れなくなります。ビザの関係で一国に長く留まることができないため、スカンジナビア地域を流浪し、現在はデンマークで就労しています。
わたしは、仕事にありつけたおかげで、ビザをもらってひとまずはデンマークに滞在することができる。子どもの頃はテレビで「不法滞在の外国人」と聞くと、遠い国の悪い人の話だという気がしていたけれど、今は、わたし自身がそうなってしまう。よく考えてみると、地球人なのだから、地上に違法滞在するということはありえない。それなのになぜ、不法滞在する人間が毎年増えていくのだろう。
短期間で国から国への移動を繰り返したHirukoは、それぞれの国の言語を習得する余裕がなかったため、スカンジナビア地域全域で汎用的に用いることの出来る言語「パンスカ」(
ヨーロッパで、日本人の同胞を探しているHirukoは、クヌートの協力も得て、テンゾ(典座)というあだ名で呼ばれている鮨職人を探し出し、久しぶりに日本語で話します。しかし、テンゾは、本名はナヌークと言い、グリーンランド出身のエスキモーでした。日本人もエスキモーも生魚が好きという理由で、日本人と間違われ、ドイツの鮨屋にスカウトされていたのです。ナヌーク自身、日本人だという誤解を解くのも面倒で、また、日本語を習得して日本人のふりをすることで、第2の人格を手に入れたようで、それが楽しかったと弁解します。しかし、そんなことを聞かされても、Hirukoは落胆しません。なぜなら、Hirukoの本望は、日本人と出会うことというよりむしろ、日本語が話せる人と出会い、母語での会話を楽しむことだったからです。
ネイティブ・スピーカーという考え方は幼稚だ。母語は生まれた時から脳に埋め込まれていると信じている人もまだいる。そんなのは、科学の隠れ蓑さえ着ていない迷信だ。ネイティブは語彙が広いと思っている人もいる。しかし日常の忙しさに追われて、決まり切ったことしか言わなくなったネイティブと、別の言語からの翻訳の苦労を重ねる中で常に新しい言葉を探している非ネイティブと、どちらの語彙が本当に広いだろうか。
若くして渡独し、ドイツ語を日本語と同等に自由に操れるまで学び、ドイツ語でも作品を発表して、2005年、ドイツ語と国際文化関係で傑出した貢献を行った外国人に授与する勲章「ゲーテ・メダル」を受賞した著者の言葉だけに、説得力があります。
Hirukoは、その後、ナヌークから、鮨職人の仲間で日本人と思しきSusanoo(スサノオノミコトを彷彿とさせる)という男性がフランスにいると教えられます。Hirukoは、ついに同郷人と邂逅することができるでしょうか。
『星に仄めかされて』母国とは、母語とは何かを問う果てしない旅
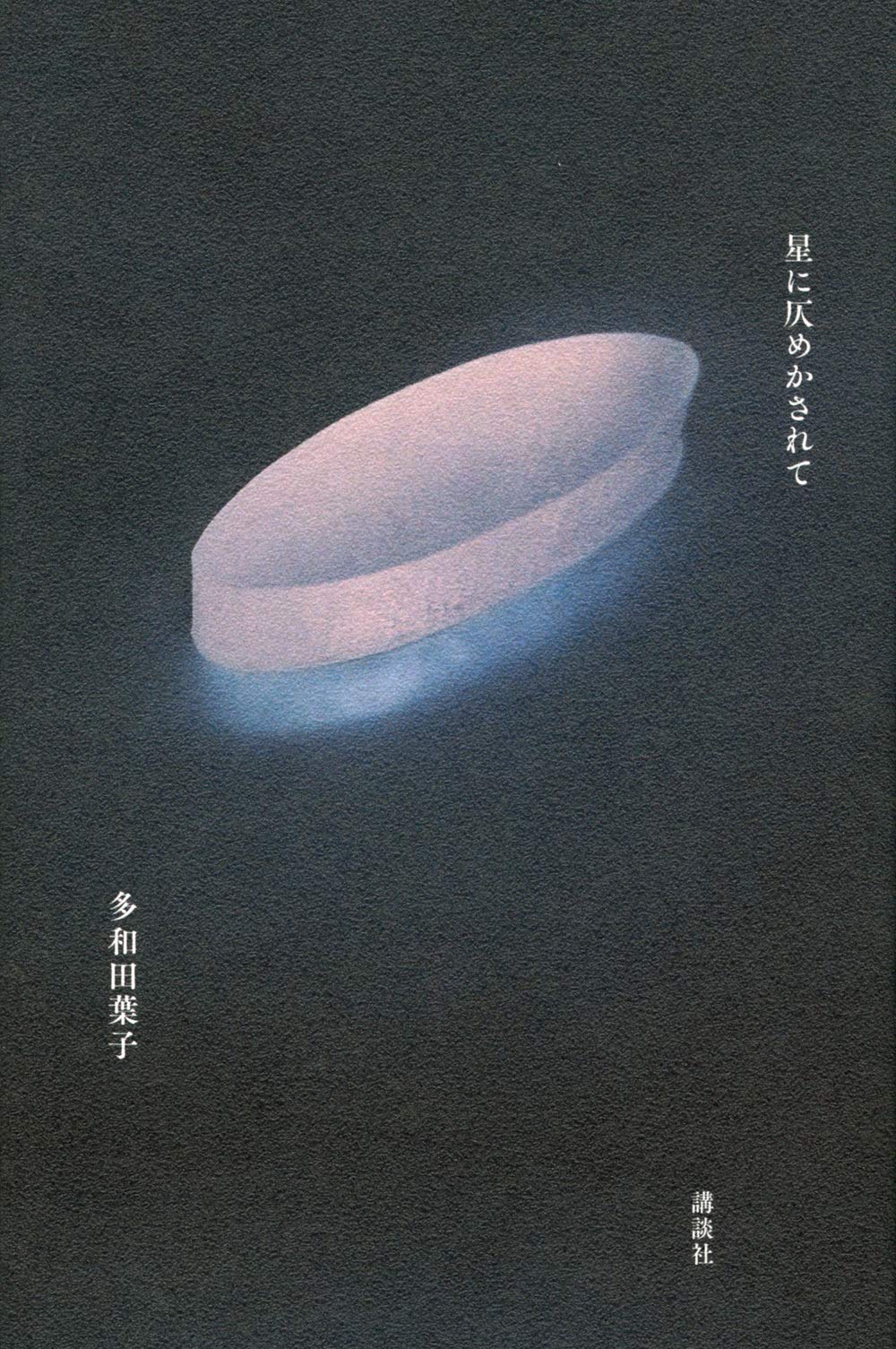
https://www.amazon.co.jp/dp/4065190290/
本作は、『地球にちりばめられて』の続編です。
クヌートやナヌークの協力を得て、Susanooと出会ったHiruko。ところが、Hiruko がSusanooに日本語で話しかけても、彼は何も話しません。彼が失語症になっているのではないかと心配したクヌートは、知り合いの精神科医・ベルマーを紹介します。ベルマーの診断を受けたSusanooは、フランス語なら話しますが、日本語は頑なに話しません。ベルマーの見立てでは、それは失語症ではなく、単に日本語を忘れたか、日本語を拒絶する意図的な沈黙ではないかということでした。クヌートは考えます。
「特にHirukoと話すのを避けているようにも見えるね。(日本語を話すことで)記憶を共有するのが嫌なのかもしれない。故郷について自分だけの物語を持っていて、それを守りたいから黙っているのかもしれない」
実は、Susanooは、「原発銀座」と呼ばれた福井の出身で、原発のPRセンター関連の仕事をする親と折り合いが悪く、高校卒業後に渡欧したという過去があるのでした。皆が心配する中、ベルマーは「そもそも、すでに滅びた国の言語を今さら取り戻したところでとうなるというのだ」と言い放ちます。これに対しては、世界中どこへ行っても同郷人がいるインド出身のアカッシュが以下のように反論します。
「どうせもう一生帰らないんだから、故郷の話なんかする必要ない、と思うかもしれないけれどそうじゃない。帰れないからこそ子供時代の鮮やかなイメージが生きるのに必要なんじゃないかな。こんな駄菓子があったねとか、こんな玩具が流行ったね、とか、たわいもない話でもすごく落ち着くんだ」
アカッシュはまた、Susanooの母国・日本では「忖度」が重んじられたため、場の空気を読み過ぎて、思ったことが言えなくなり、失語症になったのでは、と危惧します。地球人同士だから心配し合うのは当然だ、とも。
一方のHirukoは、日本が消滅したという噂を疑い始めます。日本とヨーロッパが何らかの理由で行き来が遮断されているだけで、本当はまだ日本という国があるかもしれないと信じたいHirukoは、夜空の星座を頼りに、船旅で日本に行くことを思いつきます。その航路の先に果たして日本はあるのでしょうか。
おわりに
『地球にちりばめられて』の中に、「未来をデザインできる時代は終わった」という言葉があります。そう聞くと絶望的な気持ちにもなりますが、多和田葉子はそれをネガティブな意味で用いているのではありません。限りなく予測不可能な未来を、柔軟にたくましく生きる登場人物たちの姿に、読者は励まされるのではないでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2022/07/08)

