採れたて本!【歴史・時代小説#04】
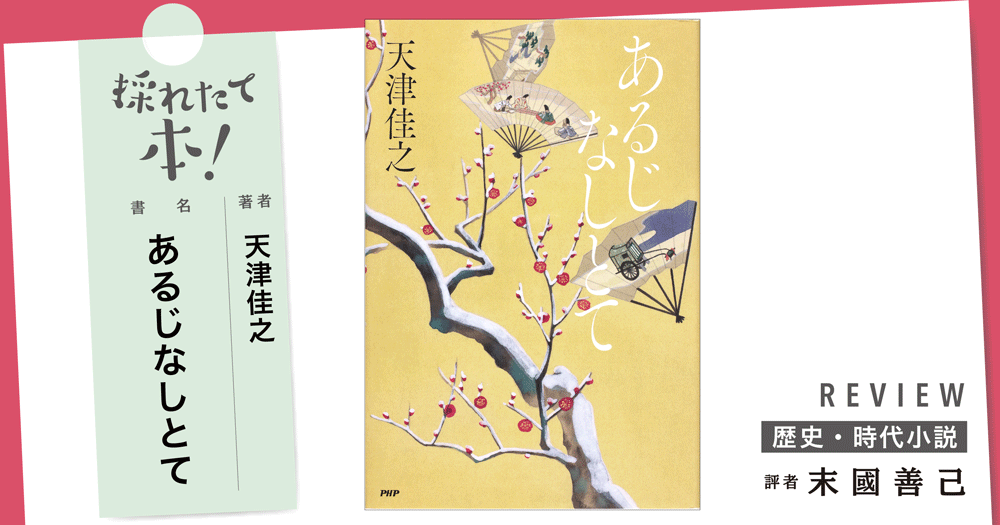
菅原道真は、今も〝学問の神〟として信仰されているだけに、漢詩文集『菅家文草』の編纂や、多くの後進を育てた私塾・菅家廊下などが注目されがちだ。これに対し『あるじなしとて』は、政治家としての道真に着目した異色作である。
八八六年。文人官吏として順調に出世していた道真は、突然、讃岐の国司に任じられる。地方の国司を数年ほど務めると中央に復帰して出世ができるが、道真には左遷としか思えなかった。
讃岐に下向した道真は、前任の藤原保則から引き継ぎを受ける。律令では税によって納める物品が決められていた。保則は、糸、土地の特産物などの「調」が足りなければ、塩、布などで納める「庸」で流用するなどしていたが、法に厳格な道真は保則の手法に疑問を持っていた。しかし土地の豪族に話を聞いた道真は、国が民に口分田を与え、そこから上がる収益で税を払う律令制の基本は既に崩れていることを知る。戸籍の調査が不十分で田を持たない民がいたり、口分田と新たに開拓された私田が分離できないほど入り組んでいたりするのに、規定通りの税を求められる民が困窮していたのだ。
讃岐出身の空海が、水が不足しがちな讃岐のために作った満濃池などを見た道真は、讃岐を浄土に変えようとした空海の理想を受け継ぐため改革に着手する。
讃岐は狭い国ながら米の生産量は高いが、積み重なった財政難が解決しておらず、水の利権を握り権門勢家や大寺社と癒着して私腹を肥やす豪族も多かった。
豊かさと統治の難しさを併せ持つ讃岐への赴任を命じた天皇の真意を考えた道真は、戸籍を基に田を分け与えるのではなく、田の帳簿を作ってそこを誰が管理しているのかを記述するなど新たな徴税システムを考案。中央に復帰し、宇多天皇、醍醐天皇の信任を得た道真は、讃岐での経験を国全体の改革に繋げようとする。だが道真の改革は、地方豪族や中央の権門の既得権を奪うことになり、これが太宰府左遷の原因になってしまう。
現代の日本は税金への不満が高いだけに、税制の原則である公平、中立、簡素に立ち返ろうとした道真が、理想の政治家に思えるのではないだろうか。
ただ本書の魅力は、大きなテーマだけではない。道真が讃岐の国司になったのは四十二歳の時。経済の低迷が続く現代の日本では、子会社への出向や早期退職を迫られる中高年が増えているので、道真の境遇に我が身を重ねる読者も多いはずだ。逆境の中で新たな課題を見つけ、それを活かしてキャリアアップした道真は、何かとバッシングを受けやすい中高年に夢と希望を与えてくれるのである。
〈「STORY BOX」2022年8月号掲載〉





