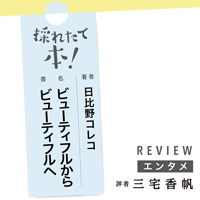採れたて本!【エンタメ#13】

ありのままの自分でいていい居場所、なんて言われると、どんなに優しくて繊細で丁寧な場所なんだろうと思ってしまう自分がいる。しかし本書で描かれた風景は、たしかに主人公にとって「ありのままの自分でいていい居場所」ではあるが、それでいて、適度に乱暴で軽薄でいい加減だ。だがその乱暴さや軽薄さが、読んでいて心地いい。現代を生きる私たちに足りないものってこういう乱暴さなのかもしれない、とすら、思う。
主人公の真野は、コロナ禍で派遣切りに遭い、イタリアンレストランで働くことになる。そのレストランの控え室では、バイト仲間も正社員も混ざりながら日々お喋りが交わされている。真野目線で描かれるレストランでの人間関係は、かなり変わった人々が集まった場なのだった。
激辛料理に挑戦したり、失恋した女の子を慰めるために元彼の家へ明け方に突入したり、クラブで踊るかのように営業後のレストランで踊ったりと、真野の日々は豊かに彩られていく。そのなかで真野は「こんなぬるま湯にずっといていいんだろうか、何者かにならなければいけないのではないか」と少し逡巡する。しかし彼女にとって、バイト仲間といる日々は、実はなにより居場所になっているのだ。
学校に行っても、職場で過ごしても、家族がいても、「ここが自分の居場所だ」と感じることは意外と難しい。もっと役に立たなければいる意味がないのではないか、ちゃんと空気を読めているだろうか、と考える自意識は、私たちに「ありのままの自分でいていい」なんて感じられる機会を奪う。さらにコロナ禍によって、感染のリスクを負ってまで会うべきかどうか、という価値観を内包してしまった人もいるかもしれない。しかし本書で描かれている風景は、たしかに真野にとって、自分のままでいられる居場所なのである。なぜそのようなことが可能なのだろうか? それは、バイト仲間たちは、いつも自分のやりたいようにやるからだ。他人のことを気にしすぎず、いい加減で、乱暴だ。真野は、そこに居心地の良さを覚えていることにはじめて気づく。
ただ、一緒にいる。そして、ごはんを食べる。その営みの繰り返しが、人の居場所を作るのだと、本書は愉快に明るく教えてくれる。人々の居場所を作るのは、丁寧さでも優しさでもなく、もしかすると明るくそしていい加減であること、かもしれないのだ。
評者=三宅香帆