作家・実業家 辻井喬(堤清二)を知るための4冊
を知るための4冊-アイキャッチ.png)
1980年代、西武百貨店やパルコ、大型書店のリブロといった事業を展開し、“セゾン文化”の時代を築き上げた実業家・堤清二。堤には、小説家・詩人「辻井喬」というもうひとつの顔がありました。今回はそんな堤清二/辻井喬を詳しく知ることができる書籍を4作品ご紹介します。
堤清二という人物をご存じでしょうか。作家としては「辻井
その名前に見覚えがなくても、1980年代に無印良品や大手書店のリブロ、CD・DVDショップのWAVEなどの事業を展開し、糸井重里の「おいしい生活。」というキャッチコピーをPRに用いた西武百貨店の代表を長年務めていた──と聞けば、誰しもピンとくるはず。堤がさまざまなクリエイターたちを巻き込んで築き上げた一連のカルチャーは“セゾン文化”と呼ばれ、1980年代を牽引しました。
一方で堤は前述のとおり、小説家・詩人としての顔も持っていました。今回は、そんな堤清二/辻井喬を深く知ることができる本を4作品ご紹介します。
『いつもと同じ春』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01CSBIHOY/
『いつもと同じ春』は、堤が辻井喬名義で1983年に発表した自伝的小説です。堤は、本作で同年に第12回平林たい子文学賞を受賞しました。
当時、堤は文化・芸術事業を中心に据えるユニークな演出によって百貨店経営を軌道に乗せ、リゾート開発やホテル経営といった事業も手広くおこない、華々しい“セゾン文化”の時代を築いていました。しかし本書には、経営者として熾烈な競争の世界を生き抜きつつも、ふとしたときに“自由への渇望”を感じる自身の心の内奥と、自分に跡を継がせた父との確執が率直に綴られています。
物語は、百貨店の社長である主人公の“私”が、高層ビルの中のオフィスに出社するシーンから始まります。エレベーターを降りた“私”は、清掃係の老人が絨毯に掃除機をかけているのを見て、ふと、ある作家の『永年勤続』という小説を思い出します。
それは、下積みの仕事を長年黙々とこなしてきた作中の主人公が、永年勤続者表彰式の朝、言いようのない苛立ちと虚しさに襲われて受賞を拒否するというストーリーでした。作中の主人公は、これまでに一度たりとも自分を対等な人間として扱かったことのない社員たちが、善人顔で表彰の儀式に連なっているのに耐えられなくなったのです。
“私”はその小説を思い出しながら、目の前の老人の境遇に思いを馳せます。
“彼が老妻と二人だけの生活をしているのか、妻とも死別して一人暮しの境遇なのか、あるいは息子達の反対を押し切って、健康のためと称して、今なお自立を目指しているのかは分らない。彼が家に帰ってから持つであろう時間の侘しさ、あるいは団欒についても何も知らない。私はただ彼の傍を通って自分の部屋に到達する。老人は定められた区域の掃除を終えて帰ってしまう。ある日、彼の姿が消える。翌日から別の男が同じ場所の掃除をする。
私は日頃、会社の部下や、仕事で識り合った人の私生活について、つとめて関心を持たないようにしていた。関心を持ちはじめれば際限なく相手の身の上に絡まっていって、途中で上手に突放すことができなくなりそうだった。そういう点で、私は如才なく振舞えない自分の不器用な性格を自覚していた。”
このように、本書の主人公は、経営者として事業を一心不乱に拡大しつつも、自分自身の不器用さに悩み続ける人物として書かれています。この“私”の姿にはまさに堤自身の、生き方に対する思慮深い姿勢が重ねられているようです。
『暗夜遍歴』

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352435
『暗夜遍歴』は、堤が辻井名義で1987年に発表した長編小説です。『暗夜遍歴』も『いつもと同じ春』と同じく、実業家一家に生まれた自身の生い立ちを振り返った自伝的作品ですが、本書では歌人でもあった堤の母・青山操の不遇な半生に焦点が当てられています。
堤の父・康次郎は奔放な女性関係の人物で、操以外の複数の女性とのあいだに子どもを設けていました。このことを理由に、堤は10代の頃から父に強い反発心を抱いていました。本書では、操をモデルとした女性“月子”と、堤自身をモデルとした“由雄”の視点で物語が進みます。
“一週間から十日くらいの間隔で帰ってくる父親は、彼等の母親を断りもなしに自分の部屋に連れ去る侵入者であり、彼女もまた日頃の呪詛の言葉を忘れたかのように、むしろ喜ばしげにさえ見える足取りで夫に従うのであった。その都度、由雄は子供心に理由の分らない敗北の感情を味った。
月子が夫に同棲している女がいると知ったのは、一緒になって間もなくのことであった。以前、郷里で結婚をしていた時期があって、娘と男の子がいるとは聞いていたが、これは初耳であった。その夜から月子は夫を拒んだ。妊娠していると知った時、自分だけの子を生もうと決心し、さらに数ヶ月のあいだ、二人には交渉がなかった。しかし由雄が生れてみると小田村大助(※由雄の父)の助けなしには育てられないのを否応なしに知らされた。月子は再び健康を害し、生れた子も弱くて泣いてばかりいた。何故小田村大助と一緒になってしまったのだろうと、月子は眠れない夜を重ねた。由雄を見ていると思わず流れてくる涙のなかを、時おり狂暴な想いが過った。”
対外的には社交的で友情にも厚かった父・大助は、家の中では横暴で身勝手な人物でした。大助と一緒にいるときの操は、常に苦しみの渦中にいます。しかし、物語の終盤で大助が亡くなると、操は途端に活き活きと自分の人生を楽しめるようになり、趣味であった作歌も本格的に再開し、亡くなるまでに9冊もの歌集を出版するに至るのです。
操というひとりの人物の生涯を通し、男性に従属して生きざるを得なかった時代の女性たちの姿を鮮明に浮かび上がらせるような1冊です。
『セゾン文化は何を夢みた』(永江朗)
.jpg)
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B00KFAKVNG/
『セゾン文化は何を夢みた』は、関係者らのインタビューを通じ、“セゾン文化”を振り返る1冊です。セゾン文化とは、堤が経営していた西武流通グループ(のちのセゾングループ)が手がけた文化事業や、そこから派生したカルチャーを指します。本書の著者・永江
西武グループの創業者であった父の秘書を経て、堤が西武百貨店に入社したのは1954年。のちに堤は西武グループの流通部門を引き継ぎ、百貨店経営を始めます。当時はまだ“B級”というイメージの強かった西武百貨店を急速に成長させたのが、1973年から本格化した文化事業でした。かつて西武池袋本店の中に位置した私立美術館、西武美術館/セゾン美術館の運営をはじめ、西武劇場/パルコ劇場の開設など、堤は次々と事業を軌道に乗せていきます。
内部からは、“イメージ戦略の一部とはいえ、美術や演劇のような儲からない事業をなぜ続けるのか”という反発も少なからずあったと言います。しかし、堤の考えの根底には、ただものが売れればいい、儲かればいいということではなく、消費の仕方やその種類を自分で選びとる「自立した消費者」「自立した有権者」を育てるべきだ、という意識がありました。
では、そのような啓蒙活動ともとれる事業をおこなう部に対し、ストレートに“文化事業部”という名称をつけたのはなぜだったのか。堤はその問いに、
“文化は事業になるが、芸術は事業にならない”
“メセナ(※)というのはいちばんいやなポジションで、文化活動、芸術創造に助けになるんだからメセナもあっていいよと、僕は自分なりに納得させていますけども。確かにいまも美術館がやってこれているのは、セゾン系の企業の助けによるところが大きいんですよね。だからありがたいと思っている、メセナを受けるほうの立場としてはありがたいと思う。それはビジネスから全部手を引いた僕だからそういうスタンスをとれるんですよ。自分でビジネスをやっていたときは、ビジネスマンとしては文化事業部なんていうのをつくってやっていても、私のなかのアーティストとしてのネイティブワークは別に取っておきたい、という意識ですよね。”
(※メセナ……企業による芸術・文化の支援活動)
と答えます。永江は堤のこの言葉を、
“文化事業部をつくり、文化的なことをいろいろやっていても、それはあくまでアーティストとしての辻井喬とは別の部分だったということなのだ”
と解釈しています。
本書は、セゾン文化というひとつのカルチャーを当時の空気を含めて追体験することができる良書であると同時に、セゾン文化を盛り上げ、支えたさまざまなクリエイターや経営幹部、そして堤本人の証言から、堤がいかに実業家・堤清二と文化人・辻井喬とのあいだで生まれる矛盾に悩んでいたかを炙り出すような1冊でもあります。
『深夜の読書』
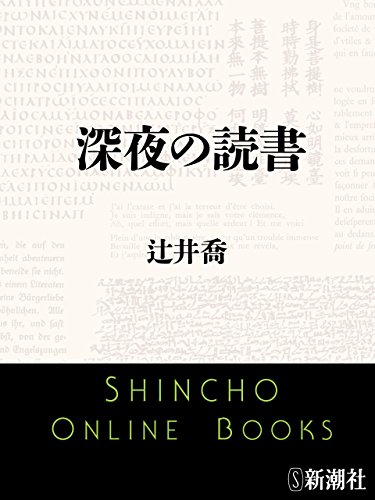
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01CSBIHR6/
『深夜の読書』は、書籍や絵画についての辻井のエッセイをまとめた1冊です。本書のタイトルどおり、辻井は実業家として激務を終え自宅の書斎に座った深夜、ゆっくりと読書を楽しむことを日課としていました。
辻井のエッセイは、短い中にも消費社会や近代主義への鋭い批判が詰まったものです。たとえば、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』をめぐるエッセイでは、作中の中心的人物のひとりであるブエンディーア大佐という男が少しも“英雄的”に描かれていないことに触れ、
“叙事詩には英雄がいなければならない、という考えは、近代主義の立場からの特殊な考え方なのではないか、という気が私にはする。“英雄”が指導者意識を隠して民衆と対話する光景などは当今流行の「民主主義」の醜悪な戯画にすぎないということが、この小説を読むと分ってくる。ブエンディーア大佐は彼の内部にギリシャ古典劇におけるコロスを所有しているのだ。英雄とは、共同体における民衆の形体だったのだと、この大佐ははっきり教えてくれるのである。”
と述べています。
また、1冊の本の話が予想もつかない他の1冊の話につながり、ひとつのテーマを成していく点も、古今東西の名著を読破している辻井ならではです。『地図を読む』と題されたエッセイの中では、プルーストの『失われた時を求めて』に登場する、「地名を口にすることで喚起される懐かしさ」についての記述から話題が展開していきます。
“私はここ数年来、胸を病んで寝ている友人の話を思い出す。彼は長時間の読書を禁じられているので、地図を書見機に掛けて眺めていると言う。
「たとえば群馬県だ」と彼は話す。地図のだいぶ上の方に月夜野町という地名がある。ここは利根郡に属し、高橋お伝の生れたところである。またこの月夜野町の深沢には虎落笛にまつわる話が残っている。その二つを想起すると彼の視野には冬の烈風に吹かれて、矢来や竹垣が笛のように苦しげな音を立てている河原の光景が浮かんでくるという。”
“地図はことほど左様に、多くの人にとって思い出の貯蔵庫であり、また想像の種子でもあるのだ。そうして私の記憶にはもう一つの懐しい作品、佐多稲子氏の『私の東京地図』が蘇ってくる。
「私の東京地図はこういうときの仕事である。自分は何であったのか、それを過去から探ろうという意図であったが、自分の歩いた道そのもの、つまり戦禍で失われた東京の街も書き残したい、またその歳月の間に関った人をも──」と、氏は自作解説で書いている。”
このように、さまざまな書物を縦断していく辻井の作品の紐解き方は、実にユニークで知的好奇心の刺激されるものです。文学や哲学、アートをこよなく愛し、研究対象としていた辻井のパーソナリティを深く知ることができる1冊です。
おわりに
バブル崩壊後、一時代を築き上げたセゾングループは解体され、“セゾン文化”が時代を牽引した華やかな時代も終焉を迎えました。しかし、実業家として一度身を引いた堤はその後、作家・辻井喬としての旺盛な創作活動を再開します。創作は晩年まで続き、2004年には『父の肖像』で野間文芸賞を、2009年には詩集『自伝詩のためのエスキース』で現代詩人賞を受賞するなど、数々の文学賞にも輝きました。堤は2013年に、その激動の生涯に幕を下ろしました。
彼が一貫して見つめ続けたのは、自身の二面性をめぐる葛藤や実親との確執といった、複雑でナイーブなテーマです。セゾン文化や1980年代のカルチャーをきっかけに堤に関心を持った方もぜひ、作家・辻井喬としての作品に目を向けてみてください。そこには、鋭い消費文化批判とともに、しなやかな感性を生涯持ち続けた一青年としての辻井の姿があるはずです。
初出:P+D MAGAZINE(2022/03/29)

を知るための4冊-アイキャッチ-501x315.png)