月刊 本の窓 スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 第2回 伊藤有希
従来の枠にとらわれず、新たな挑戦に取り組む、新世代アスリートの魅力に迫る新連載。第2回は、スキージャンプ界の「小さな巨人」を訪ねた。

自分の身体とスキーだけで“空を飛ぶ”ジャンプが大好き。一番の魅力は「飛んだ人だけが味わえる“空中感覚”と、技術を磨くほどに長く飛べるようになる楽しみがあるから」と伊藤は語る。全長368.1メートル、標高差133.6メートル、助走路最大斜度35度の大倉山ジャンプ台を、伊藤は小学5年生のときにすでに飛んでいる。
伊藤有希
(土屋ホーム)
Photograph:Yoshihiro Koike
「あははははははは!」
初対面の私の前で、スキージャンプ界のニューヒロインは何度もくったくなく笑った。テレビで見る有名人を実際に見ると、小柄で驚くことがあるが、彼女もまたとても華奢だった。けれども内に秘めたパワーは、その突き抜けるような笑い声ほど強く感じられる。
第二回はスキージャンプのオリンピアン伊藤有希。今季のワールドカップ第十七戦では、次のオリンピックの舞台となる平昌で高梨沙羅を降して逆転優勝。オスロでのシーズン最終戦にも勝利し、自己最多のシーズン五度目の表彰台トップに立った。シーズンの総合優勝は高梨が飾ったが、伊藤は高梨に次いで自己最高の二位に。水泳の萩野公介と瀬戸大也のように、日本が誇る女子ジャンプ界のオリンピアン二人はこの冬、ワールドカップの表彰台をにぎわせ続けた。
私は、次の夏季オリンピックで萩野と瀬戸のワンツーフィニッシュを思うのと同じくらい、次の冬季オリンピックで高梨と伊藤のワンツーフィニッシュを夢見ている。順位は逆なのではないか。瀬戸が金メダルかもしれないように、伊藤が金メダルかもしれない。これは、ますます面白くなりそう。そんな妄想がとまらないのだ。
2011─2012シーズンから始まった女子のワールドカップ。史上最多の通算五十三勝を誇る高梨に比べれば、伊藤は通算わずか五勝。とはいえこの五勝とも、2016─2017シーズンに挙げた。つまり、今季は文字どおり飛躍的に強くなっているのだ。しかし、まだまだ日本の報道は世界のトップを走り続けてきた高梨一色。ワールドカップで高梨が優勝できない大会が増えると、その“不安定さ”の理由を求めた。そんなことも取材で尋ねてみたが、
「でも総合優勝しているんですよ。表彰台を外れただけでもそんなふうに言われてしまうのは、高梨選手のすごさ。本当に尊敬します。それほど期待されてるっていうことですから。私なんて全然ポイントが取れなくても、何も言われない。あははははははは!」
伊藤はまた、くったくなく豪快に笑った。

今年の2月、韓国・平昌で行われたワールドカップ第17戦では高梨沙羅を抑えて優勝。伊藤は2014年のソチオリンピック前、「特別な舞台にも特別な秘けつはない」と葛西から教わった。「オリンピックでもワールドカップと同じように準備をするだけ。平昌でも同じことはできると思う」。経験して自信につなげた。(写真提供:産経新聞社)
監督はレジェンド葛西紀明
「ジャンプ以外は何もできないんです(笑)」
伊藤の出身は、北海道の下川町。人口三千五百人足らずの田舎町だが、世界有数のジャンプ先進“町”だ。史上最多七大会連続のオリンピック出場記録を持つ“レジェンド”葛西紀明も、この町で生まれ育った。
伊藤は、下川商業高校を卒業後、土屋ホームに入社。現在はそのレジェンド葛西が選手兼任監督を務めるスキー部に所属する。やはりレジェンドはすごいですか? と尋ねると、伊藤は「レジェンドはすごいです。年々オーラも増してます。監督は言葉では多くを語らないんですが、トレーニングや競技に取り組む姿勢などで教えてくださるんです。監督にしかできない指導法かもしれません。それに、家族のようなチーム作りをしてくださいます。練習は辛いけれど、より楽しくなるように。本当に尊敬します」。絶大な敬意をあらわしたり、嬉しそうに「レジェンド」と言ったり。心底慕っているのが伝わる。選手で監督の葛西は、厳しい練習を率先しながら、アットホームな雰囲気でチームをまとめているのだろう。
伊藤の両親は、ノルディック複合の選手だった父・克彦さんとアルペンの選手だった母・真智恵さん。ちなみに、三学年下の弟・将充さんも同じ土屋ホームに所属するジャンプ選手だ。ジャンプの町でスキー一家の長女に生まれた伊藤は、物心ついた時にはスキー板を履き、四歳からジャンプ台で飛び始めた。
「私、歩き始めた時にはスキー板を履かせられたんですね。下川町は田舎なので、スキー場ぐらいしか遊ぶところがなくて。スキー場があって、ロープリフトがあって、ジャンプ台があるんですけども、最初はターンを三回ぐらいしたらもう終わるような小さいスキー場で遊んでました。隣に、ジャンプ台が見えるんですね。そのうちに、そこで気持ちよさそうに飛んでるお兄ちゃんたちに憧れるようになって」
そこで、父・克彦さんは斜面に雪のコブを作ってあげた。幼い彼女は、それを滑ってジャンプしては「もっと大きいコブにして」とせがみ、夢中になって遊んだ。下川町には大小四つのジャンプ台がある。一番小さいのが五メートル級。どんどん大きなコブを飛んでは喜ぶ娘が四歳になった時、克彦さんは五メートル級のジャンプ台に連れていった。
人生最初のジャンプを伊藤はよく覚えているという。「たぶん、二~三十本は滑ったと思います」。四歳児にしてである。その理由を伊藤は続けた。「一回か二回しか立つことができなかったんですよ。もう全部、着地をしたら背中をついて転ぶような感じで。なんで立てるようにならないんだろう……。早く立てるようになりたいって。そういう気持ちで何回も行ってました」
四歳でジャンプの魅力にはまった伊藤は、克彦さんもコーチを務める地元の下川ジャンプ少年団に入り、練習に明け暮れた。ちなみに、雪国育ちなのに大の寒がり。それでも、氷点下三十度になる日でも「手が冷たいよ……」と半べそをかきながら飛んだ。
「ジャンプばっかりやってました。だから、(他のスポーツは)何にもできないんですよ。球技も何も苦手なんです」と笑う。ジャンプに飽きたことはないんですかと尋ねると、「飽きること、ないですね。飽きたことがないです」と伊藤は真剣な表情になると、力強く答えた。
偏見があった女子ジャンプがオリンピック正式種目に
女子ジャンプは、“新しい”種目だ。ノルディック世界選手権でも、正式に女子のジャンプ種目が行われたのは、二〇〇九年のリベレツ大会から。これにより、一〇年のバンクーバー大会からオリンピック種目に加わるかと期待されたが、いったん見送られ、紆余曲折の末に一四年のソチから正式種目に追加された。
ちなみに冬季オリンピックは一九二四年、フランスのシャモニーで第一回大会が開催されたが、男子は当初から正式種目だった。女子につい最近まで門戸が開かれていなかったのは、今では信じられないことだが、「ジャンプは男子の競技」「女子には危ない」「将来、子どもが産めなくなる」といった偏見が蔓延していたからだった。
そうした中、日本で女子ジャンプの道を切り拓いたのは、山田いずみ氏。これらの偏見と闘いながら、大会への出場を交渉し、実現させ、実績を重ねた。〇九年に引退し、以後は全日本女子チームのコーチや高梨のパーソナルコーチを務めるなど育成に携わる。
下川町で育った伊藤は、女子ジャンプがオリンピック種目にないと知らずに「オリンピックで金メダルを獲りたい」と言ってはばからなかった。事実を知ったのは、小学校六年生の時。この年、史上最年少で国際大会であるコンチネンタルカップで三位入賞を果たした伊藤は、それを知って心底ガッカリしたという。
「でも、その時はすごいジャンプが楽しかったので、まだ目標がなくなるっていうのはなかったです」と、その後も一途にジャンプを続けた伊藤が高校生の時のこと。二〇一一年、女子ジャンプは正式にオリンピックの種目に決定した。
女子への偏見があったことは、後になって知ったし、伊藤自身が嫌な思いをしたりしたことはないという。だから言う。「私はすごく幸せなんです。本当に山田いずみさん始め、女子の第一人者と言われる方たち先輩のおかげです。先輩たちが敷いてくれた“レール”を歩くことができて感謝しています」
男の子には負けない! 「バンジージャンプをピョンピョン飛んでみたい(笑)」
伊藤は、子どもの頃から男の子に混じって競い合った。地方の大会では中学生までは男子も女子も同じ部門で出場する。当然、中学生にもなれば男子と女子では力の強さや体力面などで差もでてくるが、「その中でどのぐらい通用するか」と挑む気持ちだったという。男の子ばかりの少年団の練習にも食らいついた。
「男の子の中、たった一人、女の子でやってたので、女の子扱いされるのがすごい嫌でした。『女子だからできないよね』とか『有希は女子だから回数少なくていいよ』とか言われないよう、必死でしたね。だから言われたことないんですけど(笑)、たぶんできない姿を見せたら絶対言われるなと思ったので、できないなりに『はい!』って食らいつきました」。そして、コーチが「練習終わり」と言うまで、絶対に休まなかったという。
「男の子の中でトレーニングしてたのは、すごい辛かったですけど、その練習ができたのも、『絶対に強くなりたい』って思いがあったからかなって思うんです」
辛いだけでなく、やっぱり楽しかった。それに、フィジカル面では男の子についていく側だったが、メンタル面ではリードしていたようだ。大きな台へとステップアップするたび、男の子たちとジャンプで競い合うたび、伊藤は一番最初に飛びたがった。「一番が一番スリルを味わえそうじゃないですか」。周囲の男の子たちが物怖じするのもかまわず、真っ先に大きな台を飛んでみせた。
幼い頃から弟と取っ組み合いのケンカをしたり、ジャンプで競い合ったり、と男の子相手にもひるむことなく「男前」だったよう。だが、謙遜しつつ、そもそも度胸は女の子のほうがあると言う。
「たぶん男の子より女の子のほうが踏ん切りがつくというか、度胸があるかもしれないです。今の下川の女の子たちを見てても、そう。すごく気が弱そうでも女の子のほうがポンポン飛んでて、男の子のほうが『スタートできません』って降りてきたりしますね」
“女は度胸”なのかもしれない。そういえば、バンジージャンプもそんな印象がある。そう水を向けると、伊藤は嬉々として、「私、(バンジージャンプ)やってみたいんですよ!」。何本でも行けそうと返すと、「うん、もうピョンピョン行ってみたいですね、ホント」と目をキラキラさせた。


バランスボールに両足ジャンプで軽々と飛び乗った伊藤。ギャラリーが歓声で沸くと「若い子のを見て覚えたんです」と照れ笑いしながら、ピタリと静止してみせた。チームの雰囲気はとてもいいそう。
「怖いと思ったことがない」大きく崩れない。少しずつ遂げる成長
身体ひとつとスキー板を履いただけで、空高くへ飛び出すスキージャンプ。インタビューを行ったのは大倉山ジャンプ競技場だったが、伊藤自身が百四十五メートルの女子バッケンレコードを持つラージヒルは、近くで見ると絶壁だった。突風が吹くこともあり、それで命にかかわる大けがを負う選手もいる。改めて恐ろしい競技だとまざまざと思い知った。それは多くのジャンプ選手にとっても例外ではなく、より大きな台に挑戦する時などは「恐怖心」と闘うという。ところが、伊藤選手はそうした思いに苛まれたことはないのだという。レジェンド葛西やパイオニア山田も、経験したというのにだ。
「正直に言うと、まだあまり『怖い』と思ったことがないんです。もちろん、すごく風が強い時とか条件が荒れてる時とか、練習の時は怖いと思いますけども、試合の時はどれだけ風が強くても怖いと思わないんです」
理由を尋ねると、なんででしょうねえ……と前置きして考えを紡ぎ出す。「たぶん私まだ怖い思いをしたことがないんですよね。捻挫もしたことがなくて、けがしたことがないんですよ。空中でバランスを崩して大転倒した経験もないし、そういう怖い思いをしたことがないからかもしれません」。続けて、「きっとセーフティに競技をしているからだめなんですよね。もっと攻めないと」と自戒しつつも、けがをしては元も子もないのだからとも言い聞かせる。
ただ恐怖心はなくとも、失敗イメージに苛まれることはあった。今年の前半は、そんな状態でうまくいかなかった時があるという。後半に伸びたのは、土屋ホーム副会長の川本謙スキー部総監督から、「もっと視野を広げてフレキシブルに競技に臨んだらどうだ」との一声がきっかけだった。そこで、これまでは他の選手のジャンプも「緊張するから」と見ないようにしていたのを、自分も含めて俯瞰して見てみるように。すると、逆に自分がよく見え、気持ちに余裕を持って臨めるようになった。
来年はいよいよ平昌で五輪が開催される。伊藤は葛西、高梨とともに強化指定選手に選ばれた。前回のソチ五輪では、一回目のジャンプで踏み切りのタイミングを外したが、二回目には見事に距離も飛型点も伸ばした。もし失敗がなければメダルに届いていただけに、悔しさは計り知れない。だが伊藤は「悔しさは次へ向かう原動力」と言い切る。「悔しい気持ちがあってのモチベーションだと思うんです。今度こそはっていう気持ちがあるので、悔しい思いをすることは、自分にとってはムダではないですし、大事なことだって思っています」
これから平昌でも、伊藤はどんなジャンプで魅せてくれるのか。選手としての自分を伊藤は客観視して語る。
「自分は急に調子が落ちることもなければ、急に調子が良くもならないんです。すごくちょっとずつなんですね。私は決して天才肌ではなくて、自分が持ったものとかで飛べるわけでもない。だから、たくさんの時間をかけてトレーニングしなきゃいけない。一つのことをできるようになるにも、他の人よりも時間が必要なんです。けれども、その分、ちょっとずつ進んでる。ちょっとずつだから、悪くなる時もちょっとずつ。だからちょっとズレた時に気づけば、ちょっとの修正でまた戻すことができるのが持ち味かもしれません。長い目で見ると、何か月前より今はいいねとか、何年前よりかは良くなったねっていうレベルなんですけれども、そういうふうにして、これからも少しずつ進んでいきたいと思います」
今年にわかに高梨のライバルとして名を轟かせた“新しい”女子ジャンパーは、突き抜けるような笑い声とは対照的に、足下を見ながら少しずつ階段を上っていた。だから、今季のすばらしい成績も急に伸びた結果ではなく着実につけた実力なのだ。ジャンプの神様がいるなら、伊藤は天使のよう。ひたむきにジャンプに人生を捧げ、少しでも遠く美しく「空を飛ぶ」ことを喜ぶ。V字の両手は、レジェンド葛西に倣い掌を下に向ける。伊藤の“伝説”はまだ始まったばかりなのだ。
プロフィール

伊藤有希
いとう・ゆうき
スキージャンプ選手。土屋ホーム所属。1994年生まれ。身長161センチ、体重47キロ。北海道上川郡下川町出身。2007年3月、小学校6年生の時に国際大会「コンチネンタルカップ」で史上最年少での3位入賞。ジュニア時代から世界選手権などで活躍を続ける。14年ソチオリンピックでは日本代表となり、ノーマルヒル個人で7位入賞を果たした。今季ワールドカップは自己最高総合2位に輝く。
松山ようこ/取材・文
まつやま・ようこ
1974年生まれ、兵庫県出身。翻訳者・ライター。スポーツやエンターテインメントの分野でWebコンテンツや字幕制作をはじめ、関連ニュース、書籍、企業資料などを翻訳。2012年からスポーツ専門局J SPORTSでライターとして活動。その他、MLB専門誌『Slugger』、KADOKAWAの本のニュースサイト『ダ・ヴィンチニュース』、フジテレビ運営オンデマンド『ホウドウキョク』などで企画・寄稿。
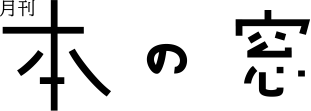
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。ページの小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激します。
スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 連載記事一覧はこちらから
初出:P+D MAGAZINE(2017/06/21)






