生き残った子どもたち(文・藤野可織)【生きるための読書#3】

「爪と目」で第149回芥川賞受賞作家となった藤野可織さんがおすすめする、「子どもを主人公に据えた海外文学」3作品。子どもならではの鮮烈な〈生〉の感覚を通じて、読者に見えてくるものとは……?
読書を通じて、〈生きること〉を再発見するための読書バトン、「生きるための読書」。
第3回は、「爪と目」で第149回芥川賞受賞作家となった藤野可織さんによる、「子どもを主人公に据えた文学作品」についての読書案内です。
読書を通じて、懐かしい子ども時代と再び出会うとき、私たちは一体何を想うのでしょうか。
▶︎「生きるための読書」第1回(加勢 犬)、 第2回(岩川 ありさ)を読む
|
【藤野可織プロフィール】 作家。京都府京都市出身。 2006年、文學界新人賞を受賞した「いやしい鳥」でデビュー。2013年、「爪と目」で第149回芥川賞受賞。 |
〔以下、藤野可織さん寄稿文〕
生きるための読書、というタイトルはちょっと大仰な響きではあるが、それはそのとおりであって、読書はもちろん生きるためのものだ。読書は人を生かす。
たいていの小説には、この世界はどういうところなのか、その中でどのような生がありうるのか、といったことが書いてあって、そこからはっと我に返って本の外側、つまりこちら側の世界を新たな価値観で測り直すと、私はどう生きるべきか、少なくともどんな具合の心がまえでいるのがいいのかがなんとなく見えてきたような気がしたりして、それは大いに有益なのだが、私にとって読書のいちばんの喜びはそこではない。
本を読んでいると、私の肉体は消滅するようでいて強く存在を主張してくる。ページをめくるとき、文字に指が触れると自分の指の大作りなのに衝撃を受けることがある。なんというか、文字の細く美しいのに比べて、デリカシーのない造作をしている。おまけにうっすら汗までかいている。肉体の不潔さを理不尽と感じ、そのことに傷つきさえする。でもしょうがない、生きている限りこの手の失望はつきものだ。

私は生きていて、これから先どうなるのかわからない。いつかは死ぬけれどそれがいつなのか、どんなふうに死ぬのかさっぱりわからない。そういった決定的なタイプのものとは別に、一日一日に、心のほうで無数の小さな生と死を体験している。その生と死にはさまざまなレベルがあって、どうってことない生や死もあれば長く尾をひく生や死もあり、これを甘く見ているといつか決定的なタイプのものを誘発することになりかねない。
読書は、この日々身体の奥底で起こっている小さな生と死を、快楽のかたちで爆発させ、消費するための技術だと私は思っている。その快楽こそが読書のもっとも大きな収穫だ。
小説の中で、人は生き、死んでいく。私は、傷つけられ、虐げられた者が、打ち勝って走り抜けていく姿が見たい。そういう姿を見せてくれる小説は尊敬に値するし、愛さずにはいられない。けれど、私にはなぜかそれだけでは苦しくて、戦い方も知らないまま不恰好に死んでいく者の姿もたくさん見たいし、見ないといけないという衝動すら感じる。小説から得るのであれば、喜びや誇りと同様、悲しみも悔しさも惨めさも苦しみも、恐怖すら快楽なのだから。

これから紹介する三冊は、子どもを主人公に据えた小説だ。私はたまたま今年の夏、この三冊を立て続けに読み、それから少し時間が経った今、もう冬でとても寒いのに、ちぢこまる体のどこかがいまだに夏の暑さに苛まれている。私は、この三冊で語られた子ども時代が、自分のものよりもずっとなつかしい。
それは、子どもが主人公の小説ならどれでも、多かれ少なかれ呼び起こす感覚だろうと思う。その子どもと読者とあいだに共通点があろうがなかろうが関係はない。なぜなら、生きて本を読んでいる私たちはみな、生き残ることができた子どもだから。
夏、私が生き残っていることを思い出させ、私に新しくなつかしい子ども時代を与えてくれたこの三冊に、心から感謝している。

スティーヴン・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』岸本佐知子訳、河出文庫、2016年

これは、傑作小説『まんが』を著した天才作家エドウィン・マルハウスの伝記という体裁をとっているが、変わっているのはエドウィン・マルハウスがたったの11歳で夭折してしまったということと、この伝記をものしたジェフリー・カートライトがエドウィンと同い年の親友である、という点だ。ジェフリーによるエドウィンの観察は、エドウィンが生まれた瞬間からはじまる。それ以降、エドウィンの短い生涯は、幼年期、壮年期、晩年期と区分され、エドウィンがいかにして言葉と文字を獲得し文学へ昇華させたのかや、エドウィンを育んだ家庭環境について、小学校での体験と初恋、街の様相、エドウィンに重大な影響を与えた同世代の子どもたちのこと、才能が彼に強いた壮絶な執筆のありさま、さらにははたから見れば謎に満ちていたにちがいない恐ろしい死の真相までもが詳細に書き込まれている。
正直に言えば、この少し分厚めの文庫本を読み通すのに、私にはかなりの時間が必要だった。ジェフリーの筆は禍々しいほどに執拗で、これを追うのは虫眼鏡を持って地面を這い回るような作業だ。その虫眼鏡の向こうにはまぶしい光の乱反射と濃縮された暗闇があり、虫眼鏡が真上を通過するのをひとつひとつのモチーフや光景が待ち構え、克明でありながらひどく歪んだ像を結んで読者に見せつけるのである。
文庫本は長いことかばんに入れて運ばれ、またしょっちゅう出し入れされたために、読み進むにつれてカバーのへりがたわんでよれ、帯の印刷の黒が剥げていったが、読み終えた私もまた同じようにぼろぼろだった。官能的ともいえる顛末を読んでしまったあとでは、この本全体が息詰まるようなある種の官能に充ち満ちていたことがわかる。いわゆる性的なものに限定されるのではないその官能の感触を、私は二度と忘れないつもりだが、おそらくこの『エドウィン・マルハウス』は読み返すたびに何度でも、まるでその快楽をほとんど忘れ去っていたみたいに生々しく、強烈にこちらに突きつけてくるだろう。
カーソン・マッカラーズ『結婚式のメンバー』村上春樹訳、新潮文庫、2016年

「緑色をした気の触れた夏のできごとで、フランキーはそのとき十二歳だった。」という最高に美しい、完璧な一文ではじまるこの小説は、兄の結婚式を前にして、自分を迎え入れてくれる世界を熱烈に求める少女の孤独な闘争を描いている。
フランキーの孤独は、十二歳の少女のものとしては適当な孤独である。彼女は同世代の女の子たちとは馴染めずにいるが、南部の片田舎での日常にはうんざりするほど馴染んでいる。それに、彼女と同じ場で同じ時を過ごす父、幼い従弟のジョン・ヘンリー、手厳しくも愛情豊かな女料理人のベレニスという世界の一員としてなら、すでに世界に迎え入れられている。ただし、今やそれは彼女にとってはそぐわないものとなってしまった。そんな中でフランキーは、兄の結婚こそが彼女が生きるべき新しい世界であると直観する。兄の結婚がもたらす新しい生活は兄と兄嫁だけのものではなく、フランキーもまたそこに歓迎されるものと思い込むのだ。
世界に迎え入れられるということは、世界を迎え入れることでもある。迎え入れられることを確信するフランキーは、入念に世界を迎え入れる準備をおこなう。自分が何者であるかを決定するために名をF・ジャスミンと改め、新しい世界と新しい自分にふさわしい態度で街をさまよい、ジョン・ヘンリーやベレニスと最後となるであろうときを過ごす……。
彼女の思い込みや熱望は子どもっぽく痛々しいが、その切実な衝動は決して子どもだけの特権ではないと、誰もが感じるのではないか。
作中で、フランキーの名前は三度変わる。はじめは子どもじみた愛称のフランキー、次はなつかしい世界を置き去りにして自立してゆくF・ジャスミン、さいごには彼女の本名であるフランセスと。
けれど、フランセスはフランキーでなくなったのではないし、F・ジャスミンを失うこともない。彼女も私たちも完成されないままで、何かを抱きしめようと腕をうつろに広げて生涯を過ごすのだ。
ノヴァイオレット・ブラワヨ『あたらしい名前』谷崎由依訳、早川書房、2016年
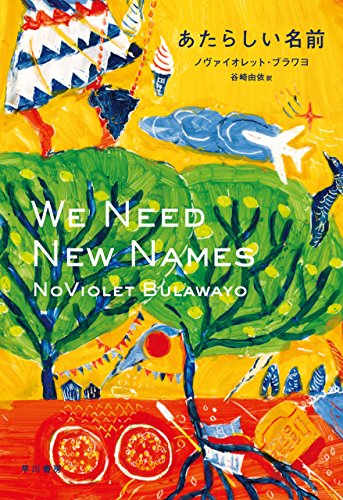
10歳のダーリンは、経済が崩壊し、医療や教育がまともに機能しなくなったジンバブエで暮らしている。かつての家は奪われ、家族や仲間はパラダイスと呼ばれる地区に押し込められ、常に飢餓状態で、ゴッドノウズやバスタードといった奇妙な名前を持つ友人たちと連れ立ってグァバを盗み、自殺者の靴を盗み、プレゼントをもらうためにNGOの無神経な扱いに耐え、暴徒に襲撃された富裕層の白人の家に侵入して食べ物を食べ散らかす。失われた秩序を悔やみ、国を変えようと熱狂しては絶望する大人たちのあいだで、子どもたちは生きるためにできることはなんでもする。ダーリンの夢は、アメリカに移住することだ。
本の半ばあたりで、ダーリンの夢は叶う。すでに移住していた叔母さんに呼び寄せられ、デトロイトで暮らすことになるのだ。けれどそれは、永住権を持たないダーリンにとっては故郷を失うことであり、長く長く、これからずっと、死ぬまで続く移民としての生活という戦いのはじまりでもあった。
ダーリンは貧しさと暴力の吹き荒れる国を出ることのできた、まさに生き残ることに成功した子どもだ。しかし、一度生き残ればそれでいいのではなくて、生きているかぎり人は一生生き残りつづけなくてはならない。生き残りつづけるダーリンの痛みと喜びに心を切り裂かれ、また切り裂かれるために心をすすんで差し出し、私はなんとか生き残っている。まだ。
〈了〉

| 【編集部より】
文学研究者や現役作家など、今話題の読み手にバトンを渡していくシリーズ「生きるための読書」。次にバトンが受け渡されるのは……? 第4回の掲載をお楽しみに! |
初出:P+D MAGAZINE(2016/12/10)

