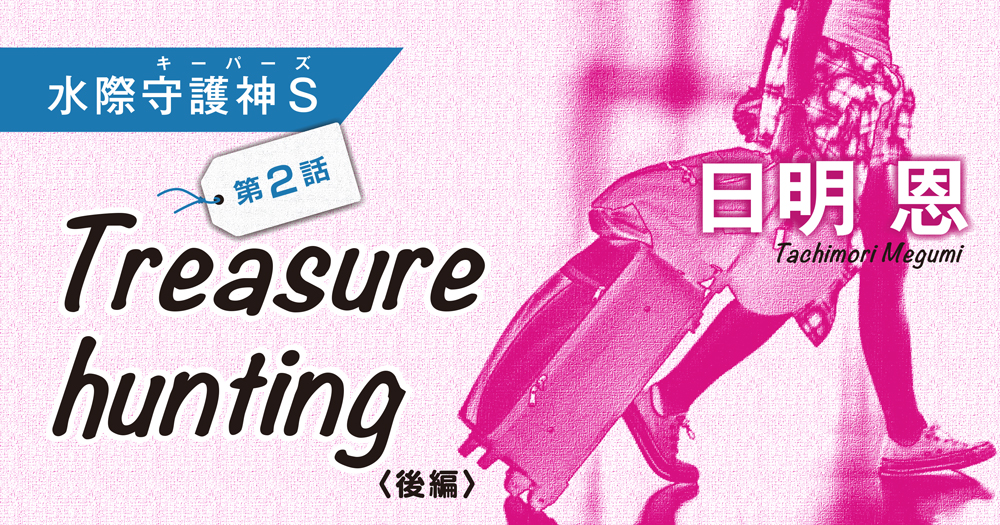◇長編小説◇日明 恩「水際守護神S」──第2話 Treasure hunting〈後編〉

午後八時を回って第一班の担当が終わり、さすがに槌田(つちだ)は空腹を感じる。
「遅くなりましたが、夕食にしましょう」と英(はなぶさ)に言われて二つ返事で同意する。
「どこか店に入りますか? 買って来て会議室で食べることも出来ますが」
持ち帰るとなるとコンビニだ。朝食もそうなるだろうだけに、二食続けてはさすがに侘しい。
「はねだ日本橋近くの飲食店街にある店舗はすべてテイクアウト出来ます。和洋中、エスニック、ファストフードまで幅広くあります」
国際線の出国ターミナルだけに、幅広い利用客のニーズに合わせているのだろう。
「ああ、そうだ!」
何か閃いたらしい英が弾んだ声で続ける。
「槌田さん、牛丼の?野家で全国で三店舗しか出してない限定メニューがあるってご存じですか?」
独身時代はかなりのペースで利用していた。結婚して行かなくなったが、独り身に戻った今、またお世話になっている。だがそんな話は知らない。
「いや、まったく」
「一つは国会議事堂内にあるので、国会関係者以外は利用できないんです」
さんざん世話になっているしありがたい存在ではあるが、特定の人にだけ向けた商売をしていると聞くとあまり面白くない。
「残る二店は一般の人も食べられます。一つは成田第二ターミナル、そして最後の一つが羽田国際線ターミナルに入っています。和牛牛重、味噌汁とお新香付きで千五百円です」
娘の結実(ゆみ)への土産話にもなるだろうか。なんなら、連れてきても良いかもしれない。面白くないと思ったのもつかの間、槌田は「それにしましょう」と答えていた。
国際線ターミナルの飲食店街エリアは混んでいた。旅立つ前の最後の腹ごしらえをしようとする客で、行列の出来ている店もある。
人混みを縫って進みながら、槌田は気になったことを口にする。
「もしかして、他の店のメニューの値段も覚えているとか?」
「さすがにそれはないですよ。勤務していたときに何度も利用してましたし、人を連れて来たりもしたので覚えていただけです。──もしかしたら、値上がりしているかもしれません」
「なるほど」
それならば分かる。同時に気づいた。人を連れて来たりも──女性だろうか? 見た目も悪くなく、立ち居振る舞いもスマートなだけに驚くことでもない。
飲食店街エリアを通り過ぎ、さらに奥に進むと見慣れたオレンジと緑の電飾の店構えが見えてきた。自動ドアの左側に女性が数名列んでいる。大きなバッグは持っておらず、中には財布だけの者もいる。
「エアラインの職員さんですね」
視線に気づいた英が言う。髪のまとめ方からして、そうだろうとは槌田も思っていた。
「あそこがテイクアウトの窓口になっているんですよ」
ドライブスルーの受け取り口のような小窓からビニール袋を受け取った女性が槌田に近づいて来る。ビニール袋は膨らんでいて一人分にしては重そうだ。大きさからして並盛りではない。大盛り、もしくは特盛りだ。サイドメニューもいくつか頼んでいるかもしれない。
「彼女たちも立ち仕事ですからね。しっかり食べないと」
言われてみれば確かにそうだ。加えて常に笑顔での応対を求められる接客業でもある。しっかり食べて備えないと、とてもではないがやっていけないだろう。次に列んでいた女性がビニール袋を受け取る。まとめてお使いを請け負ったらしく、袋は三つだ。やはりどの袋も重そうだ。髪型と黒いストッキングに黒いローヒールの革靴からして、やはりエアラインの職員らしい。綺麗にメイクした若い女性が、牛丼の入ったビニール袋を下げて、綺麗な姿勢で闊歩していく。その姿に美しさだけでなく頼もしさを槌田は感じる。
「和牛牛重はテイクアウト出来ないので。入りましょう」
夕食には少し遅いが店内は混んでいた。後ろに早くも数人列ぶ。素早く食べて退席するせわしなさは簡単に予想出来た。限定メニューは魅力的だが、夕食はゆっくり食べたい。
「混んでいるし、テイクアウトにしないか?」
「構わないですよ」と英は了承して、すぐさま女性たちの後ろに列ぶ。槌田もその後に続いた。
コンビニエンスストアに立ち寄って朝食も買って事務室に戻ったときには、八時二十分を過ぎていた。
事務室内には九時台を担当する第三班の旅具検査官たちが待機している。英と槌田はその横を通り過ぎて会議室に向かう。ドアをノックすると中から「はーい」と女性の声が聞こえた。
「使用中ですね、他に」
英が言い終える前に中からドアが開いた。第一班の桜田(さくらだ)だ。中には鈴木(すずき)と森本(もりもと)もいる。机の上には飲み物とお菓子らしきものが見えた。どうやら休憩中らしい。
「あ、ご飯まだだったんですね」
ビニール袋に気づいた桜田の声に、「ここどうぞ」と鈴木が席を立ち上がり部屋を譲ってくれようとする。
「いえ、他を当たりますから」
英が踵を返そうとするのと、机の上を片付けようとした森本がコップを掴み損ねて倒して「あっ」と声を上げたのは、ほぼ同時だった。
「やっちゃったー」「あーあー」「何か拭くもの!」
三人の女性が、いっせいに言いながら動き出す。拭くものを取りに行こうとする桜田に「大丈夫ですよ」と、英が話しかけた。室内に入った英は、ビニール袋の中から使い捨てのおしぼりを取り出し、こぼれた飲み物を拭き始めた。その手があったかと槌田も同じようにする。おしぼり二枚で机の上は綺麗になった。
「すみません」
申し訳なさそうに、森本が何度も英と槌田に頭を下げる。
「いえ、こちらこそ。急かしてしまったせいですから」
如才なく英が返して騒動は一段落した。だが部屋をどちらが使うかという問題は残っていた。改めて鈴木たちが部屋を出ようとする。せっかく休んでいたのに申し訳ないと思った槌田は口を開いた。
「一緒っていうのはどうですか? もちろん嫌じゃなかったらですけれど」
三人が顔を見合わせる。鈴木が「構わない──よね?」と、桜田と森本に了解を求めた。「全然」「いいですよ」と、二人もすぐさま同意した。
机の上に買って来た牛丼の大盛りを出すと「限定メニュー食べてくれば良かったのに」と森本に話しかけられた。
「混んでいたので」
「分かります。ゆっくりしたいですものね。テイクアウトにしてくれればいいのに」
「本当にそう!」
「ちょっとした手土産に、ちょうどいいのにね」
鈴木と桜田も話に加わる。三人はそのまま、テイクアウトできるお薦めメニューの話に花を咲かす。焼肉チャンピオンの焼肉弁当、韓国海苔巻き。天ぷらたかはしの天丼。ハローキティジャパンのこんがり焼き──。
「こんがり焼き、焼きたてが美味しいのよね」
キティちゃんの形をした人形焼きのようなものらしい。お土産にしたら、さぞかし結実は喜ぶだろう。だが次に結実に会えるのは二週間後の日曜だと思いだす。槌田は沈んだ気持ちをかき消すためにも、牛丼を口に詰め込んだ。