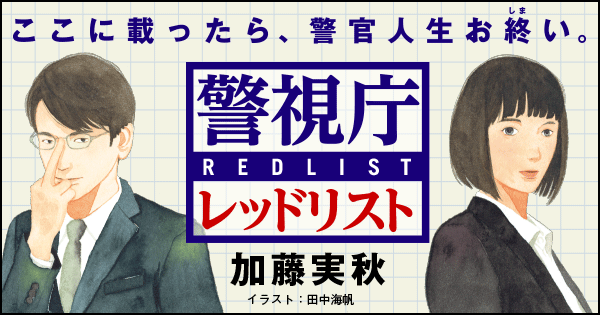〈第8回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

真相を突き止め、意外な処分を下す。
エレベーターではなく階段を使い、慎はビルの四階に上がった。階段の壁の陰から覗くと、色の褪(あ)せたビニールタイル張りの廊下に社名の書かれたドアが並んでいる。その一つに、「舟町(ふなまち)テクノリサーチ」があった。
舟町テクノリサーチは、放射線や放射性物質関係の実験用の各種測定を請け負う会社だ。佐久間の話によると、盾の家は研究所の設備では行えない測定をここに依頼しており、二週間に一度ぐらいの頻度でメンバーが来社するらしい。
あの男は、必ずここにいる。しかし、一人ではない。どうやってコンタクトを取る? 確信と課題を胸に、慎は廊下を見張り始めた。
四十分後、舟町テクノリサーチのドアが開いた。出て来たのは三人の男。全員黒いつなぎ姿でマスクを装着しているが、フードは下ろしている。初老の男と二十代後半の男の間に、あの男がいた。三人は廊下を、階段とは逆側にあるエレベーターホールに向かった。
ビルを出たところで、舟町テクノリサーチの社員のふりで声をかけるか。だがこちらの身元がバレると、あの男に危険が及ぶ。必死に頭を巡らせていると、
「ちょっとトイレに」
と声がして足音が近づいて来た。慎は素早く階段を下り、手すりの裏側に隠れた。注意深く顔を出して窺うと、階段の前の廊下をあの男が歩いて行く。歳は四十代前半。中背で痩せている。
よし、ツイてる。はやる胸を押さえ、慎は再び階段を上った。エレベーターホールを窺うと、初老の男と二十代後半の男は顔を寄せ合って話し込んでいる。呼吸を整え、慎は壁の陰から出た。エレベーターホールの二人を注視しながら足音を忍ばせて廊下を進み、突き当たりのトイレに入る。
がらんとしたトイレはドアの脇に洗面台が二つ並び、その奥に小便器が二つ。向かいに個室が一つあり、ドアは閉まっていた。慎は手前の洗面台に歩み寄り、蛇口のレバーを上げて水を出した。液体石けんで手を洗っていると、ごそごそという衣擦れの音に続いて水を流す音がして、個室のドアが開いた。出て来た男は慎に気づくなり俯き、つなぎのフードをかぶった。隣の洗面台の前に来て水を出したが、俯いたままだ。
水を止め、ハンカチで手を拭きながら慎は言った。
「昭島南署警務部公安課の新海弘務(しんかいひろむ)巡査部長ですね?」
男は無言。水を止め、濡れた手のままドアに向かおうとする。振り向き、慎は警察手帳を掲げて続けた。
「本庁人事一課の阿久津です。ご無沙汰しています」
だが男は立ち止まらず、ドアの前に行ってレバーを摑もうとした。その横顔に、慎は早口だが冷静に告げる。
「監察係の聴取でお目にかかりましたね。担当は中森翼警部補でしたが、僕も立ち会いました。あなたが本庁警備部警備第一課に所属していた昨年夏、部下の女性との不倫が疑われた一件です」
ぴたりと、男の動きが止まった。すかさず、慎は本題を切り出した。
「中森は『疑いは間違いで、不倫の事実はない』と報告し、僕はそれを受理しました。結果、あなたは中森に弱みを握られ、脅迫された。警備一課に流れた持井事案のデータを中森に渡す算段をしたのは、あなたですね。身分秘匿捜査中という立場を利用して、彼の逃亡と潜伏にも手を貸したはずだ」
「おい。やめろ」
フードを脱いでマスクも引き下げ、新海がこちらを見た。ぼさぼさの髪と青白く頰のこけた顔が露わになる。
「自分が何をしてるか、わかってるのか?」
慎に突きつけられたことよりエレベーターホールの二人が気になるようで、新海は潜めた声で問いかけドアに目をやった。
潜入捜査中の公安課の捜査員に声をかけるなど、警察官にとってはタブー中のタブーだ。明るみに出れば、慎が処分の対象となる。だが、そんなことは覚悟の上だった。
「あなたの職務を邪魔するつもりはありません。加えて、不倫とデータ抜き取りにも興味はない。僕が知りたいのは中森とデータの所在地だ。ただし、情報提供を拒否すると言うなら話は別です。不倫の再監査を求め、データ持ち出しへのあなたの関与を、中森の特命追跡チームに報告し──」
「わかった! だが、今はダメだ」
広げた手のひらを上げ、新海が慎を制した。頷き、慎は返した。
「では、中森とデータの所在地だけ」
「わからない。本当だ。持ち出しと潜伏の手引きはしたが、どこにいるのか。東日本大震災の放射能汚染以後、盾の家のメンバーは千五百人から二万人に増えた。反原発を唱えて発電所を攻撃するという情報もあって、大学院で放射線を研究してた俺が公安に引っ張られたんだ。盾の家の施設や研究所も増えて、幹部しか知らないところも多い。中森はそのどこかに偽名で潜んでいるはずだ」
ドアの向こうを気にしながら、新海は切羽詰まった様子で捲し立てた。慎が口を開こうとすると再び手のひらを上げ、
「二週間後の火曜日。今と同じ時間に、ここに来い」
と言い渡してマスクをはめた。レバーを摑んでドアを開け、トイレを出て行く。新海の足音が廊下を遠ざかっていくのを聞きながら、慎は洗面台に向き直った。心臓は激しく鼓動しているが、気持ちは落ち着いている。
特命追跡チーム七十人を総動員しても摑めなかった中森の足取りを、一人で摑んだ。やはり俺の読みと判断は、間違っていなかった。必ず中森とデータを見つけ出し、警察という組織に本当に必要な人間は誰か、証明してやる。
目の前が開けた気がして、慎は顔を上げた。鏡の中の自分は笑っていた。冷徹で邪気に満ち、白い皮膚の下のどす黒いものが透けて見えそうな笑みだ。
「だが、正しいのは俺だ」
呟いて、慎は洗面台を離れた。ドアを細く開けて廊下を窺うと、既に新海たちの姿はなかった。トイレを出て廊下を戻り、階段を下りた。がらんとした階段の壁と天井に響く自分の足音を聞いていたら、胸に醒めて尖った高揚感を覚えた。