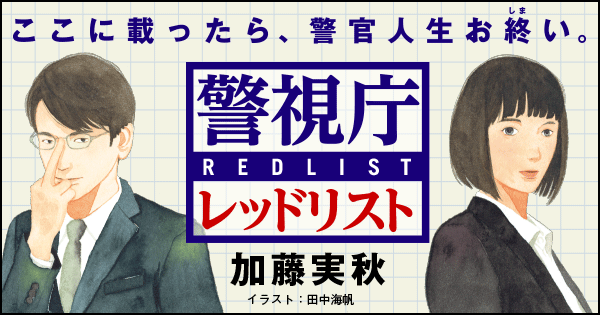〈第8回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

真相を突き止め、意外な処分を下す。
10
人差し指と親指を立てて右腕を上げ、みひろはフィニッシュのポーズを取った。曲が終わり、向かいのソファで拍手が起きた。
「よっ。みひろちゃん!」
「スナック流詩哀(ルシア)のPerfume!」
ジャージ姿の吉武(よしたけ)と、襟を立てたポロシャツを着た森尾(もりお)が声を上げる。二人の両脇では、ドレス姿のエミリとハルナが水割りを作ったり、おしぼりでテーブルを拭いたりしながら笑っている。
「はいはい。どうも」
みひろは手を振って小さなステージを下り、マイクを吉武に渡してカウンターに戻った。スツールに座り、グラスを取って飲み残しのビールを喉に流し込む。
「く~っ、旨い! ママ。ピザトーストちょうだい」
「なにそれ。普通『おかわり』か『もう一杯』でしょ」
無表情で突っ込み、カウンターの中の摩耶(まや)ママは鼻から煙草のけむりを吐いた。ママの前にグラスを置いて眉根を寄せ、みひろは返した。
「わかったわよ。ビールもお願い。もう、うるさいこと言わないで」
「とか言って、振りつきのノリノリで『チョコレイト・ディスコ』を歌ったじゃない。あんたが上機嫌な証拠よね。なんかいいことあったの? 白状しなさい」
ワサビ色のアイシャドーで飾られた目をこちらに向け、ママが迫る。今日は胸元にレースをあしらったワンピースという恰好だが、真っ黒でボリューミーなので魔女に見えなくもない。
「いいことなんてないわよ。さんざん働いて、くたくた」
そうぼやき、店内に視線を巡らす。
壁の演歌歌手のポスターも、カウンターの上の胡蝶蘭の鉢植えもいつも通り。隣に座っていたサラリーマンの二人組はさっき帰ったので、カウンターに他に客はいない。後ろのステージでは、エミリがJUJUのバラードを情感たっぷりに歌い上げている。時刻は間もなく午後八時だ。
今日はあのあと用賀分駐所から本庁に戻った。みひろは報告書を書き、慎は「ちょっと根回しに」と職場環境改善推進室を出て行った。そのまま慎は戻らず、午後五時になったのでみひろは書き上げた報告書を慎の机に置いて退庁し、スナック流詩哀に来た。
「でもまあ、初仕事の失敗は取り戻せたかな」
視線を戻して付け加えたが、ママはピザトーストを作りに行っていていない。小皿のミックスナッツを口に放り込み、みひろはジャケットのポケットからスマホを出した。カラオケを歌っている間に、豆田からLINEにメッセージが届いていた。読むと、みひろの退庁後慎から報告書を受け取ったこと、里見は内規違反処分で赤文字リスト入りは免れそうなことが記され、最後に「別件で阿久津さんに電話してるんだけど、出ないんだよ。ひょっとして、一緒にいたりしない?」とあった。
「いたりする訳ないでしょ」
眉間にシワを寄せて呟きながら、慎の根回しの早さと凄腕ぶりに驚いた。
左遷されても、エリートはエリート。それなりの人脈と影響力は維持してるってことか。言動にイラッと来るところはあるけど、ちゃんとこっちの話を聞いて仕事ぶりも見てくれるし、上司としては「当たり」なのかな。職場環境改善推進室の職務も、そんなに悪くないかも。そう思うのと同時に、取り立て屋の男を追い込んだ時の、慎の冷たく勝ち誇ったような笑みが蘇る。ぞくりとする一方、引っかかるものを感じた。だがそれが何かまでは、今のみひろは興味を持てない。
豆田に適当に返事を書いて送ると、ママがピザトーストを持って戻って来た。みひろは歓声を上げてスマホをポケットに戻し、ピザトーストが載った皿に手を伸ばした。
11
同日同時刻、慎は昭島市にいた。市の北側の、立川市との境にある工場街。その一角に車を停め、通りの先にある施設を見ている。施設は広い敷地を上に鉄条網、裏側に目隠しの鉄板が取り付けられたフェンスで囲まれ、中は見えない。出入口の脇の壁には「日本光環境研究協会」と書かれた小さな表札が出ているが、背の高い鉄の扉は閉ざされ、人の出入りはない。
無関係を装っているが、ここは「盾(たて)の家」という団体の研究所だ。盾の家が開設されたのは二〇〇〇年代前半で、代表は元学習塾講師の扇田鏡子(せんだきょうこ)という七十二歳の女。放射線の有害性を訴え、空気や大地、食品に含まれる放射性物質を遮断・除去する効果があるという装置や生活用品などを製造している。いわゆるカルトで本部施設は八王子(はちおうじ)市にある。そこでは扇田とその家族、百名ほどのメンバーが生活しており、この研究所でも約四十人が寝起きし、放射線関連の研究をしているという。
慎がここで見張り始めて三日になる。先日佐原から得た情報である人物が浮かび、調べたが、昨年秋に昭島南署警務部に異動になったのを最後に記録が途絶え、現在の職務はもちろん、自宅の住所や電話番号なども不明だった。それが何を意味するか慎には察しがついたが、次の手を考えあぐねていたところ、里見亜子の父親が昭島南署を擁する第八方面の副本部長・佐久間正二(さくましょうじ)だと判明。すぐに「義理の息子について内々の話がある」と面会を取り付けて里見の借金について話し、「情報と交換に里見は内規違反処分で済ませる」と持ちかけた。佐久間はこれを承諾し、慎にある人物についての情報を与えた。その時点では里見と川口の件は不確定で一か八かの賭けだったが、間もなく証拠を摑み、今日里見たちの証言も得た。
しかし、ぬかったな。亜子は結婚のかなり前に警視庁を退職したので、身上調査票は未確認だった。三雲みひろに言われなければ、佐久間の利用価値に気づかなかった。発想だの着眼点だのと適当に言ったが、思ったよりは使えるやつなのかもな。そんな考えがふとよぎったがどうでもいいことだと受け流し、慎は助手席から盾の家の資料を取った。
カルトとしては小規模で扇田の主張に科学的根拠はなく、メンバーも煽動されているだけで放射線と放射能、放射性物質の違いも理解していないような者ばかりだ。しかし過去には放射性物質を所持したり、「体内に溜まった放射能を排出させる」とメンバーの男性を棒のようなもので殴打し重傷を負わせたりして、メンバーが逮捕されたこともある。
一時間が経過したが、動きはなかった。盾の家のメンバーは外部の人間との接触を避け、警戒心も強い。今夜も収穫なしか。そう思い、慎はジャケットのポケットからスマホを出した。豆田から何度か着信があったのは気づいていたが、無視していた。
金属の軋む音に、慎ははっとして顔を上げた。研究所の扉が開き、中からフード付きのつなぎを着た男が出て来た。頭にフードをかぶっているが、縁の部分にゴムが入っており、顔の周りまですっぽり覆われている。放射線防護服の模倣と思われるが、色は黒。加えて、黒く大きなマスクも装着している。
男が研究所の敷地を出て周囲を見回したので、慎は頭を低くして隠れた。敷地に戻った男は扉を全開にし、中から黒いワンボックスカーが出て来た。ワンボックスカーは一旦停まり、男が後部座席に乗り込むと再び走りだした。すぐに中の誰かが扉を閉める。
ワンボックスカーが通りを直進して突き当たりの大通りに出るまで待ち、慎は車を出した。大通りに出てからも、通常の倍以上の間隔を空けてワンボックスカーを尾行した。ある人物がワンボックスカーに乗車していた場合、通常の間隔ではすぐに気づかれてしまう。
一時間近くかけ、ワンボックスカーは都心に出た。停車したのは、曙橋(あけぼのばし)の靖国(やすくに)通りから脇に入った道だ。慎は靖国通りに車を停め、徒歩で脇道に入った。近寄って見ると既にワンボックスカーは無人だったが、乗っていた男たちの行き先はわかっている。道の先の古いビルだ。