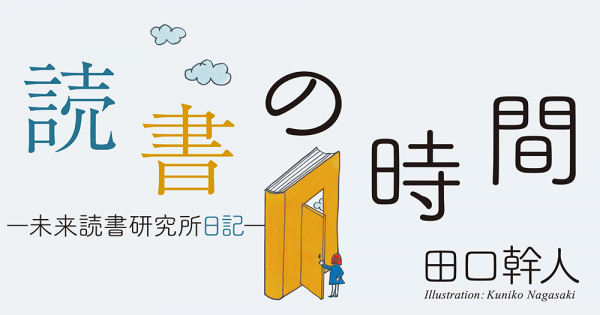田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第15回
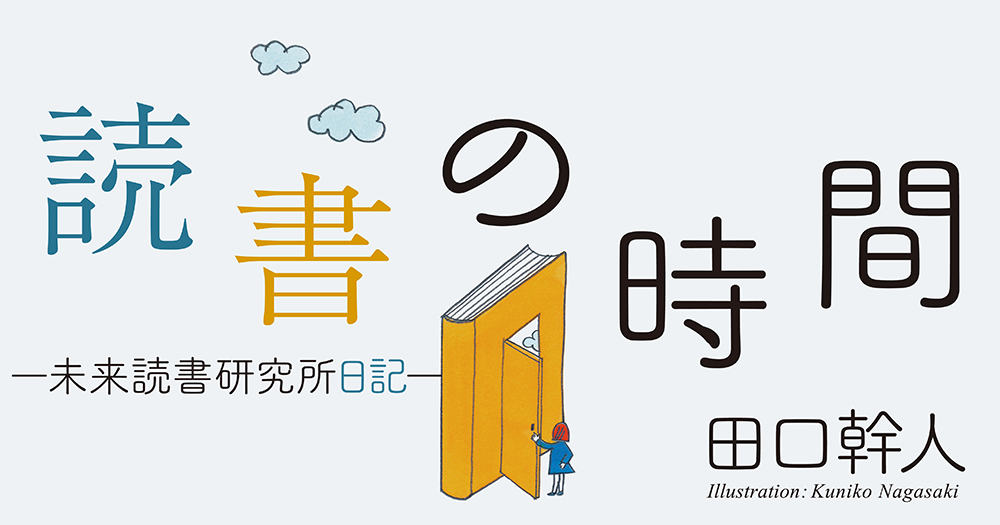
「すべてのまちに本屋を」
本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ
令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまへ、心からのお見舞いを申し上げます。そして、ご家族や大切な方々を亡くされた皆さまへ、謹んでお悔やみを申し上げます。今なお余震が多発し予断の許されない厳しい状況が続いているとの事ですが、一日も早い復旧と復興を願っております。
明日も生きているのが当たり前だと思っていた。
東日本大震災を経験するまでは。
2011年3月11日、僕は岩手県盛岡市で被災した。東日本大震災は、人間は自然の前では無力に等しいことを痛感した出来事だった。「衣食足りて礼節を知る」という諺を思い浮かべ、衣食住が満たされないうちは「嗜好品」は必要とされないのではないかとまで考えた。あの時、正直本屋にできることはもうないのではないかというあきらめさえ抱いたことを覚えている。
本屋に生まれ、子どもの頃から本に囲まれて、好きな本を好きなだけ読むことのできる環境で育った僕は、心のどこかで本は嗜好品だと思っていた。本は、本を好きな人が読むもので、気持ちに、あるいは時間的・経済的に余裕のある人が読むものなのかもしれない、と。
しかし、そうではないということをお客様から教えてもらった。
それはまたの機会に書きたいと思う。
繰り返しとなるが、今はまず被災された地域の皆さまに十分な衣・食・住環境が整備されるために微力ながら自分にできることをするだけである。
昨年末、公益社団法人日本図書館協会(以後、日図協)の図書紹介事業委員会が主催する「Live! 図書館員のおすすめ本-人はなぜ本を紹介するのか」というイベントでお話をさせていただいた。
日図協が発刊している『図書館雑誌』には、「図書館員のおすすめ本」というコーナーがあり、毎月様々な図書館員の皆さんが本の紹介をしている。掲載された「図書館員のおすすめ本」は、日図協のホームページにも一覧として転載されている。取り上げられている書籍は、新刊に限らず、ノンフィクションを中心に、世相に合わせたものが取り上げられている。新聞や雑誌、様々なwebの書評サイトは、比較的新刊が多いのだが、「図書館員のおすすめ本」を読んでいると、新刊本に追われず、既刊本においても「今こそこの一冊」というスタンスで紹介されていることが分かり、レファレンスという図書館員さんの仕事の一端を垣間見た気がする。
興味深い書籍がたくさん紹介されているので、「図書館員のおすすめ本」をチェックしてみてほしい。
前回は、本とのタッチポイントについて書かせていただいた。
市場規模を算出する意味で、タッチポイントを「書店」「CVS(コンビニエンスストア)」「インターネット」「その他店舗」「出版社直販」「電子出版物」「図書館」「教科書」の8つに分類してご紹介させていただいたが、本と出合いの場としてのタッチポイントはもっとたくさんある。新聞や雑誌、様々な web の書評サイト等を通じて誰かの読書体験のアウトプットを見た誰かが、紹介された本に興味を持ち、自身の次の読書の参考にすることもまた本とのタッチポイントと呼べるのではないだろうか。
この意味においては、「図書館員のおすすめ本」もまた本とのタッチポイントであるし、図書館員さんという本のプロが選ぶ今を反映したおすすめ本は、『図書館雑誌』の読者と図書館関係者だけではなく、もっと広く読まれる環境があればいいのに、などと思っている。
そんなことを考えていたら、僕も久しぶりに本を紹介したくなったので、一冊ご紹介させていただきたい。
忘れられない年となった2011年、もっとも多く使われた言葉は、「絆」だったのではないだろうか。人と人との縁が強く残る僕が住む東北でさえ、地域の繋がりが希薄になりつつあると感じていた矢先に起きた震災が、今一度「絆」や「繋がり」というものの大切さを意識させてくれた。使い古された言葉かもしれないが、僕はたくさんの皆さんに助けていただいたこともあり、「絆」や「繋がり」をあんなにも自分事として感じることができたのははじめての経験だった。
次は僕の番である。すぐにでも現地にうかがいたい気持ちもあったが、現在の被災地のニーズと僕のリソースがマッチしていないだろうと思われることから、その時が来るまでは今できることをしっかりやろうと思って日常を過ごしている。
2024年は、年始から震災の報道に限らず、連日、目を覆いたくなるような痛ましい事故のニュースをテレビや新聞などで目にする。
戦争で負傷した少年少女の痛々しい姿、自然災害の影響でこれまでの日常を奪われた人たち、航空機事故、理不尽な出来事に襲われた人たちの姿に、当事者の心境や状況を想像し、心を痛め、憤る人は多いだろう。
しかし、数日が過ぎ、テレビや新聞から事故の続報が聞こえてこなくなった後の当事者たちの苦悩や憎悪を想像し、思いを馳せ続ける方がどれだけいるだろうか。
『これからの誕生日』(穂高明著/双葉文庫 ※図書館、古書店、電子書籍でおさがしください)は、演劇の大会に向けての合宿の帰りに乗車していたバスが事故に遭遇し、その事故でたった一人生き残った高校生・千春の苦しみが、弟・伯母・被害者の母親・担任の教師・地元紙の新聞記者、そしてケーキ屋の6人の他者の心情を通じて描かれている。
生き残ってしまった千春の罪悪感と遺族や友人の胸に湧き出る憎悪と妬みが縦の軸に、千春を取り巻く者たちが抱える過去を横の軸に物語が編まれている。
周囲の人々が、彼女に向ける同情や善意、そして悪意と興味本位の言葉が入り乱れる。その言葉は、時に発言した人の意図しない受け取られ方をすることがある。良かれと思い何気なく発した言葉が、人を傷つけることがあるのだ。
そして、発した者は、発した瞬間に自身の言葉を忘れてしまう。しかし、受け取った者には、強く印象に残り、心の奥に傷として残り続けるのだ。お祝いの言葉が妬みに、励ましの言葉が憎悪に、がんばろうという言葉がプレッシャーに感じてしまうことがある。
それは「言葉」というものの怖さだろう。
「どうして、自分だけが生き残ってしまったのか」。千春は、自分を責めることで深い深い心の傷を負う。そして、その痛みを抱えて過ごす日々が続いてゆく。物語が進むにつれて、少しずつ千春を取り巻く者たちの過去が明かされてゆき、痛みを共有することで読者も「これから」を見据える。
僕が本書を読んだのは、2011年の6月だった。すごく心に残った素晴らしい作品だったが、その時はおすすめ本として紹介することができなかった。
東日本大震災は、あまりに多くの当事者がいた。
生き残った多くの方々が、自分を責め、自分が生きている意味を考えたことだろうと思う。僕もその一人である。
当事者でない人にとって、ひとつの事故や事件は、次々と起こる新しい出来事に覆い隠され消費されてゆく。しかし、当事者たちの苦しみは果てしなく続くのだ。当事者ではない僕たちができることは何だろうか?
それは、見守り続ける覚悟をすることなのではないだろうか。最後の「十八本のロウソク」というケーキ屋の主人の物語に、その想いを読むことができる。ケーキ屋の主人は話す。
「お客のために毎年決まった日にケーキを焼くのが生き甲斐。誕生日ケーキは、毎年ひとつひとつ歳を積み重ねてゆくことの証明みたいなものだから。ひとつひとつのケーキを焼きながら、また一年経つんだね、と嬉しくなる」と。
生まれ変わることはできないかもしれない。しかし再びやり直すことはできる。どんな苦しみを抱えていても、毎年誕生日はやってくるのだから。
誰かが手を差し伸べてくれることが救いとなり、そして誰かに見守っていてもらえることが、一歩を踏み出す勇気の糧になるのかもしれない。僕は、何もできないけど「これから」をずっと見守っていこうと思う。そんな想いを抱かせてくれた切なくも優しい人間の物語だった。
非当事者ができることは何だろう?
書店の店頭を離れて丸5年を迎える。
その間、経営者として書店に関わり続けてはいる。経理、総務、法務、入札、契約。それもまた書店を運営するには大切な仕事である。分かってはいるのだが、書店に関わっている以上、やはり店頭で本を仕入れ、棚を耕し、ご来店いただくお客様に本を手渡したいと強く思うことがある。
今、それは叶わないが、いつの日か必ずまた、と考えている。
田口幹人(たぐち・みきと)
1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。


![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)