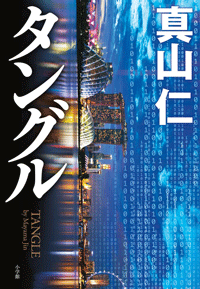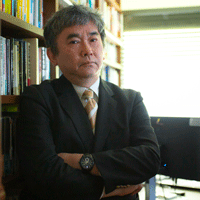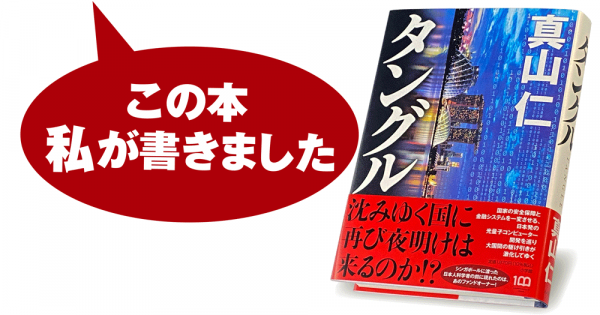真山 仁『タングル』
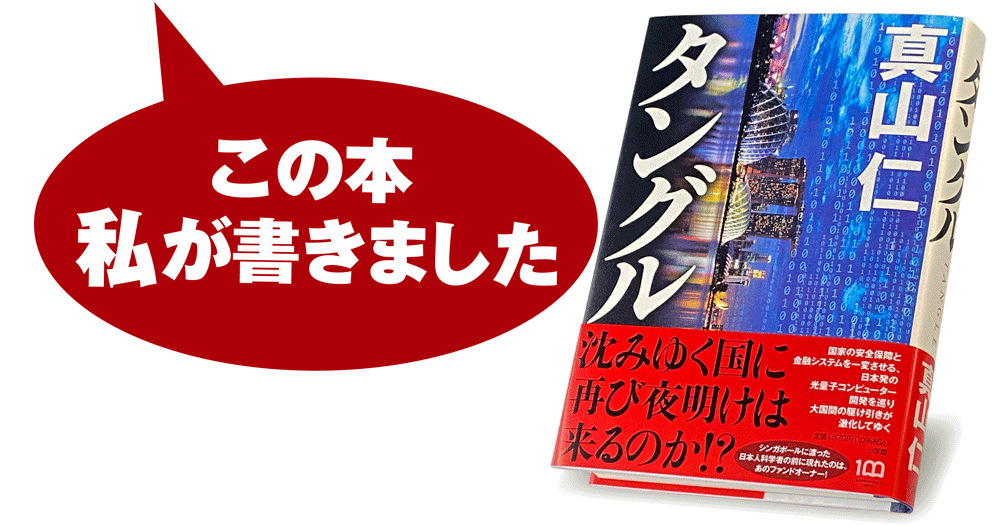
三つのお題がもつれて生まれた光の物語
シンガポール、量子コンピューター、ウルトラマン――。この三つのキーワードで物語をつくれ!
いわゆる三題噺は落語の形態で、客に自由に三つの「お題」を決めてもらい、それを落語家が一つの噺にまとめる趣向だ。
最近では、就職試験の小論文で出される場合もあるようで、確か私が就活をしていた頃には、小学館の入社試験の名物(私は受験しなかったが、これだけは挑戦したかった)だった気がする。
小説を書く時、私は、この三題噺のように一見まったく無縁のテーマを作品に放り込み、付きつ離れつしながら、なんとか収斂していく――というプロットを考えがちだ。
何より意外性があるし、書き手とすると、チャレンジが楽しいからだ。
成否は別にして、新作『タングル』は、冒頭に掲げた三つのお題を盛り込んだ。
まずは、シンガポールを舞台に設定した。そのうえで、日星(星はシンガポールの略語)共同で世界最先端研究プロジェクトを行う物語とし、その目玉を、世界初の量子コンピューターの実用化に据えた。
シンガポールと言えば、世界有数の金融大国であり、最近では統合型リゾート(ルビ=IR)の先進地として知られる。一方で、モノづくりは「苦手」という印象を持たれている。だからこそ、小説では技術開発の最先端に取り組むという意外性を狙った。
また、従来の量子コンピューターは、超伝導を用いた形式が多いのだが、本作では、光子(光の粒子のことで、量子の一つ)を用いた光量子コンピューターの開発にフォーカスした。構想当時は、超伝導タイプが実用化間近と言われていたが、取材を通して、一発逆転の可能性があること、さらに、その最先端に日本の研究者がいることを知って、光量子コンピューターを選んだのだ。
そして、ウルトラマンだ。今年は、日星外交樹立五五周年に当たるが、ウルトラマンも、今年が誕生五五年なのだ。
シンガポール政府観光局は、その縁を結び、両者がコラボレーションするPR戦略を展開した。それを執筆中に知って、ウルトラマン世代の私としてはどうしても投入したくなったのだがそれは、ウルトラマンが「光の国」に生まれているからだ。
この共通点に気付いた瞬間、三つのお題は絶妙にもつれ、物語の中で化学反応した。
ちなみにタングルというのは、英語で「もつれる」という意味であり、「もつれ」は、量子力学の重要なキーワードであり、その仕組みを発見した研究者に今年、ノーベル物理学賞が授与された。
真山 仁(まやま・じん)
1962年、大阪府生まれ。同志社大学法学部政治学科卒。新聞記者、フリーライターを経て、2004年、企業買収の壮絶な裏側を描いた『ハゲタカ』でデビュー。同シリーズはドラマ化、映画化され大きな話題を呼ぶ。他の著書に『マグマ』『売国』『当確師』『オペレーションZ』『ロッキード』『墜落』など多数。