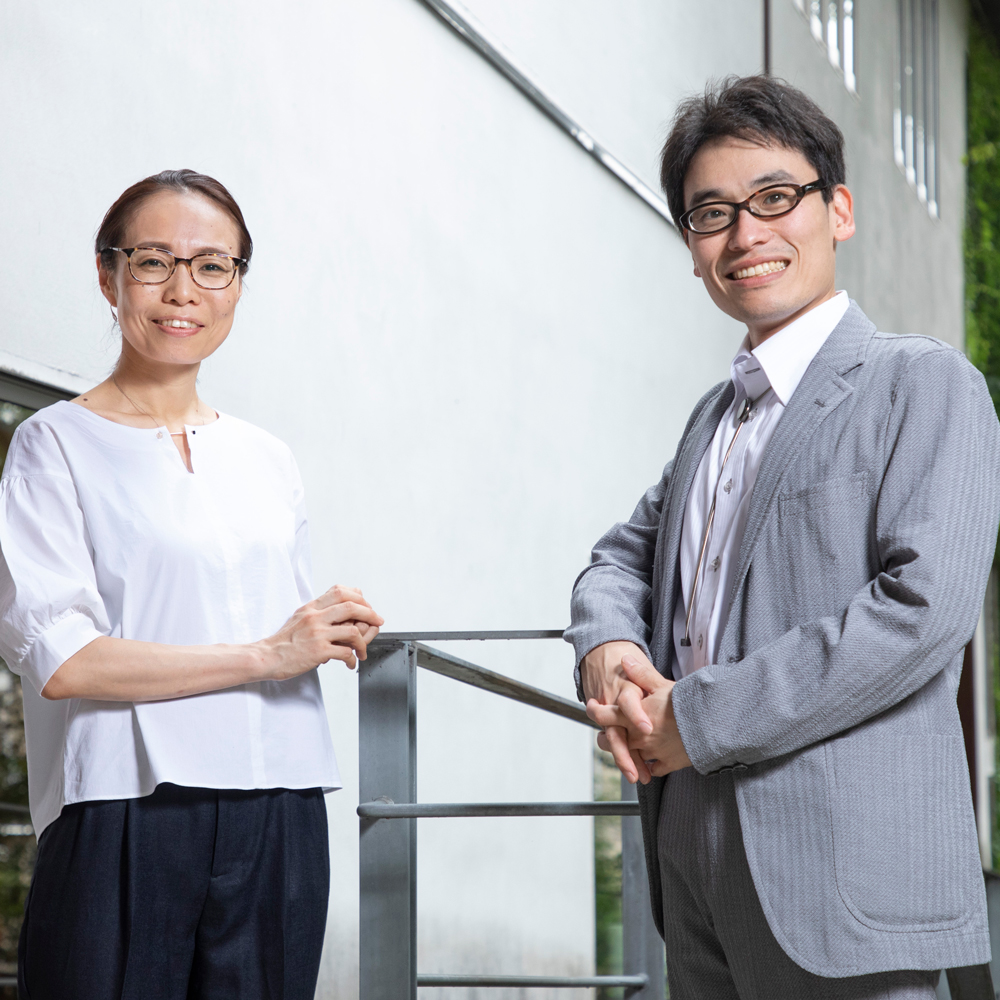長月天音『私が愛した余命探偵』

『悲しい』よりも『楽しい』がいい
私は夫を自宅で見送った。自宅といっても賃貸のマンションである。
一緒になった時に2人で選んだ部屋であり、いつかはまた別の住まいへと移っていくものと思っていた。しかし、その部屋が夫にとって終の棲家となった。
そこでの暮らしはわずか6年である。入退院を繰り返す夫と枕を並べて眠ったのは5年に満たないと思う。短い。
最後の半年は在宅緩和ケアに切り替え、訪問看護に支えてもらいながら密度の濃い時間を過ごした。
夫の呼吸に耳を澄ませ、わずかに上下する胸を見て安堵し、いつも冷たく乾いた手を握って眠った。いや、実際にはほとんど眠ることなどできなかった。
でも、私は願った。このままこの状態でもいいから、ずっと一緒にいたいと。
遠からず必ず消えると知っている命を見守るのは苦しい。
その苦しさを抱えながら、愛する人のために懸命に生きる姿を描きたいと思った。
おそらく根底にはつねに悲しみがある。恐怖があり、不安があり、虚しさがある。
しかし、まだ彼はそこにいる。暮らしも守らなくてはいけないから仕事も続ける必要がある。その状況でも「最高」と思える日々を送れたら……。
そういう時こそ笑いと明るさが必要だと思う。ささやかな笑いでいい。から元気でもいい。そうしていれば何だか「大丈夫」と思うことができる。
お世話になった看護師さんも、ヘルパーさんも皆、明るかった。元気でパワーがあった。夫も笑った。彼ら、彼女たちが帰った後、「楽しかったね」と2人で笑っていた。
そんな日々を物語にしたら『私が愛した余命探偵』はでき上がった。
幸せだけど、儚い日々を繊細なケーキに重ねた。ケーキは一時の幸せだ。
しかし、パティシエの労力を惜しまない仕事が隠されている。
華やかで繊細な形状。何層にも重なる違う味わい。中央に驚くべき仕掛けが隠れている場合もある。
それらが見事にまとまり、完成されたケーキとなる。単純ではなく、いくつもの異なる要素が絡み合う。甘かったり、酸っぱかったり、ビターな場合もある。少し人生に似ている。
実は、私は洋菓子店で働いたことがある。クリスマスの時期は死ぬほど忙しい。何日も終電に間に合わないほどケーキと格闘する。もうやるものか、と何度も思った。
しかし、私はその店を辞めた後、別の洋菓子店でも働いた。
ようは、やっぱり楽しいのである。
愛すべき、けれど憎らしいケーキは、確実に人を幸せにする。
そんな物語をこれからも書いていきたいと思う。
長月天音(ながつき・あまね)
1977年、新潟県生まれ。大正大学文学部卒業。「ほどなく、お別れです」で第19回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。他の著作に『ほどなく、お別れです 思い出の箱』『神楽坂スパイス・ボックス』シリーズ、『キッチン常夜灯』などがある。