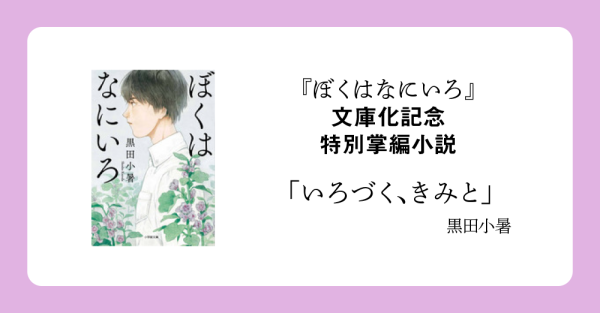『ぼくはなにいろ』(黒田小暑著)文庫化記念!特別掌編小説「いろづく、きみと」
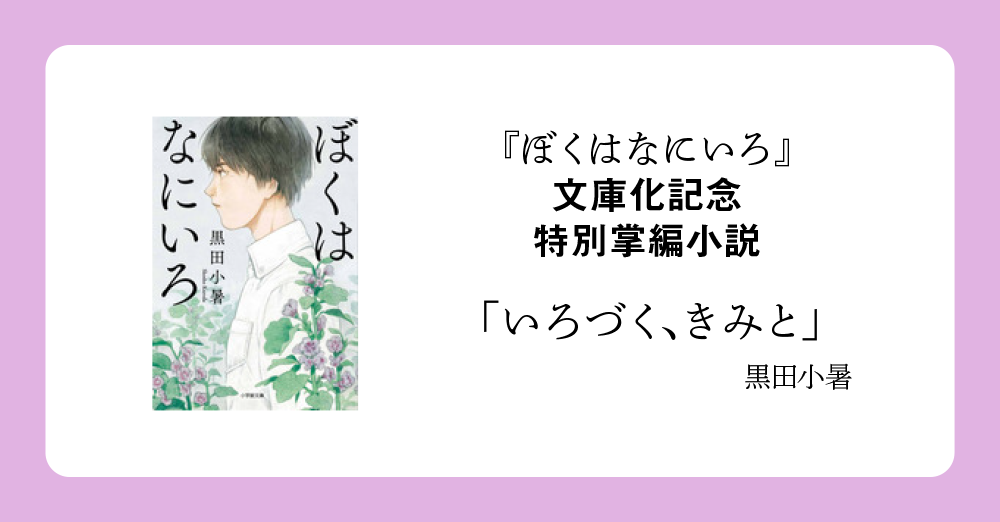
春 Ⅱ
トイレ用ブリーチを注ぎながら、祥司は右手首の腕時計を盗み見た。十四時十二分。あと一時間二十三分。便器用洗剤のボトルを持ち替え、雑巾で便器の外側を磨く。十四時十三分。あと一時間二十二分。次にセンサー周り。十四時十四分。あと一時間――。
「それ、ブリーチ」
ふいに、横から崎田の声がした。祥司は尻餅をつきそうになる。
「センサー周りはこっち。あと、雑巾も替えたほうがいいんじゃねえの」
そう言ってカートから新しい雑巾を取り、祥司に投げてよこす。
このショッピングモールで清掃員として働きはじめてこの方、アルバイト時代までさかのぼっても、祥司が公休以外で仕事を休んだことは一度たりともなかった。ここにきて、突然、希望休の申請などしようものなら、同僚たちの噂話の種となることは間違いない。希望休の理由を詮索され、万が一にでも千尋の存在を知られてしまったら面倒だ。およそ半年ぶりに千尋が東京に戻ってくるという日に祥司が休みを取らなかったのは、そういうわけだった。渡された今月のシフト表、今日の日付の欄には、当然のように出勤の文字が記されていた。
「――ったく、朝から時計ばっかり見やがって。なに、このあとデートの予定でもあるわけ?」
思わず洗剤のキャップを取り落とす。
「なんだよ、図星かよ」
「……そういうわけじゃないけど」
「前に駐車場に来てた美人か」
祥司は弾かれたように顔を上げた。
「何時に、どこ待ち合わせだよ」
首筋にナイフでも当てるような、穏やかだが鋭い口調。これが出ると、もう答えないという選択肢はなくなる。
「……十五時三十五分羽田着の飛行機で、東京に戻ってくるんだ」
「で、おまえはなんでここにいるわけ?」
崎田に言われるまでもない。こんな大事な日に、どうして自分はこんなところで、こんなことをしているんだろう。今日、出勤して、ロッカールームで支度をしているときから、後悔が波のように押し寄せてきている。今日はなにをやっていても身が入らない。目をつぶってでもこなせるほど熟練した作業の手順を間違え、それをまさか崎田に指摘されるなんて。
「……仕方ないだろ。おまえには関係ない」
そう吐き捨て、小便器に向き直る。だが、崎田はそれに倣おうとはしなかった。
「――おまえ、財布はロッカーか? いま、いくら持ってる?」
金を貸せということか。また逃げるつもりだろうか、よりにもよってこんな日に。祥司は唇を嚙みながら、黙って首を横に振った。
「……財布はいまあるけど、二千円しか入ってない」
舌打ちの音。
「仕方ねえな」
祥司の目の前に、すっとなにかが差し出された。
それは、金だった。二つ折りの、くしゃくしゃの一万円札だ。
「タクシーで飛ばせば、ぎりぎり三時半に間に合うだろ」
「は? なに言ってんだよ」
「――っせえな。いまから羽田に向かえってことだよ」
そう言われても、やはり理解が追いつかない。こいつは他人に金を貸すような人間ではない。他人の状況を慮るような人間でもない。そのはずだ。それが、祥司の知っている崎田だ。
「――俺たちに、明るい未来はあるか?」
祥司の戸惑いを見て取った崎田が、その戸惑いをいっそう深めるような問いかけを口にした。
「豊かな人生。明るい未来――。あの試合のあと、どいつもこいつも口を揃えて俺に言ってきたよ」
崎田が清掃用具のカートを蹴る。
「馬鹿じゃねえの。ボクシングがないのに、そんなもんあるはずがないんだ」
勢いよく滑ったカートが、洗面台の一つにぶつかって止まった。
「だけど」
崎田が自らカートを引き戻す。
「おまえみたいなしみったれたやつがあんな美人をモノにできるんなら、そのクソみたいな明るい未来ってのが、もしかしたらあるのかもしれねえな」
ふざけた台詞だが、その顔はいたって真面目だった。祥司はそこに、大樹だったころの崎田の姿を見た。中学時代の祥司が縋り、憧れた男の面影だ。
「でも――でも、俺、今日は四時までだ」
「抜け出すんだよ」
「そんなことできないよ」
「残りを俺が終わらせて、四時になったら控室に戻ってチェック表に二人分サインしとく。大丈夫、俺の字もおまえの字も分かんねえよ。おまえは、いまからここを抜け出して羽田に向かう。ここ出てすぐ左にバックヤード入口があるだろ。入ったらずっとテナント倉庫が続いてんだけど、突き当たりまで来たら、右手に階段がある。そこを下りていったら、従業員通用口の、荷物用エレベーターの横だ――分かってると思うけど退勤は押すなよ。タイムカードはそのままで帰って、次の出勤のとき適当な時間を手書きすればいい。サボりより勤怠の押し忘れのほうが怒られない」
「……なんか、やたら詳しいな」
「いつもやってるからな」
事もなげに言う。
「行けよ。俺のこと、とりあえず今回だけは信じていい」
崎田が顎をしゃくる。祥司はすでに雑巾を置き、ゴム手袋を外していた。だが、まだ肚が決まらない。
「ほら、早く行け。おまえの明るい未来のために一番大事なもんは便所掃除なのか? そんなんだからおまえはいつまでもしみったれてんだよ」
それでもやはり、足は動かない。崎田が、一万円札を握りこんだ拳で祥司の腹を突く。
「行け。いいか、俺が言ってんだ」
ロボットの電源がオンになったかのように、ふいに体が動いた。祥司は崎田の一万円札を奪うように摑むと、踵を返して駆け出した。説明されたとおりのルートを通り、一目散にショッピングモールの敷地を出る。
また、崎田に走らされている――。いつかの出来事を思い出して、必死に走りながら祥司は笑った。
すぐに流しのタクシーを捕まえた。羽田まで。
やった。やってしまった――。だが、その興奮も、呼吸とともに徐々に落ち着いていく。額や脇の下にじんわり汗をかいている。体は熱いが、足に痛みはない。
十四時三十八分。間に合え。間に合ってくれ。
祥司は、身にまとっている、ずいぶんくたびれた制服を見た。その下にある、汚く醜い体のことを、自らの化け物のことを想った。千尋と分け合い、崎田とも分け合った化け物。心なしか、その色が少し薄くなっているように感じる。
〈到着ロビーにいます。降りたら連絡ください〉
それだけ送信して、すぐにスマートフォンをブラックアウトさせる。
祥司を乗せたタクシーは順調に進んでいる。車内には弱い暖房が入っていた。全力疾走のあと急に止まったせいか、額や首筋や脇から汗が噴き出してくる。祥司は、仕事着のシャツのボタンに手をかけた。
――あ。
上から二つ、ボタンを外したところで、祥司はふと手を止めた。開いた胸元からポロシャツが覗いていた。パステルブルーの、半袖のポロシャツだ。
すっかり忘れていた今朝の自分の行動が、みるみる脳裏によみがえってきた。会いに行けるとは思っていない。だが、千尋が東京に戻ってくるというその日の朝、壁に掛かったポロシャツに目が留まったのだ。もうずっとそこにあって、見飽きた部屋の風景の一部としてすっかり馴染んでいた、半袖のポロシャツ。それが今朝は、周りの風景から切り離されて見えた。祥司はそれを、くたびれた肌着と仕事着のあいだに着た。持っておくだけなら構わないでしょう、といつか千尋がプレゼントしてくれたポロシャツを、今日、祥司は着ることにした。いつも通り便器を磨いたり燃えるごみを回収したりしながらも、今日という日を特別にしたかったのだ。自分なりに、密かに。
仕事着のボタンを一番下まで開け、さらにポロシャツのボタンも外して、祥司は車窓を見るともなく見ていた。このポロシャツを着るに至った今朝の出来事が、千尋がこれを買ってくれたときのことを思い出させ、そこからさらに千尋と過ごした日々の記憶が呼び起こされた。
タクシーが静かに停まって、現在に引き戻される。気づけば、すぐそこに羽田空港の巨大な建物が見えている。ほんのわずかな時間のつもりだったが、すでに三十分近く経っている。
崎田が貸してくれた一万円札で料金を支払い、お釣りをポケットに捻じこみながらタクシーを降りる。不意の突風に、羽織っているだけの仕事着がはだける。反対のポケットでスマートフォンが震えた。〈着陸しました!〉というメッセージをポップアップ表示で確認し、祥司は歩調を速めた。
空港内に足を踏み入れると同時に、さまざまな種類の喧騒が祥司に向かってきた。ひらひらとはためく仕事着の前身頃をしっかりと摑み、まっすぐ到着ロビーを目指す。
――これから、千尋に会うのだ。
その事実が、急に祥司の胸に迫ってきた。どんどん速まる鼓動に合わせて、祥司は知らず小走りになっている。
到着ロビーに辿り着いたときには、すっかり息が上がっていた。手荷物受取所からは、すでに、福岡発の便でやってきたらしい多くの人々が吐き出されている。
祥司は、その人波に目を走らせた。そこに千尋は含まれていないようだ。自動扉のほうへ視線を移す。数日前の電話で、髪色は黒に戻したと言っていた。長さはそれほど変わっていないはずだ。スーツケースは赤。今日の服装を訊いておけばよかった。
とはいえ、最後に直接その姿を見たのは、もう一年半も前だ。背格好や目鼻立ち、おぼろげな記憶を手繰り寄せる。
千尋、千尋、千尋。瞬きする間も惜しんで、そこに現れるはずの千尋を待つ。まだ見つからない。もしかして、見逃したのだろうか。スマートフォンを見る。新しいメッセージはない。
電話をかけてみよう、と、受話器のマークを押そうとした、そのときだった。
自動扉の向こうに、赤いスーツケースが見えた。引いているのは女性。黒く長い髪。見間違うはずもない。
祥司は歩き出した。仕事着を脱ぎ、ぐしゃぐしゃと丸める。季節外れの半袖。周囲の視線は、しかし祥司の目には入っていなかった。見ているのはただ、数メートル先の千尋だけだ。
千尋の驚いた顔が、すぐ目の前にあった。両手から力が抜ける。掴んでいた仕事着が、ぽとり、と地面に落ちる。祥司は両腕を広げた。傷だらけの、裸の両腕を、何も構うことなく大きく広げた。
そこにいる千尋を抱き締めるために。