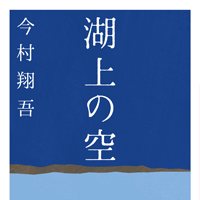源流の人 第37回 ◇ 今村翔吾(作家)

作家が繋ぐ本の未来
全国をめぐり、自ら書店を引き受けて感じた焦燥と挑戦
2017年の文壇デビュー以降、執筆活動のみならず、街の書店の経営、全国の書店をめぐる旅、子どもたちと本を繋ぐ社団法人の運営など、本に関わる、ありとあらゆる活動に情熱を注ぐ。今村は、その長文ポストでこう訴えた。
「やれることは全部やる。絶対に無理と言われても挑戦する。誰がやらなくても私はやる。そう覚悟を決めています」
それが約178万もの人々の目に留まり、1万を超える「いいね」がついた。作家として、街の書店主として、そしてひとりの読書ファンとして抱く、危機感、焦燥。そして、いまの自分が出版業界で取り組むこと、目指すもの。ほとばしる彼の思いは、瞬く間に多くの人々に共感をもって拡散していった。インタビュー冒頭、今村は顔をほころばせた。

「思った以上にめっちゃ回ったよね! あんなに反応あるとは!」
本はコスパがいい。だから勧めたい
『塞王の楯』で直木賞を受賞した後の2022年5月から、今村は全国47都道府県、津々浦々の書店をめぐる118泊119日の旅に出た。一度も自宅に帰らず、ワゴン車に執筆机を設置し、移動中も原稿を書きながら全国をめぐった。「まつり旅」と称したこの旅は、同年9月、山形県新庄市で完結したが、今村は旅の途中で、「発想の大きな転換が起きた」と振り返る。
「僕は本当に、書店に感謝し、応援したくて旅に出たんです。でも、旅の最中、ひとりでやることの限界を感じてしまった。最終的に280か所以上を回って、4か月間、お金も1000万円ぐらいかかりました。『これを毎年やるっていったら絶対無理やな』。体力的にも、お金的にも。そこで思いついたんです。だったら、ひとりが280か所を回るのではなく、いろんな人の力を借りて280人で1か所ずつ回れば、何かできるかもって」

それが2023年春、一般社団法人「ホンミライ」の立ち上げに繋がった。彼が代表を務める「ホンミライ」は、読書をする人を増やす活動の一環として、講演・セミナーを開催し、講師を派遣する事業を展開していく。読書に興味のなかった人にも、読書習慣を身につけてもらう活動だ。「ホンミライ」設立に際し、今村はこう記している。
「本に興味を持つきっかけをつくっていきたい。本を通じて地域の発展に貢献したい。そして言葉そのものの大切さも、同時に伝えていきたい」
今村はその意味について、こう語ってくれた。
「僕、本ってすごくコスパのいいもんやと思っているんです。たとえば、生まれたてで、何も世界を知らない人間が、1ヘクタールの田んぼの前で鍬1本を渡されて『耕せ』って言われたとするでしょう。何の知識もなければ10年かかるかもしれないけれど、あるところで本を読み、『トラクターというものがある』って知るのに1年、次(の作業について)調べるのに3年かかったとしても、その準備ができてしまえば4年目には全部耕すことができる。残りの6年を別の人生に使うことができる」
そして、「ホンミライ」では、言葉そのものの大切さも同時に伝えたい。このメッセージには今村の強い思いが込められている。
「敢えてきついことを言うと、言葉のプロじゃない人たちの言葉が全世界に発信されまくるこの世の中において、扱い方次第によって人を殺すことができる。それを皆、この5年10年で気づいているじゃないですか」

逆に言えば、たった一言で人生を実り多きものに変えることもできる。
SNSで簡単に発信できる現代だからこそ、言葉の扱い方、文章の使い方を気にしてほしい。気にかけてほしい。言葉は怖い。でも、言葉は素晴らしい。それを知っておかないと、未来は暗い。
今村は、アナウンサーや出版人ら、言葉や文章、本のプロたちに声をかけ、講師役として学校に派遣し、子どもたちに授業をしてもらっている。いまのところ、今村が現在暮らす滋賀県内で活動を行っており、行政と連携しながら事業内容のブラッシュアップに努めている最中だという。
「やってみてから考える。走りながら考える。『見切り発車』というと悪く聞こえますけど、やりながら修正していくしかないよね」
物語づくりの楽しさを一緒に知っていく
「ホンミライ」では、今村自身も教壇に立つことがある。低学年対象の授業で取り組んでもらうのは、「『桃太郎』(おとぎ話)の書き換え」だ。
「流れてくるのが桃でなかったら、何がいい?」
するとさっそく教室中、手が次々と挙がる。今村は快活な表情で語る。
「『メロンがいい!』『キュウリ!』って、めっちゃ出しよるの。あと、スイカは、なぜかどこで聞いても出てくるね」
いくつかの候補を黒板に書き記したのち、今村はさらに問いかける。
「じゃあ次、おばあさんが渡したものはなんですか。きび団子禁止ね!」
「仲間になるのは何ですか。イヌ、サル、キジ、禁止ね!」
再び教室が沸く。
「ライオン!」
「サメ!」
どれがいいか、多数決で決めていく。そして、決めたものを、ストーリーに当てはめ、繋いでいく。はたして繋がるのか、破綻するのか。子どもたちと共に、一つひとつジャッジしていく。
「サメって言ったけど、これ、鬼ヶ島上がれるか?」
「上がれへん!」
「じゃあ、次点のライオンに変えようか」
そして今村は、子どもたちにこう伝える。
「これが作家の頭の中で考えていることなんだよ」
いろんな意見を出していく。ライオン、トラ、強いお供ばかりになれば、「これ、めっちゃ強いけど、おもろいか?」と問いかけてみる。「鬼相手にライオンとトラ。桃太郎やることある?」。物語として圧倒的な力の差がついてしまうと、こんどは逆に鬼が虐められているように見えないだろうか。そんなふうに考えをめぐらせると、子どもたちはなお活気づく。そして今村はユーモラスに、彼らにこう語る。
「今村先生はこれを頭の中で、基本的に1分ぐらいで全部やってんで。すげえやろ!」

上級生を対象とした授業では、小説の冒頭1、2行で「読みたい」と思わせる小説を書く対決を試みる。今村は嬉しそうな表情のまま、こう教えてくれた。
「『僕がこの学校がロボットだと知ったのは、今朝のことだった』とか、書いてきよんねん。『これおもろいよな!』って。『冒頭がすごく大切で、小説の顔だよ』。読書感想文や論文も実はそうだし、人と会った時の第一声も、実は同じなんじゃないか。そんなことを僕が教えています」
そんななか、ある小学生が差別言葉を言ったことがある。すかさず、今村はこう語りかけた。
「今村先生が一番気いつけていることが、これやねん」
物語をつくるのは自由。けれども、誰かを傷つけるものになってはいけない。間違うこともあるけれど、だからこそ気をつけなければいけない。真摯に伝えれば、ちゃんと伝わっていく。
本屋のことを何も知らなかった
2021年11月、今村は、閉店の危機にあった大阪府箕面市の書店「きのしたブックセンター」の事業を承継しリニューアルオープンした。「作家が書店主に」というニュースは大きな話題となった。
「地元は喜んでくれていますね。僕が引き継いだ当時、文芸書がめっちゃ少なかった。仕入れられへんから、売れへん。売れへんとまた、仕入れられない。負のスパイラルでした。『いったんまず仕入れよう!』って言って、文芸書の量を2倍近くに増やしたんです」

選書に工夫を凝らした結果、いまや文芸書は店の主力の一つになった。つねにレジ前に最新の文芸書を並べるようにしたところ、読者層が広がり売り上げが飛躍的に伸びたという。
「きのしたブックセンターがすべての始まりです。店を引き継いでから僕は本屋さんのことを知りました。恥ずかしかったな。僕ら作家は言うんよ、『本屋のために』って。言うわりに何も知らない。そのことをまず知った」
たとえば、店頭に出てみて、思う以上に力仕事であることを知った。とにかく腰が痛くなる。それよりも心を痛めるのが、人件費だ。
「安いとは聞いていたけど、大手書店も含め、最低賃金じゃない書店の方が珍しい。たとえば書店員さんのつくってくれる POP(宣伝物)は、基本的に、家に持ち帰って、残業代もつかず、趣味でやるところがほとんど。書店員さんの給料が上がるわけでもない。『本が好き』と『やりがい』の搾取なんですよ」
ここについて、メスを入れるのなら何をすべきか。
今村が思いついた構想があるという。
それは、全国の書店員がつくった POP を、全国の書店で共有できるシステムの構築だ。彼は言う。
「たとえばAさんがつくった POP を、サーバー上に保存したら、絵や文字をつくるのが苦手な書店が1個100円でダウンロードして、そのうち30円40円が作成者の書店員さんのところに入るシステム」
売れっ子作家のための POP はみんながつくるから、ダウンロードに競争が生じる。いっぽう、書店員が推したい、まだこれからの作家の POP に関しては、オンリーワンになる可能性がある。サーバーの維持費の問題がクリアできたら、そうしたハブ(中継拠点)をつくっていきたいと今村は訴える。
「そもそも、POP がどうやってできているかを知らないと、発想すら出てこない。書店員さんにとって、『誰かが自分のつくった POP をダウンロードしてくれている』というのは、僕の本を誰かが手に取ってくれて印税が入ってくる喜びときっと一緒だと思う。そういう感じを書店員さんにも味わってほしい」
出版業界の中だけで解決しようとすると、限界があることもわかってきた。それなら、建築業、ECサイトなどの企業に聞いたり、テレビ業界に聞いてみたりする。まったく関係ない、伝統工芸で成功している企業のやり方をまねてみるのもよいかもしれないと発想する。
街の書店は、20年前と比べると約1万店に半減している。いっぽうで、「書店を経営したい」という人も、少なくはない。その人たちと、やめざるを得ない人たちをマッチングさせるやり方を模索したい。
「ただこれ、危険もあって。やりたい側は夢だけを語っていて、書店側は現実を知り抜いてる人たち。『こんなんじゃなかった』ってすぐ破綻する可能性があるんですよね」

だから、今の出版業界を知るために、小規模なスペースで1回試してみて、実地研修をした上で、引き継ぐか否かを決めてもらうのが良いかもしれない。今村は語る。
「ひとりの人生を潰しそうになってはいけない。キーワードとしてはまず『知る』こと。本当に興味を持っているのなら、書店、取次、出版社の現状を知る。そういうセミナーをやった方がいいかもしれんな。いろんな立場から、マイナスの面とプラスの面を伝えていく。うん。今、決めました。やろう」
今村はメディア出演の機会を増やしている。最初こそ、露出するべきか否か、迷っていたそうだ。彼は言う。
「僕が、尊敬する池波正太郎先生の教えを唯一破っているのがそれなんです。池波さんは『顔を出さない方がいい』っておっしゃる方でした。でも、林真理子さんや北方謙三さんに相談したら、2人とも、『出なさい』って」
作家として発信する人間が減り、作家が必ずしも「憧れられる職業」ではなくなってしまった。北方からは、「お前はもう、稀有な、みんなに遊んでもらえる存在だ。いつでも辞めていいからやれ」と背中を押されたのだという。「やれへん」っていう結論を出すのは、やってみてから。まずはやってみて、そのなかに学びやプラスになることがあれば、それでいい。
「『人脈』って言葉、あんまり好きじゃないけど、こういう繋がりは、テレビ出演のおかげやなって思っています。いろんなところから、教えてくれる人が出てきたし、『あの人に聞いたら答えがあるんじゃないか』っていう繋がりが出てきました。書斎から出て3年、いろんな人と繋がれるのは強いよね。ひとりではやれる限界があるから」
「吉田松陰みたいになれる可能性もある」
「きのしたブックセンター」や「まつり旅」を通じ、今村は、本に関わるさまざまな立場の人たちから話を聞き続けてきた。本を売る全国の書店。本を貸す図書館。本を配る取次会社。本を編んで出す出版社。そして作家。
それぞれの抱える思いや目指すもの、譲れないものを、ここ数年、一つひとつ聞いて回ってきた。ある一方の立場で見れば「悪い」と感じるものが、もう一方の立場で見れば「でも仕方ない」と思えてしまう。そこにズレやジレンマを感じつつ、出版業界という船がみるみる沈んでいくような焦燥感が、今村のなかで次第に立ち上がってきた。
「お互い言っていることはわかるんですけど、譲り合わない。もうずっと何十年間、平行線のまま。黒船が来襲している日本の幕末ぐらい、出版業界は、いよいよピンチだと思う。僕ひとりやったら大したことないんですけど、どんなことでも歴史を振り返れば、きっかけは誰かひとりのたった一歩やったはず。道半ばでアウトになるかもしれないけれど、もしかしたら吉田松陰みたいになれる可能性もある。とにかく誰か、ひとりでも歩き出すことをしないとダメだって思ったんです」

たとえば、図書館の本がどのように選ばれているのか。たとえば、書店がごっそりと減るなか、本はどこを拠点に、どんな流れで運ばれるのか。たとえば、物流の「2024年問題」は、出版業界にどんな余波をもたらすのか。
「作家はそんなこと知らなくても、って考え方も勿論あると思う。けれど、自分が立っているのは、いろんな人たちの努力と困惑と恐怖の上だってことを知ってしまった。誰かに苦しみや負担を強いるなかで回っている出版業界を、もっとミニマムにすべきか、それとも別の活路を見出し、新しい物流や出版形態にしていくのか。自分だけ書いて、本が売れたらいいんや、ではいられない」
作家である前に、どこまでいっても一読者、本のファンである。自身が作家になれて嬉しかった、夢を叶えることができた。けれども、叶えた夢の世界が、沈んでいっているのは耐えられない。それが、書店経営や「ホンミライ」などでの精力的な活動に繋がっている。今村の模索は続く。
「トライ・アンド・エラーを重ね、『これはいける』って思ったことに、他の作家たちにも『手伝ってくれ』って大声で発信していきたい。僕ひとりなら何回でも失敗しながら進んでいけるかなって思っているんです」
世界規模の挑戦を
池波正太郎の小説に、小学校5年生の時に出会ってから、ひたすら歴史小説を読みふけってきた。池波らの未完の大作の続きを夢想することを通じ、今度は自身も作家の道を志すようになった。膨大な読書体験こそが、今村の創作の源流だ。
「本を読み終えると、その時の自分も挟み込まれるんよ。だからその本を再び読めば、当時の自分が蘇る。それは思い出というレベルじゃなくて、その時の自分自身を取り返すことができるっていう感覚なんです」
たとえば司馬遼太郎の『北斗の人』。10代の頃、旅先で初めて読んだ。その後、何度も読み返してきたというが、その時々の記憶や匂いが本の中に挟み込まれ、いつでもその当時の自分に会えるのだと彼は言う。
「しかも何回、何十回も読んでいても、初めての時の感覚を覚えている。今読むとまた違う。読んだその時々の自分が挟まっているし、挟まっていく。栞になっていく。感傷的な理由ではなく、自分が変な方向に行った時に一旦思い出すために。初心を忘れない」
今村自身がいま、執筆対象として取り組みたいものがある。
「絶対、今、確信しているのが、『世界の中の日本』っていう小説。それは、アメリカやフランスの時代小説を書くのじゃなくて、『世界の中のアメリカと日本』、『世界の中の日本とイギリス』。そういう小説が僕は絶対、世界に出ていくためのポイントかなと思う」

日本視点で考える時代小説は、日本史と世界史が分かれているけれど、関ヶ原の戦いの西暦1600年と同じ頃に、イギリス東インド会社ができている。2人の主人公に微妙な接点を設けることによって、「世界の中の日本」という小説が出来上がっていくはず──と今村は語った。そんなふうに今村が世界を意識したきっかけは、何だったのだろうか。そう問うと、今村から快活な答えが返ってきた。
「WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)かな! ほんまに。すんごいミーハーなんやけど、WBCで久々に感動して。『僕より年下の人たちが、世界と、あのプレッシャーの中で戦ってるやん!』って。小説家も、勝てるとか勝てへんとかじゃなくて、僕が行って全然太刀打ちできなくても、日本の小説家が、世界の小説家と戦っていけるかもしれんと思えば、やってみたい。俺は行ってみたい。世界を意識しちゃった。なんで俺らは挑んだらあかんのやろ、って」
でもこの話、まるっきりの夢想ではないのかもしれない。そう思わせる気迫を、今村に感じてしまう。思い起こせば、「直木賞を取る」と公言し続け、実際に受賞を果たした。その記者会見で、こんどは「47都道府県の書店にお礼に回りたい」と宣言し、実際に走破した。じつに「118泊119日」の行脚を通じて知った、本にまつわる数々の問題点をすくい上げ、出版界を明るくするニュースを発信すべく、文字通り東奔西走している。そんな彼のつくり出す物語がこの先、たとえばハリウッド映画化されるとしたら、動画が世界配信されるとしたら──、「本当に叶えてしまった、今村翔吾!」。そんなふうに驚く日がやってくるかもしれない。
「『言い続ける』って大切やね。だからこのことも言ったよ!」
本に出合ったからこそ今の人生がある。何度もそう語ってきた彼ならではの説得力がそこにあった。

今村翔吾(いまむら・しょうご)
1984年京都府生まれ。2017年『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビューし、翌年同作で第7回歴史時代作家クラブ賞・文庫書き下ろし新人賞を受賞。同年「童神」(刊行時『童の神』に改題)で第10回角川春樹小説賞受賞。20年『八本目の槍』で第41回吉川英治文学新人賞、『じんかん』で第11回山田風太郎賞を受賞。21年「羽州ぼろ鳶組」シリーズで第6回吉川英治文庫賞受賞。22年『塞王の楯』で第166回直木三十五賞を受賞。