連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第26話 丸谷才一さんと『輝く日の宮』
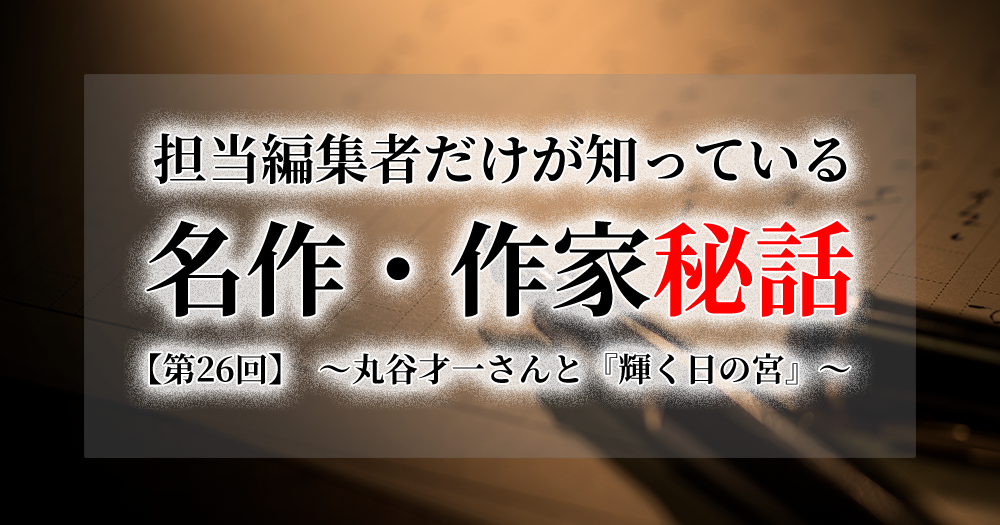
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第26回目です。今回は、異色とも言える作品を発表し続けた作家、丸谷才一さんとのエピソード。丸谷さんが『源氏物語』をテーマに書いた長篇小説『輝く日の宮』に、担当編集者として携わった時の秘話を語ります。
私が丸谷才一さんの作品のお手伝いをしたのは、長篇小説の『輝く日の宮』のほか、三浦雅士さんと鹿島茂さんとの共同選『千年紀のベスト100作品を選ぶ』(講談社2001年刊)と、「小説現代」に2004年から2009年にかけて、主に奇数月に連載され、2010年に単行本となった『人間的なアルファベット』の3つの作品である。
少ない感じがするが、10年に1作発表すると豪語する丸谷さんの担当としては、まあ、満足するべきなのかもしれない。
こう並べてみると、ありきたりの言い方ではあるが、どの作品も異色作と言っていい。
『輝く日の宮』はあとに回して、『人間的なアルファベット』は、丸谷さんの言葉を借りると、「やはらかいやうなぺダンティックなやうな」作品である。
丸谷さんの用語の1つである「やわらか」には、「エロチックな」とか「性的な」という意味があると思う。丸谷さんが編集した吉行淳之介さんの『やわらかな話』(文芸文庫刊)という文庫があるが、全編まさに、「性的な」話題ばかりを語る対談集なのだ。
『人間的なアルファベット』も、つまりは、英語辞典の体裁を借りた艶笑随筆である。
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第26話 丸谷才一さんと『輝く日の宮』写真](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/12/secret-story_26_image.png)
丸谷さんは、巻末の「おしまひの挨拶」で、「この本は一杯やりながらの冗談から生れた。」と書いている。ある時、丸谷さんと和田誠さんを招いて、講談社の編集者も何人か出席した会が開かれた。その会に、「ランダムハウス講談社といふ長い名前の会社に移つた」と紹介されている私も同席させていただいた。
丸谷さんは、この会の前に、「小説現代」に、「お色気がらみの短い随筆を三つ四つ書き、一つ一つに英語の題をつけ」ている。そして、その随筆の挿絵はイラストレーターの和田誠さんが書いた。
そんな経緯があった上での会合だった。そしてその席で、丸谷さんが言う通り、「誰かが、あれはアルファベット二十六字を全部書けば辞書仕立ての本ができる」と言い、その結果、連載を引き受けてもらえることになったのである。
実は、この時の「誰か」は、私ではないかとずっと思ってきた。と言うのも、はじめに「小説現代」に掲載された短いお色気がらみの随筆を読んですぐ、これは連載になるなと直感して、丸谷さんに連載を申し込むべきだと思ったからだ。これが、私の勝手な思い込みでなければ、私もなかなかのアイディア・マンだということになるのだが。
『千年紀のベスト100作品を選ぶ』も、一杯やりながら決まった企画だと記憶している。西暦2000年になるのを期して、これまで生まれたいろいろな分野の作品の中から、ベスト100を選ぼうという途方もない企画なんて、一杯やりながらの歓談からしか生まれそうもないしね。
2007年に刊行された文庫版(光文社知恵の森文庫)のあとがきで、丸谷さんは「無茶なことを敢へて辞さない三人が集つて、無謀きはまることをやつたが、その結果は意外におもしろく評判がよかつた」と書いているが、この無謀なことに集まったのは、丸谷さんのほか、文芸評論家の三浦雅士さん、フランス文学者の鹿島茂さんの3人である。
どこだったか記憶にないが、料亭の広い部屋で、資料をいろいろ広げての座談会になった。
丸谷さんは後で、「あんな豪勢な会場を設営してくれた度量の広さ」を褒めてくれたが、私は私で、編集長のそばで傍聴させてもらい、100作品を選ぶ座談会の面白さを満喫していたのである。
1位に『源氏物語』が選ばれ、100 位にジョン・コルトレーンの『至上の愛』が決まるまでの座談会はとてもスリリングだった。結局、文学作品、映画、音楽(クラシック、オペラ、ジャズなど)、舞踊、絵画、建築などさまざまな分野から、作品が絞られていく過程を聴いているのは編集者冥利に尽きると言うものだ。
座談会に選ばれた100作品は、「小説現代」の2000年1月号と2月号に分載され、2001年の5月に単行本として出版された。
その単行本には、「異議あり」と題した反論を2つ掲載しているのが慧眼である。そこで、翻訳家のサイデンステッカー氏は、マーク・トゥエインやディケンズ、オースチンなどが選ばれていないところや中国の文学作品がないことを嘆じ、比較文学者の張競氏も、中国文学作品がないのを残念がりつつ、粘土を膠で固めた単漢字を彫り、活字を作った功績を、せめて鼎談の中で一言触れてほしかった、と発言しているのは傾聴に値する。
つまり、この本は、一読した後、「異議あり」と、自分なりの100作品に作り替える楽しみがあるところが、異色であり、面白いところなのである。
自慢できる話ではないが、私は、大相撲を観る以外、テレビを観ることはない。であるから、『源氏物語』のことを扱っているらしい大河ドラマの『光る君へ』が、どのような内容なのか知らないのだ。
不勉強の謗りをまぬがれないことであり、忸怩たる思いをしているのは、実は私が、丸谷才一さんが『源氏物語』をテーマに書いた長篇小説『輝く日の宮』の担当をしたからである。
担当者としては、ドラマ『光る君へ』と、小説『輝く日の宮』とがどう違っているのかなど比べながら、ドラマを観ることは義務なのかもしれない。
だが、遅きに失した今、丸谷さんの『輝く日の宮』がどうやって書かれたかを思い出してみたい。
『輝く日の宮』が書かれる随分前のことになるが、長篇小説を書き下ろすという約束が、私の上役である局長と交わされていた。
たしか、目白の小料理屋だったと思うが、丸谷さんと、局長と私の三人で、食事をしながら、書き下ろしの催促をすることがあった。
このとき、丸谷さんは、
「おいしい料理をいつも食べているけれど、自分では不味い料理しか作れない女性を主人公にできないかと考えているんだ」
というようなことを話した。
このときは、長篇小説の書き下ろしのテーマとして、『源氏物語』のことはまだ浮かんでいなかったと言える。
丸谷さんの小説に登場する女性は、どの人物も個性的で、しかも一癖あり、そして魅力的なので、この変わった個性の女性が主人公になる小説を、私は大いに楽しみにしていた。
丸谷さんの頭の中に、いつごろ『源氏物語』がテーマとして浮かんだのか、担当者の私にもよく分からなかった。ただ、会うたびに、小出しにいろいろなことを話してくれた。
一体に、丸谷さんの小説の特徴は、品が良くて、知的で、酒場で友人に話したくなるような興味深いゴシップの積み重ねだと、私は思っている。
「ゴシップ」と言えば、「広辞苑」には、「うわさ話、無駄話。特に、有名人の私生活に関する話題。」とあり、『現代英英辞典』には、「人の行動や私生活について、人から人へ伝えられる情報。しばしば、不親切だったり、嘘だったりすることが多い」と書かれている。
つまり、あまりいい意味には使われない言葉である。
だが、丸谷さんは、『ゴシップ的日本語論』というタイトルのエッセイ集があることからも、「ゴシップ」という言葉を、いい意味で使っているのである。
ところで、丸谷さんが「今度の小説に、何人も抜いて社長になる男を出したいんだけど、どんな会社がいいか迷っている。ロボット会社なんかどうだろう」
と、相談を持ちかけきた。古い体質の会社ではなく、どこか新しい可能性を開拓している会社が必要らしい。
早速私は、丸谷さんと、富士山麓にあるロボット工場を見学に同行した。介護や医療など新しい分野に役に立つようなロボットを作っている工場で、それはとても面白かったが、丸谷さんの考えている小説のためには、どこか物足りないようだった。
そしてある時期から、丸谷さんは、「水の会社」はどうだろうと言いはじめた。
それを聞いて、私はすぐ、砂漠にかつて存在した「さまよえる湖」のことを思った。探検家ヘディンが発見した「さまよえる湖・ロブノール」のことである。
「水の会社」は、とてもロマンティックな想像をかき立てるアイディアだ。
私たちは、すぐに水を商品にしている会社の人に会って話を聞いた。
「さまよえる湖」のことも話題になったし、水の浄化の話から、海水浄化の話まで話題はとても面白かった。
主人公の一人、長良豊が6人抜きの抜擢を受けて、社長に就任する会社は、水の会社で決まったと、丸谷さんも私も思った。
水の話題は、小説の中で、様々な形で表現される。
長良が提案した海水浄化のこと、古代ローマの水道橋、アメリカの大平原の地下にあるオガララ滞水層が2020年に枯渇するということ、そして、500万年前、伊賀上野のへんにあった湖(いま琵琶湖と呼ばれている湖)が、1年に1センチか3センチの速度で、ゆるゆると北へ移動して、やがては日本海に飲み込まれてしまうという話など、まさに興味満点のゴシップとして出てくる。
さらに、長良は、サミュエル・テイラー・コールリッジの『老水夫譚』の一部を互いに暗誦し合ったことが縁で、ホテルを半ダースも持っている実業家と知り合うようになる。
もちろん、その詩は水をテーマにしている。
『老水夫譚』はとても長い詩なのだが、丸谷さんは、小説の中で、水のテーマが色濃く出ている次の6行を引用している。
Water, water, everywhere, (水、水、一面に)
And all the boards did shrink; (板という板は縮んでしまった)
Water, water, everywhere, (水、水、一面に)
Nor any drop to drink.(なのに、飲む水は一滴もない)
The very deep did rot : O Christ !(ずっと深くまで腐敗してしまった、お、イエスよ!)
That ever this should be !(こんなことが起こっていいものか!)
また、長良は吉川英治の『宮本武蔵』「円明の巻」の「魚歌水心」のあたりを老いた祖父に読んで聞かせる。それから間も無く亡くなった祖父の葬式の夜、そのくだりをお経をあげるように読みふける。
空で言えたその大団円のところを、いまになって長良は暗誦してみる。ここは『宮本武蔵』からの引用になるが、この年になっても暗誦できた最後の部分、
波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚は歌い雑魚は踊る。けれど、誰か知ろう、百尺下の水の心を。
水のふかさを。
というところを暗誦し終わった長良は、
「おれはこの刷り込みで水屋になったのか」
と叫ぶのである。
そして、物語の終わりに近いところで、もう一人の主人公・杉安佐子と教え子の十河佐久良が、長良との関係をめぐって会話を交わす。その舞台が、白金の自然教育園の池の畔であることだ。やはり、水に関係したところなのだ。
さて、後回しになってしまったが、『輝く日の宮』の、もう一つの大事なテーマ『源氏物語』のことに触れたい。
いろいろな試行錯誤を経て、2003年の6月に刊行された『輝く日の宮』は0から7まで、8つの章立てになっていて、章ごとに文体が変わっている。例えば、0の杉安佐子が中学3年生の時に書いた小説は、泉鏡花の文体模写で書かれているのだ。
はじめにその部分を読んだ私は、この文体で全編書かれるのかと心配になった。その顔を見て、丸谷さんは「大丈夫。このスタイルはここだけ。あとはいろいろ違えるつもり」と言った。
ジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』の影響だろう。
杉安佐子は、女子大の国文学の専任講師をしている。その安佐子がローマの空港で、ロンドン行きの便に乗り換えるために待っている間、隣に座った長良が、英語のアナウンスを聞いた途端に、安佐子の手を取って挙手した。安佐子にはよく聞き取れなかったが、それは、オーバー・ブッキングのために、明日の便に乗ってくれれば、400ドルのクーポンをくれるというアナウンスだったのだ。
長良が安佐子の手を取って挙手したのは、安佐子には断りもなく、それに志願したわけである。結局、2人はローマで、甘いひと夜を過ごすことになる。こうしてはじまった安佐子と長良の付き合いの進展と、国文学者としての安佐子の『源氏物語』との関係が同時に進行していく。
安佐子は、『源氏物語』は「桐壺」の巻と「帚木」の巻の間に、「輝く日の宮」の巻があったと考えていた。
「輝く日の宮」とは、源氏が「光る宮」と呼ばれるのに対して、源氏の生母・桐壺の宮に生き写しの、帝の新しい愛人・藤壺の宮に贈られた異称である。光源氏は、会うことのなかった桐壺の宮に生き写しと言われる藤壺の宮が、今は帝の愛人になっているのにもかかわらず、密かに思慕の念を抱くようになっていたのである。
また、学会のシンポジウムの光景は、舞台劇のように書かれていて、芭蕉がなぜ東北に行ったのかなどの話題にも躍動感があって愉しい部分だ。
ここで、ひょんなことから、安佐子は、それなら、あなたが書いたらいいじゃないと唆され、 自分なりの「輝く日の宮」の巻を書かなくてはならない羽目におちいる。そして、なぜ「輝く日の宮」が無くなったのかと考えて行くうちに、こうして、自分なりの「輝く日の宮」の巻を書かなくてはならない羽目になった安佐子は、なぜ「輝く日の宮」が無くなったのかと考えて行くうちに、作者の紫式部とその庇護者・藤原道長との関係に行きつく。時の権力者である道長は、紫式部の情事の相手でもあり、自分の性的な経験の数々を作品のために語り、紫式部が書く作品のはじめの読者でもあり、その作品の編集者でもあった。そして、なにより大きい存在だったのは、当時は、金と同じくらい貴重な物だった紙を、作品のために、惜しみなく与えてくれるパトロンであったのだ。
丸谷さんは、瀬戸内寂聴さんとの『源氏物語』をめぐる対談で、『輝く日の宮』は、「『源氏』を知らない人でも、ヒロインの安佐子さんのラブアフェアだけを、追っていって、充分おもしろいと思いますね」と言われて、「一つには、ある女の人の半生を書いて、その半生を、私生活と職業生活と両方書きたいという気持ちだったわけです。」と言って、「私生活が入るとすると、当然、色恋沙汰が入ってくるわけです。そちらのほうがおもしろく書いてあると、ほかならぬ瀬戸内さんからおっしゃっていただけると、非常に光栄です。何しろ、色道の家元みたいな方だからな(笑)」と加えている。
「新刊ニュース」のインタビューに答えて、丸谷さんは、「動機は非常に複合的なものでして、僕は日本文学史全体が一つの小説になるような小説を書きたいという気持ちを持っていました。ですから、紫式部や芭蕉ばかりでなく村上春樹『ノルウェイの森』とか俵万智『サラダ記念日』とか井上ひさし『父と暮せば』とかも出てくる。そういう、日本文学史が全部入る小説を書きたかったんです。」と言っているが、それを本人が一番愉しんでいる様子が、読者には愉しい。
ところで、我が家には丸谷さんからの葉書が何葉かあるが、そのうちの一葉に、
「今安佐子さんは机に向つて考へ込んでゐます。輝く日の宮のことを、自分のことを、人生について、文学について。」
と書かれている。
安佐子は、小説の中で、恋と文学で大活躍し、謎とされている消えた「輝く日の宮」を、ついに書き上げるだから、年の暮れ、感慨に耽るのは無理からぬことである。
葉書の消印は14.12.19.とあり、「輝く日の宮」が刊行されたのが、翌年2003年の6月であるから、小説のすべてが手を離れた年の暮れ、丸谷さんは、安佐子に託して、自身の感慨を述べているのであろう。
この本の装丁と装画は和田誠さんが手がけているのだが、丸谷さんと和田さんの希望で、帯やバーコードなどを取り払った形にして出版した。当方としては実験的な英断だったのである。出版して間も無く池袋にある大型書店、ジュンク堂に市場調査を兼ねて行ったら、カリスマ店員の田口久美子さんから、お小言を頂戴した。
「これじゃあ、なんの本だか分からないじゃないの。これをどう売ればいいのよ」
その通りである。私は、尻尾を巻いて退散した。
最後にそっとお教えするのであるが、この小説を読むと、『源氏物語』ってこんなにエロチックだったのと感嘆すること請け合いです。丸谷さん流に言うと、全編が、まさに「やわらかな」んですねえ。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第25話 挿絵画家のはなし](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/11/secret-story_25_banar_t-e1731410062147.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_banar_t-e1728473891678.png)
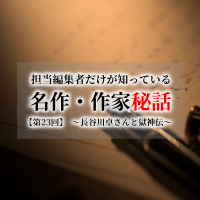
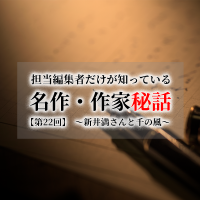
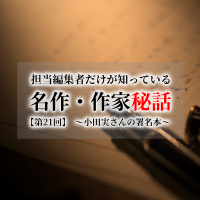
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第26話 丸谷才一さんと『輝く日の宮』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/12/secret-story_26_banar-600x315.png)