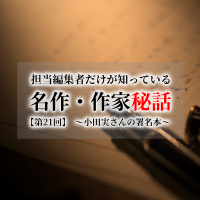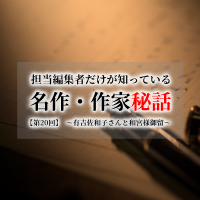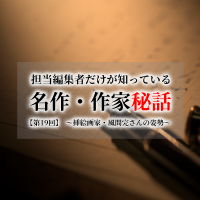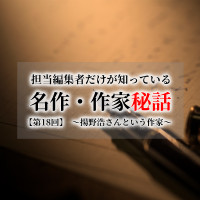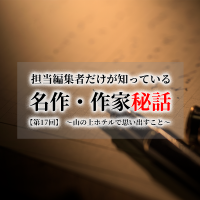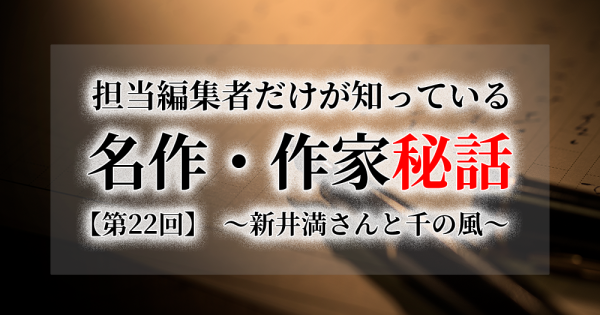連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第22話 新井満さんと千の風
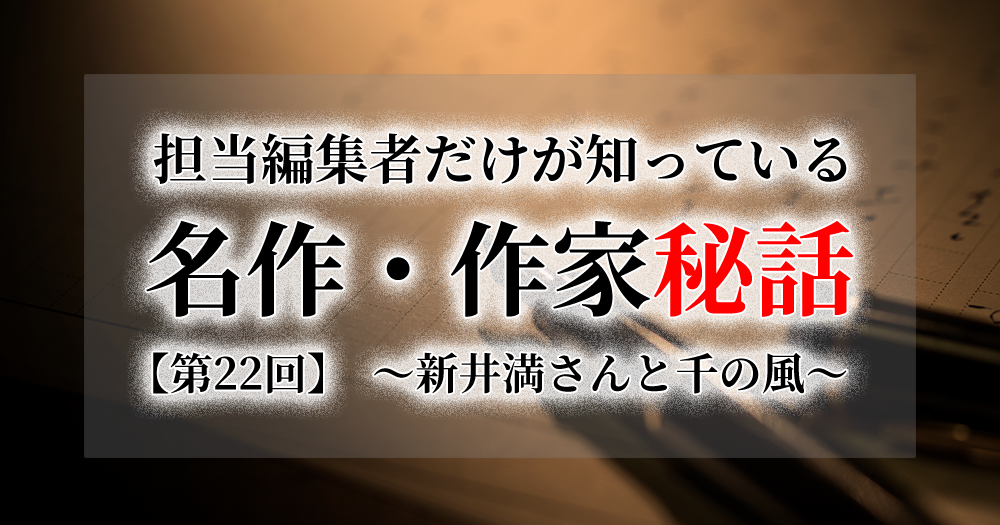
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第22回目です。今回は、著者にとって特別な、そして少し不思議な縁を感じる仕事を共にした、新井満さんについての秘話を紹介します。あの有名な大ヒット曲、『千の風になって』にまつわる興味深いエピソードも披露します。
今年開催されたパリ五輪の象徴となったのは、やはりエッフェル塔だったようだ。
そのエッフェル塔は、1889年のパリ万博を記念して建てられたのだが、建築しているときから、悪評紛々だったと言う。
そして、その頃のパリはすでに世紀末の雰囲気が漂い、多くの若い芸術家やその卵たちがモンマルトルに集まって、酒と恋と議論の日々を送っていた。そのボヘミアンな生活ぶりは、オペラ『ラ・ボエーム』に、鮮やかに描かれている。
私は、エッフェル塔やモンマルトルなどを舞台にして小説を書いた新井満さんと、とても興味ある付き合いをしたので、そのことを書き留めておきたい。
新井満さんは、小説家であり、作詞作曲家であり、歌手であり、写真家であり、環境映像のプロデューサーであり、そして絵本作家でもあった。その上、電通という広告会社の社員でもあって、こちらは定年まで勤め上げた。つまり多彩な才能の持ち主だったのである。
その新井さんは、1946年5月7日、新潟に生まれ、幼少の頃から身体の弱い体質だったようだ。大学生の時には、生死の境をさまようような大きな病を患ったこともあるという。大学を卒業後、電通に入社して、環境ビデオ映像の制作に携わるようになる。
1977年、カネボウのCMソングで、作詞・阿久悠氏、作曲・森田公一氏の「ワインカラーのときめき」を、新井さんは歌手として歌い、これがヒットした。
その頃には、新井さんは、すでに小説も書き始めていて、1987年、「文学界」に掲載された『ヴェクサシオン』で、芥川賞は逃したが、第9回野間文芸新人賞を受賞した。1986年に、『サンセット・ビーチ・ホテル』で、第95回芥川賞に候補になるや、3回続けて候補になり、1988年に『尋ね人の時間』で、第99回芥川賞を受賞した。
この頃の私は、東京會舘で行われた芥川賞と直木賞の受賞記者会見には毎回顔を出すようにしていたから、もちろん、この時の記者会見にも出かけた。新井さんの記者会見の内容はよく覚えていない。同じ年に直木賞を受賞した景山民夫さんとは仕事を一緒にしてきたし、仲もよかったのだが、新井満さんとはまだ縁がなかったのだ。

記者会見が始まる時間になっても新井さんの姿は見えなかった。賞を運営している人たちも、落ち着きを無くしていた。のちに『尋ね人の時間』のあとがきに書いているのだが、新井さんは「自宅で待ちつづけることをよしとせず、街に出た。/できることならば、人間が一人もいない場所で待ちたかった。だがそれは、大都会にあっては無理な注文だった。街を歩き、地下鉄に乗り、JRに乗り換え、いつか山手線の車中に私は、いた。秋葉原から、時計回りで一周していたのであった。」
「まさに『尋ね人の時間』だね」という冗談を言いながらも私たちは待っているしかなかった。
ところで、新井さんはマガジンハウス社から、1992年に短篇小説『オンフルールの少年』を出版している。ここに描かれている「オンフルールの少年」とは、作曲家のエリック・サティのことである。エリック・サティは1866年に、フランスのノルマンディ地方の港町・オンフルールで生まれた。環境映像のクリエーターとしての新井さんは、サティの創った曲を環境音楽として高く評価していた。
サティが活躍していた世紀末のモンマルトルには、すでに芸術家になっていたり、芸術家の卵たちだったりしたゴッホ、ヴィヨン、マティス、シュザンヌ・ヴァラドン、ドガ、ロードレック、ドビュッシーたちがたむろしていた。私はその雰囲気の中で生きた人たちに興味があった。特に、ロートレックの荒廃した生き方には、編集者としてだけではなく、個人的にも惹かれるものがあった。
少しずつ新井さんと私は会うようになっていた。そして、文芸図書出版部に異動していた私が担当となり、1999年、アンソロジー『エッフェル塔の黒猫』を出版した。表題作の『エッフェル塔の黒猫』は、1993年に、「小説現代」に掲載された作品で、『オンフルールの少年』の続篇である。
中篇小説『エッフェル塔の黒猫』の冒頭で、若きサティはアラス歩兵連隊の中隊長室にいる。12歳の時、オンフルールを後に、パリに出て、音楽院に進んだものの、学校になじむことが出来ず、軍隊へ潜り込んだのだ。しかし、それは完全な間違いだった。音楽院よりももっとひどい環境で、いまサティは、中隊長室で除隊許可を得るところだ。
逃げるようにして、パリへ戻ると、サティは、入隊前に知り合っていた詩人のパトリスと再会する。ボードレールが翻訳したエドガー・アラン・ポーの『黒猫』を紹介したり、「薔薇十字教団」を主催したジョセファン・ペラダンの神秘思想をサティに吹き込んだりしたのがパトリスで、音楽院がいやなら軍隊へ行けとそそのかしたのも、パトリスだった。
サティとパトリス、それにパトリスの妹・ルミヤの3人は、モンマルトルで、ボヘミアン的生活を送ることになる。パトリスは実在の人物だが、ルミヤは新井さんが創作した人物のようだ。サティはモンマルトルの文学酒場「Le Chat Noir(黒猫亭)」の専属ピアニストになり、モンマルトルのコルトー街に自分の部屋を借りる。
引越し祝いにパトリスが山高帽を、ルミヤが握りに黒猫の飾りのついた蝙蝠傘を贈ってくれた。サティが初めてキャバレー「黒猫亭」を訪れた時に即興で弾いた曲が、『ジムノペディ』だ。
3人は1889年の7月、建設されたばかりのエッフェル塔に上ってみる。エレベーターが故障していたため、パトリスとルミヤは途中であきらめ、サティだけが蝙蝠傘を杖にして階段を上っていった。しかし、そのサティも1280段に達したところでへたり込んでしまう。意識もぼやけてきた。耳の奥で自身の曲『オジーブ』と『ジムノペディ』が聞こえてくる。そして、その時、蝙蝠傘の柄が1匹の黒猫に変身した。黒猫はサティをさらにエッフェル塔の天辺まで連れて行き
「あたしのために作ってくれたあの曲を演奏してくれないか」
と話しかける。サティはしばらく考えたのち、『ジムノペディ』のことだと気づき、メロディを口ずさむ。黒猫とサティはその調べに合わせていつまでも踊り続けるのだった……。
アンソロジー『エッフェル塔の黒猫』にはもうひとつ、書き下ろしの長篇小説『モンマルトルの薔薇と憂鬱』が収録されて、結局、550ページを超す分厚い本となったが、これで、新井満さんの、いわゆる、サティ3部作が完成したのである。
この本を出したことによって、私もサティの音楽のファンになった。新井さんの小説『ヴェクサシオン』の中で、主人公のCFクリエーターが、耳の聞こえない女性からサティの音楽のことを細かく教えてもらうように、私も新井さんから、サティのことを教えてもらった。
残っているかもしれないサティの時代のにおいを嗅ごうとして、私はすぐにモンマルトルに出かけた。
サティが専属ピアニストだったキャバレー「Le Chat Noir(黒猫亭)」は、とうの昔に廃業していたし、キャバレーの「Moulin de la Galette(ムーラン・ド・ガレット)」は昔日の面影を無くしていた。ずっと営業を続けていた「Auberge・du・Clou(オーベルジュ・ド・クロ)」は、サティたちが夜な夜なたむろしていた店だが、私は、そこでまだ食事をすることができた。オーベルジュとはレストランがついた宿屋のことだ。
あるオーベルジュの地下の壁に、ロートレックしか描けない女の絵があるから、見てくるといいよと新井さんに教わっていた。
どこの店だか記憶にないのだが、店のマダムに、
「ここにはロートレックの落書きがあるそうですね」
と言うと、
「見てみる?」
と、今は倉庫として使っている地下室の壁に案内してくれた。その色のついた絵は、酔余の落書きのようだが、まさにロートレックしか描けない女性の絵だった。
「こりゃあ、ロートレックに間違いないですよ」
「私もそう思うけれど、サインがないからねえ」
と、マダムは、大きなため息をもらした。
その時、私はオンフルールにも足を伸ばした。オンフルールはサティの生まれ故郷にふさわしく、小さな港町で、どこを切り取っても絵になるような町だった。停泊している船のマストが何本も空に伸びていた。路地に入ると、この地方独特の木組みで、白い漆喰の壁の建物が並んでいた。
『オンフルールの少年』に書かれていることだが、サティは移り住んでいたパリで母が亡くなると、オンフルールへ帰って、祖父母に育てられることになる。サティは、祖父母からはあまり好かれなかったが、自由な気質を持つ叔父のアドリヤンには可愛がられたようだ。
アドリヤン叔父さんのヨットでオンフルールからイギリス海峡に出るところで、サティが尋ねる。
「叔父さん。今日はどこへ?」
アドリヤン叔父さんの答えはいつもこうだ。
「ここではない、どこか遠くへ……」
二人は海の上で、サティの人生のキーワードとなるこの言葉を、何度も叫ぶ。
そして、サティがアドリヤン叔父さんにもらった木彫りの鳥が声を限りに叫んでいるのを聞く。
「ここではない、どこか遠くへ!」
長篇小説の『モンマルトルの薔薇と憂鬱』は、1890年の大晦日から始まる。この日サティはシュザンヌ・ヴァラドンと出会った。シュザンヌは、ロートレックやルノワールなどの絵のモデルをしていたが、彼女自身も才能豊かな画家でもあった。サティが生涯でただ一人つき合った女性であるシュザンヌには、誰との間にできたか分からない男の子がいた。のちに有名な画家になるモーリス・ユトリロである。
この作品になって、シュザンヌとモーリスがサティの人生にかかわってくる。シュザンヌとの仲は半年しか続かなかったが、サティはシュザンヌと別れたあと、息子のモーリスとは心を通じ合うようになる。それは、ちょうど、アドリヤン叔父さんとサティとの関係をコピーしたようなものだった。
私の家の壁には、そのモーリス・ユトリロが描いたモンマルトルの冬景色のエッチングがかかっている。画商は、3階建てのボロ屋を指さして、「オペラ『ラ・ボエーム』のミミたちが住んでいた建物だよ」と言ったが、もちろん当てにはならない。
『モンマルトルの薔薇と憂鬱』では、言葉を話す黒猫の代わりに、おしゃべりな蝸牛が登場する。ベッドに寝転んだサティが、天井に張り付いてのろのろ移動するその姿を見て、蝸牛の旅は無駄な骨折りなのではないかと思った時、
「失礼ながらエリックさん、あなたが今、心の中で考えた言葉を、そっくりあなたにお返しいたしましょう」
という声が天井から降ってくる。そして、サティは蝸牛と会話を始め、馬ぐらいの大きさに変身した蝸牛の背中に乗ってかすかに聞こえる音楽の方へと向かう。
着いた先はどうやら子宮の中らしく、サティは精子になっていて、天井から降りおちてくるピアノ音を聞いていた。執拗に繰り返される憂鬱のメロディ、哀しみのルフラン。サティが目覚めたのは、ちょうど八百四十回のルフランが終わったときのことである。
サティは、急いでその曲を五線譜に書き留め、楽譜の冒頭に「この音楽を八百四十回くり返して演奏せよ」という指示を記した。この曲名の『Vexations(ヴィクサシオン)』は、屈辱や侮辱を意味する言葉だが、自分とシュザンヌの名前、そしてヴァギナの文字を組み合わせたのだとも言われている。この曲はサティの指示通り演奏すると37時間以上かかる。
小説の最後で、サティは上着のポケットに入っていた、アドリヤン伯父さんにもらった木彫りの鳥をモーリスにプレゼントする。
ルミヤにねだられた時には、
「この木彫りの鳥はね、本当にこれを必要としている人間だけが持つべきなんだ。これが傍にいることで救われる、そういう人間だけがね」
と言って、渡すことを拒んだものだ。
木彫りの鳥をもらったモーリスは、それを高々とかかげ、左右に大きく振りながら、叫ぶのだった。
「おじさん! ありがとう! この鳥はこんなふうに鳴くんだよね」
ここではない、どこか遠くへ!
ここではない、どこか遠くへ!
『モンマルトルの薔薇と憂鬱』は、当時の値段で税別2800円もした。正直、よく売れたとは言えなかったが、本としての出来栄えはたいしたものだったと思う。私は手に取ってはその重さを感じながら、サティも満足しているだろうと思った。
そんなある日、新井さんから電話があった。汐留にできたばかりの電通ビルにきてくれないかという誘いだった。約束の夜、新井さんは、すぐに46階にあるレストランに連れて行ってくれた。レストランの内部と言い、そこから見える夜景と言い、光に満ちたまばゆいような光景だった。その光景に押しつぶされるような気持ちで、テーブルについた私に、新井さんは、
「今夜はご馳走するからね」
と言ってくれた。
注文を終えると、新井さんはまた、こうも言った。
「これまで赤字の原稿に付き合ってくれたから、今度は儲けさせてあげるね」
とてもありがたいことだが、出版の世界はそんなに簡単に思い通りにはいかないものだ。
「『千の風になって』という詩があってね。僕がその詩を訳して、曲をつけたものがあるんだ。本にすると売れるはずだよ。それを君が出してもいいからね」
少し高い声で、新井さんはそう言った。
その夜、新井さんと別れた私の気分は夥しい光に包まれたままだった。気がつくと、何枚かの企画書のようなものを手にしていた。その中に、『千の風になって』の原詩とその翻訳もあった。
Do not stand at grave and weep
I am not there; I do not sleep
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s rush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circling flight.
I am the soft starlight at night.
Do not stand at grave and cry,
I am not there; I did not die
この英語の詩は、アメリカの先住民が伝えてきた詩だとか、Mary Frye氏が書いた詩だとかいろいろ説が唱えられているが、新井さんは、「ネイティブ・アメリカンの誰かが書いた、と推理するのがもっとも自然ではなかろうか」と言っている。たしかに、この詩は、どこか原始的なアミニズムの香りがしている。
その原詞を、新井さんが日本語に訳し、曲をつけ、それがCDになったきっかけになったのが、友人の奥さんが若くして亡くなったのを慰めるためということが、私たちが出した単行本「千の風になって」のあとがきに書かれている。
新井さんは、その原詩を次のように訳していた。
私のお墓の前で泣かないでください
そこに私はいません
眠ってなんかいません
千の風に
千の風になってあの大きな空を吹きわたっています
秋には光になって畑にふりそそぐ
冬はダイヤのようにきらめく雪になる
朝は鳥になってあなたを目覚めさせる
夜は星になってあなたを見守る
私のお墓の前で泣かないでください
そこに私はいません
死んでなんかいません
千の風に
千の風になってあの大きな空を吹きわたっています
千の風に
千の風になってあの大きな空を吹きわたっています
あの大きな空を吹きわたっています
とてもいい訳だ。
新井さんが言うように売れるなんてことには、正直、私にとっては信じられることではなかったが、この訳詩の柔らかな調子は素晴らしいと思った。
「いません」と断定的な強い音のリフレイン、それに呼応して「あの大きな空を吹きわたっています」という雄大な動的なイメージ、さらに、「秋」と「冬」と「朝」と「夜」のイメージはまことに美しい。是非とも出版したい作品だと思った。
2003年11月に、写真入りのエッセイ集『千の風になって』を、74ページの薄い本だが、私たちは出版した。これらのことが、朝日新聞の「天声人語」に紹介されてから、問い合わせが急に多くなり、ポニーキャニオンが出したCDと合わせて、新井さんの予言通り、ビッグ・セラーになった。
2005年には新井さんの歌唱が吹き込まれたCDブックも発売した。私は細かな数字は知ることはしなかったが、新井さんが予言したように赤字を解消するどころではない売上げを上げたはずだ。
晩年、新井さんが北海道の七飯町に暮らすようになってから、私は、気になりながらも、会う機会はなくなってしまった。2021年12月に、突然の訃報が届いた。悲しい報だったが、新井さんはきっと、サティの物静かなメロディを聴きながら、千の風になって広々とした北海道の原野を吹きわたっているはずだ。享年75。それにしても、若すぎる死だ。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。