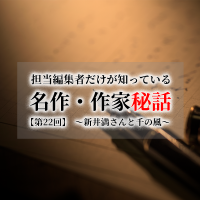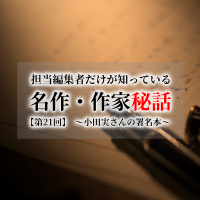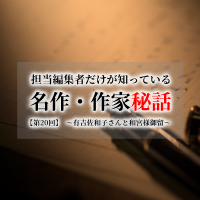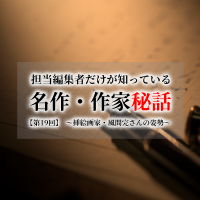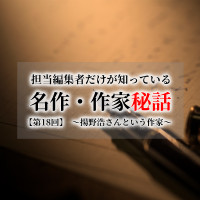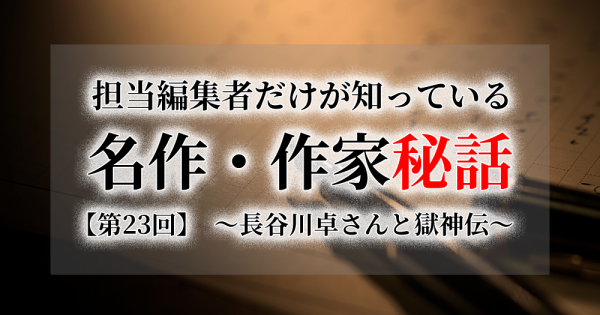連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第23話 長谷川卓さんと獄神伝
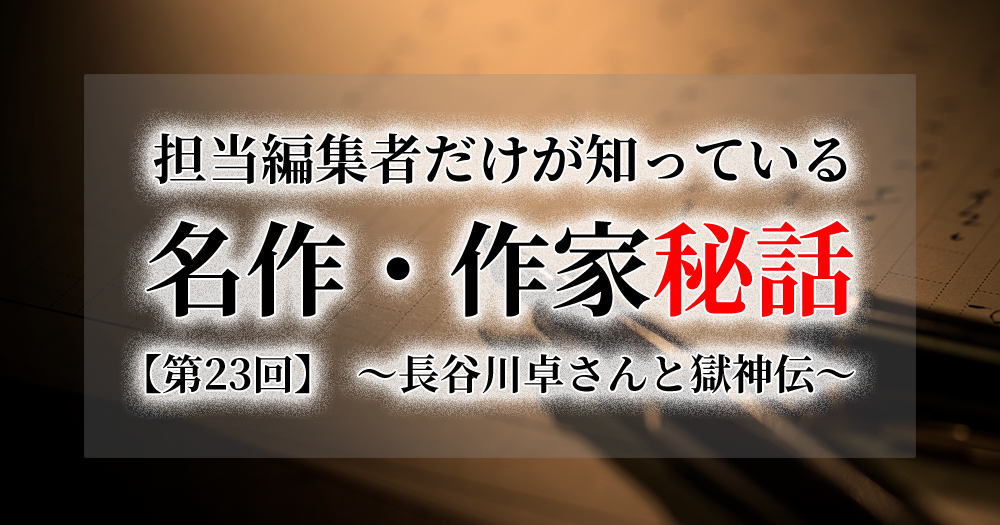
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第23回目です。今回は、「編集者と作家」という関係性にも、さまざまな形があることを表したエピソードを紹介します。担当編集者だからこそ感じる、作家との縁。作品の誕生を通じて、時を経ても紡がれる絆について語ります。
長谷川卓さんは、1980(昭和55)年、第23回「群像」新人賞を、『昼と夜』で受賞した。この作品は、同年6月号に掲載されている。
この年の新人賞の選考委員は、佐々木基一さん、佐田稲子さん、島尾敏雄さん、丸谷才一さん、それに吉行淳之介さんの5人であった。この選考委員すべてが、選評の中で、「昨年、一昨年にくらべて少し低調のようだ」と書いている。
ちなみに、選考委員たちが、前2回と比べて低調だと言っている「前2回」とは、1979年の、村上春樹さんの『風の歌を聴け』と、その前年の、中沢けいさんの『海を感じる時』が受賞作であった。
私は、この年も長谷川卓さんの「昼と夜」が、応募作品中、一番面白いと思って強く推した。その証に、私が、前年の村上春樹さんに引き続き、今回当選した長谷川さんの担当をしているからだ。私自身は、この作品が、前の2回の作品にさほど劣っているとは思わなかった。
佐田稲子さんの選評から、『昼と夜』について書かれた部分を引用してみる。
『昼と夜』は、二人の男の描き分けに判然としない弱さがある。が、都会の底に今日を生きてゆく人間の内面と、日常性の頼りなさを、挿話をはめ込みながら描き出してゆく力量は、当選の水準を持つものにおもえた。まやかしの行為へのうしろめたさと、それに挑んでゆく結末に作者の思考があるだろうか。その途中にはめ込まれる幾つかの挿話に、おもしろいものと、何か少し不安を感じさせるものがある。不安というのは、作者自身がおもしろがり過ぎている、という感じを私が持つ部分である。たとえば郵便番号簿一冊を暗記している男に行き逢う箇所などがある。そしてまた、作者自身がおもしろがり過ぎている調子は、全体に流れていると云えなくもない。
(1980(昭和55)年6月号の「群像」より)
会社を無断欠勤して、駅のベンチでうたた寝をして指に挟んだ煙草で火傷してしまう男、建売住宅を売る男と、買うつもりもなどないのに建売の中に上がり込んでしまう男、幼い二人の子供を道連れに自殺を図る主婦、表札詐欺をする男、表札詐欺を見破る主婦、精神に異常をきたしていて、なんでもかんでも覚えこんでしまう男……私からしてみると、佐田さんが指摘したように、こうした挿話のそれぞれが、都会の底に今日を生きていく人たちの頼りなさをうまく表現しているのである。
ちなみに、この年、「異様なるものをめぐって─徒然草論」で、評論部門の優秀作となった川村湊さんは、これをきっかけに活動をはじめ、文芸評論家として、今でも多彩な仕事をこなしている。
長谷川卓さんの本名は佐藤春夫というのだが、文芸の世界では、この名前を持つ偉大な先人がいて、このまま本名でデビューするわけにはいかない。そう言うと、長谷川さんは、「よ〜く心得てます、長谷川卓でいってください」とニンマリと笑った。

私はその頃、新人作家への歓迎とこの世界への洗礼をするのに、新宿ゴールデン街の酒場「まえだ」を使った。いつもの通り、ゴールデン街に案内したところ、「僕はアルコールを受け付けないんです」と言うではないか。私はしばらく思案して、
「とんかつは好きですか?」
と、訊くと、
「大好物です」
と、幼児のように顔をほころばせた。
当時、ゴールデン街には、食べ物屋は、ラーメン屋と老夫婦でやっているとんかつ屋くらいしかなかったのではなかろうか。
佐藤春夫改め長谷川卓さんは、そのとんかつ屋で、おいしいおいしいと言って、大振りのをペロリと平らげ、満足そうに微笑んだ。
「アルコールを受けつけない小説家だなんて!」
私は不思議な人間を見るような気持ちがした。
それから翌年にかけて、長谷川さんは『百舌が啼いてから』という129枚の短篇小説を書き上げ、1981年「群像」の5月号に掲載した。そして、それが1981年上半期、第85回芥川賞の候補作になった。
その回の受賞作は吉行理恵さんの『小さな貴婦人』で、長谷川さんと同時に落選したのが、宮内勝典さん、木崎さと子さん、森瑤子さんなどの実力者たちだった。
そう言えば、私が担当していた吉行淳之介さんはその時の芥川賞の選考委員だった。
選考の後、吉行さんのところに行くと、当然、選考会のことが話題になった。
受賞した吉行理恵さんは吉行淳之介さんの妹だ。
「最初に、マルとかバツとかを言うんだけれど、身内のことだから、ぼくは『パス』と言ったんだ。参加しないという意味でね」
「はあ」
「それがほかの選考委員たちにバツと聞こえたら、理恵に悪いことをしたと思うけれど、そうでもなかったようだ」
吉行さんは、そう言って笑っていた。
閑話休題。
ところで、長谷川さんが、落選したとは言え、2作目で芥川賞の候補になっている。私たち編集者は、いつもなら賞を目指して頑張っていきましょうというところだが、その年に私は文庫出版部に異動することになってしまった。
結局、長谷川さんも私も、中途半端な気持ちのまま、それぞれ別の道を歩むことになったわけである。それから、2008年に、不思議なえにしとか言いようがない再会を果たすまで、17年もの長い間、長谷川さんは独自の道を歩んでいたのである。
1949(昭和24)年に小田原で生まれた長谷川さんは、早稲田大学大学院演劇学科を修了している。私たちが会うこともなかったおおよそ17年間の長谷川さんの生活振りは、2021(令和3)年の新装版『柳生七星剣』『柳生双龍剣』『柳生神妙剣』の三部作(祥伝社刊)のそれぞれのあとがきとして奥さんが代筆して書かれている。
それによると、1992年、43歳の頃、長谷川さんは、エッセイストでもあり、翻訳家でもある奥さんの故郷、清水市に移り住んで、そこでのんびりとした明け暮れをしていたようだ。
その間、作家活動と言えるのは、1994年の、初の時代長篇小説『運を引き寄せた男──小説・徳川吉宗』を、かんき出版から出版しただけのようだ。その小説には、あとでよく使うことになる「多十」という名の忍びの者が、すでに、吉宗の手先となって働いているのが目に付くし、根来衆とか根来涌井衆などの忍びの集団の名前が登場しているのだ。
2008年4月のことだったと思うが、帝国ホテルで、吉川英治文学賞の贈呈式が行われた。この時の受賞者は浅田次郎さんで、受賞作は『中原の虹』という作品だった。私も会場係として駆り出されていた。宴の中頃、会場の隅に近い方で、浅田さんが、ひとりの中年の男の人を話しているのを見た私は、浅田さんにお祝いの言葉をかけるために近づいていった。
なんと、浅田さんが話している相手は長谷川卓さんだった。あれから17年も経っているのに、あまり変わっていなかった。相変わらず、やや小太りの身体、丸くて人の良さそうな顔をして、あの時、とんかつを平らげてしあわせそうに笑っていた顔と同じ顔をしていた。
「どういうお知り合いなんですか?」
私が訊くと、長谷川さんが、
「浅田さんのお兄さんなんかと、同人誌をやってましてね」
と、答えてくれた。その答えが終わるや否や、浅田さんが、
「この人は大変な流行作家なんですよ」
と、言った。
「流行作家!?」
私は戸惑った顔をしたのだと思う。
「宮田さんは読んだことないでしょうが」
そう、浅田さんは付け加えて、その話題は終わった。
まことに恥ずかしながら、私は長谷川さんのことは念頭からなくしていたので、浅田さんの言っていることに衝撃を受けた。
すぐに、私は、インターネットで「長谷川卓」と検索してみて、2000年に、第2回角川春樹小説賞を受賞していたことを知った。受賞作「血路」は、2001年3月ハード・カバーで、刊行されていた。
その帯文には《武田の暗殺集団<かまきり>と、山の者の集団<七ツ家>の壮絶なる死闘を描く、ノンストップ時代アクションの最高傑作。選考委員の森村誠一氏、北方謙三氏、高見浩氏、福田和也氏、角川春樹氏に絶賛された第2回角川春樹小説賞受賞作》とある。
早速、読んでみた。とても面白かった。私が学生の頃、古本屋で見つけた山田風太郎の「忍法帖」を思わせるスピード感溢れる作品だった。
時は戦国時代。長谷川さんの『血路』に書かれた、山の南側の稜に7軒の家を建てて暮らす山の者の生活は、私に作家・三角寛の小説が描く山窩の人たちを思い出させた。三角寛が紹介した山窩の民は、里の人たちと交わらず、山奥で漂流生活を送りながら、山菜などを採取し、狩猟や川での漁に長けてもいた。そして、竹細工を巧みにして、蓑や籠を作って暮らしていた。『血路』で、山の者たちが武器として使う長鉈は、山窩の民が使ったものと酷似している。
私が五木寛之さんの作品の中で好きなものの一つである『風の王国』にも、山の道を翔ぶように走る山の民の末裔が出てくる。『風の王国』が現代の山の民の末裔を描いているとすれば、長谷川さんの描くのは、戦国時代の山の者たちだ。
「七ツ家」は他の山の者と違い、狩りをするだけでなく、山城への兵站と、人質や囚われ人を敵の城から「落とす」仕事を請け負い、「落しの七ツ」という異名を持つようになっていた。
城主である父母を殺された喜久丸の復讐に力を貸して、「七ツ家」の者たちは、難攻不落の龍神岳城を爆破、山の下に沈めるという荒技を見せる。そして、喜久丸は自ら望んで、山の者の術を習得、山の者の一員となり、二ツを名乗るようになる。
『血路』の、もう一つのストーリーとして、《忍び殺し》と言われる、忍者の侵入を許さぬ武田藩の躑躅ヶ崎館から、乳幼児・寅丸を助け出し、駿河にいる武田晴信(信玄)の父・信虎のもとに届ける仕事を請け負う。寅丸を助け出した七ツ家の者たちは、武田の最強の忍者集団「かまきり」に追われることになり、山の中で生きるための技術を駆使する山の者と暗殺のプロ集団「かまきり」との壮絶な闘いの連続となるのである。
2008年に浅田次郎さんに、「流行作家」と呼ばれた長谷川さんは、時代小説賞を受賞後、しばらくして、流行り始めていた書き下ろしの時代小説文庫に、いくつものシリーズを持っていたのである。
『北町奉行所捕物控』シリーズ(ハルキ文庫刊 2005年から)
『高積見廻り同心御用控』シリーズ(祥伝社文庫 2007年から)
『戻り舟同心』シリーズ(学研M文庫 2007年から)
『雨乞の左右吉捕物話』シリーズ(徳間文庫 2009年から)
それまでの私は、書き下ろし時代文庫に関心が薄かったが、長谷川さんの作品をいくつか読んでみて、考えを改めなくてはならなかった。私が特に面白いと思ったのは、『戻り舟同心』のシリーズだ。
定廻り同心だった、六十八歳になる二ツ森伝次郎が、かつて迷宮入りした事件(永尋)を再捜査するために再出仕して活躍する連作シリーズだ。第一に、さすが芥川賞の候補になっただけに、文章がとてもいい。そして、偏屈にして頑固一徹な伝次郎、その親に似ず堅物の息子の新次郎、食べることに目がない孫の正次郎という3代にわたる親子関係が楽しい。さらに、いいのが、永尋掛かりのため、伝次郎が呼び寄せた往年の仲間たちのユニークさだ。
私は、きちんとした形で、長谷川さんと会いたいと思った。それは長谷川さんが上京した折に実現した。長谷川さんは上京すると、実家で老母を見舞い、神保町の古書店街を巡り、喫茶店の「伯剌西爾」か、移転する前の「ミロンガ」かで、好きなコーヒーを啜る習いだった。このふたつの喫茶店は、喫煙が許されていて、愛煙家でもあった長谷川さんの好みにあったのだろう。
たしか、再会したのは、「伯剌西爾」だった。
ここで、『血路』を応募した時の話もしてくれた、何かのことで、長谷川家にまとまったお金が必要になったようだ。長谷川さんは、「よし、何月何日には確実に百万円入るからな」と奥さんに約束してから、原稿用紙に向かい、『血路』を完成させ、応募して、見事に当選。賞金百万円を約束通り、奥さんに渡したのだそうだ。
そして、「芥川賞を落ちたままになってしまって、借りがあると、ずっと思ってきました。出来たら、この山の者のシリーズを一緒にやってくれませんか」という申し出があった。こんなに嬉しい言葉はなかった。むしろ、会社の都合とは言え、異動して、そのままになってしまった借りがあるのは私の方なのだ。
長谷川さんの口から、山の者の生活振りが紹介された。戦場での死体の扱いなども話が出た。私も、たとえばTVのドラマなどで、美麗な鎧兜を身にまとった武将たちがアップに映されるけれど、では、その鎧兜を作った職人たちのことに目を向けることはないし、戦場での食事、排便、また怪我の治療や死体の片付けなど、下っ端たちがやったであろうことは何も描かない。それが不満だと思っていたと話した。
私たちの間には17年の空白を感じさせるものはなかった。神保町で中華料理を食べ、コーヒーを飲みながら、私たちは忌憚のない意見を交わした。私にとっては書き下ろし時代文庫という仕事ははじめての経験だったが、出来上がった『嶽神伝』というシリーズは自慢できるものとなった。それも長谷川さんの特異とも言うべき、豊富な知識と、何より人柄の良さとがあってのことだと思う。
『嶽神伝』というシリーズ名のほかに、ふた文字のメイン・タイトルを決める必要があったが、「孤猿」など長谷川さんのアイディアがすぐ採用されたが、ひとつ「鬼哭」だけはなかなか決まらなかった。次回までの宿題にすることにして、長谷川さんと別れてから、護国寺で地下鉄を降りる講談社の担当編集者の後ろ姿を見た途端、なぜか、「鬼哭」というふた文字が浮かんできた。それは次回に採用と決まったが、背中を見て、「鬼哭」という文字が浮かんだと言われた編集者の嘆きたるやはなはだ大きいものとなった。
私が担当してきた『嶽神伝』シリーズ8作品、13冊を、講談社文庫の発行順に並べると、以下の通りになる。とても面白いものになっているので、ぜひ読んでいただきたい。
『嶽神(上)白銀渡り』(2012年5月刊)
『嶽神(下)湖底の黄金』(2012年5月刊)
『嶽神伝 無坂(上)』(2013年10月刊)
『嶽神伝 無坂(下)』(2013年10月刊)
『嶽神伝 孤猿(上)』(2015年5月刊)〈文庫書き下ろし〉
『嶽神伝 孤猿(下)』(2015年5月刊)〈文庫書き下ろし〉
『嶽神列伝 逆渡り』(2016年3月刊)
『嶽神伝 鬼哭(上)』(2017年1月刊)〈文庫書き下ろし〉
『嶽神伝 鬼哭(下)』(2017年1月刊)〈文庫書き下ろし〉
『嶽神伝 血路』(2018年10月刊)
『嶽神伝 死地』(2018年11月刊)
『嶽神伝 風花(上)』(2019年10月刊)〈文庫書き下ろし〉
『嶽神伝 風花(下)』(2019年10月刊)〈文庫書き下ろし〉
こうして、このシリーズを終えるのであるが、まだまだ山の者シリーズからスピン・オフした戦国の物語が描けるはずで、私たちは、そこに目を向けはじめたその頃、長谷川さんは癌に侵されて、闘病生活に入ってしまう。
苦しい入院中も、周りの人たちのことを気遣い、笑わせたりしていた。私に送ってきたメールにも細かな情報が書いてあった。そして、病室で見せていた笑顔が映っている写メも添付してあった。
長谷川さんの癌に向かう姿勢は、気張らず、落ち込まず、周りの人に気を遣うものだった。それはあたかも、『嶽神伝』の山の者たちが、死をも含めて、すべてを自然に受け止める生き方をしていたが、長谷川さんはそれをそのままに生きているようだった。私もやがて闘病生活を余儀なくされるときが来るだろうから、それをこんな風にやんわりと受け止め、周りに気を遣う病人でありたいと思わせてくれた。
2020年11月4日。長谷川さんは71歳の生涯を終えた。
長谷川さんは、私に借りがあると言い続け、そうだとすると、17年の空白のあと、その借りを『嶽神伝』シリーズで何倍にもして返してくれたわけだ。作家と編集者の間には、こういう関係もあるのである。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。