連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第25話 挿絵画家のはなし
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第25話 挿絵画家のはなし](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/11/secret-story_25_banar.png)
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第25回目です。今回は、作品を出版する上でとても大切な役割を果たす、「挿絵」と、挿絵画家についてのエピソードです。編集者と挿絵画家の関係性には、意外なドラマが。時代が変わることで仕事の進め方も様々な変化があったそうです。作家の意向と、それを汲み取り具現化していく編集者の腕。そこにはどんなやりとりがあったのでしょうか?
私は、2008年から2009年にかけて、吉行淳之介さんの、文庫版のエッセイ集全3巻を出版して、その3巻のカバーを、イラストレーターの和田誠さんにお願いした。
千駄ヶ谷にあった和田さんのアトリエに、約束の時間に画稿を受け取りに行った。2階の応接室に行く階段の壁に古い映画のポスターなどが貼ってあり、応接室の壁は本棚になっていて、映画関係の資料などが埋めていた。いかにも和田さんらしい、いい雰囲気のアトリエなのだ。
和田さんの画稿は、文字やイラストなどすべて、画稿を覆っているトレーシング・ペーパーに色指定がされている。和田さんには、仕上がりの色がはっきりと分かっているのだが、私などには、その指定から、印刷が完成したところを想像することは難しかった。
和田さんが、そんな画稿を整理するのを待ちながら、応接室でいろいろな本や資料を眺めていることは楽しかった。まさしく、編集者の特権である。
画稿を手に和田さんが部屋に入ってきてから話をするのも楽しいことだった。
和田さんが、突然、
「今どき、原稿を取りにくるのは、あなただけですよ」
と言った。
「はあ?」
私はその意味をはかりかねて、奇妙な声が出てしまった。
「原稿ができましたかと電話があって、できてるよと言うと、すぐバイク便を出しますとなるんですよ」
バイク便? 私が現役のときは、そんなものなかったぞ。
「あらら」
思わず、そんなことを口走っていた。
「折角、和田さんのアトリエを訪ねたり、和田さんとお話しできるチャンスなのにねえ」
「いまはそうなってるのよ。あなたみたいなのは時代遅れなんですよ」
時代遅れという言い方に、和田さんらしい、なにか親愛の情がこもっていた。
「時代遅れの編集者」にだって、ずいぶんと昔のことになるが、新入社員時代があった。
そのときは、まだ担当作家を持たせてもらえないから、忙しい先輩編集者たちの代わりに、挿絵画家のお宅に画稿を受け取りに行ったものだ。
挿絵画家の多くは、自宅の一部をアトリエにして、挿絵を書いていた。あまり表に出ないせいか、参上した編集者から、文壇やら出版界の情報を聞きたがった。
だから、お宅にうかがうと、編集者を引き留めるためか、珈琲や紅茶や、それに甘いものまでが用意してあることが多かった。
どなたのお宅だったか忘れてしまったが、パリで絵の勉強をしたためだろうか、夫人が、
「今日はカフェ・オ・レにしてみましたわ」
と、いかにもエレガントな口調で言われ、人生ではじめて飲んだカフェ・オ・レには、たしかにパリの香りがしたと思う。
私の年齢を訊いて、「ああ、次男と同じだよ」と、夫妻でうなずきあっていることなど、今でもはっきり覚えている。
お宅にいる間、私は、先輩たちが話していた文壇事情など聞きかじった知識を、僭越にも披露してお茶を濁していた。そんな話でも、喜ばれたのではないかと、私は思っている。
文芸編集者が特定の挿絵画家を担当することはほとんどない。
今月掲載の小説の雰囲気に合った絵を、そのたびごとに選んだ画家に依頼することが多いのだが、作家と画家のコンビが出来上がってしまうこともある。
思いつくままにあげると、川上宗薫さんと濱野彰親さん、野坂昭如さんと黒田征太郎さん、田辺聖子さんと灘本唯人さん、山口瞳さんと柳原良平さん、伊集院靜さんと長友啓典さん、池波正太郎さんと中一弥さん、平岩弓枝さんと蓬田やすひろさん、宮城谷昌光さんと村上豊さんか原田維夫さん、山村美紗さんと深井国さんなどである。
こう書いてみて、作家と画家のコンビとして一世を風靡した、小説家の川口松太郎さんと画家の岩田専太郎さんのことを思い出さざるを得ない。
川口さんの小説に、岩田さんの挿絵が描かれていて、もはや死語になっているかもしれないが、「洛陽の紙価を高らしめた」時期があったのだ。
ふたりは若い頃から知り合っていたが、1939(昭和14)年から1940(昭和15)年にかけて、『東京日日新聞』と『大阪毎日新聞』に連載した川口さんの小説『蛇姫様』の挿絵を、岩田さんが描いて、大好評を博した。
名コンビの誕生と言うわけだ。
ただ、その絵があまりに妖艶、華麗な筆致だったので、戦時に向かう時局がそれを許さずに、段々仕事が減っていくことになったようだ。
戦後、岩田さんが挿絵を描き、装丁をした作家をざっと上げると、国枝完二、船橋聖一、大佛次郎、小島政二郎、川端康成、田村泰次郎、山手樹一郎、源氏鶏太、横溝正史、尾崎士郎、村上元三、有吉佐和子、松本清張、曽野綾子、柴田錬三郎、山岡荘八、三島由紀夫、檀一雄、山田風太郎、司馬遼太郎、吉行淳之介などだ。
つまりは文壇のほとんどの作家の挿絵を描き、装丁を手掛けたことになる。
岩田さんが、生きた昭和文壇史と言われる所以である。
ちなみに、1970年2月号の『小説新潮』に、野坂昭如さんは『浮世一代女』という200枚の中篇小説を書いているが、その挿絵を岩田さんが描いた。
その時、野坂さんが、
「ぼくは、岩専に間に合った」
と、手放しに喜んでいたことを思い出す。
野坂さんは、若い頃、川口松太郎と岩田専太郎のコンビの仕事を見て、憧れていて、自分の小説にも、「岩田専太郎に挿絵を描いてもらう」ことがひとつの夢だったのだ。
その夢が叶ったわけで、このとき、いつもは原稿の遅い野坂さんが、岩田さんに気を使って、早めに書き上げていたのが印象的だった。
その後、1973(昭和48)年に、アンソロジーとして刊行された『浮世一代女』(新潮社刊)の装丁も岩田さんが手掛けているが、その口絵に描かれた女の線画は、岩田さん独特の洒落た線で描かれている。
岩田専太郎さんは、翌年の2月に亡くなっているから、まさに、小説家・野坂昭如は、挿絵画家・岩田専太郎に間に合ったということになる。
川口さんと岩田さんのコンビは、戦前なら、『新篇丹下左膳』『春よいづこ』(昭和15年)、『若い力』(昭和14年)、『振袖御殿』『明治美人館』などがある。
戦後の川口さんと岩田さんのコンビでなされた仕事は、『火の鳥』『情熱の部屋』『宮城広場』『妻の持つ扇』『振袖狂女』『飯と汁』『新源氏物語』『破れかぶれ』『商魂さん』『しぐれ茶屋おりく』『日光月光』『皇女和宮』『獅子丸一平』『源太郎船』『新吾番外勝負』『紅梅曽我』『鏡台前人生』『度胸かぶら』『新吾十番勝負』『新吾二十番勝負』『紅夜叉』『純潔は武装する』『俺は藤吉郎』など無数にあり、このコンビで読者を惹きつけたのである。
戦前にはスタートして、戦後30年も挿絵の世界のトップ・ランナーであり続けた岩田さんも、挿絵の描き方に大きな変革を経験している。
私が文芸編集者になった頃に、もう変革は終わっていて、挿絵の形に関しては、編集部が前もって、四角形にさまざまな変化を持たせ、割り付け用紙に指定して、挿絵を注文するように変わっていた。
40枚の小説なら、3枚の割り付け用紙が必要で、最初の見開きページには「カット」と言って、小説全体の雰囲気を表すような大きめの絵型、その何ページか後に、横長の四角形の絵型を持ってくると、そのまた何ページか後に、変化をつけるために縦長の絵型を使うというような塩梅だった。
それ以前の、とくに大衆小説雑誌や新聞の連載などでは、たとえば、若き姫君の乗った駕籠が雲助たちに襲われるシーンがあるとして、駕籠の中からはみ出している振袖とか、そばに立っている雲助の上半身など、四角形からはみ出して描かれていることが多い。
だから、「絵型」は、単なる四角ではなく、曲線的だったのだ。そのために、挿絵のあるところに組んでいく活字の文字数は、一行ごとに字数が違っていた。それを組む植字工(当時は鉛の活字を使っていて、一字一字、植字工が拾っていたのである)の苦労は並大抵のことではなかったと思う。
で、この曲線的な「絵型」は、編集部ではなくて、原稿を読んだ挿絵画家が決めていた。
作家の和田芳恵さんが、次に書いているように、絵型は挿絵画家に決定権があったわけだ。
「昭和十年一月、『日の出』で連載がはじまった吉川英治作・岩田専太郎画「新編忠臣蔵」について、原稿を読んだ画家が『挿絵がしめるスペースを割付用紙に示した』絵型の段階から作っていたとの証言もある」
(和田芳恵『ひとつの文壇史』2008年、講談社文芸文庫刊)
つまりは、こういうことだ。
編集者は、小説の原稿ができると、コピー機なんて便利なものはなかったから、そのまま、それを割り付け用紙と一緒に画家のところに持参する。
画家は、さっと原稿に目を通すと、挿絵にするのに適当な場面を想定して、カットはこう、次の絵はこう、最後にこうしようと、「割り付け用紙」に、曲線的な「絵型」を書く。
この「割り付け用紙」と原稿を印刷所に入稿すると、一行ごとに違う複雑な字組を「割り付け用紙」に従って、植字工が組み上げてくれるわけだ。
この間、画家は自分が指定した「絵型」に合うように絵を描き上げる。
編集者はそれを受け取り、製版所に入稿して、銅版にしてもらって完成というわけである。
私が駆け出しの頃、「小説現代」誌に、のちに時代小説を書く赤木駿介さんの競馬評論の1ページコラムが載っていた。
まだ競馬評論家としてもそれほど有名でなかった赤木さんのコラムがなぜ載っているのか不思議だったが、そのときの編集長と赤木さんは、多忙だった岩田さんの画稿待ちの仲間だったのだ。
注文が殺到している岩田さんの画稿を確実に手にするために岩田邸に居続けて待っていなければならない。でないと、順番を飛ばされる恐れがあるので、アトリエの隣の部屋で待っている必要があるのだ。そこで、他社の編集者たちと呉越同舟、将棋をさしたりして待っている間に、顔見知りになっていくわけだ。
編集長と赤木さんはそういう関係だったのだ。
ところで、「絵組」という用語もある。これは、たとえば松本清張さんのように、新聞と週刊誌と小説雑誌など、いくつも同時に書いている超多忙の作家は、おいそれとは原稿が書き上がらないことが多い。そこで、編集者は、原稿ができる前に、作家から聞いた筋や挿絵にしてほしいところを、画家のところに行って、今回は、かくかくしかじかのストーリーになるから、こういう挿絵を描いておいてほしいと注文するのである。
これを「絵組」と呼んでいた。
編集者から小説家には、「もう間に合いそうにないから、『絵組』を下さい」という形で使い、挿絵画家には、「原稿が間に合いそうにないから、今回は『絵組』でお願いします。」と伝えることになる。
昭和47年2月号から、昭和48年6月号までに掲載された、笹沢左保さんの『木枯らし紋次郎』の挿絵を、岩田さんが描いている。
社会現象ともなった人気作品だった『木枯らし紋次郎』だが、筆者の笹沢さんも岩田さんも多忙な人であった。
担当者が笹沢さんの原稿を手にするため、ホテルに缶詰にしている間、誰かが、表参道から一本入った路地にある岩田邸に詰めている必要があった。
私は、グラビア担当をしている時に、岩田さんと「新派」の女優の光本幸子さんと並んだ写真をお願いしたことがあったので、その縁を頼りに、『木枯らし紋次郎』の担当者の代わりに岩田邸に詰めていたことが何度もある。
アトリエの隣の部屋で、時折、他社の編集者と一緒に待ちながら、なるほど、岩田さんのお宅で待機仲間となるのはこんな気分なんだなと思ったものだ。
忙しさのあまり、癇癪を爆発させると噂されていて、私はおそるおそる待合室に座っていた。だが、岩田さんはその時も忙しかったのだろうが、イライラを表に出すこともなく、穏やかな下町の好々爺という感じだった。
「野坂さんが、岩田専太郎に間に合ったと感激していましたよ」
と告げると、岩田さんはとても喜んで、
「若い作家だから、新鮮な境地の挿絵にしたからね」
と言った。なるほど、岩田さんから見ると、野坂さんは若い作家なのだな。
岩田さんは、女性にモテて、すぐ一緒に暮らしたが、その人に飽きてしまうと、絵筆だけを風呂敷に包んで、着のみ着たまま、家をあとにしたと言われる。もちろん、その家は手切れ金代わりに残してきたのだそうだ。
私は、そんな「時代遅れ」とも言うべき生き方の画家との仕事に間に合った編集者だったことを密かな喜びとしているのである。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_banar_t-e1728473891678.png)
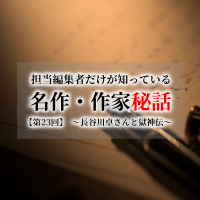
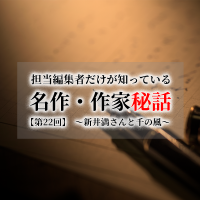
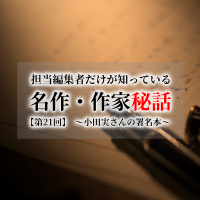
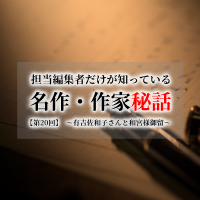
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第25話 挿絵画家のはなし](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/11/secret-story_25_banar-600x315.png)