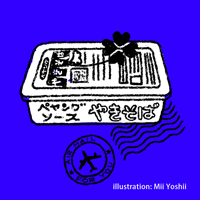思い出の味 ◈ 嶋津 輝

だいぶ前、まだ横須賀線の車両の大半がボックス席であったころのこと。
上り電車は空いていた。ボックス席には私と、通路を挟んで反対側に六十代くらいの女性が一人座っているきりだった。
その女性が大きなカバンからおもむろに、カップ焼きそばの容器を取り出した。たわんだ紙蓋には一度剥がした形跡があり、重量感のある容器は、水平を保つように捧げ持たれていた。
すわ、ここで湯切り?
電車の中でそんな場面に出くわしたことがないから、私は目を瞠った。しかし蓋を開くとそこには湯も麺もなく、白いご飯がぎっしりと詰められていた。焼きそばの容器は弁当箱がわりだったのだ。
女性は割りばしを手に取り、猛然と白飯をかっこみはじめた。梅干しもふりかけもない白いご飯だけを、物凄い勢いで食べている。味気なくないのだろうか、などと心配するのは余計なお世話で、至極旨そうに、一心に食べ続けている。
白飯を平らげると、彼女は別のカップ焼きそばをカバンから取り出した。白いプラスチック製の、四角い、関東人にはなじみ深い銘柄の容器である。覗き見ると、中には里芋の煮物が並んでいた。
彼女はやはり猛然と、芋だけを食べ始めた。いやいや、片方ずつ平らげるのなら、味の濃い芋が先でしょう! 私は心の中でツッコミを入れた。私だったら絶対にお芋が先、いや、ご飯の上に芋をのっけて一緒に食べるかな、私だったら──。何度も唾を呑みこみながら、彼女の食事を最後まで見届けて電車を降りた。
そのころ私は離婚を控えて家庭内別居中という難しい時期で、ろくな食事も摂らず、著しく体重を落としていた。しかしその日は意気揚々と二種類のカップ焼きそばを買って帰った。焼きそばを平らげたのち、ご飯を炊き、里芋の煮物を拵えて、焼きそばの容器に詰め込んだ。そしてあの女性のように、一心に、もりもりと食べた。ひどく美味しかった。腹を満たすことにのみ集中している彼女の姿が、私の食欲を甦えらせたのである。人は何かに無心に取り組んでいるとき、知らずに誰かを救っているのかもしれない。