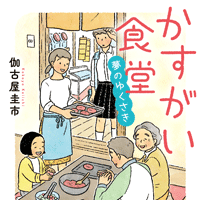柏井 壽 × 伽古屋圭市〈美味しい対談〉五感を使って、味を書く。

本誌の人気連載「鴨川食堂」の著者柏井壽氏と、今号に新作「冥土ごはん」を掲載する伽古屋圭市氏が食をテーマにした小説を書くことの楽しさを語り合った。

──大正時代を舞台にした小説を多く書いてきた伽古屋さんが、"飯もの"小説に挑戦した経緯を教えてください。
伽古屋 まず、僕の好きな大正時代に洋食が盛り上がっていたことを知ったんです。当初は大正時代の洋食店を舞台にと思っていたんですが、打ち合わせを重ねて舞台は現代の洋食店になりました。
柏井 まず大正ありきだったんですね。僕は柏木圭一郎というペンネームでミステリーを書いていましたが、食をテーマにした小説を書いてみようと思って始めたのが「鴨川食堂」です。
──お二人は食事に行った時、小説用にメモを取ったりしますか?
柏井 僕は一切取りません。写真も撮らないし、素材の産地や料理人の修業先にもあまり興味がないので、料理人に話しかけることもほとんどないですね。大間のマグロだと聞くと、それだけですごいと思ってしまいがちですが、味だけを純粋に楽しんだ方が、書く時に、素直に表現できるんです。味の記憶は、五感を使うのが一番。メモしてしまうと頭で書くようになりますから。それよりもお店に居合わせた人の観察をよくします。きつねうどんを店内で食べている女性がどこから来て、どんな人生を送ってきた人なのかを想像すると物語が生まれます。「妄想」が大切なんです。
伽古屋 それにしても「鴨川食堂」にはたくさんの料理が出てきます。すべて記憶を引き出して書くんですか?
柏井 「鴨川食堂」では、客のわずかな記憶から板前の鴨川流がその料理を捜し出し、再現して食べてもらいます。初めて店を訪れた客に出すのが、京のおばんざいです。毎回五種類以上を出すのですが、物語の季節に僕が食べたいと思うものを書いているので、大体どれも旬の素材を使った料理になりますね。
伽古屋 これまで食べてきたものの蓄積が違います。羨ましい。「冥土ごはん」では、幽明軒という洋食店に、死者が最期の食事をしにくるんです。死者は、料理を食べながら思い出を語るのですが、そこにある誤解や思い違いを料理長の九原脩平が推理します。初回はオムライスを取り上げようと、何軒かの洋食屋へ食べに行き、忘れないうちに素材をメモしたり、写真を撮ったりしました。
よだれを垂らしながら書いています──柏井
柏井 料理は、やはり実際に自分で食べないと書けないですね。
伽古屋 けっこうたくさん食べましたが、それでも味を文字だけで伝えるのは難しかったです。
柏井 僕はいつもよだれを垂らしながら書いています(笑)。それくらいでないと、美味しそうには書けないから。
伽古屋 読者に「美味しそう!」と思ってもらいたいというのはありますよね。
柏井 でも無理に美味しく感じさせようとすると失敗するんです。書きながら、自分が美味しいと感じることが大事です。
伽古屋 この小説に取り組み始めて、実生活でもこれまで以上に味わいながら食べるようになったんです。甘さ、辛さ、酸っぱさ、歯ごたえ。それといろんな料理を食べたいと思うようになりました。
──普段、料理はしますか?
伽古屋 ほとんど作りません。でも、取材として編集の方と料理教室に参加しました。やり出したらハマるでしょうね。
柏井 「鴨川食堂」では毎回、思い出の料理を捜すのですが、その料理を決めたら必ず自分で作ります。

伽古屋 どの料理にも一般的な作り方と違う工夫があるのは、柏井さんが実際に作っているからですね。
柏井 作るだけじゃなくて、市場調査もしています。コンビニにも美味しいものがたくさんあるんです。みたらし団子やプリンもかなりいい線いっています。最近感心したのは、某チェーンの冷凍チャーハン。安くて十分美味しい。
伽古屋 僕もよく利用しますよ。ナポリタンやミートソースも美味しいですね。
美味しいだけの料理では物語にならない──伽古屋
柏井 コンビニを利用しながら、こんなに安くて美味しいものが食べられる時代に、どういう料理を描けば読者の琴線にふれることができるか常に考えています。「鴨川食堂」第6話の肉じゃがには、牛肉の大和煮の缶詰を使いますが、これで肉じゃがを作ると美味しいんじゃないかと思ってやってみたら、本当に美味しくできたので、そこからどんな人が食べてどんな物語にすればいいかを考えました。高級食材ではなく、身近な食材を使ってお話を作るようにしています。
伽古屋 オムライスをテーマにした時に、定番のオムライスにとらわれてしまうと、面白くないと思いました。美味しいだけの料理では、最期に食べたいとは思わないですから。でも僕自身はレシピ頼みで、自分で自由に料理を作れるほど経験がないので、少しずつ取り組んでいきたいところです。
柏井 既存の料理とは違う何かがないともう一度食べたいとは思いませんからね。僕もそこは、いつも考えています。
伽古屋 ところで「鴨川食堂」には、時々すごくギャップのある組み合わせが出てきます。トップモデルが焼飯を捜したり、大企業のCEOが先ほどの肉じゃがを捜したり。
柏井 なぜか自然とそこに行き着くんですよね。僕はプロットを作らないので、オムライスだとしたら、大体こういう人というのが自然と出てきます。
伽古屋 僕はプロットから作ります。第1話をオムライスにしたのは、誰もが知っているメジャーな洋食なのに、意外とバリエーションがあって、見た目や作り方が店によって違うからなんです。それがミステリーとして使えそうだと思いました。
柏井 店のモデルはあるんですか?
伽古屋 特にありませんが、人形町を歩きまわって、イメージを膨らませました。あの辺りにはけっこう古い造りの店があるんです。洋食屋以外の店の佇まいも参考にしています。
柏井 鴨川食堂はモデルがあるんです。京都の東本願寺の近くにあった食堂で、数年前に閉店してしまったのですが、その店に行っていた時に「鴨川食堂」を思いついたんです。こういう店にはいろんなドラマがあるんじゃないかと妄想しているうちに、どんどん広がりました。
伽古屋 それがもう29話まで続いているのだから、すごいですね。

小説のドラマ化にはコツがある──柏井
──こんなに続くと思っていましたか?
柏井 できればそうしたいと思っていました。だけど映像化に関しては、絶対にオファーがくる自信があったんです。
伽古屋 ドラマにしやすいように書いたということですか?
柏井 そこまではしていないのですが、登場人物を少なくして、シーン転換をなるべく減らしました。そうするとドラマになりやすいと思ったんです。
伽古屋 コストがかかりそうな小説はドラマ化しにくいですもんね。僕は、時代ものはドラマ化しにくいですよってよく言われます(笑)。
柏井 「冥土ごはん」は、狙えるじゃないですか。たまに時代が飛びますが、あれくらいだったら大丈夫です。幽霊は出演料が安いでしょうし。
伽古屋 いや、本物の幽霊にはご出演いただけません(笑)。
柏井 「鴨川食堂」を映像化した時、流役が萩原健一さんになったのは少し意外でした。僕は、和久峻三さん原作の『京都殺人案内』というドラマが好きでよく見ていたんです。刑事役が藤田まことさんで、主人公の流はそれをイメージしていました。流の娘のこいしもそのドラマで娘役を演じていた萬田久子さんをイメージしていました。
伽古屋 最初にモデルを作るんですか?
柏井 そのほうが書きやすいですね。その人たちに喋らせる。
伽古屋 僕は、基本的にモデルは作らない主義なんです。最初からかっちりキャラクターを作ってしまうと、そこにとどまってしまって、意外な面が出しにくくなるので、回を重ねながら固めていくようにしています。だけど物語の枠組みは、最初にしっかり作ります。
柏井 「鴨川食堂」も毎回物語の枠組みは同じなんです。一度それを変えてみたんですが、編集の方から、やっぱり今までと同じで、と言われて戻しました。
伽古屋 変わらないほうが、読者もきっと安心して読めるんですよね。
柏井 その枠組みの中でも冒険はできるので、自分なりに工夫しています。取り上げていない料理がたくさんありますから、それを考えるのが一番の楽しみです。
伽古屋 洋食もまだまだたくさんメニューがあるので、「冥土ごはん」のシリーズ化を目指して頑張ります。
柏井 壽(かしわい・ひさし)
京都生まれの京都育ち。テレビ番組や雑誌の京都特集で監修をつとめる。エッセイ作品に『極みの京都』『日本百名宿』『ぶらり京都しあわせ歩き』など、著書多数。小説作品に、『鴨川食堂』『鴨川食堂おかわり』『鴨川食堂おまかせ』『鴨川食堂いつもの』などがある。
伽古屋圭市(かこや・けいいち)
1972年大阪府生まれ。第8回『このミステリーがすごい!』大賞優秀賞を受賞した『パチプロ・コード』(文庫時『パチンコと暗号の追跡ゲーム』に改題)で2010年にデビュー。著書に『帝都探偵 謎解け乙女』『からくり探偵・百栗柿三郎』『散り行く花』などがある。