月村了衛著『水戸黄門 天下の副編集長』は痛快時代娯楽小説!著者にインタビュー!
あの手この手で楽しませようとする構造で描いた、原稿集めの珍道中。爆笑必至、痛快時代エンターテインメント作品が登場!著者・月村了衛に、創作の背景をインタビューします。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
原稿集めの珍道中爆笑必至の痛快時代娯楽小説!
『水戸黄門 天下の副編集長』
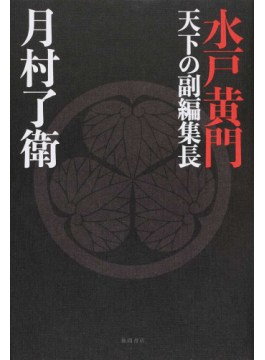
徳間書店 1600円+税
装丁/岩郷重力+K.M
月村了衛

●つきむら・りょうえ 1963年大阪生まれ。早稲田大学第一文学部文芸学科卒。2010年『機龍警察』で小説家デビュー。12年『機龍警察 自爆条項』で第33回日本SF大賞、13年『機龍警察 暗黒市場』で第34回吉川英治文学新人賞、15年『コルトM1851残月』で第17回大藪春彦賞、『土漠の花』で第68回日本推理作家協会賞を受賞。他に『神子上典膳』『槐』『影の中の影』『ガンルージュ』等、ジャンルを超えた作品を続々発表。176㌢、62㌔、A型。
社会に閉塞感が漂い、娯楽が失われつつある今の日本に必要なのは笑いだと思う
国民的で痛快で、「みんなが楽しい」娯楽の王道―。
エンタメ界注目のストーリーテラー・月村了衛氏は、だからこそ「水戸黄門」に着目したという。表題は『水戸黄門 天下の副編集長』 。副将軍ではなく、副編集長である。
「副将軍というのはあくまでドラマ上の演出ですし、水戸黄門=諸国漫遊というイメージも後世の講談以来、多くの映画やドラマが作られる中で定着した。
今作の“史実により忠実なコメディ”が成立するのもそうしたイメージのおかげで、喜劇的想像力を非常に刺激される、やりがいのある素材でした(笑い)」
出色は、水戸藩前藩主がなぜ諸国を旅したかという、その理由である。引退後は小石川の藩邸内に「彰考館」を設置し、『大日本史』編纂に尽力した光圀は、一向に進まない作業に怒り心頭だ。ある時、彼は締切を守らない執筆者に自ら談判すると言い出し、安積澹泊覚兵衛(覚さん)や佐々介三郎宗淳(介さん)を供にお忍びで旅に出る。つまり水戸の御老公一行が諸国を漫遊した動機は、世直しではなく〈原稿取り〉だった!?
*
〈一つ、執筆者は生かさず殺さずを以て旨とすべし〉
〈一つ、締切破りは天下の大逆と心得べし〉……と、光圀直筆の心得が仰々しく張り出された彰考館の一室。それを見る度に本書の語り手で同館総裁・安積覚兵衛は人知れず溜息をついた。
「日本書紀」以来の編年体ではなく、予算も人手もかかる紀伝体による国史編纂にこだわる光圀の夢を実現すべく彼は頭を痛め、反対派との板挟みにもなってきた。が、光圀は先ごろお吟というの女を机(つまり編集デスク)に抜擢。〈なるほど男には為し得ぬ冷酷〉〈男はつい同情する。執筆者への義理や後々の付き合いも考える。そこが女は容赦がない〉と覚兵衛は思う。
そう、字こそ違うもののあのお銀である。覚兵衛や編修顧問の介三郎は実在の人物だが、元々虚構の産物だったお銀や〈風車の男〉こと隠密の〈中谷弥一郎〉までが本書には登場し、下田から駿府~藤枝~掛川まで全4話にお吟の入浴シーンがあるのも一興だ。
「実は最初の行き先を下田にしたのも温泉があったから(笑い)。元々第1話は作品の幅を警察小説だけに狭めたくなくて『機龍警察 自爆条項』(11年)の直後に書き上げていたんです。その後、〈書物問屋〉の隠居に扮した一行の歩みが徐々に小刻みになるのは、続編の連作が決定したから(笑い)」
まずは下田在住の儒学者〈錫之原銅石〉から原稿を取り立てるべく箱根の難所を越えた御一行。ところが銅石は地元質屋〈戸的屋〉の息のかかる場で借金を作って姿を消したらしい。娘〈志乃〉も妙に頑なな中、城下では〈『夢現桃色枕』〉なる春本が人気を集め、やがて全ての接点に代官ぐるみの裏商売のカラクリが見え隠れする……。
この時、〈こちらにおわすをどなたと心得る〉の名台詞はまだ登場しない。敵味方が相乱れる中、元々文人の覚兵衛はオロオロするばかりで、印籠を見るや一同ひれ伏す状況を作ったのは別の人物だ。覚兵衛は2話以降、これを真似して事態を収拾したに過ぎない。
「私が考えたのは、ドラマ定番のシーンや人物像をどう転がせばより面白いか。ちょっとずらすだけでおかしみが出るのも、水戸黄門ならではでした。特に今は社会全体に閉塞感が漂い、先の都知事選の結果にしても、どこかスッキリしない気分が支持政党にかかわらずあるように思う。そうしたモヤモヤが一瞬でも晴れて、ああ面白かった、明日からまた頑張ろうと思わせてくれるのが、私の考える本来的な大衆文学なんです」
あの手この手で楽しませる構造
それにしてもお吟が柔肌を晒し、どこからか風車が飛んでくるだけでニヤリとしてしまうほど、水戸黄門が自分の一部と化していることに改めて驚かされる。
「たぶんドラマを観ていない人でも懐かしさを覚えるくらい、あの勧善懲悪劇は日本人のDNAに刷り込まれていると思うんです。
私はそうした娯楽が失われつつある現状を何とかしたくて、自分が親しんできた大衆文学や冒険小説の本流を後世につなげる覚悟で小説を書いています。水戸黄門に代表される明朗時代劇も読んでさえもらえればみんなが楽しめるはずだし、今の日本に必要なのは笑いではないかと思うので」
第1話のモチーフが作家を脱稿するまで閉じ込める〈缶詰〉なら、2話は〈パクリ〉で3話は〈スランプ〉。そして最終話では執筆者の〈恋わずらい〉が思いもよらない結末を招き、編集者の苦労は今と昔を問わない。
その上で〈かの『史記』の編修者が司馬遷を夏陽県の缶都館なる旅館に閉じ込めた〉、はたまた〈パクリとは、明代に著された古典『三国志演義』の作者の一人とも言われる箔李が、執筆に行き詰まった挙句、他人の作を盗用した故事に由来〉などと、月村氏はいかにもありそうなウソを織り交ぜ、一行の行く先々で事実そっちのけの世直し譚が喧伝されたりする落差にも、笑いやおかしみを見出す。
また、第2話以降のセミレギュラーで、光圀に先んじた豊臣寄りの国史編纂を目論む真田家の末裔〈月読姫〉や美貌のくノ一軍団と、お吟たちが対決するアクションシーンも、自身、山田風太郎ファンを公言するだけに見物。さらに最終話では遠州を二分する学閥の子女〈門田露水鴎〉と〈珠里〉の恋を黄門様が助太刀するなど、シェークスピアであれ何であれ、面白いものには目がない月村氏なのだ。
「もちろん各話ともその事件を通じて登場人物がどう成長するかというドラマを軸に組み立てるんですが、どうせならくノ一がずらっと並ぶ方が華やかですしね。それこそ昔の東映時代劇にはレビューの要素もあったと思うし、中学時代は北杜夫や小林信彦やモリエールを読み、高校生の時にバスター・キートンのサイレント喜劇にとどめを刺された私には、あの手この手で楽しませるエンタメ構造が刷り込まれているんだと思う。ムダに読み散らかしてきた年月が、ここにきて生きてきたんですかね(笑い)」
文体も正統派時代小説に則り、「あえて滑稽な喜劇をやる」作家の覚悟が、時代の閉塞感に発していることはこの際忘れよう。読む者はただ笑いあり涙あり、各宿場の名物や〈一件落着〉のカタルシスまである痛快な世界に遊び、明日への英気を養うのが唯一の作法なのだから。
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年9.9号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/09/10)

