中原中也の「スゴい詩」4選

夭逝の天才詩人として知られる中原中也。『サーカス』や『汚れつちまつた悲しみに……』といった中原の代表的な詩とその魅力について、彼の生涯を振り返りながらご紹介します。
昭和期に活躍し、30歳で夭逝したことで知られる詩人・中原中也。その作品にあまり馴染みがない人でも、『サーカス』や『汚れつちまつた悲しみに……』といった詩は、学生時代の国語の教科書で一度は触れたことがあるのではないでしょうか。山高帽を被り、真っ直ぐにこちらを見つめている肖像写真が印象深い、という方も多いかもしれません。
また、近年では実在の文豪たちが活躍する漫画作品『文豪ストレイドッグス』や、文豪たちとともに敵を討伐するシミュレーションゲーム『文豪とアルケミスト』といった作品の中でも中心的な役割を担うキャラクターとして登場しているため、漫画作品やゲームを通じて中原を知ったという方もいらっしゃることでしょう。
その短くも太い生涯を通じ、私たちに強烈な存在感を与え続けている中原中也。今回は、そんな彼が生み出した“スゴい詩”たちを、主に年代順に、中原の年譜を追いながらご紹介していきます。
トタンがセンベイ食べて 春の日の夕暮は穏かです──『春の日の夕暮』
トタンがセンベイ食べて
春の日の夕暮は穏かです
アンダースローされた灰が蒼ざめて
春の日の夕暮は静かです
吁 ! 案山子はないか──あるまい
馬嘶 くか──嘶きもしまい
ただただ月の光のヌメランとするままに
従順なのは 春の日の夕暮かポトホトと野の中に伽藍は紅く
荷馬車の車輪 油を失い
私が歴史的現在に物を云えば
嘲 る嘲る 空と山とが瓦が一枚 はぐれました
これから春の日の夕暮は
無言ながら 前進します
自らの 静脈管の中へです
中原が本格的に詩作を始めたきっかけは、1923年、京都の古書店で詩集『ダダイスト新吉の詩』に出会ったことでした。
1907年、山口県に生まれ、“神童”とも呼ばれるほど優秀な子ども時代を過ごした中原。中学時代には早くも短歌の才が評価され、友人たちと合同歌集『末黒野』を刊行するなど、地元の文学好きな若者たちとの交流を楽しんでいました。
しかし1923年の春、文学に耽溺するあまり学業成績が落ちつつあった中原は、中学3年から4年に進級できず、落第してしまいます。中原は知人に勉強を見てもらうという条件つきで親元を離れ、地元・山口から京都の立命館中学校に転入しましたが、彼にとってこの京都行きは不名誉なものではなかったようで、むしろ“飛び立つ思い”だったとのちの随筆の中で綴っています。
そんな中原が同年の秋に古書店で出会い、衝撃を受けた『ダダイスト新吉の詩』は、当時まだ無名の詩人ながらも文士たちに注目されつつあった、高橋新吉による詩集です。高橋は前衛詩運動の先頭を走り、当時ヨーロッパで流行していたダダイズム(第一次世界大戦に対する反抗や虚無感を根底に持つ、既成の秩序を破壊、解体しようとする芸術思想・芸術運動)を日本語の詩の世界に持ち込んだ人物。中原はこの詩集の中の“DADAは一切を断言し否定する”という言葉に強く惹かれ、ダダイストと自称するようになりました。その心酔ぶりは、当時、京都の友人たちや、中原が同棲していた女優・長谷川泰子から「ダダさん」とあだ名されるほどだったといいます。
京都に移り住んだ中原は短歌をやめ、詩を書くことにその情熱を注ぐようになっていました。『春の日の夕暮』は当時の中原による一作で、“トタンがセンベイ食べて”といった一見意味不明なフレーズからは、ダダイズムの影響が強く感じられます。
しかしこの詩からそれ以上に滲み出ているのは、後年の中原の詩の特徴でもある叙情性です。古いトタンに風が吹き、まるでせんべいを食べているときのようにバリバリと音を立てる。その風が止むとしだいに灰色がかった空がアンダースローで投げられたボールのように蒼ざめてゆき、辺りが静けさに包まれていく──。そんな美しい光景が“自らの静脈感の中”に入り身体へと落とし込まれるという感覚は、ダダイズムが重視する無意味性や反抗精神とはすこし違ったベクトルのものであるように思われます。
つまり、中原の詩人としての出発点はダダイズムにありましたが、彼ははじめからその手法だけに頼らず、独創的な感性によってすでに自らの詩を確立しつつあったのです。『春の日の夕暮』はそれを暗示するような、最初期の中原を代表する一作です。
うしなひしさまざまのゆめ、森竝は風に鳴るかな──『朝の歌』
天井に 朱きいろいで
戸の隙を 洩れ入る光、
鄙 びたる 軍楽の憶ひ
手にてなす なにごともなし。小鳥らの うたはきこえず
空は今日 はなだ色らし、
倦 んじてし 人のこころを
諫めする なにものもなし。樹脂の香に 朝は悩まし
うしなひし さまざまのゆめ、
森竝 は 風に鳴るかなひろごりて たひらかの空、
土手づたひ きえてゆくかな
うつくしき さまざまの夢。
中原は同じ頃に同世代の詩人である富永太郎と出会い、富永の影響で、アルチュール・ランボーといったフランス象徴派詩人たちの作品に魅了されます。富永が結核の療養のために京都から故郷の東京に戻ると、中原は(表向きは大学予科受験のためという理由で)富永を追うように長谷川泰子を伴って上京し、1925年春、日本大学予科に入学します。しかし、1科目も試験を受けないままで翌年に退学しています。
この頃に中原が作った詩が、『朝の歌』です。4行、4行、3行、3行の全14行から成るソネット形式のこの詩は後年、作曲家の諸井三郎によって歌曲となり、当時の前衛的な音楽サークルであった「スルヤ」の機関誌の中ではじめて発表されました。
『朝の歌』に書かれているのは、朝、扉の隙間から漏れてくる光をぼんやりと見つめながら手持ち無沙汰な気分でいる主人公の、弛緩した心身です。朝という言葉からイメージされるような爽やかさや1日への期待とは対照的に、この主人公はまどろみと倦怠感に包まれ、それらを諌めてくれる“なにものも”いないことを嘆いています。しかし、さまざまな夢を失ったと語る3連と4連からは、喪失感だけではなく、どこか解放感のようなものも感じられます。
この解放感の正体はいったい何でしょうか。当時の中原と交流があり、彼が自室で早朝に『朝の歌』を歌う姿を時折見ていたという音楽評論家の吉田秀和は、それを解き明かすヒントになりそうなことを、随筆の中で綴っています。
天井にゆれている光をみながら彼の歌をきいていると、私には、小鳥と空、森の香りと走ってゆく風が、自分の心の中でも、ひとつにとけあってゆくのを感じた。そうして、この倦んじた心、手にてなす何ごとも知らない心。私は、そこに、泰西象徴派詩人のスプリーンより、中原自身の倫理の掟をみるのだ。動いてはいけない。あせってはいけない。
──『ソロモンの歌』収録「中原中也のこと」より
吉田のいう“中原自身の倫理の掟”とは、朝を爽やかな気持ちで迎え1日の仕事を始めるべきだといういわば社会的倫理のようなものではなく、また、フランス象徴派詩人たちのようにそのことに“スプリーン”(憂い)を感じることでもなく、“動いてはいけない、あせってはいけない”と悠然と構え、“さまざまのゆめ”を失うことを見つめ続けることを選ぶという感覚であるように思われます。
中原はこの詩を当時知り合った文芸評論家の小林秀雄に見せ、“方針立つ”とのちに記しています。長谷川泰子は当時、中原との同棲を解消し小林と暮らし始めていましたが、その歪な三角関係の中にあってもなお、中原は小林に『朝の光』を見せたかったようです。本作は中原自身にとっても、詩人としての方針を明瞭にさせた記念碑的な作品であったことは間違いありません。
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん──『サーカス』
幾時代かがありまして
茶色い戦争ありました幾時代かがありまして
冬は疾風吹きました幾時代かがありまして
今夜此処での一と殷盛 り
今夜此処での一と殷盛りサーカス小屋は高い梁
そこに一つのブランコだ
見えるともないブランコだ頭倒さに手を垂れて
汚れ木綿の屋蓋 のもと
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよんそれの近くの白い灯が
安値 いリボンと息を吐き観客様はみな鰯
咽喉 が鳴ります牡蠣殻と
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん屋外は真ッ闇 闇の闇
夜は劫々と更けまする
落下傘奴 のノスタルジアと
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん
『朝の光』とほぼ同時期かそれ以前に書かれたと推定されている詩が、中原の代表作として現代では広く知られている『サーカス』です。高校の国語教科書にも収録されることの多いこの詩のことを、“ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん”という空中ブランコが揺れるさまを描いた強烈なオノマトペによって覚えている方も多いのではないでしょうか。
この詩について、詩人で文芸評論家の北川透が興味深い評を残しています。
《幾時代》といい、《茶色い戦争》とか《冬は疾風》という恣意的な言語を必然と化す、中原の語法は、恣意性において実に天賦の才能を持つこの詩人の力ではあるが、しかし、無限定なこのような語法が許されるのは、これがうただからである。批判的に言えば、このような短絡に行ってしまう中原の自意識は稀薄であり、弱さである。(中略)そのように批判しても、なお、詩の方から吹きよせてくるものがある。
──『中原中也論集成』収録「中原中也の世界」より
詩の冒頭で矢継ぎ早に登場する“茶色い戦争”、“冬は疾風”といったイメージは、特定の戦争や冬のある日のできごとからのリアリティのある連想というよりも、“うた”的なフレーズ(歌詞のような、と言い換えてもよいかもしれません)だと北川は言います。それは“短絡”であり“弱さ”だと批判しつつも、“なお、詩の方から吹きよせてくるものがある”というのはどういうことでしょうか。北川は“茶色い戦争”も“冬は疾風”も中原の閉塞的な心象風景を表していると分析した上で、こう続けます。
“彼は閉ざされた自意識がノスタルジアに流されていく、その心のゆれうごき、不安こそにことばを与えたかったのに違いない。そしてそれが一つの世界をつくるよりも、うたの相貌をおびてしまうことの困難は先に言ったが、しかし、実はこの詩にそうした批判を越えてなおせまってくるものを正当に見るとすれば、それはこの詩に流れている強烈な音楽性というものであろう。(中略)”音楽的な激しい流れを内部に秘めて、この詩は、閉ざされた中原の自意識が、ノスタルジアへとむけられていく不安や同様の心象をうつしだしていると考えることができるのである。”
──『中原中也論集成』収録「中原中也の世界」より
ここで言う“音楽性”とは、“ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん”といったオノマトペや冒頭の2連のリフレイン、そして“屋蓋のもと”、“牡蠣殻と”、“ノスタルジアと”といった脚韻が生むリズムを指していると考えてよいでしょう。また、中原がこの時期に宮沢賢治の詩集『春と修羅』に出会い、その詩を“民謡の精神”が感じられるという理由で高く評価していることからもやはり、中原が詩作において音楽性に重きを置いていたことがわかります。
『サーカス』の魅力は、内部に脈々と流れているこの“音楽性”と、その裏で併走するノスタルジーに向かって開かれていくことへの期待と不安が、奇跡的とも思えるバランスで結晶化している点にあるように感じられます。
汚れつちまつた悲しみは たとへば狐の皮裘──『汚れつちまつた悲しみに……』
汚れつちまつた悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れつちまつた悲しみに
今日も風さへ吹きすぎる汚れつちまつた悲しみは
たとへば狐の皮裘
汚れつちまつた悲しみは
小雪のかかつてちぢこまる汚れつちまつた悲しみは
なにのぞむなくねがふなく
汚れつちまつた悲しみは
倦怠のうちに死を夢む汚れつちまつた悲しみに
いたいたしくも怖気づき
汚れつちまつた悲しみに
なすところなく日は暮れる……
1929年の春、中原は河上徹太郎、村井康男、大岡昇平らといった仲間とともに同人誌『白痴群』を創刊しています。この雑誌は翌年に終刊となるものの、中原は毎号精力的に詩を発表しました。『汚れつちまつた悲しみに……』は、最終号であった第6号で中原が発表したアンソロジーの中の1篇で、のちに本作は中原の第一詩集『山羊の歌』にも収録されることとなります。
この詩のユニークさはやはり、“汚れつちまつた悲しみ”と何度も執拗に書きながらも、その“悲しみ”の内容や詳細ではなく、比喩としての“悲しみ”に焦点が当たり続けることです。中原が自らの“悲しみ”の宿命に気づくまでの過程が、そこには書かれています。特徴的なのは、“悲しみ”に“小雪”が降りかかって縮こまる、という点。中原は『白痴群』第6号に同じく収録された『生ひ立ちの歌』、『雪の宵』という他の2篇の詩の中でも降る雪の姿をモチーフにしており、中原にとって“悲しみ”は雪が自らに降りかかるイメージと非常に密接なものだったのでしょう。
この“悲しみ”の中身の具体性を推し量ることはできませんが、小林秀雄はのちに、中原が抱えていた“悲しみ”と彼の詩作について、こんな文章を残しています。
中原の心の中には、実に深い悲しみがあつて、それは彼自身の手にも余るものであつたと私は思つてゐる。……彼は、自己を防御する術をまるで知らなかった。世間を渡るとは、一種の自己隠蔽術に他ならないのだが、彼には自分の一番秘密なものを人々に分ちたい欲求だけが強かつた。その不可能と愚かさを聡明な彼はよく知つてゐたが、どうにもならぬ力が彼を推してゐたのだと思ふ。……彼の詩は、彼の生涯に密着してゐた、痛ましい程。
──『中原中也の思い出』より
小林が言うところの“手にも余るほどの悲しみ”が中原を一番強く襲ったのは、1933年に結婚した遠縁の女性・上野孝子との間に生まれた長男・文也が、小児結核で命を落とした1936年でした。溺愛と言ってもよいほど文也を愛していたという中原は子どもの死以降、徐々に神経衰弱に陥っていきます。翌年の秋、彼は第二詩集『在りし日の歌』の原稿を小林秀雄に託し、結核性脳膜炎のために生涯を終えました。
中原の死後に発表された『在りし日の歌』に収録されている詩の中には、“死児”のモチーフが繰り返し登場します。文也の死以前に書かれた詩の中でも、中原は何度も“死児”の幻覚を見ているのです。そこには、失われた自らの子ども時代への憧憬と、それでもなお現在の自分に何度でも立ち返り、深い悲しみの中で生きていかなければいけないという諦めや絶望が表れているかのようです。
おわりに
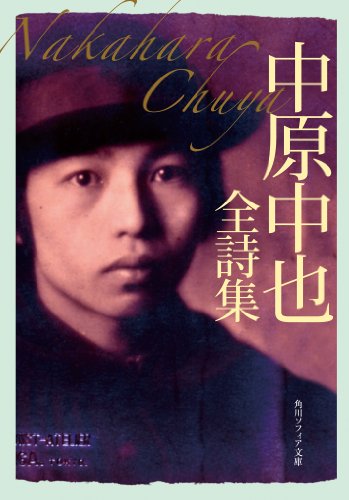
『春の日の夕暮』『朝の歌』『サーカス』『汚れつちまつた悲しみに……』収録/
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4041171040/
中原中也と交流があった文士たちが彼について語るとき、決まって飛び出すのは「自分の詩を独特な節回しで所構わず歌うので疎まれていた」「酒癖があまりに悪く、まともな付き合いができなかった」──といったエピソードです。彼の詩と生活とは常に密着しており、だからこそ詩人としてしか生きられなかった中原は、社会には終生馴染めませんでした。
詩人・井川博年は、中原の詩を読むということについて、かつてこんな風に綴っています。
結婚して子どもができるようになると、私とて生活の心配をせねばならず、妻子を養うために稼がねばならない。そうして年月が経ち、仕事もなんとか一人前にできるようになり、社会の仕組みもわかってき、この世で生きるコツ(中也にはこれがわからなかった)がわかってくると、それと共に中也の詩を読まなくなる。誰でもがそうかも知れないように、私も「中也離れ」をしたのである。
──『私の中の中原中也』より
“この世で生きるコツ”は、小林秀雄の言う“世間を渡るための自己隠蔽術”とほぼ同じものと考えられます。それが終始わからなかった中原の言葉は、私たち読者が大人になり、“コツ”や“自己隠蔽術”を掴み始めるに従って、どこか気恥ずかしいものに感じられてくる──というのが井川の言葉の意味でしょう。しかし裏返せば、“この世で生きるコツ”や“自己隠蔽術”の対極にある中原の詩は、もっとも純粋なもの、汚れていないものとも言えるのです。
※参考文献
・中原中也『中原中也全詩集』(KADOKAWA)
・北川透『中原中也論集成』(思潮社)
・佐々木幹郎『中原中也 沈黙の音楽』(岩波書店)
・大岡昇平『中原中也』、『富永太郎と中原中也』(第三文明社)
初出:P+D MAGAZINE(2021/05/13)

