誰より本が好きだからこそ。「本屋さんによるエッセイ」のおすすめ5選

日々、多くの本と接し、大切な本を売ることに情熱を注いでいる書店員。書店員が自分の店のことや本のこと、毎日の生活のことを綴ったエッセイには、本への愛情を感じられる名著が多くあります。そんな“本屋さんによるエッセイ”を集めました。
すばらしい本を世に広めるべく、日々さまざまな工夫を重ねている書店員たち。書店で目にする熱のこもったPOP(店頭に置かれる手書き広告)や個性のある選書に惹かれ、普段は買わないような本を思わず手にとったことがある、という方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな“本選びのプロ”である本屋さんが書いたエッセイのおすすめ作品をご紹介します。本屋さんによる渾身の書評や本にまつわる思い出のエピソード、そして本屋を開店・運営していくための心構えまで、多種多様なエッセイをお楽しみください。
『本屋の新井』(新井見枝香)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4065249708/
『本屋の新井』は、「日本一有名な書店員」と呼ばれる著者の新井見枝香が2018年に発表したエッセイ集です。著者はもともと三省堂書店で働いており(現在はHMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE勤務)、当初から“売る機会を逃しているかもしれない”本が1冊でもあることが耐えられなかったと言います。日々販促に励むなかで、作家とトークイベントをしたり、個人的なイチオシ本を芥川賞・直木賞の時期に合わせて発表する“新井賞”を創設したりと、型破りとも言えるやり方で多くの本を世に送り出してきました。
本書にはそんな新井が、書店のことや日常のこと、そして大好きな本について自由に綴る短いエッセイが50以上収録されています。なかには、価値ある本を1冊でも多く売ることを常に考えている書店員だからこその問題提起や提言をしている文章もあります。たとえば、書店が提供するサービスのひとつである“無料の紙袋”について触れたエッセイでは、このように綴っています。
書店で働くようになって、まず本の利益率の低さに仰け反った。私が以前働いていたアイスクリーム屋では従業員割引が30%で、半額じゃないのかよーと残念に思ったものだが、書店なら30%でも、大出血で死んでいる。
さらに備品として毎日補充している紙袋の値段を知り、バターンとひっくり返った。書店のロゴが印刷された紙袋は重さ2キロにも耐える頑丈な作りで、それはそれは高級品なのであった。
客のなかには、週刊誌を1冊買うだけでも「紙袋を何枚もつけてほしい」とリクエストする人もいると言います。新井は、快適に買い物をしてほしいものの、過度な要求に応え続けていると、書店はいつか無料で紙袋を提供できなくなるかもしれない──と述べます(※現在は環境負荷の問題もあり、多くの書店チェーンで紙袋は有料化されています)。
書店員が“商売っ気”を出すことを否定的に捉える人もいるものの、よい本を売り、書店の運営を続けることこそが書店員の仕事であるという新井の姿勢は一貫しています。本を愛する人はもちろん、書店の現状や未来について考えたい人にとってもおすすめの1冊です。
(あわせて読みたい:【『本屋の新井』発売】「売り場にいないと死んでしまう」──書店員・新井見枝香さんインタビュー)
『絵本のなかへ帰る』(高村志保)

出典:https://www.keibunsha-books.com/shopdetail/000000025523/
『絵本のなかへ帰る』は、長野県茅野市にある老舗本屋「今井書店」の店主・高村志保によるエッセイ集です。タイトルのとおり“絵本”の記憶にまつわる文章がまとめられた本書は、書評としても、著者の子ども時代について綴った随筆としても味わうことができます。
父が読み聞かせてくれる絵本で育ったという高村は、現在は一児の母として子育てをしています。『おおきなかぶ』にまつわる記憶について綴るエッセイのなかで、高村は息子がまだ小さいときのエピソードをこんな風に振り返っています。
私は無条件に絵本を読んでもらって育った。けれど、私が息子に絵本を読むようになると、その体験は自分のものとはかなり違っていた。読み手である私が息子に質問を次から次に投げかけてしまうのである。(中略)
「この色は?」
「赤」
「正解」
「じゃ、この色、英語でなんて言うの?」
「レッド」
「正解」
そして読み終わると、感想を聞いた。
「おもしろかった」
息子がそうこたえると、
「どこがどう面白かった? 言ってごらん」
息子にとって私が絵本を読むということは緊張の時間以外の何物でもなかったと思う。どこからどう質問が飛んでくるかわからない。さらに、その質問に正解しなければ母親の機嫌はドンドン悪くなる。
どうしてこうなってしまったのか、と聞かれたら、賢い子に育てたかったからと正直に答えるほかない。
高村は、当時の自身の子育てを、“下心に満ちていた”と正直に述懐します。そして、思い通りに育たない息子への苛立ちがピークに達していたある日、息子が『おおきなかぶ』を8回も読んでほしがったと言います。
八回目の「やっと、かぶは ぬけました。おしまい」のその最後の「おしまい」の声が、自分でも驚くほどやさしかったのがわかった。その瞬間、息子と目が合って二人でぷっと吹き出した。
自分がどれだけ身勝手に突き放してもこちらに寄り添おうとしてくれる子どもは、本当にすごい存在だ、と高村は自省も込めつつ語ります。絵本を誰かに読んでもらうという行為、そして自分が誰かに絵本を読むという行為の偉大さやおもしろさについて、やさしい文章を通して考えさせられるような1冊です。
『暗がりで本を読む』(徳永圭子)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4860114485/
『暗がりで本を読む』は、九州の書店に勤務するベテラン書店員・徳永圭子による書評集です。本書のなかで紹介されるのは売れ筋の本や人気のある作家の本というよりも、海外文学や新書など、どちらかと言うと普段スポットが当たりにくい、静かな本ばかり。タイトルの“暗がり”という言葉がそれを象徴しているかのようです。
徳永は、本を通じてふと“記憶の蓋”が開く瞬間について、このように綴っています。
東京で通勤のしやすい手頃な部屋を借りた時、地名に聞き覚えがあった。そこは子どもの頃に読んだ『ぼく日本人なの? 中国帰りの友だちはいま…』(ほるぷ出版)という児童向けのノンフィクションの舞台。江戸川区葛西にある小学校に通う中国残留日本人孤児二世の話で、拙い日本語で綴られた日記に先生たちが静かに奮い立つ姿が心の片隅に残っていた。(中略)
今話している言葉を忘れてしまう日がくるのか。もし私が遠い国へ遣られたら家族の名前、住所、電話番号、生まれた場所、誕生日、あとは何を覚えていれば私を見つけてもらえるのだろうと、幼いながらも誰かに相談できることではないような気がしてひとり考えていた。そんな思いも随分と遠い日のことのように感じる。
過去の読書を通じて知ったことや触れたことに、大人になってから予想外の場所で出会い直す、という経験をしたことがある方はきっと多いはず。幼いころになにげない気持ちで読んでいた本のなかの言葉が、あるとき突然自分にとっての指針や助けになることは決して珍しいことではありません。本書は、そんな本の“時差”ありきの効能を感じることのできる1冊です。
たくさんの本を読む人に出会い、私ももっと本を読める人になりたいと思ってきた。読むことの難しさを痛みのように感じることもあり、すべてを手放したらどんな暮らしが待っているのだろうと思うけれど、もうそれすら想像できないところへ来てしまった。抱いた不安や嫉妬を捨て去ることは難しい。私よりもたくさんのことを知っている、多くの物語を持っている人へのあこがれを纏って、僅かでも近づくために本を手にする日々はこれからも続くと思う。
という言葉の通り、著者の本の読み方はとても丁寧でありながら、本書ではその過程で抱いた“不安”や“嫉妬”についても隠さずに綴られています。難解な本や知名度の低い本もとっつきやすい言葉と視点で紹介しているので、これから読みたい本を探すためのブックガイドとしても非常におすすめです。
『これからの本屋読本』(内沼晋太郎)
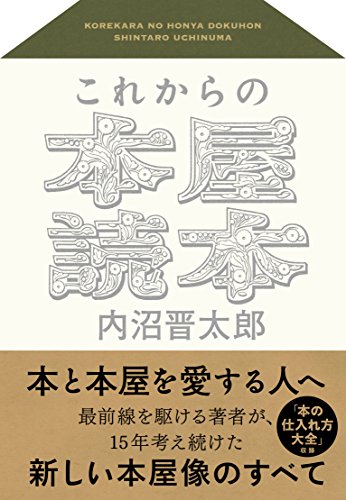
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07DHBPTNN/
『これからの本屋読本』は、下北沢の本屋B&Bを経営し、「NUMABOOKS」という屋号でブックコーディネーター・出版社としても活動をおこなっている内沼晋太郎による書籍です。本書は書評や随筆という形ではなく、そのタイトル通り、“これからの本屋”について考えたい読者や未来の書店員・書店経営者のための1冊となっています。
内沼は、本書を書いた背景をこのように語っています。
昔ながらの本屋がきびしい。背景にはもちろんインターネットとスマートフォンがある。一方で、小さな本屋をはじめる人が増えている。これは日本特有の現象ではなく、どうやら世界中の、特に読書人口が多い先進国では共通する流れのようだ。必ずしも儲かりはしない。けれど、本を愛する人が、本を愛する人のために本屋を開く。そこには大抵、これからの時代に継続していくための、従来の本屋にはない新しいアイデアがある。
そして、内沼は本屋という場の根源的な魅力がどこにあるのかを、書籍を引用しつつ複数の視点から紐解いています。たとえば、“その本屋らしさ”というものがどこから生まれるかについて考察している章では、
その本屋らしさをつくっているのはほとんど、そこで働く人であるといえる。
もちろん、棚に並ぶ本を、ひとりの人間の完璧なコントロール下に管理することは、なかなかできない。どの本が売れるかは客次第であるから、同時に客によってつくられているともいえる。店という場所には、予想外の急な出来事がたくさん起こる。本は人によって能動的に発注されるものだけではない。新刊書店であればシステマティックに、古書店であれば誰かからの買取として、受動的に入荷することも多い。(中略)
その本屋らしい選書、その本屋らしい並べ方。コントロールの効かせ方。それは、本を仕入れ、陳列する個人のフィルターにかかっている。
と分析し、だからこそ遠くの本屋にまでわざわざ足を運ぶ価値が生まれてくるのだ、と語ります。
特に先進的な取り組みをしている“小さな本屋”の数々のアイデアやコンセプトを紹介したり、本の仕入れのためのノウハウを具体的に解説したりと、本書で言及される“これからの本屋像”は決して抽象的なものではなく、地に足のついたものばかりです。本屋のしくみやその魅力の理由に興味のある方はもちろん、いつか書店や出版社を開くことを夢見ている方にとっても必読の書籍です。
『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』(辻山良雄)
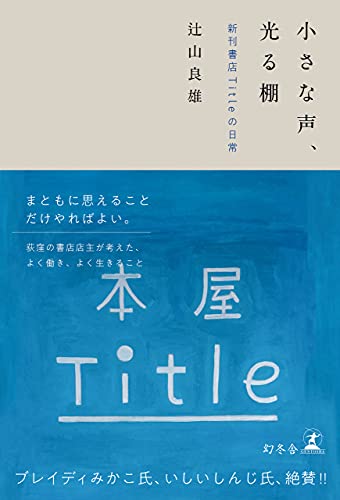
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B096ZQT9HV/
『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、東京・荻窪に2016年にオープンし、本好きの人たちや作家から熱い支持を集めている本屋Titleの店主・辻山良雄によるエッセイ集です。辻山は本書のなかで、書店チェーンを辞め、個人書店を始めた理由を、こう語っています。
会社を辞め個人の本屋を始めた理由の一つに、自分の責任だけで解決する、継続的な場所を作りたかったことがある。書店チェーンに勤めていたころは、その店に慣れたと思ったらすぐ異動になり、知らないあいだに会社の事情で、店の閉店までもが決められてしまうことさえあったから、自分の意志とは反して仕事が一本の線となって続いていかないジレンマがあった。(中略)たとえ小さくても、自分が責任を持てる場所ではなくては意味がない。そう思い書店をはじめた。
まともに思えることだけやればよい。
それは個人経営のよいところであり、その店が長く続いていくための秘訣でもある。
“まともに思えることだけ”をやるという辻山のモットーは、書店としてのスタンスや棚作り、選書にも表れています。本書のタイトルにもあるとおり、Titleは“小さな声”の本を集めることに重きを置いていると言います。
休日。他の書店に入ってみると、必要以上に大きな声をした本が優先して並べられていることに気がついた。あわよくばたくさんの人から注目され、他を圧倒してやりたい。そうした自意識を隠そうとしない本に触れると心底ぐったりとして、その店からはほうほうの体で出てしまう。
本屋とは、同じように本を並べていても、こうも違う店ができあがってしまうものなのだ。Titleに並んでいる本は声が小さく、ほかの本の存在をかき消すことはないが、近くによってみるとそれぞれ何ごとかつぶやいているようにも思える。
本たちのその微かな声を聞き逃さずにいれば、書店の本棚に並べられた本は自ずと光って見えるようになるのだと辻山は綴っています。効率や生産性ばかりを重視する働き方に疑問を感じている、という方にはぜひ手にとっていただきたい1冊です。
おわりに
高村志保は『絵本のなかへ帰る』のなかで、自分が店主を務める今井書店では、長年にわたって『こどものとも』を保育園に届ける活動をおこなっていると語っています。その理由を、高村はこう綴ります。
今のロングセラーと呼ばれる絵本をつくったのは絵本作家でも、出版社でもない。それをつくったのは保育園の保育士さんたちであり、絵本を買い、手元に置いてきた人たちだ。これからのロングセラーを作るのも、彼ら読者たちだ。
そのために私は重たい月刊誌の束を保育園へ運ぶ。決して楽な仕事ではない。でも、一冊の絵本がきっかけになる。読まなければ何も始まらない。どうか、読んでください、と祈る。
これは、絵本に限らず、大切な本を読者に届けようと日々奮闘しているすべての書店員に共通する思いのように感じられます。
今回ご紹介した5冊のエッセイはどれも、そんな書店員たちの矜持を体感することのできる本ばかりです。気になる本に出会うためのヒントとしてはもちろん、1冊の本が私たちの手元に届くまでの背景を知るためにも、ぜひこれらのエッセイを読んでみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/12/01)

