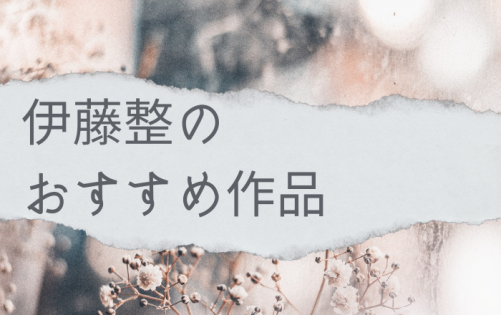【『若い詩人の肖像』など】小説家・詩人 伊藤整のおすすめ作品
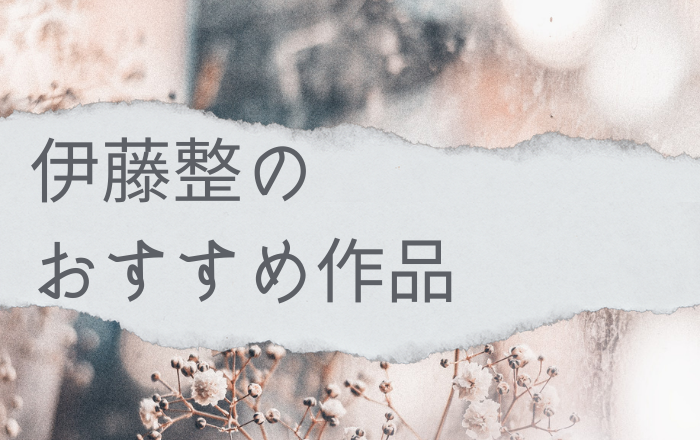
新心理主義を代表する小説家として知られる伊藤整。自伝的小説『若い詩人の肖像』やチャタレイ事件について綴ったノンフィクション作品『裁判』など、伊藤のおすすめ作品を3作品ご紹介します。
抒情派の詩人として出発し、のちに小説家・文芸評論家としても多くのベストセラー作品を生んだ作家・伊藤整。小説家としては「意識の流れ」(※流動していく人の意識の流れを文章表現に組み込む技法)を多用し、1930年代には横光利一らと並んで新心理主義を代表する小説家とも言われました。
今回は、自伝的小説『若い詩人の肖像』や“チャタレイ事件”を克明に描いた『裁判』など、初めて伊藤整を読む方におすすめの作品を3作品紹介します。
『若い詩人の肖像』
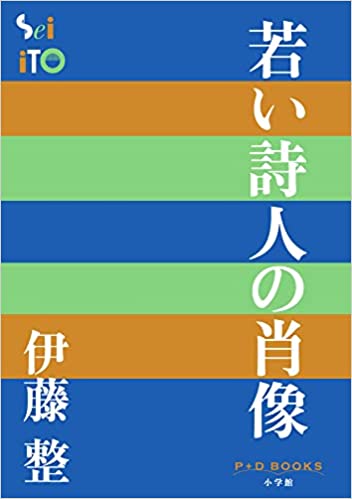
出典:https://www.shogakukan.co.jp/digital/093524290000d0000000
『若い詩人の肖像』は、伊藤整が1956年に発表した、青年期の伊藤自身について綴った自伝的小説です。1950年代に発表した複数の短編小説を、のちに長編小説としてまとめました。
作中で描かれるのは、伊藤が故郷の小樽で過ごした学生時代から、文学への関心を抱き始め、詩人として名を成そうと上京を決意する20代までの物語です。伊藤は内向的な若者でしたが、高等商業学校(現在の商科大学)時代からすでに、趣味の詩作にふけっていました。
私は自分を、大人のふりをしている子供、または普通人の言動をする能力のないニセ者と感じていた。私がそれ等の普通人の型に入って行けなかった理由は、私の言葉には自分の育った漁村の東北訛りが混っていて、全国から集まった級友たちの使う「内地」の言葉に較べて躇いを感ずるせいらしかった。しかしそれだけではなく、私は十五六歳から近代日本の象徴詩や自由詩やヨーロッパ系の訳詩を読み、自分でも詩を書き、詩の表現を自分の心の本当の表現だと信じていたからであった。詩の表現以外の言語表現を、私は真実のものと見ていなかった。
“詩の表現以外の言語表現を、私は真実のものと見ていなかった”と言い切る伊藤。彼は商業学校卒業後、一度は地元の中学校の英語教師として就職しますが、形だけの仕事のやり方に空虚さを感じ、詩作を職業にしたいと一念発起します。仕事を辞め、上京するに際してはさまざまな障壁が伊藤を阻みますが、詩人として生活したいという彼の決意は固いのでした。
詩の中の感情や、詩の中の判断を日常生活の中に露出すれば、人を傷つけ、自分も傷ついて、この世は住み難くなることを、私は本能的に知っていた。私は詩を読み、詩を書くことにだけ結びついている自分の心の本当の働きを、人目に曝すのを恐れた。
無意味な形式や礼儀を守って、面白くもない話に耳を傾けているという生命の空費の時間が、私をやりきれない気持にさせた。そして、こんな人生には生きる意味が何かあるだろうか……こんな無意味な厭わしいものの連続が、四十年も五十年も続くとしたら、そんな生活の中で生きつづけることは愚劣なことではないのか?
本作は、文学者を志すに至る伊藤自身の経験を率直に綴ったものですが、こういった自分の好きなことに人生を費やすべきかという葛藤や、社会生活のなかの無意味なしきたりに対する憤りは、多くの10代、20代にとって強く共感できる感情のはずです。若い時代ならではの焦燥感や緊張感が追体験できるような一作です。
『氾濫』
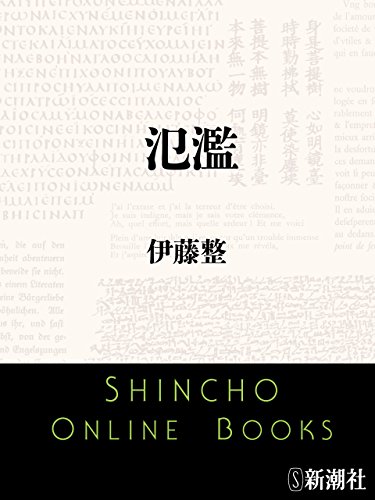
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B01GJGMKCO/
『氾濫』は、1958年の作品。元研究者で実業家の真田佐平と計算高い大学教授の久我象吉を中心に、さまざまな人物たちの人間模様を描いた長編小説です。
50歳を手前にして、高分子学の研究者として国内外で有名になり、高い社会的地位を得るようになった真田。彼の人生は一見、順風満帆そのものでしたが、実際には派閥争いやあらゆるしがらみに縛られ、窮屈な日々を送っていました。
真田は、同じく高分子学の研究者でありながらも、大学教授としてアカデミアでの地位を確立している高校時代の同級生・久我を内心羨み、妬んでいました。一介の研究者から叩き上げで実業家としての地位を手に入れた真田と違い、久我は真田に言わせれば、“人工培養された秀才の一族”の出身だったからです。
避暑地、音楽会、猟、ゴルフというような生活の伴奏をその身辺に持ち、学者として理想的な経歴を踏んで、出世して行く久我象吉を、真田佐平は、町工場がやっと株式会社になったような、三立合板の子会社なる三立化学株式会社の技師として見ていた。
一方の久我は、長年続けた贅沢三昧によって、借金で生活が破綻しかかっていました。
久我は戦前には、相当大きな資産を持っていた。時々久我は真田を連れ出し、いかにも楽な気持で、気に入った酒場を二三軒飲みまわった。そういうとき、久我がどの店でも大事にされていることに真田は気がついていた。だが戦後になって、彼の持っていた植民地の独占企業の株は無価値になり、田舎の土地は小作人の手に入り、別荘は税金として物納された。戦後に値の出た株も多少は持っていたが、久我は今では豊かな人間ではなかった。久我の女遊びはまだ続いていた。そのための金や、父の代に建てた大きな邸に住んでいたので、それを維持するために、彼は著述や雑文書きに力を注いでいた。
久我は、大学院でのポストを真田に譲ることを引き換えに、自分の恩師の研究を真田に買ってもらい、その仲介料として金を得ようと企みます。
真田と久我、そして彼らの妻や娘といったさまざまな人物の思惑と深層心理を赤裸々に描き、エゴイズムの醜さをありありと見せつける本作。華やかな世界の裏に潜む人々の本音は、読んでいて思わず絶句してしまうほど底意地の悪いものばかりです。しかし、それこそが人間の心理の本質的な部分なのかもしれない、と思わされてしまいます。
『裁判』
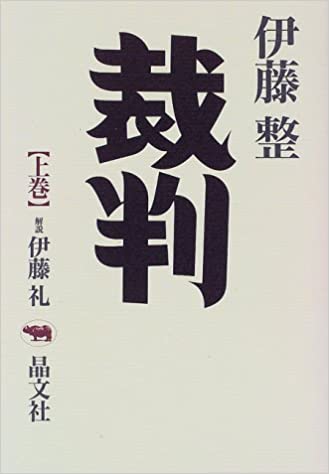
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4794963068/
現代においては、伊藤の名前を聞いたとき、歴史の授業で習った「チャタレイ事件(チャタレイ裁判)」を最初に想起する人も少なくないかもしれません。『裁判』は、このチャタレイ裁判をめぐる記録を書き記したノンフィクション作品です。
チャタレイ事件とは、1928年にイギリスの小説家D・H・ローレンスが発表した小説『チャタレイ夫人の恋人』が“わいせつ文書”とみなされ、日本語訳を担当した伊藤と、版元である出版社の社長・小山久二郎に対しわいせつ物頒布罪が問われた事件。『チャタレイ夫人の恋人』は、貴族階級の女性と労働者階級出身の男性の禁断の恋愛を描いた作品ですが、性描写が多く、一度はイギリスでもわいせつ文書として告訴される憂き目にあっています(小説家のフォースターなどが出廷した結果、判決は無罪)。
日本では、政府とGHQによる検閲がおこなわれていた1950年に発表され、すぐに摘発を受けます。本書をめぐる裁判は翌年から始まって、数年間にわたり、なんと計36回もの公判を重ねました。伊藤と小山は1957年に有罪判決を受け、それぞれ罰金10万円と25万円を支払っています。
裁判の主な争点となったのは、わいせつ文書に関する規制が憲法の保障する「表現の自由」に反しないか、という点と、版元のみならず翻訳者を罪に問う正当性はあるのか、という点です。実際の判決では、
性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当である
という理由で上告が棄却されました。
『裁判』では、伊藤自身の反抗はもちろん、福田恒存や吉田健一、波多野完治といった高名な専門家たちが弁護人として法廷に立ち、表現の自由を勝ち取るために戦い抜いた様子が克明に記されています。本書で描かれる裁判の様子は、表現が“性的”“わいせつ”という名のもとに過度に規制されていく現代の事情にも通ずるものがあり、非常に読み応えのある作品です。
おわりに
チャタレイ事件への関心の高まりや婦人誌への軽妙な寄稿エッセイなどの影響で、1950年代には、伊藤整の作品は一大ブームを起こしました。しかし、現代では昭和文芸を代表する他の作家と比べ、伊藤の本は手に取られる機会が少ないように思えます。
伊藤整の作品の魅力は、人間の醜さや恥ずかしさ、青臭さを大胆に、それでいて理知的に描く点にあります。作品は非常に読みやすいながらも、人間心理の深みを切り取ったものばかりです。これまで文学史を通してしか伊藤の名前を聞いたことがなかったという方も、ぜひ、その作品に手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/12/28)