浅倉秋成さん『家族解散まで千キロメートル』*PickUPインタビュー*

テーマへの思いと仕掛けを緻密に組み合わせる
解散予定の家族に降りかかるトラブル
古くなった実家を取り壊してばらばらに転居し、〝解散〟することが決まった一家に降りかかった大災難。予測もつかない展開で現代の家族観を提示してくるのが、浅倉秋成さんの新作『家族解散まで千キロメートル』だ。
「『教室が、一人になるまで』で高校生を書き、『六人の噓つきな大学生』で大学生や社会人を書いた後、編集者から〝次は家族ですかね〟みたいな提案を投げていただいたのが始まりでした。それと、自分のこれまでの小説を振り返ってみた時にやはり今回もどんでん返しを入れておかないと読者のニーズと合致しないのかな、というところから設定を考えていきました」
山梨県で暮らす喜佐家では末っ子・周が結婚のために家を出ることとなり、両親二人で老朽化した家を管理するのは無理だろうと、実家の取り壊しが決定する。もうすぐ家族がばらばらになるというその年の元日、父以外の面々が集まり家の片づけをしていると、倉庫から見覚えのない仏像が出てきた。それがいま世間を騒がせている、青森の神社から盗まれたご神体そっくりだと気づいた家族たちは、即座に父の仕業だと確信。というのも不在がちな父は、家族にとって奇行の多いやっかいな存在で、過去にもあることをやらかしているのだ。といって身内から犯罪者を出すわけにはいかない。ニュースで神社の宮司が日を跨ぐ前に返却すれば被害届を取りさげると発言するのを聞いた彼らは、青森まで仏像を返しに行こうと決意する。
物語は、車を調達して青森へ向かう母・薫、長男の惣太郎、周、長女あすなの婚約者・賢人の様子を周の視点で追う「くるま」パートと、家に残って父の行方の手がかりを探すあすなと惣太郎の妻・珠利の様子をあすなの視点から追う「いえ」パートで構成されていく。
道なき道を選んだ家族小説
あらすじだけ読めば、ばらばらになりかけた家族がトラブルを乗り越えるために一致団結していく話だと思わせるが──。
「我々は物語の枠組みを見た瞬間、ある程度オチを予想するじゃないですか。それは必ずしも悪しきことではなく、マーベルの映画だって最後には主人公が勝つんだろうなと思いながらも楽しく観ますよね。今回はそんなふうに分かりやすいゴールを頭に描いてもらって読んだほうが面白くなるだろう、という感覚がありました」

だが本作の執筆前から、「家族小説を書く予定ですけれど、心温まる話にはならないと思う」と語っていた浅倉さん。
「いま家族の話を書くとなると、ほっこりする話か、毒親に育てられたようなドロドロの話か、両極端な話になりがちな気がしたんです。だったらどちらかに寄せることはせず、別の道なき道を進もうと思いました。いろんな設定やどんでん返し的な展開を考えているうちに、仕掛けと作品の中で書きたいことを合致させるならこれだな、というものを思いついて。その仕掛けと、車で長距離移動することと、パートをふたつに分けることを決めてから、家族構成などを詰めていきました」
なぜ長距離移動が先に決まったのか。
「移動があったほうが面白そうだなと思って(笑)。それに、自分から一緒にいたいと望んだわけでもない人と同じ箱に入れられて、〝行きたくない〟とか〝行くしかない〟とか、やんや言いあいながら長距離移動することって、家族のメタファーになるなと思いました」
「くるま」パートで周たちは謎の車に追跡され、「いえ」パートではあすなたちが重要な手がかりを発見。謎が謎を呼ぶ展開のなか、読者はところどころ、なにかしら違和感を抱くかもしれない。
「真相に気づかれそうな攻めた一言を入れるか入れないか、相当迷いながら書きました。『六人の噓つきな大学生』の時も再校の段階で、〝この一言は攻め過ぎた気がするから抜きたい〟と言ったら編集者に〝いや、ばれないですよ〟と言われてそのままにした箇所があって。今のところその箇所で真相に気づいたという感想は見当たらないんですが、自分では気づかれるか気づかれないか全然判断つかなくて、今回も不安で仕方ないです(苦笑)」
終盤、伏線が一気に回収され、作品の中で描かれているものが鮮明に浮かび上がる瞬間がある。その時、読者はこれがどういう物語であるのか、しっかりと受け止めるはずだ。
家族の影響を受けた人格形成を考えた
家族構成についてはどのように考えたのか。一人一人の来し方も掘り下げられ、人格形成が丁寧になされているのが印象的だ。
「それぞれが今の性格に至った原因の七割から八割は家族の影響だ、という造形を考えました。多様な価値観を書きたかったので、同じ家で過ごしてきたけれど、みんな違う方向を向いている状態にしました。そうはいっても家族というクローズドな環境で生活してきただけに、共通して持っている部分もある。そういう人たちだけでトラブルを解決するのは難しく、打破してくれる外部の人が必要だということで兄の配偶者や姉の婚約者を配置しました」
長男の惣太郎は「金持ちになる」と宣言して家を出た人間。今は会社経営者として羽振りのよい暮らしをしている様子で、妻の珠利は元地下アイドルだ。
「たとえば小さい頃に家でゲームを禁止されてきた子供って、本当にゲームをやらなくなる子と、逆にゲームの虜になる子がいると思うんです。家族ってそうした反復の中で紡がれていく気がします。貧乏な家に育った影響で大人になって金遣いが荒くなる人がいたり、金遣いの荒い親を見て質素に暮らしたいと思うようになった人がいたり。惣太郎の場合、育った家がお金がなさすぎて、お金が欲しくなりすぎちゃった人ですね。傲慢だし言うことは下品ですけれど、書き終えた今となっては愛おしいです」
長女のあすなは美術会社に勤務し、こだわりが強く自分の主張を譲らないタイプ。家族の中でも個性的だとみなされている模様。
「家族から見たら変わった人なんですけれど、彼女の中では筋が通っているんですよね。はみだし者っぽい人なので、家族は彼女が怒りださないように気を遣っておこう、という面がある。そういう人がこの家族にどういう不満を抱いてどういうひね方をするかを考えました。で、末っ子の周はそういう上二人を見て育ったから、自分はちゃんとやらなきゃと思っている」
そんな周の婚約者・咲穂は、警察官だ。それもあって身内の不祥事はなんとしてでも秘密裡に解決したい、という立場である。
「解散しようとする家族がいるなら、新たに家族を立ち上げようとする人も出したほうがバランスがいいと思いました。でないと、家族解散推奨小説になってしまいますから(笑)。ただ、周もなぜ自分が家族を立ち上げようとしているのか、深い考えはないんですよね。彼は今二十九歳ですが、なんとなく、三十手前で結婚するものだと思っているふしがある」

この騒動を通して、周は自分の家族観をどう見直していくのか。一方、母親の薫は、家族に対する責任感が非常に強い。実は、そんな彼女が生まれ育った家庭環境は良好だったとは言いづらい。
「良き母とされるもののロールプレイをしている人ですね。家族はこうじゃなきゃいけない、という価値観に一番とらわれているかもしれません。お母さんのお母さん、つまり周にとっての祖母はいわゆる毒親です。家族小説を書くとなった時に毒親を出すアイデアはあったんですけれど、そうすると、いろんな問題が毒親のせいになってしまう。なので毒親を出すにしても、親が毒親に育てられました、くらいの距離感にしておきました。自分が育った家にお金がなかったからお金にこだわるようになった惣太郎のように、このお母さんは、自分が家族ばらばらの中で育ったから、結束した家族を作りたがっている」
では、ある出来事を機に、家に寄り付かなくなった父親の義紀はどうか。
「彼のような人のリアリティを考えていくと、たぶん良くも悪くもあまり会話ができない人だろうなと思いました。寡黙で主体性がなくて流されがちで、それで駄目な人扱いされているけれど、彼にも考えていることはあるはずなんです。ただアウトプットが苦手すぎるだけ。このお父さんほど過剰でないにしても、深く考えているのに自分の深さを他者に説明できない人って多い気がします」
読者にお土産を持って帰ってもらいたい
作中、登場人物たちが Mr.Children のアルバム『Q』を聴く場面が数回登場する。
「これはシンプルな理由で、自分自身がずっと聴いていたんです。いつもお話を考える段階で、これから書く小説っぽい曲を集めてセットリストを作るんですが、今回は圧倒的にミスチルが多くて。特に『Q』は〈ロードムービー〉や〈その向こうへ行こう〉という曲があり、歌詞を見ても今回の話と親和性が高いので、これはもうこの家族にも聴かせようと思いました。アルバムの最初の曲が〈CENTER OF UNIVERSE〉で、最後の曲が〈安らげる場所〉なんですよね。それを宇宙の中心から安らげる場所に行くという解釈にして、作中にも書きました」
少しずつ、家族に関する従来の常識や、それに対するまた違った考え方が見えてくる。たとえば義紀と薫が結婚した頃は三十歳手前で結婚して家庭を作るものだ、という考えが強かったが……。
「今はもう、別に結婚しなくてもいいでしょう、と言われるご時世だといわれていますよね。明らかに独身者に対する風当たりが弱まったし。でも今回最後のほうで、ある人物に少々時代錯誤なことを言わせたんですが 、あれは僕の友達が実際に言った台詞なんです。それを聞いた瞬間、僕、戦慄したんですよ。そんなことを言う奴だったのか、っていう。仲いい友達が野良猫を蹴飛ばすのを見た、みたいな、胃袋が浮くような感覚でした。時代は変わってみんな考え方がリベラルになったといわれているけれど、本当に社会はそこまで賢くなれたのか、などと考えるきっかけを作ってくれた一言でした。だからこれは、彼が書かせてくれた小説です(笑)」
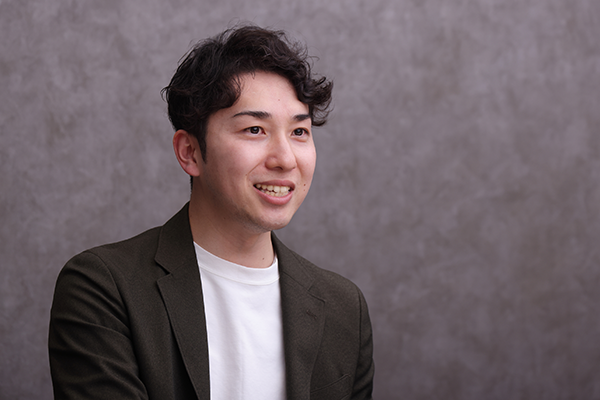
『六人の噓つきな大学生』や『俺ではない炎上』も、人々の固定観念や同調圧力、他者への無配慮などを鋭く突いてくる内容であったが、そうして小説内で現代社会の問題点を掬い上げるのは、強く意識していることなのか。
「別に〝家族というものに関して言いたいことがあるのでこの小説を書きました〟ってことではないんですよ。家族というテーマを渡されて、僕なりに書くとこうなる、という感じです。礼賛するでもなく非難するでもなく、〝なんか変だよね〟ってところを書きたくなる。それに、たとえば友達を大切にしようとか、親孝行しようといった、これまで何度も言われてきたことをもう一回小説に書くのは……という思いがあります。読んでくれた人に、少なくとも一個くらいは、〝言われてみれば考えたことなかったな〟というお土産を持って帰ってもらいたい。そのバランスを考えながら書いた結果、こんな話になりました」
エンタメとしてがっつり楽しめるだけでなく、自分の固定観念を今一度見直す視座を与えてくれる本作。間違いなく満足度の高い一作なのだが、ご本人はなんだかとても不安そう。
「いつも本が刊行される直前って〝ゴミみたいなものを書いてしまった……〟と思って、お腹が痛くなるんです。でもこのネガティブな性格が、ちょっとでも作品を良くしなければという使命感に繫がっているので。〝どう? 僕の書いたもの面白いでしょ?〟と言い始めたら終わりだと思っています(笑)」
浅倉秋成(あさくら・あきなり)
1989年生まれ。2012年に『ノワール・レヴナント』で第13回講談社BOX新人賞Powersを受賞しデビュー。『教室が、ひとりになるまで』『六人の噓つきな大学生』『俺ではない炎上』『フラッガーの方程式』『失恋の準備をお願いします』『九度目の十八歳を迎えた君と』など、著書多数。「ジャンプSQ.」にて連載の『ショーハショーテン!』(漫画:小畑健)の原作も担当。







