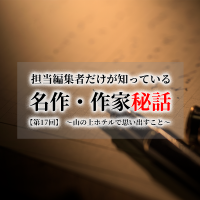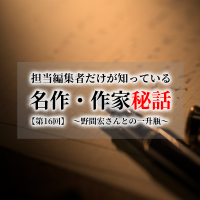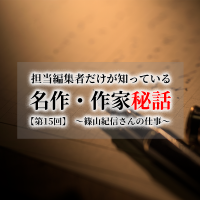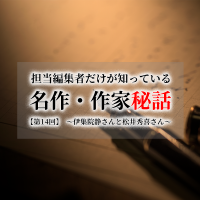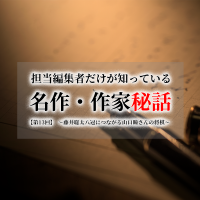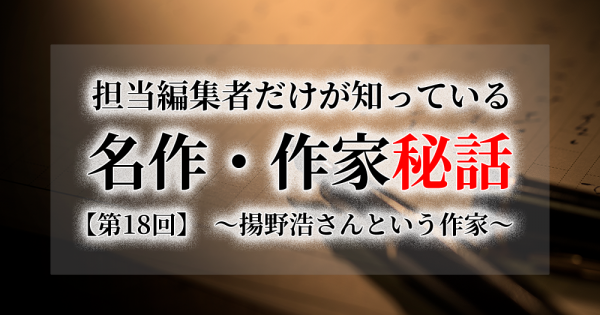連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第18話 揚野浩さんという作家
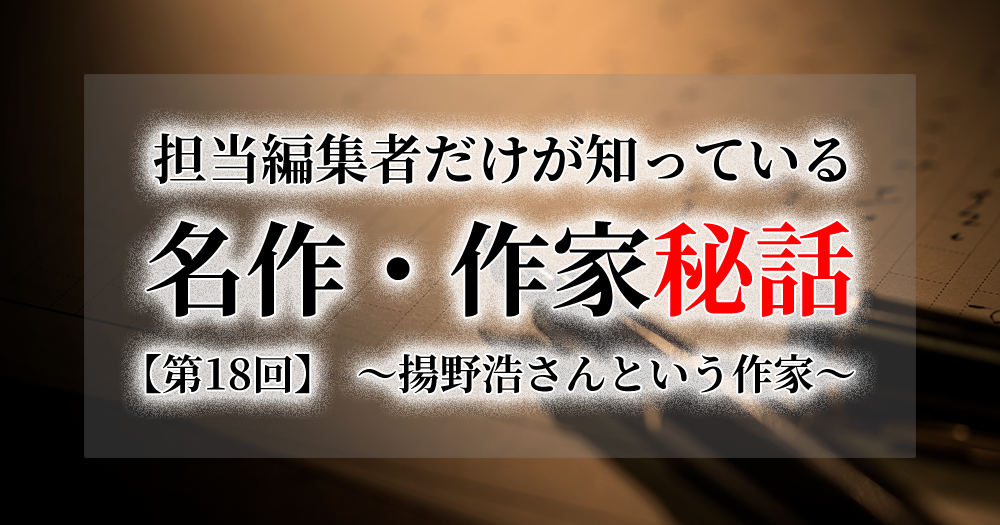
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第18回目です。「破天荒な作家」といえば、誰を思い浮かべるでしょうか。今回紹介する「揚野浩」さんは、遺した作品数は少ないながらも、芯の通ったテーマを掘り下げることに関しては唯一無二。担当編集も驚かされるようなエピソードが満載の作家です。当時を振り返ってみましょう。
揚野浩さんは、私が知る限り、2冊の短篇集と、その短篇集に未収録の3作の短篇、それに見開き2ページのエッセイ1作を遺して亡くなった作家である。
2冊の短篇集は、1973年に講談社から刊行された『プロレタリア情話』と、翌74年に光風社書店から刊行された『プロレタリア哀愁劇場』であるが、それぞれ5篇と6篇の短篇小説が収録されている。つまり、揚野さんは14作の短篇小説とエッセイ一作を遺して亡くなった作家だが、私にとって忘れ難い作家のひとりである。

揚野さんがはじめて小説を発表したのは、1967年に発行された文芸雑誌「新日本文学」の10月号で、「人生漫画」という短篇小説である。「新日本文学」は、先の(記事へのリンクつける)「野間宏さんと一升瓶」の中でも触れたが、戦後すぐに結成された「新日本文学会」の機関誌として、1945年12月に創刊された文芸雑誌である。
私は、この雑誌はどちらかと言えば日本の左翼運動に携わる作家たちの活躍の場となっていたと思っていたが、こうした雑誌のご多分に漏れず、経営的にはよい時代もあったようだが、苦しい時期が続いたらしい。そして、やはり経済的に発行を続けることが難しくなり、2004年に終刊となったと聞く。
「新日本文学」は、宮本百合子『播州平野』、金達寿 『玄界灘』、開高健『パニック』、大西巨人『神聖喜劇』などの問題作を掲載した。また、設立した新人賞で、永山則夫や見沢知廉など、獄中からの受賞者を出したことでも知られている。
大手出版社の文芸編集者だった私には、「新日本文学」は少し煙たい存在であったが、しかし、どこか畏敬の念を持って眺めてもいた。
一方で、「新日本文学」は、1963年5月号に、当時北九州市にあった八幡製鉄所の職員だった佐木隆三さんの「ジャンケンポン協定」を掲載するなど、労働者や農民出身の作家たちを育てることに貢献した。その労働者文学を書くひとりとして、揚野浩さんの名前も挙げられている。
Amebaでブログを開設している中浦ジュンさんは、現代思想と演劇を愛する事務系サラリーマンと自分を紹介しているが、そのブログの中で、「1970年代にプロレタリア文学の傑作が書かれていた──揚野浩『プロレタリア哀愁劇場』」と題して、この短篇集を紹介している。
こうした評価を受ける揚野さんだが、揚野さんの小説の問題性と面白さは、これに収録されている「F4ファントムジェット機を降ろせ」という短篇小説を例にとるとよく分かる。
実際、1968年6月に、アメリカ空軍のF4ファントムジェット機が、九州大学の建物に墜落したという事件があった。その後、米軍、日本政府、大学当局、学生などがすくみ合い、ジェット機は校内の建物に吊り下げられた状態のまま、その残骸をさらしていた。そして、翌年の1月5日の深夜、何者かによってそれが引き降ろされるという事件が起きたのである。この短篇小説は、この事件に材を取って生まれた小説で、1970年3月号の「新日本文学」に掲載された。
この小説に登場する人物のその後を、揚野さんは、
「石山栄造氏は息子の結婚式の祝い酒を飲み過ぎて座敷中に血を吐き、救急車で運ばれて行った承天寺裏の胃腸病院で息を引き取った。/家出娘の冴子は東中洲人形小路にあるバアで、つい近頃までは働いていたのだが、このあいだ様子を見に行ってみると、/『それがねえ、髪の長い男の子と店を出て行ったきり帰ってこないの、いい娘だったけどねえ。あんた、だれか替わりの女の子はいない?』という無責任なママの言葉である。(略)
主役陣のうち二人は三途の川を渡ってしまい、残りの脇役陣は舞台衣装のまま行方をくらませて」
と、言っているが、これらの登場人物の有り様を見て、「F4ファントムジェット機を降ろせ」がどんなに破天荒な物語なのか想像がつくだろうと思う。
結局、引き降ろされた残骸は、10月14日、4000人の学生が見守る中、アメリカ軍の手によって、当時のアメリカ軍板付基地に搬送された。今も、日本では、墜落したオスプレイ機など、秘密保持のため、さっさとアメリカ軍の手によって接収されるが、日米の関係は、45年前と何ら変わっていないことをこの小説は如実に語っているのである。
揚野浩さんは、処女作品集になる「プロレタリア情話」のあとがきで、こんなことを書いている。
ぼくは少年時代から、ゆくゆくは考古学者か小説家になりたいと思っていた。この道はなんせ好きなんだし、好きこそ物の上手なれというでしょう。しかし、肉親の情愛に薄く生活に追われて、その日、その日を生きんがため浮世の底辺を転々と渡り歩いて来た。
あねさ被りをしてダンプにも乗ったし、日雇い人夫もやったし、「プロレタリア八十八夜」の中で語っている通り消防署員もやった。どの職業も面白かった。
人間が二人でもいい、集まって働く現場というのは面白くって、この面白さをほかの現場で働いているお方に伝えたい。
ぼくの心の中に、何かこう少年時代からの夢でもあった「物語作家」としての本能が目ざめてさ、せっせとワラ半紙の上に文章を書きはじめた。この時の年齢は満で二十七歳の時だったと思う。
九州の孤独な山猿がワラ半紙の上に文章を書きはじめたのを、まるで望遠鏡で見てでもいたのか、東京から野坂昭如氏、「小説現代」の編集長であった大村彦次郎氏が来て、原稿用紙の書き方だとか、激励を受けて、まあまあ、生活の方は一パイ機嫌でなんとかやっているうち、結局はこの短篇集になった。
世にも不思議な感じがする。アハハハ。
「肉親の情愛に薄く生活に追われ」とあるのは、揚野さんは鹿児島の出身で、生まれて間もなく、日本三大台風のひとつに数えられる枕崎台風に遭遇して両親を亡くし、それから苦労の連続だったと、私に語ったことがある。
小説には、大型トラックの運転手、消防署員、バーテンダー、選挙運動の車の運転手などを経験したと書かれているが、「プロレタリア競艇哀話」では、競艇の選手を目指したことがあるが、養成所へ支払う四万五千円がなくて断念したと書かれている。いつだったか、その通りのことを話してくれたことがある。
野坂昭如さんと大村彦次郎編集長が、はるばる九州に足を運んだのは、「ゲリラの棲む岸壁」か「F4ファントムジェット機を降ろせ」を読んで興味を持って、「小説現代」に作品を書くように勧めるためだろうと思う。
野坂さんを担当していたためだろう、揚野さんの担当は私になった。
揚野さんの小説は、ユーモアとペーソスに溢れ、港湾労働者の世界を活写したものだ。小説の書き方など勉強したことがない揚野さんは、子どもの頃から本を読むことが好きだったし、そこから自然に吸収したのだろう、描写は的確だった。「プロレタリア競艇哀話」の競艇のシーンや、材木をクレーンで吊るすシーンや、重量オーバーに積んだダンプのタイヤの軋み、居酒屋の焼酎の匂いなど、物の見事に描かれている。たぶん、労務者の時代に、宿舎に転がっていた本などは片端から読んでいたはずだ。達筆に崩した大振りな字で書かれた画数の多い漢字は、時々、旁と偏が左右入れ違いになっていることがあったが、これなど、漢字を形で覚えたせいで、旁と偏を左右逆に覚えていたのだろう。
そんな才能豊かな揚野さんが、「小説現代」に原稿を書くやり方はユニークだった。
締め切りが近くなると、東京駅から編集部に電話がかかってくる。揚野さんが博多から乗った夜行列車が東京駅に着いたのだ。ほとんど金を持っていない揚野さんは、上京するのに新幹線などを使うことはなく、夜行を使った。東京駅に到着した時には、もう電話代くらいしか持ち合わせはなかったはずだ。この電話があると、私はタクシー代を用意して会社の前で待っている。着いたタクシーの支払いをして、揚野さんを、そのころ本社の裏にあった別館に案内する。別館には畳敷きの部屋があって、揚野さんはそこにカンヅメになって、原稿を書き上げるのだ。
この畳敷きの部屋は、よく作家のカンヅメに使われた。小島信夫さんがここに籠って、『抱擁家族』を書き上げたと聞かされたときはなんだか感激した。そう言えば、地下にあった社内食堂で、お盆に定食を乗せている小島さんを見かけたことがあった。
揚野さんは、魔法瓶にお茶の用意をしてある部屋に入ると、ごく普通の原稿用紙と、鉛筆を何本かと消しゴムをザラザラと出して座卓の上に置き、すぐに書きはじめる。三度の食事は、小島さんと同じように社内食堂で、勝手に済ませてくれた。
翌朝、私は早目に出社して、揚野さんがカンヅメになっている部屋をノックする。揚野さんは一晩かかって書いた分、5枚から10枚くらいを渡してくれる。私はそれに目を通す。
たとえば、「プロレタリア哀愁劇場」は、
私が晴れ姿、三日月印の地下足袋をはいて博多港の岸壁の上を
どたどたと歩いてゆくと。
──暴力手配師──
の栗原清右衛門の「寺西君ヨオオオイ」とこういうのだ。
とはじまっていた。このどたどたはご丁寧にも、原稿用紙のマス目に足跡の形が三つ並んで描かれていた。私は咄嗟に、これはこのまま活かしておきたいと思う。当時は版下屋さんに足跡を三つ描いてもらい、それを製版所に持ち込んで、縮尺したものを銅版に焼き付けて版にした。面倒な手間になるが、この変な感じを活かしたいと思ったのだ。
「これ面白いから、このまま活かしましょう」
「よろしく」
「では、この調子でお願いします」
こんなやりとりの後、揚野さんは、またひと晩、またひと晩と部屋にこもって書き続けていく。私は、翌朝、部屋に行って、できた分を読んで感想を言い、これから書く分のアドバイスをしたりして、1週間から10日かかって、70枚から100枚くらいの短篇小説が出来上がるのである。
「プロレタリア日銭酒情話」では、村岡慧という寡黙な墓石専門の石工の物語だが、村岡には四歳になる、いかにも可愛らしい舞里という娘がいる。話の成り行き上、この舞里に死んでもらわなくてはいけなくなった。
ある朝、私は言った。
「どうしても舞里ちゃんには死んでもらわなくては」
「イヤだなあ。どうしても殺すの?」
「そうですよ。それで、村岡が舞里ちゃんの石像を刻むところで終わりにしましょう」
揚野さんはとても哀しそうな顔して、空白の原稿用紙を見つめていた。
そして、明くる朝、私が部屋を覗くと、原稿はできていた。
村岡舞里は倉庫の壁と石材のあいだの僅かな隙間にスラム街の男の子と一緒に死んでいた。そばには大きすぎる哀れな靴と砕け散った長崎ちゃんぽんのガラスの破片が保税倉庫の軒下を照らす青い灯りに浮かびあがっていた。
と、描かれていた。そして、小説は次のように終わっていた。
彼がまた白い作業服を着て彫っている石の表面には、髪を支那人形風に編んだ女の子の顔が首から下を残して浮き上がっていた。/村岡慧が魂のない石にハンマーを揮っている。/トオーン、カーン、トオーン、カアーン。
こうして小説が出来上がると、私は前もって経理に申請しておいた原稿料を、現金で揚野さんに渡すのだった。これで、博多への夜行の運賃や博多での生活費が稼げたわけだ。こんな風にして原稿を書き上げる小説家は、私の長い編集者生活でも揚野さんしか知らない。特異な無頼派作家だったと言えよう。
このあと、しばらく東京で遊ぶことになるが、先輩作家の野坂昭如さんは、ことのほか揚野さんを可愛がって、書き上がるのを待ちかねたように夜の街に誘い出した。
野坂昭如さんは1972年からラグビーに凝り出して、「アドリブ倶楽部」というチームを結成した。翌1973年、信濃森上で初めての夏合宿をやった。その合宿の練習風景と集合写真に、揚野さんのジャージー姿の勇姿が映っている。この合宿にも、揚野さんは野坂さんに頼まれて往復のマイクロ・バスの運転手を引き受け、ついでに練習にも引っ張り出されたのだ。
この夏だったと記憶しているが、野坂さんの一家は避暑で家を留守にすることになった。その留守番を買って出たのも揚野さんだった。1週間くらい、揚野さんは野坂さんのお宅で独りで暮らしていた。野坂さんが独りで家に立ち寄ると、庭に白い鶏の羽根が散らばっていた。揚野さんに訳を糺すと、
「美味そうに肥えたトリに見えたけん、シメて食いました」
という返事が返ってきて、野坂さんを驚かせた。その鶏は、野坂さんの長女がペットとして可愛がって飼っていた白色レグホンだったのだ。
言葉も無くした野坂さんは、とにかく、庭に散乱する羽根だけは片すように頼んで、なんとかお嬢さんの手前を取り繕ったようだった。
しばらくしてから、野坂さんが私に、
「あれはぼくがいけなかった。鶏は食べるもので、太った鶏を見て美味そうだとシメた揚野は正しいんだ。いつの間にか、ぼくも軟弱になっていたんだなあ」
と言った。
私は戦後間もない子供の頃、父親が鶏をシメて、集まった人たちみんなが相好を崩していたことを思い出して、野坂さんに告げた。
破天荒な揚野さんの生き方は、数少ない著作の中に込められていると思う。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。