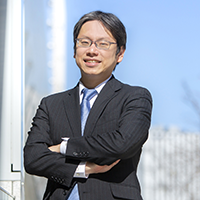源流の人 第46回 ◇ 宮入圭太(型染作家、染色家)

令和の民藝の旗手が染める「無作為の美」の先にあるもの
そぼ降る雨の日。東京・小石川植物園の鬱蒼とした深緑を眺めつつ、汗をふきながら築40年のビルにある宮入圭太の工房を訪ねた。「これだけは必ず伝えよう」と考えていたのであろう、工房に迎え入れられるや否や、彼は、いま思っていることを朴訥とした口調で語り始めた。

「自分が描いた絵を、『自然に還す』『浄化させる』っていうのが、私の型染の目的だと気づきました。自分の絵は、作品の自我がものすごく強い。その絵が、自分から離れていく工程は、多ければ多いほど良いと思います。だから、型紙を繰り返し使ったり、水に何回もつけたり、刃物で彫ったりしていく。そのたびに、自分のものから離れていく。自然に還っていく」
それまでは、自分の描いたものを「描いたまま」表現できることが正しいと彼は考えていた。それを実現できるほど、彼は子どもの時から手先も器用だった。でも、それは正解ではないとわかってきた。
「作った自分よりも、天然のほうが正しい。意図からどんどん遠ざかってくれないと美しくならない」

型染の工程は7つある。鳥取出身の染色家・岡村吉右衛門(1916~2002)の記した本を、宮入は熟読した。岡村吉右衛門もまた、柳宗悦の思想に心を奪われ、同じく民藝運動の共鳴者で型染の大家・芹沢銈介(1895~1984)のもとで研鑽を積んだ人物だ。宮入は工程の説明を続ける。
「絵を描いて、型紙を切り取って、網を張る。『紗張り』っていうんですけど、紗を張って、布の上に型紙を置き、糊を塗って、にじみ止めをひいて色を染めて、水の中につけて浮かび上がらせる」

糊を塗ると、塗った部分には着色せず、水の中につけた時点で糊だけが落ちることになる。宮入は泥絵具を使っている。べったりした発色を気に入っている。
「型染って日本独自のもので、食べ物と直結しているんです。糠、もち米、大豆、海藻。それが型染の基本です。泥絵具は大豆を混ぜると定着する。膠は水に溶けちゃうんですけど、大豆は溶けない」
海藻を布にひくと、にじみ止めになり、染料が均一になってムラが出にくくなる。ところが、そうした工程を重ねるうちに、独特のにじみ、ゆがみが生まれてくる。型紙もそうで、使えば使うほど角が取れていく。宮入の場合、紙は粗目のものを使う。布も、目がきっちりしているものは使わない。型染の道具はどれも高価なので、ほとんど代用品を使っている。「100円ショップで買った品物を使うこともある」。彼は笑って言う。

午前5時から11時半まで作業を続けたら、お昼はお休み。作業の再開は午後6時からだ。午後10時を過ぎた頃には手を止め、1日を終える。作業時間を朝と晩に分けるのは、その間に濡れた紙を乾かすためだ。宮入は語る。
「『無心』になることは難しくても、型染の技法は自ずと布や紙を自然に近づけ、自分の作為も浄化してくれていたことに気づきました。型染の7工程によって、自然の力が加わる時、布や紙は、しぜんと『自然』へ還っていく。だから自然の力に任せる。そういう効果を強めた表現をしたい」
民藝との出合い
幼い頃から宮入は、先祖の墓のある長野で頻繁に目にした、型染の「のれん」に郷愁を感じていた。それが「民藝」という潮流に属したものであると知り、東京・駒場の「日本民藝館」に足を踏み入れたのが、40歳を過ぎてから。そこで宮入が衝撃を受けた型染作品がある。
「柚木沙弥郎さんという型染の先生の布です。いろんな傷とか跡があって。糊が残っていたり、もう、はっきり言って、『きたねえな』って思ったんですよね(笑)。でも、それを見てすごく嬉しくなった。自分には美しく見えた。すごく感動しました」

芹沢銈介の作風のような綺麗で上品なものよりも、何も気にしない、ある人にとっては失敗だと捉えられそうな傷が、美しいと彼には感じられたという。
日本民藝館で柚木が個展を初めて開いたとき、その初日に宮入は自らの作品を持参して駆けつけた。周りの人がいなくなる瞬間を待って、思い切って声をかけ、おそるおそる、自分の作品のポストカードを見せた。
「柚木先生が作品を『すごく面白いね』と言ってくれた。嬉しかった。型染って、食っていけない人が多いんですよ。ハガキ1枚100円とか、そういう世界なんで」
頑張ってやりなさい。そして柚木は、宮入にこう言葉を続けた。
「基本色だけでやりなさい」
「不器用のままでいなさい」
赤、青、黄色、緑、黒などの8色。子どもたちのクレヨンにあるような色たち。それまで宮入は、くすんだトーンや、和を感じる色を好んで使ってきたが、これを機に改めることにした。柚木の個展開催のようすがテレビで報道されると、翌日から大行列に。宮入はこの日も民藝館に出向き、客たちの靴を並べるお手伝いをした。柚木は一躍「ときの人」になった。数々の弟子を育て上げた彼は2024年、その生涯を閉じる。
「無作為の美」のその先へ
民藝運動の祖・柳宗悦が説き続けた、「無作為の美」。作為的でないことを、宮入も、ただひたすら目指してきた。
「でも、やっぱり、いじっている。無作為じゃないんです。完全な無作為というのは無理なこと」
どうしたら、無作為の境地に達することができるのか。宮入は苦悩した。ある日、宮入が尊敬する日本民藝館職員の月森俊文に相談することに。月森はこう答えてくれたという。
「呼吸してみなさい」
宮入は述懐する。
「『呼吸しろ』って言われたって、そう言われたことを意識せずにできないじゃないですか。その問題は持ち帰って、ずっと無意識で呼吸する方法を考えていたら、過呼吸になっちゃったんです」

民藝館に再び出向き、月森に再質問した。
「すみませんけど、過呼吸になっちゃって。答えを教えてほしい」
すると月森はこう答えてくれた。
「それ! そうなったことが、作家、つくる人になったっていうことです」
民藝の作家という存在は、つねに無作為について考えているからこそ苦しくもなる。そこから離れられないほどになる。過呼吸になるほど無意識について考えたなら、それは作家になったということだ。月森はさらにこう付け加えた。
「それぐらいにならなければ駄目」
「無作為」であるということは、人間である以上、わからない。だったら、もっと、自然に還っていく技法を探す道を選ぶほうがいい。「無作為」という言葉が、ともすれば自身を苦しめていたことに気づいた。考えても無理なこと。
「それですごくラクになったし、楽しくなった。一番言いたいのは、原画の絵に関しては、自分の意識で描くものなので、しょうがない。そこから型染にして自然に還し、浄化させる。それが型染の本質。自分がやっている理由です。図案は奇をてらうことはしない。直観に従い、正しく、間違えないように表現できればと思う」
「ズレてて、いい」
作品を見た客からは、直接声をかけられることもよくある。彼は表情を崩してこう語る。
「私は接客を積極的にやるんで、反応は間近で見ています。嬉しいですね。『これでいいんだ』って思える人が多いらしくて」

たとえば、PCを駆使し、ミリ単位の幅やズレを気にしながら絵を描くような仕事をしている人たちが、宮入の作品に出合うと、「これでいいんだ」と感動するという。それは宮入の印象にも強く残っている。彼の作品は、およそその対極にあるのに、訴えかける強い力があり、新たな発見がある。
宮入の創作が、これほど着目されるようになったのは、米サンフランシスコの人気現代アーティスト、バリー・マッギー氏による功績が大きい。バリー氏が、彼の作品を自身の展示会で紹介したことが発端だった。そのため、まずアートやファッション寄りの人たちが宮入に注目し、その個性が広がっていった。2023年には「伊勢丹新宿店」で作品展が開かれ、ファッション誌、モード誌がこぞって紹介。新聞の「ひと」欄にも掲載された。
いっぽうで「民藝」というと、どこかソリッドで、しかもハイソサエティな雰囲気をまとう。柳宗悦のメソッドを理解し、彼の哲学に共鳴する者だけのもの、という印象も持ってしまう。同業の人たちからは「異端児」だと捉えられていないか。そう宮入に問いかけると、彼は首を大きく横に振った。
「異端児、みたいな認識はない。自分はもう柳の本をめちゃくちゃ読んだので、『わかってない』って言われたくない。『精読した』っていう気持ちがある。保守だと自分では思っているんで。たぶん民藝館に一番行ったのは自分だと思っていますから。いっときは週に2回とか、めちゃくちゃ見に行っていた。だから『盾突く』ような、そんな気持ちはいまもありません」
民藝の美学の基盤を、浄土思想に求めた柳宗悦は晩年、仏教美学の世界に到達した。彼の著した『美の法門』は、宮入にとって座右の書となり、びっしりと書き込みが入っている。彼は語る。

「自分は民藝を一宗派だと思っているんです。仏教をわかりやすく教えてくれたのがこの本です。美しいものが、唯一の手がかり。美しいものを見たときの自分が、浄土と繋がる」
「型染」という制約された表現を通じ、柳の説いた道に沿う仕事をしたい。宮入はそう決めている。
ソフビ人形は民藝に通じる
東京・池袋で生まれ育った。おもちゃが買えなかったので、粘土や紙を使って自分で怪獣やロボットを作って遊んでいた。
「紙粘土は買えなかったので、油粘土を使いまわしたり、ブロックを使ったり。一時期、昆虫にハマったときは、いろんな果物の種を昆虫だと思い込んで遊んでいました(笑)。ゲンゴロウが好き。思い出すと笑ってしまいます。スイカ食っているとね、ゲンゴロウに見えるんですよ、種が」
都立高校に進むも、校内が荒れており、行く気もしなくなって、2年生のときにやめた。「モノ作りが得意」であることは、周囲に知られていて、ソフビ(ソフトビニール)人形の原型を作成する「原型師」の仕事にありついた。永井豪の「マジンガーZ」が人気だった頃のことだ。敵のロボットの原型を作りながら、じつはロボットがあんまり好きではないことに、宮入は気づいてしまう。彼は振り返る。

「ロボットはね、左右対称できっちりしていないと駄目なんですよね。でも私はそれが好きな性格じゃない。なのに、きっちり作っていないとすごく怒られる」
キャラクターの資料を渡されて作業に入っても、宮入が作ると、なんだかロボットらしくない仕上がりになる。
「人間みたい。ロボットっぽく見えないって言われた。ちょっと人間っぽいかな。それか、昆虫っぽい」

そのうち、生産拠点が安価な中国に移り、食えなくなった。そんな頃に訪れたのが、駒場の日本民藝館だった。宮入は語る。
「ソフビも、民藝品に近いものだと自分は思った。ソフビって、そもそも普段は瀬戸物とかを作っている職人がアルバイトで作っていたんですよね。だから顔とか元のモデルに全然似てなかったり、形もめちゃくちゃだったりする。あと、やっつけ仕事。民藝に近いと思う理由は、もともと普段は農業をやっている人たちが片手間で作っていた、無作為で欲がないものだから。同じ面白さ、美しさがある」


こうして宮入は型染作家に転身した。のれんやTシャツ、手ぬぐい、バッグ。型染の依頼がひっきりなしにやってくる。モチーフは、紙片を利用した幾何学的なものや、宇宙船やマグカップ、磁石に蛇口といったポップで若者に好まれるものが多い。実際に都内のセレクトショップでも扱われて人気を博している。そんな現在がとても嬉しい。価値が知られ、価値のわかる人々が増え続けている。どこかスノッブさをまとう民藝の印象が、変わりつつある。
もういちど民藝と向き合う
宮入に影響され、型染の世界に入った人もいる。弟子もできた。現在、中学2年生の、宮入の長女・ちょう。
「小学校のときに、全然お金がなくて、習い事とか塾とか何も行かせられなかったんです。それで、教えられることは教えておこうと思って。民藝館にも一緒に行っています」
いま、宮入が強く心に決めていることがある。
「2023年からの巡回展示『民藝 MINGEI──美は暮らしのなかにある』のグッズ作成などをやらせてもらったことで、今後、もっと『民藝』をやっていこう、という気持ちになった。アートのほうで世に知られるようにさせてもらったんですけど、『工藝』を頑張る。そっちを軸にしていこうと思っています。製造や販売を積極的にやっていこうって思っている。この世界ではまだ若手なんですけど、もう50歳。開き直ってきた。民藝の仕事を、工人として、職人として、仕事としてやっていこうと思う」

今年10月にはワタリウム美術館(東京・青山)内の「ライトシード・ギャラリー」で、アーティストの DIEGO と二人展を開く。葛藤を抱えたことと、自分なりに出した答えが、新しく多くの人々の共感を生む。民藝の「ド本流」にいる人たちとも、良い意味でのハレーションが起こるかもしれない。言葉を一つひとつ確かめるように語る宮入の、強い決意を感じた取材だった。
メールが苦手だという彼から後日、編集者を通じてメールのメッセージが届いた。
「無作為(無心)な物をつくる事へのあきらめから理解したことは『自分』の受容です。『無作為』にどれだけ執着してしまったか、どんなに苦しんでも考えてもダメだった、ということ。『つくる』もしくは『考える』と言っている時点で間違いなのだとわかったことです」
執着への諦めと、受容は、宮入自身を良い意味で開き直らせ、背中を押した。すると以前よりも、素直な図案が描けるようになったという。自分ではどうしようもない力のことに、柳宗悦は「直観」という呼び名をつけた。
わかっていないのに、わかったような態度はとりたくない。それでいい。宮入の創作人生は、新たな局面に入っていく。

宮入圭太(みやいり・けいた)
1974年東京都生まれ。ソフビ人形の原型師を経て、独学で型染を習得。柳宗悦の思想に惹かれ、民藝を学び、民藝と向き合いながら作品を制作している。2022年ユニクロのフリーマガジン『LifeWear magazine』秋冬号の特集、表紙に採用され、2023年1月には伊勢丹新宿店で作品展を開催。来年にかけて全国巡回中の展示「民藝 MINGEI──美は暮らしのなかにある」ではメインビジュアルを担当している。