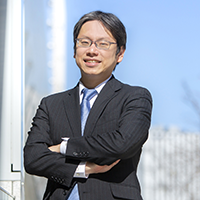源流の人 第45回 ◇ 室橋裕和(フリーライター)

日本を席巻する「インネパ」カレー店から移民を取り巻く現状を読み解く
取材協力=ナナハウス
東京・大久保。街を行き交う人々からは、さまざまな言語が聞こえてくる。大久保通り沿いにある本格ネパール料理店「ナナハウス」で、室橋と待ち合わせた。この店は、国内で約5000軒ともいわれる「インネパ」料理店が看板としている、大きなナンとカレーをセットにしたおなじみのメニューはもちろん、本場のネパール料理も充実している。名物「ハングアウトスペシャル」は、マトン、チキン、ポークから選べるさらりとしたカレーに「ダール(豆スープ)」「マトンチョイラ(焼きマトンのスパイス和え)」「タルカリ(野菜炒め)」「サグ(青菜)」「アチャル(漬け物)」といった内容だ。

そもそも室橋はどうして「インネパ」の取材を始めたのか。
「多くの日本人たちもそうだと思うのですが、『なんでこんなにあちこちにあるの?』って気になって、調べてみたくなったんです」
30代の10年間、タイ・バンコクに暮らし、タイやその周辺国の取材に従事してきた。40歳になって帰国してからは、アジアに生きる日本人や、日本に生きるアジア人をテーマに取材を続けている。外国人と接する日々を送るうちに室橋が気づいたのは、周りにネパール人が激増していることだった。
「以前に夜間中学の取材をしたことがあったんですね。夜間中学には外国人がたくさん通っていて、そこが日本語や日本の文化を覚える場所になっていたんです」
生徒のうちの一人、ネパール人の男の子に出会った。彼は「夜間中学に通わなかったら、自分は日本社会に溶け込めなかったかもしれない」と話していた。そしてこう言った。「僕は『カレー屋の子ども』として日本に来て、すごく苦労しました」。彼のその言葉が、室橋の印象に強く残ったという。

「ずっと引っかかっていたんですよね。『カレー屋の子ども』という世界があることに。日本に図らずも来てしまった。そうどこか自虐的に話してしまうような、『カレー屋の子ども』たちの世界。そしてその親たちの世界ってどうなっているんだろうって気になりはじめたんです」
とりわけ、室橋が注目したのが「インネパ」店の激増だ。そもそも何で日本じゅうに広がったのか。どうして似たようなメニューばかりなのか。だいたい、バターチキンカレーはネパールでは主流ではない。ナンよりも「ロティ」(小麦粉を使った薄焼きパン)や「チャパティ」(全粒粉を使った薄焼きパン)のほうを彼らは口にする。そして、インドとネパールの食文化は、じつはだいぶ異なっている。
あの「インネパ」の定番メニューは純正インド料理なのかと言うと、それもじつは違う。
室橋曰く、「取材をはじめようとしたらあれもこれも気になってきた」。彼は、まず手始めに、東京・大久保のネパール語新聞「ネパリ・サマチャー」発行人で「在日ネパール人の父」のような存在、ティラク・マッラ氏を訪ね、そして取材を重ねていった。
「失敗するのが怖い」から「同じメニュー」
日本に長年住むネパール人。
ネパール人を仕事相手にする日本人。
彼らが読むマッラさんの新聞に、室橋は広告を出した。
「カレービジネスについて意見を言いたい関係者、求む!」
それでコンタクトをとってきた人たちに話を聞いていく。
東京、名古屋、岐阜、大阪。話を聞いてはカレーを食べ、カレーを食べては話を聞く。
北海道から沖縄まで、離島も含め、全国に「インネパ」店が深く根づいていることを痛感した。そこで気づいたことがあるという。
「彼らは冒険して失敗するのが怖い。日本までやってきて『失敗できない』という気持ちが強いんです。それで普段、自分たちが食べているものではなく、『このメニューなら日本人に好まれるはず』という、日本人好みにアレンジした、いわば王道の味を狙っていたんです」

日本人は、もう少し多様な食文化を受け入れるはず。日本風アレンジを加えずとも、純正ネパール料理は日本人の舌に合うのではないか。そう室橋が主張しても、「いや、違う!」。強いこだわりを彼らから感じたと室橋は明かす。
「そして、日本人の好みを把握しているように見えて、どこか、ちょっと的外れなところがある。それが文化の違いだと思うんですよ。考えているのか、安直なのか、よくわからなくなってくるところがありました」
もっとも、ラーメン屋にしようか、それともコンビニ弁当にしようか、それとも「インネパ」のカレーにしようか──。それぐらいのノリでランチに行く多くの日本人をターゲットにするならば、本場ネパール料理よりも、彼らの言うところの安全策をとり、絵に描いたような典型的メニューを出すのは正解なのかもしれない。
いっぽう、この現状を見て、「ネパール人は自分たちの食文化にもっと誇りをもった方が良くないか」と考える人もいるかもしれない。だが、室橋は「そういうことを言える余裕は、先進国からの『上から目線』であると思います」と一刀両断する。「ネパール人は失敗が許されない」というのには、深い理由がある。
ヒマラヤ山脈の中央部にあるネパールは、小さな山岳国だ。インドとチベット高原の間に位置し、観光と農業のほかに、これといった産業はない。3000万人の国民の約40%は貧困層だという。本国を出て外国で働くネパール人は人口のおよそ1割。出稼ぎによる送金額が国内総生産(GDP)に占める割合は29.9%(2020年)。ネパールは世界屈指の「出稼ぎ国家」である、と室橋は教えてくれた。
「日本に住む古株のネパール人たちは、みんな悩みを抱えている。日本でそれなりに成功した人たちですが、『はたして、これでよかったんだろうか』って言い始めているんですよね。人材が流出して空洞化が進んでいるネパール国内の現状では、なかなか産業も育ちにくい。はたしてこれでよかったのか、と」

本国に貢献すべきだ。
老いた親の面倒は誰が見るのか。
それでも家族を食わせるためには出稼ぎするしかない。
俺たちだって先進国の人たちと同じ生活がしたい。
そんな葛藤を、つねに抱えて彼らは生きている。家族滞在の在留資格をもって日本で生活している外国人の割合では、ネパール人が突出している。つまり、日本には興味もなかったのに、親に言われて仕方なく日本にやってきた家族がたくさんいるということだ。
なぜ日本なのか。そのわけは、隣国インドに出稼ぎに行った人が、その雇い主ごと日本に移ってくるパターン、または親戚や知人が既に日本で出稼ぎをしていて、それを頼りにしてくるパターンなど多種多様だ。
海を渡ってやってくるも、親は多忙で小学校に行っても日本語がわからず、日本社会からドロップアウトしてしまう子どもも多い。室橋が出会ったような、夜間中学に通って日本社会に溶け込めた子どももいるが、言葉や文化の教育や、地域が包摂していく態勢の整備は、いまや急務となっている。
新大久保はアジアの首都
バンコク時代の室橋は、タイ国内の政変や地震・津波災害など、あらゆるトピックを取材してきた。そしてタイのみならず、周辺アジア諸国にも取材先を拡げ、ネットワークを構築してきた。2014年に帰国した時、室橋は、日本の風景が様変わりしていて、驚いてしまったという。
「噂には聞いていたけれど、これほど外国人の多い社会になっていたのか。『日本、変わったな』と思いました。昔は中国人、韓国人ばかりだったのが、彼らがむしろ減って、東南アジアとか南アジアの人が増えてきた。自分もタイで外国人だった経験から、彼らがどういう生活をしているのか気になったんです」
バンコク時代、室橋は日本人コミュニティに片足を置いて、もう片足はタイ人社会に置くような生活を送っていた。バンコクの日本人エリアには、日本の食材店や居酒屋、カラオケ屋、学習塾、眼鏡店などが並び、日本語の窓口がある病院があり、日本人学校があった。
「日本人が暮らすための生活インフラが完璧に整っていたんです。もしかしたらそういう場所って、東京、あるいは日本にもあるのかもしれないと思って探し始めたら、バンコクの日本人街ほどの充実ではないですけれど、あちこちにあったんです。西葛西(東京・江戸川区)に行けばインド人街、高田馬場に行ったらミャンマー人街、というふうに」

この発見をきっかけに、室橋は「日本の外国人コミュニティ」についてネットニュースで連載を始めた。その取材中に出会う外国人の多くが、「新大久保」の名を口にすることに気づいたという。室橋は語る。
「たとえば中国人が、『昔、新大久保の日本語学校に通っていたよ』とか、バングラデシュ人のレストラン経営者が『新大久保に食材の仕入れに行くよ』とか。みんな言うんですよね。休日は新大久保で友達と会うとか。新大久保が首都圏における外国人たち、特にアジアの人たちの首都的な存在になっているような、そんな印象すら受けたんです」
新大久保と言えば、いまやコリアンタウンの印象が強いが、それが本格化したのは2000年代、ドラマ「冬のソナタ」あたりに端を発した「韓流ブーム」以降のことだ。じっさいに街を歩いてみると、さまざまな国の言語が飛び交う多国籍タウンであることが窺える。
「そしてこの5年ほどで、新大久保に似たような街がほかにも増えましたね。たとえば十条や小岩、大塚、錦糸町など。多国籍化した、ごちゃついた商店街的な街が各地に増えたなって思うんです。大阪、名古屋、福岡、沖縄も同様です。多民族化がすごく進んできた印象はありますよね」
はたから見ると、「外国人がたくさんいる」イコール「治安が悪い」と思われそうだが、実際に新大久保に居を構える室橋によると、「そういうわけではない」。彼は言う。
「酔っ払い同士のケンカ、ごみの分別問題は、ときどきありますけれど、そんなに治安は悪くない。『民族紛争があるんでしょう?』とか言われるんだけども、ないですね。お互いにエリアの境界線で揉め事があるのではと誤解されがちですが、そんな境界線はなく、新大久保はごちゃごちゃの混在地域です。それほど各コミュニティ間で大きな交流はないし、トラブルもないんです」
増える移民、困惑する日本人、双方に考えるべきことがある
出入国在留管理庁によると、日本に在留する外国人は、2023年12月末時点で340万人を超え、過去最多となった。大阪市の人口が約277万人、横浜市が約377万人であるから、「ここまで外国人が増えているのか」と驚いてしまう。日本政府や経済界の方針としては、労働力確保のため、もっともっと増やしていきたい。ただそうすると、外国人に対して免疫のない島国の日本人のなかには、外国人に対し複雑な感情を抱く人も出てくる。最近では、たとえば埼玉県南部で増え続けるクルド人に関するトピックなど、ニュースになることが増えている。室橋は言う。
「不思議であるのは、外国人をどんどん受け入れようと言っているのは、この国の政府。できるだけ安い労働力がほしい産業界からの要請ですよね。安い労働力を入れてまで存続する産業ってどうなのかとも思うけれど、外国人を入れている人たちにヘイトの矛先が向かう。現場にいる外国人にヘイトが向くのは、いびつな状況だと思います」
いっぽうで、と彼は付け足す。
「クルド人の問題にしてもそうだけども、火のないところに煙は立たない。何度もクルド人の取材はしていますし、問題は多々あるわけです。たとえば難民でもないのに難民申請している人たちを見ていますし、親が教育に対し無理解なせいで、日本語も、クルド語も、トルコ語もよくわからない子どもたちが育ってしまい、彼らが不満を溜め込んでいるのもまた事実なわけですよね」

難民申請をして、それが受理されず、本来ならば出入国在留管理局に収容されるべきところを、仮放免されている人たちがたくさんいる。在留カードがない、日本人で言えば住民票がない状態で暮らしている人が約3000人もいる。健康保険も入れないし、表向きには就労もできない。
「今まで、それでやってきてしまったクルド人にも、問題は、やはりあると思います。それを放置し続けてきてしまった日本にも、いろんな問題があると思うんですよね。日本社会のルールやマナーを会得し、地域との交流を考えてほしいと思うんです」
ひとこと、挨拶するだけでも、日本人の不安は和らぐ。
そこからいろんな交流が生まれてくるかもしれない。室橋はこう語る。
「日本人側もおかしなところはあるんですけど、外国人の方ももうちょっと考えてっていうのは、取材しているとすごく感じます。だから両方です」
外国人との共生なくして、日本社会の未来はない
今や外国人労働者の存在は、日本社会の継続にとって欠かせない。農業、介護、コンビニ、製造業、水産加工業、漁業、あらゆる現場で働いている。室橋は敢えて極論めいた言い方で訴える。
「外国人に対してアレルギーがあるならば、そしてこの国を日本人だけの国にしたいと思うならば、民主的に選挙なりなんなりでそうすれば良い。それも一つの日本人の幸せかなと思います。無理に外国人を入れることはない。でもそれで干上がる産業があるならば、それはそれで日本人が選んだことなので仕方ないでしょう」
たとえば、クリックすれば翌日に商品が届くシステム。なぜ届くのか。それは、流通センターの中で多くの外国人を含むスタッフが昼夜汗を流して働いているから。あるいは、ホテルや温泉地の露天風呂。なぜ美しいのか。それは、外国人を含む従業員が夜中にゴシゴシ清掃に明け暮れているから。室橋はこう述べる。
「みんながよく食べるコンビニ弁当、スーパーの惣菜。誰が工場でつくっているのかって言ったら、ネパールのおばちゃんたちがすごく多いわけです。もし、彼らが一斉に帰国したらどうなるんだろうなって思いますよね。インバウンドにしたって、これほどみんなが嫌で嫌で仕方がないんだったらば、観光入国を制限するのも、一つの方法なのかなと思うんですね」

外国人との共生なくして、もはや今の日本社会は成立し得ない。それを、日本ルーツのわたしたちはじっくり考えなければならない時期に来ているということだ。それも急激なスピードで。
「ただ日本政府も、まったく何の方策も立てていないわけではないんです」。室橋は言う。
日本で暮らす外国人が増えるなか、2024年4月、日本語教育の水準を高めるために「公認日本語教師」の国家資格を創設した。これまで公的な基準がなかった日本語教師の社会的地位を高め、担い手を増やし、外国人が日本語を学びやすい環境をつくっていくのだ。
「これまでの政府のスタンスは、出稼ぎの外国人は移民ではなく、短期滞在者との扱いでした。そんな人たちに対する長期的対応を考えていなかった。これが変わるきっかけになれば」
かつて室橋は、沢木耕太郎の『深夜特急』に魅せられて世界を放浪し、20代を週刊誌記者として、30代をバンコクの日本語情報誌記者として奔走してきた。そして今、日本のなかのアジアと向き合っている。室橋は語る。
「ここまで足を踏み入れてしまったからには、在日外国人の話について引き続き追っていきたい。僕の本を研究者の方が読んでくれていて、大学での講演を頼まれたり、非常勤講師や研究員の話をいただいたりするんです。性には合わない気もするけれども、若い人たちに何か伝えるっていうのは大事だって気持ちはあります。彼らに何かしらプラスになるものを伝えていく仕事も、これから大事にしていきたい」
考え方もずっと柔らかく、体力も知力もネットリテラシーもある若い世代にこそ、未来を託したい。アジアを見つめ、日本を見つめ直したからこそ得た室橋の着眼点は、これだけ日本社会が激変するなか、誰もが急いでインストールしなければならない視座だといえるだろう。……豆のスープ「ダール」が冷えてしまった。また近々、この店に訪れることにしよう。お店のスタッフの人たちは終始、微笑んでいた。彼ら、彼女らの人生についても知りたくなってきた。

室橋裕和(むろはし・ひろかず)
1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイに移住。現地発の日本語情報誌に在籍し、10年にわたりタイ及び周辺国を取材する。帰国後はアジア専門のジャーナリストとして活動。「アジアに生きる日本人」「日本に生きるアジア人」をテーマとしている。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に在住。外国人コミュニティと密接に関わり合いながら取材活動を続けている。おもな著書は『北関東の異界 エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本』(新潮社)、『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(角川文庫)、『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『ルポ コロナ禍の移民たち』(明石書店)など。