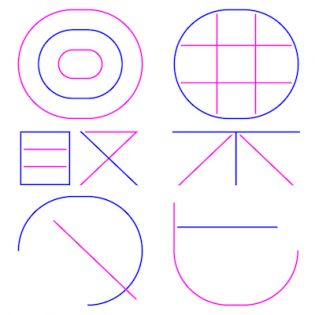最果タヒ『夜空はいつでも最高密度の青色だ』––「レンズのような詩が書きたい」に込められた想い。
「レンズのような詩が書きたい」:何を書いているのかわからなかった状況を変えたもの。
レンズのような詩が書きたい。その人自身の中にある感情や、物語を少しだけ違う色に、見せるような、そういうものが書きたい。(中略)私は自分の言葉単体よりも、その人と作り出したたったひとつの完成品を見ていたい。その人が、自分の「かわいい」を見つけ出す、ちいさなきっかけになりたかった。
『夜空はいつでも最高密度の青色だ』あとがきより
––最果さんは『夜空はいつでも最高密度の青色だ』のあとがきで「レンズのような詩が書きたい」と書かれていましたが、このような思いを持たれたきっかけをお聞かせください。
最果:私にとって言葉は、自分のものではなく、みんなのもの、という意識が昔から強くあります。自分自身の気持ちを伝えるために言葉を書いたり話したりするのがあまり好きではなくて、自分の言葉を読んで相手がなにかを思ったり考えたりする、というのが言葉を書く醍醐味だと思っていました。
なので、自分の書いた文章が誰かの内面で勝手に消化されていくものだという認識はずっとありました。ただ、「レンズのような作品」というものが理想だ、と自覚したのはかなり後です。
詩を書き始めたころは、自分が何を書こうとしていて、実際どういうものが出来上がっているのか、今よりずっとわかっていませんでした。もともと、詩を書こうと思って書き始めたのではなくて、書いていたものを「詩っぽい」と人に言われて、詩として作品を発表するようになったぐらいなので、「詩」というもののイメージ自体がはっきりしていなかったのだと思います。
––そのような状態だった最果さんを変えたものは何だったのでしょうか?
最果:少年漫画誌で詩の連載をしたのが大きなきっかけだったと思います。漫画雑誌の連載なので、読者は詩に触れたことがない人がほとんどなんです。それに連載では漫画家さんやイラストレーターの方に挿絵も描いていただいていました。そうした中で、自然と「どんなふうに読まれているのか」ということを意識するようになりました。「そういえば、昔からこんな感じで言葉を書いていたな」とそのとき思い出したんです。
––自分の書いた言葉が、相手に読まれていることを思い出させてくれたきっかけになったと。
最果:そういえば読まれることが私にとってはとても大切だったなあ、と。それからしばらくしてTwitterでも詩を書くようになり、いろんな人から直接反応をもらえるようになりました。そのとき、読んだ人によって詩の解釈が本当にバラバラで、詩は私ではなく読者を反映して完成していくものなんだなと強く実感するようになりました。
詩と映画のアプローチの違い。
––ご自身の作品をもとに映画が制作されることを知ったとき、どんな印象を持たれましたか?
最果:今回映画化のお話をいただいたとき、「詩は読み手の解釈に委ねているので、詩の中身を具体的にしていくというよりも、詩の外側の世界を描くようなものにしてほしい」と伝えていました。自分の作品をきっかけにして全く別の作品が生まれるということはとても光栄なことですし、「作りたい」と思っていただけたことが嬉しかったです。
ただ、やっぱりどういうものになるのかは想像ができなくて……。私にとって詩は、中心に気持ちや心があって、それを受け取った読者が自分のおかれた状況や起きた出来事に照らし合わせて読むものなんですが、映画は中心に出来事があって、その出来事から登場人物や自分の心へとつながっていくものだと思っています。受け手へのつながっていき方が、全く逆の表現なので、イメージがなかなかできませんでした。映画化の許諾については、脚本を見てからでいい、と言われていたので、とにかく石井裕也監督が書かれた脚本を読んでみたのですが、詩ひとつひとつと表面的に物語をつなげているというよりは、もっと根底の部分がつながっている気がして、安心もしましたし、嬉しかったです。
––詩と映画では、登場人物の有無も大きな違いだと思うのですが、映画の主人公は最果さんから見てどのように感じましたか?
最果:この作品の主人公はふたりの男女ですが、そのひとり、慎二は饒舌なんです。それがすごくしっくりきました。今の生きづらさや苦しさは、沈黙よりも饒舌に近いんじゃないかなと、そのときに強く思って。インターネットではたくさんの情報があふれています。みんなが言葉を発信して、どんどん吐き出していて、でもなにひとつ自分の芯をとらえていかない、そういう苦しさ。そうした中で溺れかけた時、人は沈黙するのではなくて、きっと自分も言葉を吐き出すように思うんです。
––映画を鑑賞されて最初に感じた印象についてお聞かせください。
最果:ただただ、「すごくいい作品を観たな」と思いました。脚本をあらかじめ読んでいたので、ストーリーそのものは知っていましたが、俳優さんの体を通して発せられた台詞が、その登場人物の人生の結果として出てきた言葉になるんです。それがすごく面白くもありました。
––「透明にならなくては息もできないこの街で、きみを見つけた」という映画のキャッチコピーも、作品の世界観を表現しているようで非常に美しいですね。
最果:映画を観た後に映画のキャッチコピー案を見せてもらって、その時すでに「きみを見つけた」という部分はあったのですが、「何かいい案があれば見せてください」と言われて、それで「透明にならなくては息もできないこの街」という部分を書きました。
東京には色がたくさんあります。ごちゃごちゃとしていて、整理もされておらず、自分自身が新しく何かをそこに足すなんてきっとできないだろうなと思ってしまう。自分自身の色というものを塗る場所がもうどこにも残っていないような、そんな場所なのかな、と思います。だから「透明にならなくては息もできない」と書きました。透明になってしまえば楽なんです、自分の言葉や気持ちを持たずに、順応していけば、どんなにたくさんの色があっても平然としていられる。でも、主人公のふたりはそれができなかった。自分の言葉を、気持ちを捨て切れなかった。慎二は饒舌になってしまうし、美香は自分を守るために否定的な言葉ばかり口にしてしまう。でも、だからこそ、ふたりはお互いを見つけたのだと思います。美香と慎二のような人たちにぜひ観てほしいなと思っています。
<了>
| 最果タヒ プロフィール 1986年生まれ。詩人、小説家。 詩集に『グッドモーニング』(中原中也賞 新潮文庫nex)、『空が分裂する』、『死んでしまう系のぼくらに』(現代詩歌花椿賞)、『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(石井裕也監督・脚本で映画化。2017年5月27日全国公開)があり、小説に『少女ABCDEFGHIJKLMN』、『十代に共感する奴はみんな嘘つき』などがある。エッセイ集に「きみの言い訳は最高の芸術」。 小学館「本の窓」において詩『±愛している』、小学館「きらら」2017年5月号より小説『恋の収穫期』連載中。 |
初出:P+D MAGAZINE(2017/05/20)
- 1
- 2