月刊 本の窓 スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 第1回 田澤純一
さまざまなスポーツのジャンルで、従来の枠にとらわれず、新たな挑戦に取り組んでいる新世代アスリートの魅力に迫る新連載。第一回は野球界の革命児に会いに行った。

田澤純一
(マイアミ・マリーンズ)
Photograph:Yoshihiro Koike
かっこいいと思った。堂々とした立ち姿は、アメリカ人に引けを取らない。どっしりとグラウンドに根を下ろした大木のよう。フロリダの太陽の下、ボールとグラブを手にしたユニフォーム姿は、とてもこなれている。
メジャーリーガー田澤純一を訪ね、話を聞いた。連載「アスリートの新しいカタチ」の記念すべき第一回の選手である。日本で長年最も人気の高いスポーツ“野球”で、社会人アマチュアからいきなりアメリカのMLBに渡り、成功を収めた。まさに、飛躍を遂げたニュータイプの一流選手である。
ここ数年の間、多くの野球選手を取材してきて、いつか話したいと思っていた意中の日本人メジャーリーガーは、いともあっさりと取材を快諾してくれた。勝手ながら、ドラフト上位指名級の“エリート”投手でメジャーに挑戦をした異色の経歴から、気鋭の飛び抜けた(ちょっと難しい)人物像をどこか想像していた。ところが、どっしりとした風格にどこかおっとりした雰囲気を漂わせている。会ってすぐに優しい人柄が見てとれた。
マウンドでアメリカの強打者を相手に、真っ向勝負を挑む姿からは想像もつかなかった。質問をすると、「いや、まあ、別に……」「そうですね……」「基本的には……」と丁寧に言葉を選びながら、多弁に語ってくれる。落ち着いているし、とても成熟していると感じた。後で周囲に彼の印象を尋ねたが、監督やチームメイトからも同じように「大人でプロフェッショナル」といった答えが聞かれた。メジャー九年目。新しいチームでもすぐに親しまれ、その人間性はリスペクトされているのがわかった。
現役最高打者「カブレラ斬り」でも有名に。
剛速球勝負でワールドチャンピオンに輝く
その穏やかな性格からは想像もつかないくらい、田澤のピッチングはアグレッシブだ。百五十キロ超のキレのあるストレートを力強く投げ込み、名だたるメジャーリーガーから三振を奪う。胸がすくとはこのことで、彼のピッチングは見ていてワクワクする。
二〇一三年にレッドソックスがワールドシリーズを制覇した時は、上原浩治が胴上げ投手になったが、田澤はその前を担う「火消し役」として大活躍した。タイガースとのリーグ優勝決定シリーズでは、現役MLB最高打者とも言われるミゲル・カブレラと三度対戦。どれも接戦の終盤(!)で、ヒット一本で得点が入るこれ以上ないプレッシャーのかかる場面だったが、真っ向勝負で“完封”。最強打者をねじ伏せると、現地メディアやファンから大絶賛の評価を集めた。
それが、普段はそんな姿とは好対照なまでの穏やかさ。最初に会って「やっぱり大きいですね」と印象を伝えた時も、「僕なんてこっちじゃそんな大きいって程でもないです」とすぐにやんわり否定する。そうした、どこまでも謙虚な人柄は、大木がしっかりと養分を吸収して逞しく育ったように、ちゃんとした土壌があった。
ピッチャーしかできなかった。
高校時代はやめたくて仕方なかった
「野球を始めたのは、小学校三年生の終わりから四年生ぐらい。当時は、Jリーグが始まったばかりでした。サッカーがすごい流行ってたので、ちょっとサッカーもやったんですけど、同時に野球も盛り上がっていったのを覚えています。野茂英雄さんが大リーグへ渡ったり、イチローさんが二百本ヒットを打ったり。僕はたまたま通ってた学校で、野球がすごい流行ってて、たまたま野球をやってたってだけですけども」
当初からピッチャーをやることが多かったという。理由を尋ねると、「ピッチャーしかできなかったから」と即答。続けて、「親父に『やるならピッチャーやった方がいい』って言われてましたし、バッティングが良くなかったんで、まあ、投げれて良かったかなと思いますけれども」と苦笑交じりに振り返る。周囲に促され、何となく始めたピッチャー。本人いわく「お遊び程度」の延長で中学生まで楽しく野球を続けた。ところが、熱心なオファーを受けて、それじゃあと入学した高校で、「野球をやめたい」日々を過ごすようになる。そこは強豪校を目指す「本気」の野球部だったのだ。
「とにかく厳しかった。高校の時はずっとやめたかった。毎日どう監督に怒られずに帰るかっていうことばかり考えてましたね。怒られると周りに迷惑がかかるから、野球が上手くなることよりも、どうやったら無事に一日がやり過ごせるかってことばかりを考えてました」
振り返りたくないぐらいと言う田澤は、切り替えて続ける。
「もったいない過ごし方をしてたなと思います。でもそれがあったから今があったのかもとも思います」

ボストンは地元の横浜に似た赤レンガの街という親近感があったが、フロリダは椰子の木が茂る南国地方の雰囲気。「観光らしいことはできないけれど、まったく違って楽しみに思う」と田澤。
社会人で初めて食事が楽しく……。
ENEOSと恩師大久保監督との出会い
高校卒業後は、野球をやめるつもりで一般企業への就職を決断していた。ところがその前に新日本石油ENEOS(現・JX-ENEOS)が田澤にオファー。屈指の実業団チームで野球を続けることとなる。
もともと食は細かったという。
「今はこうやって大きくなりましたけれども、高校の時はすごく細くて『食え食え』言われながらも、高校、まあ社会人に入ってからも最初はあまり食べられなかった。ENEOSで先輩からも良くしてもらったりして、初めて『食事って楽しいな』って思うようになりました」
こうして食事が楽しめるようになった田澤は、身体も大きくなるとともに、投手としてもみるみる成長していく。入社一年目から監督を務めた大久保秀昭氏の指導のもと、三年目にはプロ野球から声がかかるように。だが、ENEOSに恩返しがしたい。田澤は、「チームに貢献してから、その後でもう一度チャンスがあればプロに行きたい」と決断して残留すると、有言実行。見事その翌年の都市対抗野球でエースとしてチームを優勝に導いた。二〇〇八年、田澤二十二歳の秋だった。
メジャーに行くことは挑戦ではなかった。
「どちらが自分を成長させてくれるか」
この年の田澤はドラフト一位最有力候補だった。だが、田澤はレッドソックスからのオファーを受諾し、メジャーリーグへ行くことを表明する。これが日本初のアマチュアFAからメジャーに直接契約した例だった。すると逸材の「メジャー流出」を恐れたNPB(日本プロ野球機構)は、緊急会議を招集。以後、ドラフト指名を拒否してメジャーに行った選手は、帰国してもNPB球団とは一定期間契約ができないルールを制定した。通称「田澤ルール」。議論は今も続いている。
当時はやたらと「日本人投手がいきなりメジャーで通用するのか」と取り沙汰された。だが、本人にとってはより野球が上手くなるための環境が「たまたまアメリカだった」だけという。
「僕は別にNPBが上とか下とか、メジャーが上とか下とか、そういうのは別にあまり関係なくて、ただ単に僕をどうやって成長させるか、そういうことを言ってもらえたのがレッドソックスだったんです」

アメリカやチームについて、「僕は別に馴染んでる感もないし、馴染んでない感もないですけど、まあ別にこう、何ていうか自由にやってたらいいと思うんです」と田澤。
実は、プロ入りを目標に掲げたENEOSでの最終年、日本の球団からの接触はなかった。だが田澤は、プロ経験のある大久保監督や元日本ハムの高橋憲幸投手コーチから、プロの世界やプロ入りするための指導をみっちり受けたという。本人も「日本で即戦力になるにはどうすればいいか」を念頭に一年間励んだという。
そこに名門レッドソックスが田澤を育てたいと申し出た。大久保監督も「アメリカのシステムの方がいいんじゃないかと思う」と後押しした。「いろいろな人から意見をもらったり、サポートしてもらった上で、僕が自主的に決断しました」と田澤。ルールができたことを申し訳ないと語りつつ、周囲に励まされ、熟考の末にアメリカ行きを選んだ。
騒動には、常にENEOSや大久保監督が“盾”になってくれたという。他のスポーツではアマチュア選手が高みを目指して、海外のプロチームに移籍することは珍しくない。ENEOSも全面的に田澤を守った。
「そういった人たちのサポートがあったおかげで、今があると思います」
順応性もない。人に助けられただけ
アメリカで活躍できているのも、周りのサポートがあってこそ。感謝の言葉を繰り返す田澤だが、実際に海の向こうで成績を伸ばしていったのは本人の努力の賜物。これまで多くの日本人がメジャーに挑戦したが、ほとんどが数年の内に日本球界に復帰か引退している。九年目を迎える田澤は、なぜ順応して続けられているのか。
「順応性? あんま考えてないってのが一番大きいと思います」と田澤は笑うと、「いやまあ、でも僕は、何か考えるより前に、人との出会いに恵まれてきたのだと思います」と笑顔をかき消し、真摯な表情で語りだした。
「まずENEOSっていう会社に入れたのもそうですし、大久保さんに出会えたのもそう。たまたまレッドソックスに入ってみたら、(斎藤)隆さん、松坂(大輔)さん、岡島(秀樹)さんがいて、そういった人たちから、メジャーのルールっていうのを教えてもらえました。だから、僕の順応性というより、その時その時に、すごい自分のためになるような人が現れているような気がします」
環境の違いは先輩が教えてくれた。語学も特に困ることはなかったという。というのも、レッドソックスには日本人スタッフが要所にいる。広報やトレーナーも複数いるため、日本語で不自由がなかった。「レッドソックスはずば抜けて日本人が行きやすい球団だと思います」
今年からはマーリンズという新しい球団に所属することとなったが、移籍の多いメジャーリーグならではで、球団ごとの違いはそれほど感じられないという。「システムはほぼ変わらないので、あとはチームの雰囲気に早く慣れるだけですね」
とはいえ、中南米出身の若い選手とも楽しげに話していた田澤。「イジられたりするんです。前の球団でもそうでしたけど、スパニッシュ系の選手とか、結構おちゃらけて来るんですよね。僕は嫌いじゃないですけども」と満更でもなさそう。
時々で人に恵まれたというが、そうした人を惹きつけるだけの魅力が田澤には備わっているのだと思う。
休みは月二日。
「辛いことと楽しいことがあるから面白いのかな」
メジャーのキャリアも決して順風満帆ではなかった。入団した年の二〇〇九年八月にメジャーデビューを果たすも、マイナーとの行き来を余儀なくされ、股関節を痛めて一年目を終了。再起を期した二年目の春季キャンプで、右ひじの靭帯損傷が判明した。
「普通にキャンプで投げてて、一イニングで三本塁打打たれた次の日にミーティングしようって言われました。野球のことかなと思ったら『病院に行ってこい』って。試合で投げててこれからシーズンに入るって時に手術って言われたんです。小さい頃からずっと野球をやってきて、一年ぐらいまったく投げられないって初めてで、やっぱ辛かったです」
トミー・ジョン手術という靭帯の移植手術を行い、同年はリハビリで全休。翌年、マイナーから再スタートし、九月に二年ぶりにメジャーのマウンドへ復帰した。チーム全面サポートのスケジュールだった。
「まだここがこうこう痛いんだけど、手術後ってどうなの? って質問にも、それならこうだから絶対に大丈夫と答えてくれた。サポートしてくれた人をしっかり信じることができたことは、本当に良かったと思います」
良いこともあれば悪いこともある。オフは身体づくりが基礎になるし、ひとたびシーズンが始まれば、「休みは月にせいぜい二日」のハードスケジュール。たまの休みも身体を休めるので精一杯という。
「野球は仕事ですから」とクールに言う田澤だが、充実感がにじみ出ている。「抑えれば楽しいし、打たれれば悔しいし、それは色々あります。その繰り返しだから面白いのかなと思います。いかに楽しいことを増やしてシーズンを終わるかってのをやっていかなきゃいけない」
シーズン中の小さな楽しみは、ニューヨークやロサンゼルスなどの大きな都市で美味しい日本食を見つけることという。アメリカでは日本食があまり食べられないのが当たり前なので、帰国したら「コンビニがすごい楽しい」と田澤。日本食を見つける楽しみは些細で大きい。
アメリカを拠点に二月から十月まで野球漬けでも、周りの仲間や日本人に感謝しながら懸命に自分を磨き、オフには帰国してENEOSのグラウンドで練習し、後輩との交流を楽しむ。たまたま「職場」がアメリカだけれど、心は常にすぐ近くの人、そして日本の人々とともにある。人として選手として成長しつづける「新しいアスリート」は、根を張った大木のように、地に足をつけて野球人生を歩んでいた。
プロフィール

田澤純一
たざわ・じゅんいち
プロ野球選手。米メジャーリーグのマイアミ・マーリンズに所属する投手。1986年生まれ。横浜商科大学高校を卒業後、新日本石油ENEOS(現・JX-ENEOS)に入社。4年目、社会人野球の全国大会「都市対抗野球」でチームを優勝に導き、MVPの「橋戸賞」を受賞。日米のスカウトから注目を集め、レッドソックスに入団。2013年は不動のセットアッパーとして活躍、ワールドシリーズ制覇の一翼を担った。
松山ようこ/取材・文
まつやま・ようこ
1974年生まれ、兵庫県出身。翻訳者・ライター。スポーツやエンターテインメントの分野でWebコンテンツや字幕制作をはじめ、関連ニュース、書籍、企業資料などを翻訳。2012年からスポーツ専門局J SPORTSでライターとして活動。その他、MLB専門誌『Slugger』、KADOKAWAの本のニュースサイト『ダ・ヴィンチニュース』、フジテレビ運営オンデマンド『ホウドウキョク』などで企画・寄稿。
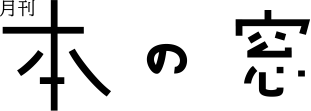
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。ページの小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激します。
スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 連載記事一覧はこちらから
初出:P+D MAGAZINE(2017/05/22)






