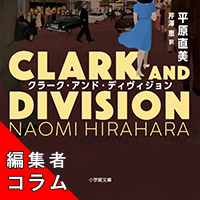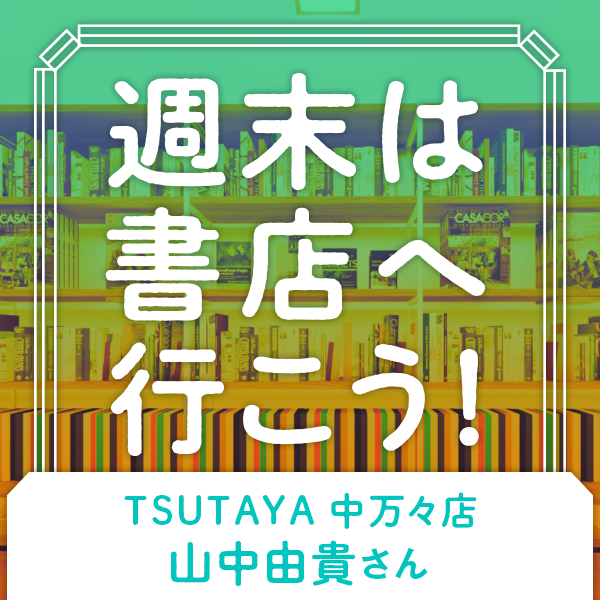翻訳者は語る 芹澤 恵さん
科学者レイチェルが開発した、自分と瓜二つのアンドロイド。『iレイチェル』は、彼女の死後、そのアンドロイドと暮らすことになった夫と娘の葛藤や成長を描いたイギリスの小説です。フロスト警部シリーズなどのミステリーから、ロマンス、純文学、児童書と多彩なジャンルの本を手がけてきた芹澤恵さんは、このAI小説とどう向き合ったのでしょうか。
〈小さいからこそ胸に迫るエピソード〉
最初に原書を読み始めた時はチャーミングな作品だなと思いつつ、人間の死ってもっと重いことじゃないかな、こういう軽やかな描かれ方でいいのかしらと、少しモヤモヤを抱えながら読みました。
でも、読み進めるほどにアンドロイドのiレイチェルを介して伝える親の子に対する思い、遺していく配偶者への思いが伝わってきて、かなりぐっときましたし、たびたび涙腺が緩みました。よく考えるとすごく他愛ない話だし、あらすじもシンプルだし、これで手もなく泣くかと思いましたが……(笑)。
全体の設定は夢物語ですが、家族の日常生活の描写はとてもリアルですね。娘は優秀な母に対してコンプレックスを抱いていたけれど、実は母も完璧な女性ではなく、家庭に時間を割けないことを申し訳なく思っている普通の「働くお母さん」だったり。そういうことが、小さなエピソードを重ねて綴られていきます。翻訳前はその「小ささ」が作品の弱さにならないかと少し心配でしたが、作業を進めて読み返すほどに、小さいエピソードだからこそ、切実に、リアルに、胸に迫るのだと気づきました。
AIを描いていますが、これは「喪失と再生と成長の物語」なんですよね。
〈「家政婦のミタ」を参考に〉
学習するアンドロイドのiレイチェルが家族と暮らすうちにどんどん人間らしくなっていく姿も、本作の大きな魅力ですね。その変化が伝わるようにと、彼女の台詞はメリハリをつけるよう工夫しました。最初はとても機械的なので、参考にしたのは「家政婦のミタ」(笑)。その後少しずつ人間的になるのですが、途中でプログラミングされていた妻の言葉を喋り出す場面もあり、「人間の妻」の言葉との差異をつけるためにも堅苦しい喋り方を生かしました。
娘のクロエと友人たちの会話やSNSのやりとりもたくさん描かれます。若者の言葉は、訳す時のさじ加減が難しいんですね。実在の十五歳の言葉をそのまま活字にすると、どうしてもすぐに古びてしまうので。今回は比較的お行儀のいい子たちだったので助かりました(笑)。
〈ロマンスからミステリーへ〉
子どもの頃から海外文学が好きで、『赤毛のアン』のような少女文学も、ホームズの『まだらの紐』『踊る人形』などのミステリーも夢中になって読みました。中学生の頃は少し背伸びしてロシア文学を読んだり。本と同じくらい映画も好きで、将来はタダで映画がたくさん見られる仕事に就きたい、それなら字幕の翻訳の仕事だ、と漠然と思っていました。
結局、大学を卒業した後は親の希望もあり母校の中高一貫の女子校の教員になるのですが、しばらくして「これでいいの?」と思うようになって。そんなときに子どもの頃の夢を思い出し、翻訳学校に通い始めたんです。当時は字幕の仕事が少なくて、「文芸をやれば?」という周りの勧めもあり、編集プロダクションを通してロマンス小説の翻訳の仕事を始めました。「第一次ロマンスブーム」で、ハーレクインシリーズが飛ぶように売れていた時代です。二十代でまだ恋愛が自分にとってリアルだったこともあり、一緒にハラハラドキドキしながら翻訳をするのがとても楽しかったですね。
そのうちにロマンスブームが下火になり、改めて田口俊樹さんの翻訳講座に通い始めて弟子となり、ミステリーの翻訳もやらせていただくようになりました。
ロマンスとミステリーでジャンルは違えど「人が描かれている」ことは変わらないので、違和感は全くなかった。ロマンス小説って究極のサービス業なんですよ。読者を夢の世界に連れて行き、いい気分にさせるという。読んでくれる人を意識して訳すという意味では、どんなジャンルでも同じ。なので、ポリシーは「来た仕事は拒まず」です(笑)。
〈「感じることは同じ」という発見〉
以前は翻訳書の意義は、「読むことで知らない世界のことを知る」ことにあると思っていましたが、最近はむしろ、「国は違っても、感じることは同じなんだ」という発見にあると思っています。
私はもともと短篇が好きなのですが、そんな発見が出来る、日本ではまだ紹介されていない作家の魅力的な短篇集がたくさんあります。実はこれまで何度も出版社に企画を持ち込んでは玉砕しているのですが(笑)、くじけずにいつか日本でも紹介できたらと思っています。