出口治明の「死ぬまで勉強」 第18回 ゲスト:生田幸士(東京大学名誉教授) 「考えるバカが世界を変える」(前編)
子どものころ、アトムになって
悪者をやっつけたいと思っていた少年は
大人になって医療用ロボットの大家になった。
だが、それを真っ先に認めてくれたのはアメリカの研究機関。
日本には活力を生むためのダイバーシティが足りないという。
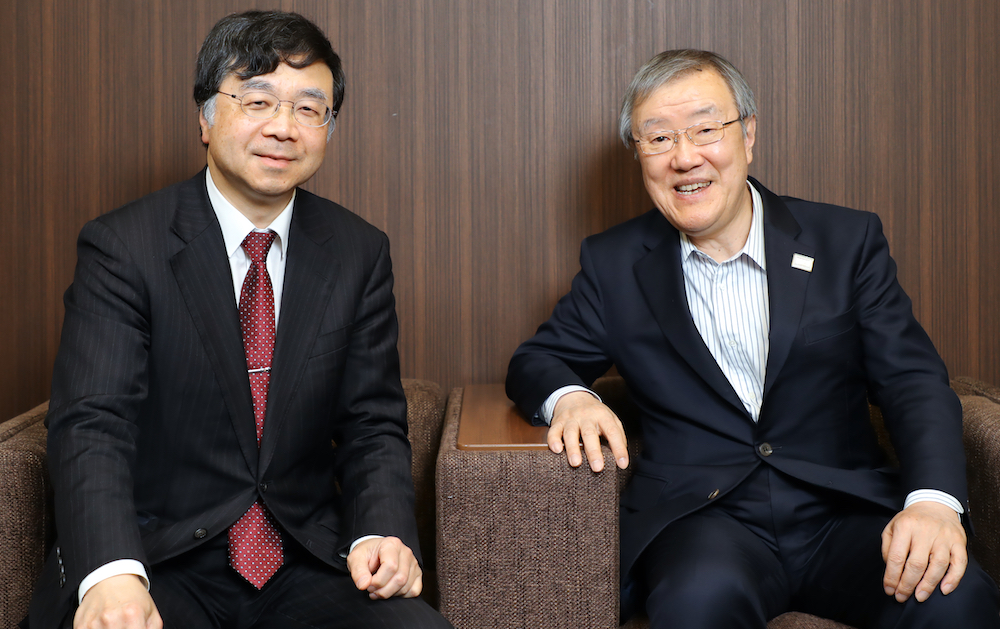
■出口「ロボットという子どものころの夢を追い続けられたのですね」
■生田「僕はアホやから、単に成長しなかっただけです(笑)」
出口治明 生田先生は医療用マイクロマシンや大腸の内視鏡検査に使える新しいロボットなどを開発してこられたそうですね。ロボットの研究は、子ども時代からの夢だったのですか?
生田幸士 やはり「鉄腕アトム」や「鉄人28号」を見てあこがれました。といっても、「いつかロボットをつくろう」という夢を抱いたのではなく、「自分がアトムになって敵と戦おう」と妄想していたわけですが(笑)。
そういう意味では、前回の東京オリンピック(1964年)のときに子どもだった僕たちの世代は、いまと違って幸せでしたね。科学を究めれば社会は良くなるとみんなが信じていて、その象徴として「鉄腕アトム」や「鉄人28号」があったのですから。
出口 当時はアトムなどにあこがれる子どもが多かったんですよね。
生田 男子の大半はロボット好きです。僕は以前、日本ロボット学会の理事をしていましたが、そのとき学会員に「あなたはなぜロボット研究者になったのか」というアンケートを取ったところ、なんと約4割が「アトムにあこがれて」と答えていました。意外と単純ですね(笑)。
出口 子どものころロボットが好きだった人も、やがてほかのことに興味が移ったりします。生田先生はロボットへのあこがれをずっと持ち続けてこられたのですね。
生田 僕はアホやから、単に成長しなかっただけです(笑)。
少し真面目にお話しすると、日本のロボット研究の第一人者である森政弘先生(現在は東工大名誉教授)の影響が大きかったですね。
中学生になって、「自分はアトムにはなれない。つくる側になるしかない」と気付いたとき、当時は東大の助教授だった森先生の入門書を読んで一気にファンになりました。本は何冊も読んだし、森先生のテレビ出演があるときは、高校の授業をサボって近所のうどん屋さんでテレビにかじりついていたほどです。当時まだ家庭用のビデオは商品化されていませんでしたから。
大学に進学するとき、森先生が東工大に移られたので、僕もそこで学びたいなと思っていたのですが、遊んでばかりいたので叶わず、1浪して大阪大学の工学部金属材料工学科に進みました。
出口 では、森先生とは学校も学部も違ってしまったのですね。
生田 ええ。初めてお会いできたのは大学3年生のときの春です。父が機械エンジニアで、たまたま父の本棚の日本機械学会誌をめくっていたら、森先生が東大の年次大会で特別講演をする、ということを発見したんです。これは聴きに行かなあかんと思って、大阪から安い深夜バスに乗って聴講にいきました。
学会員でもない学生が一番前に座って身を乗り出して聴いていたから、目立っていたかもしれませんね。あの講演で話された内容は、いまでも再現できるくらいはっきり覚えています。
それから阪大の基礎工学部の生物工学科に学士入学して、修士課程を修めたあと、ようやく博士課程で東工大の制御工学専攻に入ることができました。
出口 そこでようやく森先生に教えてもらうことができたと。
生田 はい。僕が最後の弟子でした。実際に指導してくれたのは森先生のお弟子さんたちで、僕は森先生が定年退職される前の最後の主査(博士論文を審査する責任者)をしていただきました。当時はいまと違って、論文を5本は書かないと博士にはなれなかったので、結局、書き上げるのに5年かかりましたね。
出口 具体的にどんなことを教えてもらったのですか。
生田 森先生は大先生なので、年に数回しか直接お話しする機会はなかったのですが、そのなかで印象に残っているのは、研究室の飲み会で「生田くん、まだ論文を書くための研究をしてるのか。もっとバカにならなあかんよ」と言われたことです。
僕が、「バカだからまだ論文が書けないんです」と答えたら、「論文なんてどうでもいいから、自分がおもしろいと思ったことを追求しなさい。そうしたら結果はついてくる」といわれたのです。
当時の僕は家庭教師のバイトをしながらなんとか食いつないでいたので、内心では「そりゃ大教授は気楽でええわ」と聞き流していました(笑)。いまならその意味がわかりますが……。
出口 人間がその能力を存分に発揮できるのは、自分がおもしろいと思ったことをとことん追求するときなので、森先生のおっしゃることは理にかなっていると思います。
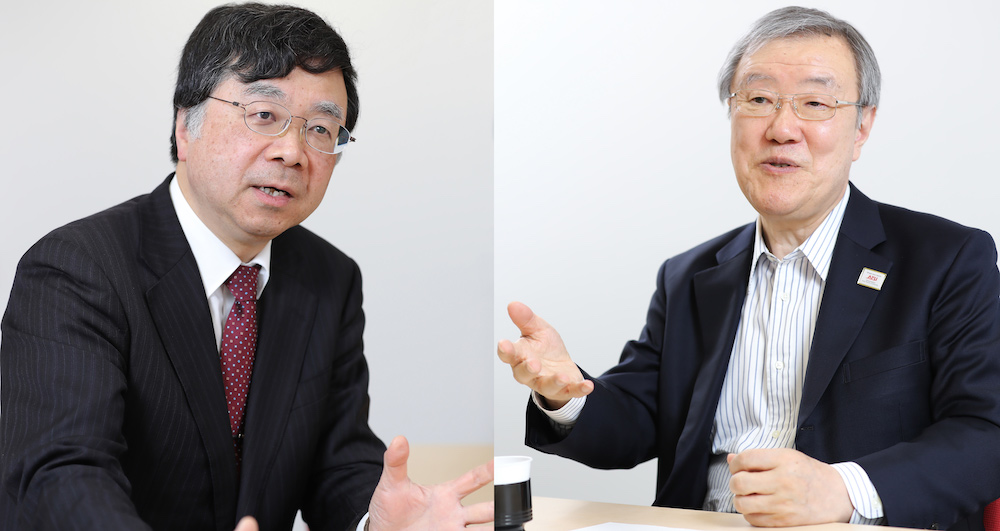
出口「自分がおもしろいと思ったことをとことん追求するとき、人間はその能力を存分に発揮できます」
生田 そうですね。だから博士課程で森先生のおっしゃるとおり、バカになって、肛門からお腹に入っていくヘビ型の能動内視鏡の研究を続けていました。ただ、そんな変わった研究だと、日本では評価してもらえません。国内の大学で職を探していたのですが、なかなか色よい返事をいただけるところがなくて……。
そんなとき、カリフォルニア大学サンタバーバラ校にロボットセンターが設立されて、ハードウエアの若手研究者をリクルートしていました。僕も声をかけられて、リクルートに来られた研究所長に会ってみたら、「こんな研究をやっている人はいない。おもしろい」と30分で即決したのです。それから2年間、ここで働きました。
出口 理解できないことに直面したとき、それを排除してしまう日本式と、わからないことをおもしろがるアメリカ式の違いですね。
生田 おっしゃるとおりです。
帰国することになって、東大の講師のポストをいただいたのですが、あらためて後悔しました。東大は普通の大学の3倍は会議があって、細々とした用事も多い。僕を呼んでくれた有本卓先生は雑用を押しつけるようなことは一切ありませんでしたが、他の先生は下っ端の僕に雑用をどんどん押しつけてきます。朝から大学にいるのに、自分の研究を始められるのが夜の7時。これはおかしいぞと。
その後、九州工業大学で助教授、名古屋大学で教授を務めさせていただいたのですが、会議の多さは東大と変わりません。「欧米なら会議数は10分の1しかない。それでも回る仕組みをつくったらええねん」と主張していましたが、結局何も変えられませんでした(笑)。
出口 アメリカをはじめとする海外の大学では、研究や学生たちに教える活動と、研究活動をサポートし、その成果を内外に伝えていく大学リサーチ・アドミニストレーター(RA)の活動が明確に分けられています。ところが日本の大学では、一般に研究とマネジメントの両方を先生たちがやらなければいけない仕組みになっていますから、その負担は大変ですね。
生田 そのとおりだと思います。では、日本の大学が、マネジメントに関してもきちんとやっているかといえば、私は疑問ですね。あれはマネジメントではなく、その真似事だと思います。
日本の大学で偉くなるのは、みなさん基本的に人柄がいい方たちばかりです。嘘はつかないし、人のために尽くされるから、多くの仲間から支持されてリーダーになっていきます。もちろん、研究もコツコツやっておられて、世界的な評価を得ている方もいらっしゃいます。でも、マネジメントに関してはアマチュアだと言わざるをえません。
たとえば欧米の場合、学長や学部長など大学のマネジメントを主な業務とする職種は、教授のなかからマネジメント能力と人格がともに備わった方が40歳台から学部長として選出され、そのなかから経験を積んだ人が選抜されて副学長、学長になります。
さらに大学のマネジメントで実績を挙げると、別の大学から幹部としてヘッドハンティングされ、いっそう経験を積みます。企業トップが、もっと大きい企業で社長を務めるのと同じです。
一方日本の場合、学部長はその学部に所属する全教員の投票で決まるので、実績より人気投票となりがちです。大学が大失策をした場合以外、革新派にはあまり票は入りません。
また、反対意見が出された場合、アメリカなら仲のいい相手に対してもロジカルに反論し、相手がまたロジカルに反対するということを繰り返して妥結点を探りますが、日本ではそうではありません。ロジックで戦うかわりに、「まあまあ、ここはひとつ……」と情に訴えるだけです。
出口 ちなみにカリフォルニア大学の場合、先生に対する評価はどのようにして決められていたのですか。
生田 まず、研究者の本分である論文や研究業績ですね。次に、それを前提とした研究費。アメリカの大学では修士1年目からRAを雇いますから、プレゼンをしっかりやって研究費を取らないと、何もできません。
そして教育です。研究費を取って論文を書いていても、学生による評価が低いと出世は遅れます。
出口 つまり、学生を満足させないといけないわけですね。
生田 ええ、そうです。
カリフォルニア大学時代、ある教授の研究室に遊びに行ったら、「今日はコーヒーを飲んだらすぐに帰ってくれ。明日、授業だから、その準備で忙しくて」と言われました。
日本の大学では、「毎年同じことを教えるのだから、準備なんてたいして必要ない」というのが暗黙の了解というか、半ば常識になっています。ところがその教授は、「学生は毎年変わるから、こちらも毎年、講義内容を最適化しなければならないんだ」というのです。意識の差を見せつけられたような気がしました。
- 1
- 2




