いま、産むこと・産まないことを考えさせる本5選

少子化に歯止めがかからない現代の日本。母子家庭の貧困問題、いじめや虐待といった子どもを取り巻く暗いニュース、先行きの見えない経済状況、こうしたニュースに接し、子どもを持つことに躊躇する人も多いかもしれません。「案ずるより産むが易し」と無責任には言えないいま、出産について考えさせる、気鋭の女性作家の本を紹介します。
小川洋子『妊娠カレンダー』~「おめでた」って、本当に「めでたい」の?
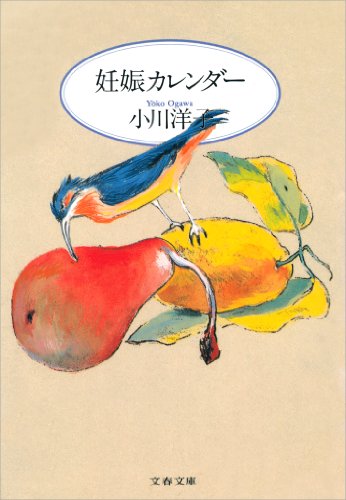
https://www.amazon.co.jp/dp/4167557010/
大学生の「わたし」は、姉夫婦と同居する大学生。ある日、姉が妊娠し、突然のつわりが始まります。姉の好物だと思って「わたし」が作ったマカロニグラタンに対し、
「グラタンのホワイトソースって、内臓の消化液みたいだって思わない? マカロニの形がまた奇妙なのよ。口の中で空洞がぷつ、ぷつ、って切れる時、わたしは今、消化管を食べてるんだなあという気持ちになるの。胆汁とか膵液が流れる、ぬるぬるした管よ
と、姉は言い表します。グラタンが好きな読者は思わず目を覆いたくなるような描写ですが、美味しそうな食べ物がグロテクスな物体に見えてしまうくらい、姉のつわりは深刻なのです。他にも姉は、肉の焼ける匂いに窒息しそうになるから家では料理しないでほしいとか、夜中に突然枇杷のシャーベットを食べたいとか無理難題をふっかけたり、自分の子どもに会うのが怖い、難産になったらどうしようなどと泣き言を言い、家族を振り回します。
情緒不安定な姉の世話に追われるうち、「わたし」は姉に「おめでとう」を言い忘れたのに気づきます。妊娠は「おめでた」と言いますが、そもそも「めでたい」ことなのか? つらそうな姉を見ると、どうしてもそうは思えません。そして、姉を苦しめている「諸悪の根源」は、まだ赤ん坊の形もしていない染色体なのだと、「わたし」は考えるようになりました。
そんな折、「わたし」はバイト先のスーパーで売れ残ったグレープフルーツを大量にもらいます。つわりが終わり、今度は過食が止まらない姉に、それをジャムにして食べさせようと考える「わたし」の頭の片隅にはこんな考えがあるのでした。
危険な輸入食品! 出荷までに三種類の毒薬に浸けられるグレープフルーツ! 防カビ剤PWHには強力な発癌性。人間の染色体そのものを破壊する――「PWHは、胎児の染色体も破壊するのかしら」
妹の仄暗い悪意に気づかず、PWHをたっぷり摂取した姉は、無事出産することができるのでしょうか。妊娠の是非に根底から揺さぶりをかけた、第104回芥川賞受賞作です。
川上未映子『夏物語』~子を持ちたいと願うのは、人間の最大のエゴかもしれない~

https://www.amazon.co.jp/dp/4163910549/
自分の子どもには、この世に生まれてきてよかったと、心の底から思ってほしい。それは全ての親の願うことでしょう。では、もし自分の子どもが、ある日こんなことを言い出したら親はどうすればいいのでしょうか。
お母さんを見ていたら、毎日働きまくっても毎日しんどく、なんでわたしを生んだん、と思ってしまう。これいっこだけでも大変なことやのに、そのなかからまたべつの体をだすのは、なんで。ぜったいに、子どもなんか生まないとわたしは思う。
初潮を迎えた女の子を主人公にした本があって、これでわたしもいつかお母さんになれるんだわ、感動、みたいな、お母さん、わたしを生んでくれてありがとう、とか、本に書かれている生理は、いい感じに書かれすぎているような気がする。
こんなことをノートに書きつけた緑子は小学校高学年。母子家庭でホステスの母・巻子とかつかつの暮らしをしています。緑子は、大人が蓋をしてやり過ごしている、生と性への根源的な疑問を読者に投げてくるようです。日常会話の中でこういった発言をすると、面倒くさい子と思われて引かれてしまうようなことも、緑子は率直に言い表しています。
緑子は、第二次性徴により自分の胸がふくらんでゆくことに嫌悪感を抱いている時、母が豊胸手術を受けようとしていることを知ります。産後、授乳によって形が崩れた胸を元通りにしたいと願う母に対しても、
ほんだら、生まなんだらよかったやん。お母さんの人生は、わたしを生まなかったらよかったやんか
と非常に辛辣です。しかし、ある時、緑子は、自分が好きで生まれてきたわけじゃないのと同様に、母もまた好きで生まれてきたわけでも、好きで苦しい生活を強いられているわけでもないことに思い当たり、母への思いを複雑にしてゆくのでした。
誰も、産んでくれと頼んだ覚えはないという緑子の心の叫びを聞いていると、子どもを持つことは人間の最大のエゴかもしれないということを否応なしに考えさせられます。『乳と卵』で第138回芥川賞を受賞した作家による最新の話題作です。
村田紗耶香『殺人出産』~「10人産めば、誰か1人殺してもいい」という法令で少子化に歯止め!?~

https://www.amazon.co.jp/dp/4062934779/
草食系、セックスレスという言葉が蔓延する昨今。近未来には以下のような世の中がやって来るのかもしれません。
昔の人々は恋愛して結婚してセックスをして子供を産んでいたという。けれど時代の変化に伴って、子供は人工授精で産むものになり、セックスは快楽だけのための行為になった。避妊技術が発達し、偶発的な出産がなくなったことで、人口は極端に減っていった。
そこで政府が少子化に歯止めをかけるために打ち立てた苦肉の策とは、
10人産めば、1人殺してもいい、という「殺人出産制度」
子どもを10人産めば(この世に10人の命を送り出せば)、誰か1人殺したい人を殺してもよい。反対に、子どもを10人産まずに殺人を犯した者については、有無を言わさず子どもを10人産ませる「産刑」を課す。従来の「死刑」より「産刑」の方が、ずっと過酷で「罰」としてはふさわしい。男性であっても、人工子宮を体内に装着する手術をして「産刑」を受けてもらう。
一見、荒唐無稽な設定ですが、この小説は、社会通念をくつがえし、読者に命の重さを鋭く問いかけてきます。それは例えば、中絶手術や出産前の染色体検査は認められているのに、幼児虐待で死なせるのはなぜ罪になるのか、といった問いにも通じるものです。
遠くない未来、「殺人出産制度」は果たして上手く機能するのか、ぜひ本書で確かめてください。
角田光代『八日目の蝉』~子どもを産めない女性に「母性」はないのか、という問い~

https://www.amazon.co.jp/dp/4122054257/
ある未婚女性が、不倫相手と妻との間に出来た赤ん坊を誘拐した、そう聞けば普通、相手への憎しみからそうしたのだ、赤ん坊は女によって虐待されるだろうと予想します。けれど、本作のヒロイン・野々宮希和子は違いました。
秋山丈博はほぼ同時期に、妻・恵津子と、愛人・希和子を妊娠させます。丈博は希和子に堕胎を迫り、これが原因で希和子は子宮内空癒着、つまり二度と妊娠できない身体になります。立場の強い妻は希和子に対し、こんな捨て台詞を吐いたのです。
あなた、自分の子どもを殺したんでしょう。信じられない。あんたが空っぽのがらんどうになったのはその罰じゃないの。殺された子どもが怒ってんだよ。ざまあみろ
自分はもう何も生み出すことができない、“空っぽのがらんどう”だと言われたことに苛まれる希和子。妻が産んだ赤ん坊を一目見たら諦めもつくと、夫婦の留守中に相手宅に侵入し、不注意に放置された赤ん坊と対面します。そこで湧きあがってきた感情は、意外にも愛おしさでした。
東京の学生時代の友人宅、エンジェルホームと呼ばれる名古屋の怪しい宗教施設、住み込みで働ける小豆島の素麺屋。希和子は赤ん坊を連れて各地を転々としながら、逮捕されるまでの4年間を過ごします。
子どもを産みたかったんです。彼との子を産みたかった。でも産めないんです。この子が私の子どもだったらどんなにいいかって思ったんです。四年間、子育てという喜びを味わわせてもらったことを、秋山さんに感謝したい気持ちです
「謝罪」ではなく「感謝」。不倫相手の子を育てる「喜び」。裁判で放った希和子の言葉は、多くの人々の物議を醸し、「母性」とは何かと社会に問うきっかけとなっていきます。
不妊に悩み、よその赤ん坊を誘拐して数年に渡り大切に育てたある女性と、彼女を本当の母だと信じて育った娘。本作を読めば誰もが、彼女を誘拐犯ではなく「母」だと認めざるを得なくなるはずです。
酒井順子『子の無い人生』~少子化の時代、社会の一員として、子の無い人生の是非を問う~

https://www.amazon.co.jp/dp/4041071992/
三十歳以上・未婚・子無しの女性を「負け犬」と定義したエッセイ『負け犬の遠吠え』で人気となった酒井順子は、自身も、未婚子無しの人生を送ってきました。ある日、著者は、こんな話を耳にします。
知人男性は、結婚してから二十数年、子供が出来ないまま過ごし、五十代となりました。そんなある日、ふとした出来心から、男性は三十代の女性と浮気。そしてその女性は妊娠します。知人は、「俺は本当は子供が欲しかったのだ。妻には申し訳ないが、離婚して愛人と再婚し、父になる」ということに。
日本において結婚とは、「子供を作るための行為」という向きがまだまだ強いと分析する著者。結婚しながら子供がいないと、「何のために結婚しているの?」と、周囲から思われ続けることになると指摘します。そこで著者は、結婚していても子どもを持たない、ある女性を取材しました。
私は安倍首相夫人の昭恵さんに、お話をうかがう機会をいただきました。歴代ファーストレディの中で、子供がいないケースは初めてであり、昭恵さんも「嫁として失格」と言われたこともあったとのこと。不妊治療をされたこともありましたが、病院嫌いで長くは続けなかったのだそうです。「もっと頑張れば、子供ができたのかもしれません。けれど私は、子供のいない人生を天から与えられたのだと思って、その中で自分に何ができるのか、と考えています」
少子化の時代、社会の歯車として、やっぱり子どもを産むのが女の「正しい」生き方なのか。産めるのに産まない女は怠慢なのか。「産む機械」と失言した政治家の真意から、不妊治療の現在、子無し族の介護・看取り問題、日本の養子事情まで、タブーになりがちな話題にあえて本音で切り込んだ、社会派エッセイです。
おわりに
妊娠・出産の問題に、これが絶対に正しいということはありません。けれど、子どもを持とうか持つまいか、自分の選択は正しいのかどうかと悩んでいる読者に、これらの本はたくさんのヒントを与え、そっと背中を押してくれるはずです。
初出:P+D MAGAZINE(2019/10/28)

