白石一文著『記憶の渚にて』は直木賞作家による傑作長編!著者にインタビュー!
直木賞受賞作家が放つ最新傑作長編は、予想だにしないラストが圧巻!記憶をテーマにした三部構成の小説は、驚愕の展開をたどるーーその創作の背景を著者・白石一文にインタビューしました。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
直木賞作家が
小説の限界に挑んだ
圧倒的長編小説
『記憶の渚にて』
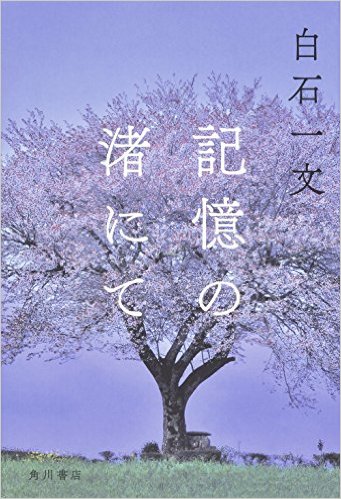
KADOKAWA 1700円+税
装丁/鈴木成一デザイン室
白石一文

●しらいし・かずふみ 1958年福岡県生まれ。早稲田大学卒。文藝春秋に勤務していた2000年に『一瞬の光』を刊行。09年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で山本周五郎賞、10年に『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞。WOWOWでドラマ化された『私という運命について』は30万部を超えるロングセラーになっている。『不自由な心』『すぐそばの彼方』など著書多数。父の故白石一郎さんも直木賞作家、弟文郎さんも作家という作家一家である。170㌢、65㌔、O型。
いたずらに死の恐怖を持たされている人に
自分自身が大切なんだとわかってほしい
世界的ベストセラー作家の兄壮一(筆名手塚迅)が一人暮らしのアパートで自殺を図る。連絡を受けて、弟の純一が郷里の地方都市から上京するが、発見者の女性は姿を消していた。兄が雑誌に書いた「ターナーの心」というエッセイに、純一は奇妙な記述を発見する。そこに書かれている事実は出鱈目で、自分の記憶とは大きく異なる。これは何かのメッセージなのか。
純一は、兄の死の真相を探ろうと動き始める。
*
記憶をテーマにした三部構成の小説は、第一部で驚愕の展開をたどり、その後も息をつかせず九百枚を一気に読ませる。
タイトルからもわかるように、人間の記憶のに迫る小説である。たとえば壮一には〈記憶が見える〉し、純一は、人や動植物や物質が存在した痕跡を〈記憶の匂い〉として感じ取ることができる。
「もともと、記憶っていうのは、自分の中だけに存在するのではなく、外部にもあるんじゃないか、という漠然としたイメージを小さいときから持っていたんです。自分の外側にある何かと交信することで、自分という像が結ばれる感じというんでしょうか。それを小説として面白く書いてみたい、という気持ちがありました」
長年あたためてきた記憶にまつわる仮説が小説をダイナミックに動かし、やがては、〈生命とは記憶〉、自分自身を〈「私という人生」を記憶する装置(ないしは容器)〉と見なす思考へとたどりつく。
初出は新聞連載だが、細かなプロットはつくらず、大まかなイメージだけで書きすすめていったという。
「スキーのスラロームで旗門ってあるじゃないですか。通らなくちゃいけない旗門はだいたい見えてるんですよね。通らなくていい旗門もあるし、旗をなぎ倒していってもいい。そんなイメージで書いていきました。最後のほうはもう旗門だらけで、自分で滑りをコントロールできる状態ではなくなってくるんですけど、絶対に辻褄は合う、という確信はありました」
偽名を使い、姿を消した発見者の女。純一にあてた兄の遺書。〈ホホジロザメ〉なる人物から兄に送られてきたメール。が新たな謎を呼び、小説は波乱万丈の展開をたどるが、この作品をミステリーとして書いたつもりはないそうだ。
「ぼくには小理屈を書きたいって欲求がどうしてもありまして(笑い)。ミステリーばかり求められる小説の状況ってどうなの、という思いもあり、一方で、そういうものならいつでもできる、って気持ちもあったんです。自分も年をとってきて、そんなことを言うなら書けないことには始まらないので、今回は、この人はいったいどうなるんだろうという興味で読者を引っ張っていく話のつくりかたを徹底してみました。でもやっぱり、この起承転結はミステリーではないですね」
兄弟、兄妹、姉弟、姉妹など、さまざまな血のつながりが小説の中で明らかになり、見えなかった運命の糸が結ばれていく。
〈「お姉ちゃんは、もう来年の桜は見られへんなあ」〉。幼いときに、桜の木の下で何者かの〈声〉を聞くという神秘的な体験でつながっている壮一と純一兄弟のように、白石さん自身、双子の弟(作家の白石文郎さん)との間で、もしかしたらそうした体験を共有したことがあるのだろうか。
「以心伝心的なものなら全然なかったです。弟はぼくとは違っていて、大学受験の前でも、ぼくが一生懸命、鉢巻しめて頑張ってる横で、彼は小説を読んでいました。そういう意味で、この小説に出てくる兄弟でいうなら、ぼくは兄貴(壮一)のほう、なにごとにも過剰なタイプですね」
だれもが共通体験
できるキーワード
アトピーに効く石鹸の販売や、巨大な新興宗教の教団、〈人工肉〉の開発など、どこかいびつな今という時代を照射する装置が次々に登場するのも白石さんの小説の特徴である。
「小さいときからぼくは異様に記憶力がいいんです。人から何か話を聞いたら、忘れようにも忘れられない。ふつう、食べたら出すじゃないですか。それが自然に出ていかないから、つねに脳の便秘みたいな状態です(笑い)。この小説で書いた新興宗教にしても、アトピーやてんかんといった病気にしても、もともと記憶の中に蓄積されていた話が、人との会話で刺激されて、すっと出てきたものを書いていますね」
けがをした純一に、教団の教区長が手当てする場面がある。〈教区長の掌が足に触れて一分もたたないうちから、次第に痛みが薄れていくのが実感できた〉。医学によらず人を癒す力や、〈生まれ変わり〉〈呪い〉といった、現代科学では説明できない事象も出てくる。
「時代や国を超えて、だれもが共通体験できるようなキーワードっていくつかあるでしょう? たとえば、生まれ変わりという仮説を導入するとわかりやすく整理される事実があったりします。もちろん、そうじゃない、という反証も山のようにあるわけですが、じゃあどう説明すればいいんだろう、ってことはずっと考えていますし、そういうことこそ小説で書いてみたいと思うわけです。
ただ、そういうものを別次元で利用している人たちもいて、それはすごくいやなんですよね。人を癒す力だって実際にあると思いますけど、さほどたいしたことでもない。最低でも、不死ぐらい実現してくれないと木戸銭は払えません(笑い)。そんなことで担保されるような教団をあがめる必要は全然ないと思います」
南にある地方都市から東京、大阪、広島、ロンドンへと小説の舞台は移り、思いがけないラストが待ち受けているが、主人公はそこで〈懐かしさを呼び寄せるあたたかな記憶〉の海に戻ったという感慨を抱く。
取材の中で白石さんは、科学技術や経済の発達、政治制度も、すべてが私たちひとりひとりを、取るに足らない小さな存在だと感じさせる方向に導いている、と語った。小説は抵抗、人間性回復の試みだろうか。
「そこまで強い意識はないですけど、いろんなことを疑わないといけない。ぼくたちはすぐに何か大きなものに身を委ねて自分を捨てようとするけど、それはいたずらに死の恐怖を持たされているからなんですよね。そのことをこれまでずっと書いてきたし、読者には自分自身が大切なんだとわかってもらいたいと思います」
□●構成/佐久間文子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年7.22/29号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/08/02)

