『蜜蜂と遠雷』は傑作青春群像小説。
3年ごとに開催される国際ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、音楽を描いた、青春群像小説。創作の背景を、著者にインタビューしました!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
人間の才能と運命、そして音楽を描き切った傑作青春群像小説
『蜜蜂と遠雷』
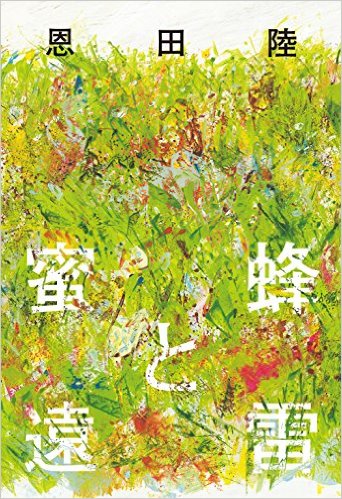
幻冬舎 1800円+税
装丁/鈴木成一デザイン室
装画/杉山 巧
恩田 陸

●おんだ・りく 1964年宮城県仙台市生まれ。早稲田大学教育学部卒。会社勤務の傍ら92年に第3回日本ファンタジーノベル大賞最終候補作『六番目の小夜子』でデビュー。05年『夜のピクニック』で第26回吉川英治文学新人賞と第2回本屋大賞、06年『ユージニア』で第59回日本推理作家協会賞、07年『中庭の出来事』で第20回山本周五郎賞。ミステリー、SF、怪奇小説や恋愛小説、エッセイまで幅広い作風で読者を獲得。映像化も多数。159㌢、A型。
愚かで醜い面までも音楽や文学にできるのは人間だけに許された最も美しい昇華のさせ方
〈ミュージック。その語源は、神々の技だという〉。
幼い頃から練習を積んでなお、一握りの人間だけが神秘に触れ、プロになれる音楽の世界。そんな悲喜こもごものドラマが交錯する〈芳ヶ江国際ピアノコンクール〉が、恩田陸著『蜜蜂と遠雷』の舞台だ。執筆7年、取材も含めれば12年がかりという文字通りの大作では、国籍も来歴もそれぞれ違う4人の出場者を軸に、一次予選から二次、三次を経てオーケストラと共演できる本選まで、2週間に亘る選考過程を具に追う。
火種は没後もなお敬愛を集める世界的音楽家〈ユウジ・フォン=ホフマン〉の推薦状にあった。彼は養蜂家の父親と流浪生活を送り、ピアノすら持っていない無名の16歳〈風間塵〉を愛弟子と呼び、こう書き遺した。〈彼は『ギフト』である。恐らくは、天から我々への〉〈甘い恩寵などではない。彼は劇薬なのだ。中には彼を嫌悪し、憎悪し、拒絶する者もいるだろう。しかし、それもまた彼の真実であり、彼を『体験』する者の中にある真実なのだ〉……。
まるで小説と読者の関係をも挑発するような挑戦状と、愛すべき天才たちが各々の音楽を発見していく過程に、著者が託した思いとは?
*
「入賞者が海外のコンクールでも好成績を残しているゲンのいい大会だと聞いて、浜松国際ピアノコンクールを見に行ったのが第4回の時。以来3年ごとの開催に4回、結局12年も通いつめてしまいました(苦笑)。
そもそも数値化できない音楽に点数をつける矛盾を全員が承知していることが興味深いし、明と暗がハッキリ分かれる点もドラマとして面白い。そうした敗者が死屍累々といる上に今の音楽があること自体、凄まじい話ですし、音楽の本質についても一度、真正面から書いてみたかった」
自身、高校生までピアノを続け、大学時代はビッグバンドでアルトサックスを担当。が、「ここまで人生がかかった場はさすがに縁がない」という恩田氏は無類の想像力と描写力をもって、天才だけに見える景色や孤独に肉薄してみせる。
近年躍進著しい芳ヶ江では、書類選考の落選者にも再挑戦の機会を設けており、中でも〈嵯峨三枝子〉ら、毒舌3人組が審査を務めたパリ会場に、あろうことか遅刻してきたのが件の天才〈蜜蜂王子〉だ。尤も三枝子は優等生など興味はない。〈求めているのは「スター」であって、「ピアノの上手な若者」ではない〉〈それほどに、「あの瞬間」には完璧な、至高体験と呼ぶしかないような快楽があるのだ〉
しかしその三枝子ですら、圧倒的な音で聴く者を呑み込む〈自然児〉の演奏には拒絶感を禁じ得ず、〈快楽と嫌悪は表裏一体〉だった。それでも〈もう一回聴いてみたくない?〉という審査員仲間に丸め込まれ、塵は、日本へ向かうこととなる。
さらには天才少女として華々しくデビューしながら、母親の死を境に弾く意味を見失い、演奏会から逃亡した過去を持つ20歳の音大生〈栄伝亜夜〉。大手楽器店に勤める妻子持ちで、〈生活者の音楽〉を標榜する28歳の最年長者〈高島明石〉。そして実力・人気共に群を抜く〈ジュリアード王子〉こと、日系三世を母に持つ〈マサル・カルロス・レヴィ・アナトール〉19歳と、今回も幅広い才能が集結した。
審査員も前述の3人組や、マサルの恩師でジュリアード音楽院の名教授〈ナサニエル・シルヴァーバーグ〉らが顔を揃える。ナサニエルは三枝子の元夫にしてホフマンの元弟子でもあった。またマサルは幼い頃、自分を音楽の道に導いてくれた日本の少女〈アーちゃん〉を探しており、一次予選の90人から6人が本選に進み優勝を競う熾烈な闘いに、まだ年若い彼らの恋心までが絡んでくるのである。
今や我を失う程の感動は危険物扱い
〈世界はこんなにも音楽に溢れている〉と、風間塵は蜜蜂の羽音やふとした自然にも音楽を感じ、またナサニエルはマサルの高い才能をこう評した。〈君は、早熟というのじゃない〉〈「知っている」のさ。最初からね〉
一方、ある出場者の技巧を駆使した熱演を前にして、〈最近のハリウッド映画はエンターテインメントではなく、アトラクションである〉と揶揄したある映画監督の言葉を思い起こすのが感性鋭い元天才少女・亜夜だ。なるほど凄いと感心はするが、〈感動はしない〉と。
「私も映画や音楽に限らないアトラクション化は常々感じていて、まあマッサージみたいなものですよね。ハイ、ここは感動のツボ、泣けるツボって、感動のための感動を消費すればそれで安心というか。でも私は感動って、もっと違うところにあると思うんですよ。
前々回の浜松国際でも、本選でブラームスの1番を弾いた女の子の演奏がもう、震えがくるほど素晴らしくて、気づくと聴衆もオケも涙を流していた。私はその光景にもグッときたくらいなんですが、今や我を失うほどの感動は危険物のような扱いなんですかね……」
現にナサニエルは、聴衆を解放し、〈広くて思いがけないところに連れ出してゆく〉塵の音楽は、他でもない聴き手の自我を剥き出しにすると分析する。
〈根こそぎ持っていかれる〉〈どこへ行く〉〈どこに行きたいんだ、おまえは〉
「人間、わからないものほど怖いものはないですからね。ただその恐怖を乗り越えて何かに触れた時の全能感や、一瞬に永遠を感じるような瞬間は書いていても楽しいし、4人が弾く曲目に関しても何度も繰り返し聴いて、選曲や聴こえ方がそのまま人物描写になるように書いたつもりです。それは小説にしか、できないことですから」
例えばラフマニノフ二番を聴きながら、マサルは確信する。〈人間の最良のかたちが音楽だ〉と。そもそも芸術はこの世界や宇宙の在り様を映して生まれ、光も影も全て呑み込んでこそ、音楽は美しいのだ。
「昔、『どんな苦労も音楽にしちゃえば美しい』と言ったチェリストがいて、人間のいい面だけを音楽にしても確かに心は動かない。愚かで醜い面も音楽や文学に昇華できるのは人間だけに許された〈オプション機能〉で、それが最も美しい昇華のさせ方なんじゃないかなって、私自身、再確認させられた思いがします」
塵やマサルや亜夜や明石を媒介として、本来あるべき姿へと解放された音楽が、本書には無尽に鳴り響いている。その自由な在り様がとかく形骸化した私たちの感動の解放をも、喚起しているように思えてならない。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年10.28号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/10/29)

