芦沢央『貘の耳たぶ』が描く切なすぎる「事件」。著者にインタビュー!
同じ日に同じ産院で男の子を産んだ2人の母親―子供をすり替えた繭子と、すり替えられた郁絵の、4年余りを追う。その切なすぎる「事件」の慟哭の結末とは?創作の背景を著者にインタビュー!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
若手女流作家のホープが切なすぎる「事件」を描く慟哭の書き下ろし長編
『貘の耳たぶ』
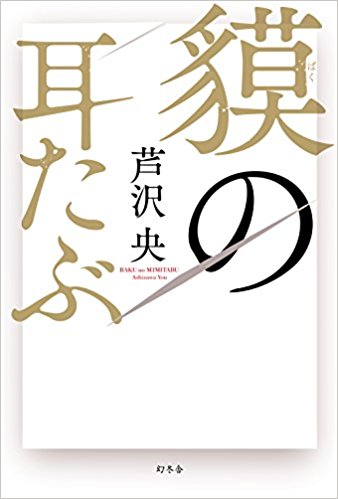
幻冬舎 1700円+税
装丁/bookwall
芦沢央

●あしざわ・よう 1984年東京生まれ。千葉大学文学部卒。出版社勤務を経て12年に野性時代フロンティア文学賞受賞作『罪の余白』でデビュー、同作は15年に映画化された。「受賞の2週後に妊娠が発覚して。今回の話には子供を保育園に預けて小説を書いている自身の葛藤も反映されています」。15年「許されようとは思いません」で日本推理作家協会賞短編部門候補、同短編集で吉川英治文学新人賞候補。他に『今だけのあの子』等。156㌢、A型。
道を誤るのも人間なら、生き直せる強さをもつのも人間。その両方を書いていきたい
最新作『貘の耳たぶ』は、同じ日に同じ産院で男の子を産んだ2人の母親―子供をすり替えた〈石田繭子〉とすり替えられた〈平野郁絵〉の4年余りを追う。当初は「じつは犯人は実の母親だった」というところを後半で明かす構成のミステリーだったという。
「けれどあらすじを話した父から、母親が自分の子供を取り替えるなんてあり得ないと言われて動機について説明していくうちに、これを正面から書くべきじゃないかと思うようになりました。そうしてまったく構成を変えて書き直しているうちに、繭子の子供のタグがたまたま外れ、それを郁絵の子供に付けてしまったこと自体はほとんど事故だったのではないか、と思うようになっていきました。むしろ罪を告白しようとしてはしそびれ、4歳まで〈航太〉を育ててしまった繭子の心理にミステリー性を感じるようになったんです」
*
デビュー作『罪の余白』を始め、イヤミス界の新星的扱いを受けることも多い芦沢央氏。だが、女子間の格付けや不条理にも怯まない書きっぷりはその実、世間の常識や欺瞞を疑い、人々が何に囚われているかを正視する真摯な視線を感じさせる。
「私自身、『自分のことが書いてある』と思える小説に何度も救われてきました。だからこそ、人間の弱さやずるさ、欲望というネガティブな側面を描くことから逃げたくないという思いがあります。ふとしたボタンの掛け違えで道を誤るのも人間なら、そこから生き直せる強さもあるのが人間だと信じてもいて、その両方を書いていきたいんです」
本書にも、わかりやすい悪人はいない。繭子は、保育士として働いてきたこともあって育児に慣れている郁絵に対して劣等感を抱いており、彼女の強さからくる、時に無神経な言葉に追い詰められる。また、繭子は弁護士の義父と明るい義母を持つ夫の〈旭〉の〈すこやかさ〉に気後れを感じてもいる。繭子の母は元々は教師だったが、ある事件を機に心身の均衡を欠き、実家にゴミを溜めこむようになった。そうした事情を旭にすら隠していたからだ。
「でも、郁絵はたとえば看護師に対して『看護師さん』ではなく、きちんと名前で呼びかけるような気遣いができる側面を持っているし、繭子の母親が心身の均衡を崩すきっかけとなった出来事は、彼女が強く正しい人だったからこそ起きたものなんです。そして、旭がすこやかなのは、もちろん悪いことではありません。ただ、正しさって優しくないと私は思うんです。正論には誰も反論できないから」
そして、この
「母乳神話や3歳児神話など、
だが、それは所詮、虚像の積み重ねでしかない。本書でも、繭子が郁絵に、郁絵が繭子に対して、それぞれ相手の方が自分よりも母性があるんじゃないかと考えるシーンが出てくるが、それは結局のところ、相手の言動を勝手に解釈しているだけでしかない。
「だからこそ、様々な
母性の象徴が代替し得るという希望
本書のタイトルにある〈耳たぶ〉という単語は、〈耳たぶの感触はおっぱいの先の固さと同じなんだって〉という、ある熟練保育士の台詞に由来。
「私自身が以前、知人から聞いて驚いた話だったのですが、おっぱいという母性の象徴としてとらえられがちなものが、耳たぶという誰もが持っている、それこそたとえば男性でも持っているものと、少なくとも感触だけは代替し得るということに、希望のようなものを感じたんです」
物語は後半、繭子の子に〈
「結末を決めず、一緒に郁絵と悩みながら答えを探していきました。旭の母親は〈孫が増えたような気もしているの〉と言います。それは素敵な考え方だし、そう考えてみんなで育てるというのは一つの理想ではあると思います。でも、この物語の場合、事件を引き起こしたのが繭子だからそうはいかないんです」
そして、その事実を知った郁絵が、事件そのものについてだけではなく、こうなることを知っていた繭子を
郁絵は繭子に〈あなたなんて、母親じゃない〉という言葉を突きつける。
「ですが、そのまま終わるわけではないんです。彼女たちは何を得て、何を失うのか、その先に彼女たちが目にすることになる景色はどんなものか―ぜひ本書で確かめていただければ幸いです」
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2017年5.5/12号より)
初出:P+D MAGAZINE(2017/08/30)

