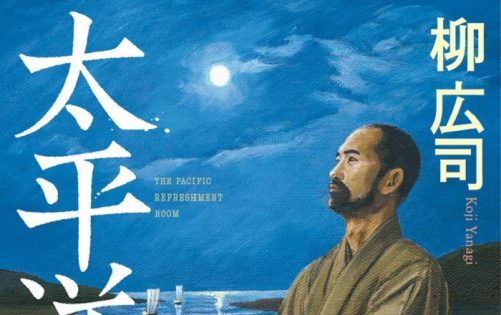【著者インタビュー】柳 広司『太平洋食堂』/「ひげのドクトル」は、なぜ死ななければならなかったのか
周囲から「ドクトルさん」「ひげのドクトル」と呼ばれ、慕われていた大石誠之助。彼はなぜ罪に問われ、消されてしまったのか――渾身の歴史長編小説が書かれた背景を、著者に訊きました。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
本誌人気連載が早くも単行本化! 誰からも愛された「ひげのドクトル」は
なぜ歴史から消されたのか―人気作家が心血を注いだ渾身作
『太平洋食堂』
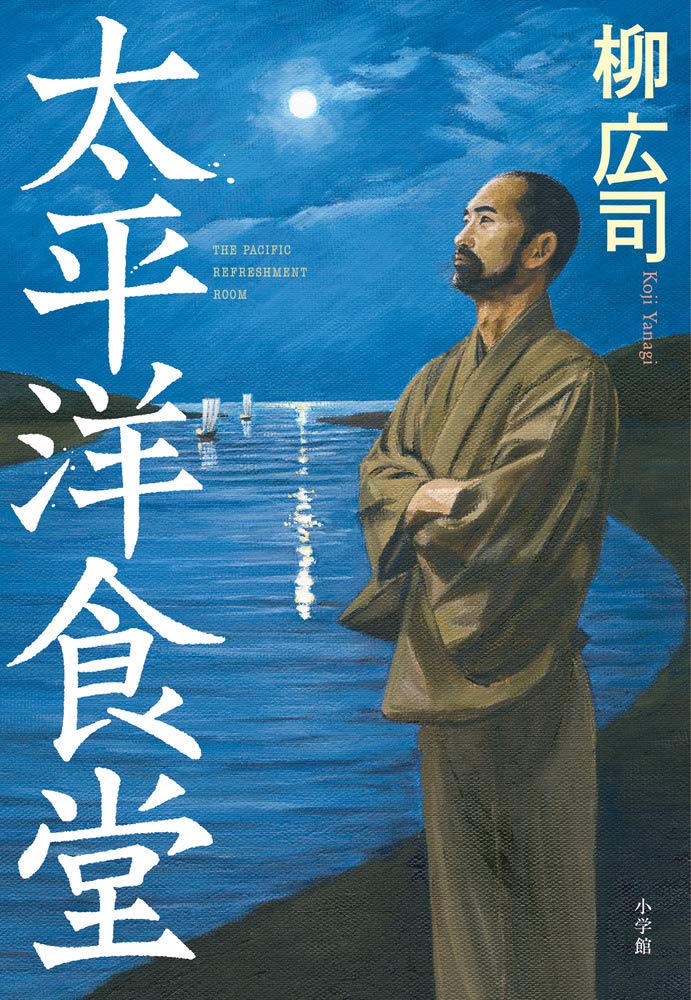
小学館
1800円+税
装丁/bookwall 装画/吉實 恵
柳 広司

●やなぎ・こうじ 1967年三重県生まれ。神戸大学法学部卒。2001年『贋作「坊っちゃん」殺人事件』で朝日新人文学賞受賞。09年『ジョーカー・ゲーム』で吉川英治文学新人賞と日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門をW受賞。陸軍中野学校を彷彿とさせる同作はその後「D機関シリーズ」としてベストセラーに。著書は他に『はじまりの島』『新世界』『トーキョー・プリズン』『漱石先生の事件簿 猫の巻』『象は忘れない』『風神雷神』『二度読んだ本を三度読む』等。177㌢、65㌔、A型。
言葉の選択や題材一つに書き手の社会的態度は現れるし、作品の面白さに繋がる
大石誠之助、享年四十三。
周囲の者たちから〈ドクトルさん〉あるいは〈ひげのドクトル〉と呼ばれ、親しまれていた彼は、なぜ罪に問われ、死ななければならなかったのか―。
物語は、誠之助自らが厨房に立ち、人々に料理をふるまった食堂の開店日、明治37年10月1日に幕を開ける。〈皮肉とユーモアと反骨の
大石誠之助は1867年紀州・新宮生まれ。アメリカ・カナダへの留学経験を経て、故郷に戻って医院を開く。幸徳秋水、堺利彦、与謝野鉄幹らと親交し、治療代は貧乏人からはお金をとらない〈無請求主義〉。食堂では、今でいうこども食堂のようなこともやっていたらしい。
そんな彼のあり方に○○主義と名前が付けられた瞬間、既に悲劇は始まっていたのかもしれない。
*
「誠之助を書こうと思った直接のきっかけは、18年1月に新宮市議会が彼を名誉市民とすることを決議した記事を新聞で読んだことです。デビュー以来、この時代のことを書けないかと色々調べて準備をしていたのですが、何を軸に書けばいいのかがピンとこなくて書きあぐねていました。そこに飛び込んできた名誉市民の一報で全部が繋がったというか、例えるなら、過冷却状態のコップの水に氷を入れたら全体が一気に固まるような、そんな感じがしました」
大政奉還の年に生まれた誠之助は夏目漱石や正岡子規らと同い年。22歳で渡米し、開業後もインドまで伝染病の研究に赴くなど、〈何でも自分でやってみないと気が済まない性分〉だ。36歳の時には、病院の向かいに甥で後に文化学院創設者となる西村伊作の絵を看板に掲げた西洋風の建物を自ら建てる。その食堂を彼は「太平洋食堂(パシフィック・リフレッシュメント・ルーム)」と呼び、当時珍しい洋食を提供する傍ら、文化交流や教育の場としても広く開放した。
ちなみに彼の口癖は、〈(自分が)楽しくないと人はついてこない〉。喩え話を交えて難しいこともわかりやすく語る誠之助の講演は常に好評で、彼の周りには幼い子供から歴史上の人物まで、自然と人が集まった。
「知識というのは本質的に内に閉じていきがちですが、それを皆で分かち合おうとした誠之助は真の知識人、インテリゲンチャだったと思います。誰もがおかしいと思ったことはおかしいと言える社会を目指し、立場の弱い人に諦めを説くのは耐え難いと書く彼にとって、常に問題は今、目の前の相手をどう救うか、でした」
彼が食堂を開いてから、明治44年1月、〈刑法七十三条事件〉で処刑されるまでを追う本作では、古くから熊野川の水運と材木業で栄えた新宮の町や、揃って個性的な誠之助の一族など、理不尽な結末に比して、物語の陽性な世界観が印象的だ。
「新宮といえば中上健次の物語世界が有名なので、今回は中上の新宮とは違う新宮をいかに描くかが最初のハードルでした」
また柳氏は舞台である新宮の方言に〈敬語がない〉ことも注目すべきだという。
「実際に何度か足を運び、地元の人たちと言葉を交わすうちに、誠之助の行動原理のようなものが理解できる気がしました。それほど、人間関係や社会の在り様は、言葉によって規定されているということです」
司馬さんとは違う「明治」を
第9章「社会主義とは何か?」や第14章「足尾銅山事件」など、書き手自らが登場し、最新の研究成果も踏まえて解説を加えるくだりは、司馬作品さながらだ。
「日露戦争勝利までを日の当たる場所から描いたのが司馬さんの明治だとすれば、私はそうではない立場から日露後の明治を書こうと」
その日露戦争に関しても、〈国家や資本家(金持ち)のために、日露両国の労働者(貧乏人)が殺し合う必要はない〉と誠之助の態度は一貫し、〈社会主義者であったから戦争に反対したのではなく、戦争が嫌いであったから社会主義者を名乗るようになった――案外、その辺りが真相なのかもしれない〉。
目の前で困っている人を一人でも救うべく奔走する誠之助を〈かれは根っからのリアリストなんだよ〉と幸徳が評したように、その思想以前、宗教以前のあり様は、人間的と言う他ない。
「本来国家が当然行なうべき経済政策をアベノミクスと呼んだ途端、特定首相在任中の経済動向へと論点がズレるように、誠之助を“主義者”と呼ぶことで本来知られるべき実像が置きざりにされてしまうのは、あまりにももったいないことです」
誠之助や幸徳ら、既に他人とは思えない登場人物のうち12名までが処刑された事件の顛末もまた、法の言葉の曖昧さが恣意的に利用された一例といえる。
「私は殊更に政治的なことを書いているつもりはなく、言葉の選択や題材一つにも書き手の社会的態度は現れるし、作品の面白さに繋がる場合もあると思っています。井上ひさしさんの原爆を扱った一連の作品もそうでしょう。歴史なり社会に関して作家が自らの考えを表明することが、世界のどこかで今も誰かが殺され、飢えに苦しんでいる事実と直接繋がるかもしれない。小説というメディアはそうやってもっと自由に可能性を追求していいはずです」
言葉に希望を託すリアリストという点では著者も同様だ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2020年2.14号より)
初出:P+D MAGAZINE(2020/07/05)