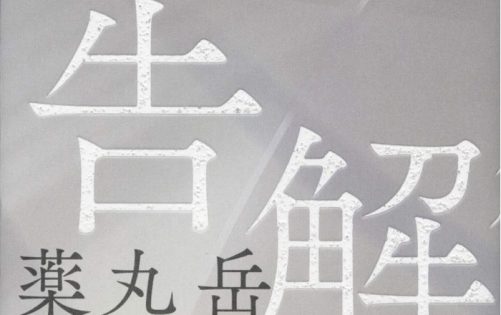【著者インタビュー】薬丸 岳『告解』/轢き逃げ事故の「加害者」視点で、真の贖罪の形を問う
高熱を出した夫のために買い物に出た81歳の主婦が、車に轢かれて200メートル近く引きずられ死亡した。犯人は人気教育評論家の息子。しかも飲酒運転とあって、世間は一家を徹底的に糾弾するが……。著者初の加害者視点に挑んだ長篇。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
自分が轢き逃げ事故の「加害者」になったら――〝罪〟と〝償い〟を問い続けてきた著者が満を持して放つ長篇
『告解』
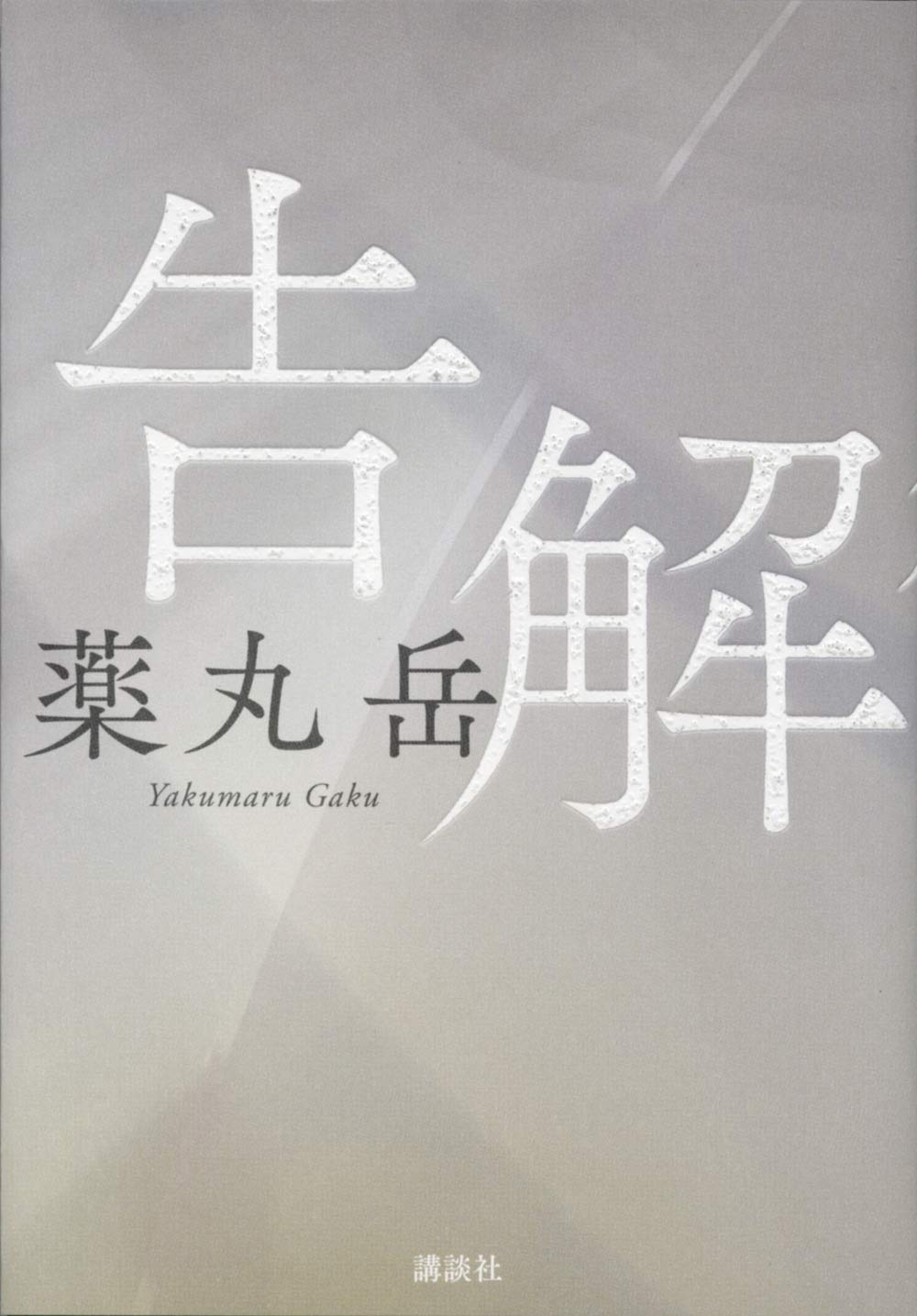
講談社
1650円+税
装丁/岡 孝治
薬丸 岳

●やくまる・がく 1969年兵庫県生まれ。駒澤大学高校卒業後、劇団員、旅行会社勤務を経て、2005年『天使のナイフ』で第51回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。16年『Aではない君と』で第37回吉川英治文学新人賞、17年「黄昏」で第70回日本推理作家協会賞短編部門を受賞。著書は他に刑事・夏目信人シリーズ(『刑事のまなざし』『その鏡は嘘をつく』等)や、『闇の底』『虚夢』『悪党』『死命』『友罪』『神の子』『蒼色の大地』等。178㌢、58㌔、O型。
罪を認め悔い改められるか否かは当人の人間性や他者との関係の築き方にもよる
冒頭に〈父に、母に〉と献辞のある薬丸岳氏の新作『告解』は、「私にしては珍しく、ラストに至るまでほぼ一晩で一気に物語の骨格ができた作品」だとか。
「実は昨年、父を亡くしました。その父親と同年代の老人が、過失とはいえ人の命を奪ってしまった若者に何を伝えようとしたのかという、最後のシーンがしっかり目に浮かんだんです」
発端は平成21年11月21日深夜。高熱を出した夫のために雨の中、近所まで氷を買いに出た埼玉県上尾在住の主婦〈
やがて犯人は、バイト帰りに酒を飲み、帰宅後に父親の車で再び外出した〈
自分にすら言い訳を重ね、逃げてばかりの翔太を主人公に、
*
少年法の限界と問題点を問い、大きな話題を呼んだ乱歩賞受賞作『天使のナイフ』から15年。「罪と人」を巡る、重く過酷な現実からも目を背けない真摯な姿勢は、読者からの信頼も厚い。
「もともとは『刑事・夏目信人』シリーズの長編を書き下ろす約束で、一応脱稿もしていました。それを大幅に改稿しようとした矢先に、父が入院したのです。父は中軽井沢の自宅に1人住まいでしたので、関東にある自分の仕事場と向こうの病院の行き来で忙しくするうちに、次第に作品への熱が冷めてしまったんです。
そして父の死後しばらくして浮かんだのが、最愛の妻を失った元教師〈法輪
事件のあった平成21年は危険運転致死傷罪の成立前だが、飲酒運転は犯罪だと翔太も自覚はしていた。が、冷戦中の恋人〈綾香〉から〈すぐに会いに来てくれなければ別れる〉とメールがあったことや、その夜は両親が留守で車が使えたこと、そして助手席の愛猫に気を取られた次の瞬間に衝撃音と悲鳴を聞いたことなど、あくまでも自らの
「彼の弱さや狡さに読者が多少は感情移入できなければ主人公は務まりませんし、『自分も同じ立場だったらそう思うかも』と『何だよこいつ許せない』の両立が、加害者を描く上で最も難しかったかもしれません。
犯罪に限りませんが、自分の身勝手な行動が取り返しのつかない事態を生んだ時に、自ら罪を悔い、謝罪できるのがもちろん一番いい。ただ、怖くてなかなかそうはできないのも事実です。外出自粛下で宴会に出かけ新型コロナに感染しても、自分の不注意のせいじゃなく運が悪いんだと思いたがる人は多いでしょうし、まして世間に散々叩かれた翔太が都合の良い考えに逃げたくなるのもわからなくはない。ただそうやって楽な方に流されて生きるのが本当にいいことなのか、僕自身が問いたい気持ちもありました」
罰は免れても心は偽れない
第1章では事件発生から収監、2章では刑期を終えた翔太が派遣で働き、生活を立て直すまで。そして3章では晴れて介護士の資格を取り、綾香とも新たな関係を築き始めた彼を待ち受ける数々の落とし穴と出会いが、翔太や綾香、二三久や長男〈昌輝〉の視点で描かれる。特に注目すべきは、探偵事務所に翔太の消息を調べさせた二三久の、出所後の翔太との
なぜか裁判を一度も傍聴しようとせず、同居を持ち掛けても〈やらなければならないことがあるんだ〉と言って実家に残った父のことが、名古屋で妻子と暮らす昌輝は心配でならない。だが当の二三久は、彼を慕う元後輩教師〈永岡〉の協力を得て、翔太が住む北本市内の安アパートに部屋を借りる。そして偽名を使って翔太や綾香と近所づきあいを始めるのだ。
だが、事件当時84歳だった二三久も今や89歳。探偵事務所に毎週、翔太のことを報告するよう頼んだものの、日に日に記憶が薄れていく状態だ。それでも忘れたくないことはペンで座卓に直接書きつけ、翔太たちと関わり続ける彼の、果たして「やるべきこと」とは?
さて翔太が罪と向き合う過程で大きな役割を担うのが、1つは父・敬之の手紙、もう1つが二三久の存在だ。面会や裁判にも顔を見せず、母親と離婚後、最期は酒に溺れて死んだという父親を、翔太は〈アクリル板越しでいいから、父に会いたい〉と思うほど慕い、同じ大学を志すほど尊敬もしていた。
「全く違う道に進みながら、社会人、家庭人として父を心底尊敬する私に、そこは結構近いかもしれません」
その父が残した手紙を読む勇気が出ずにいる翔太が、被害者の遺族と知らずに二三久に出会い父への思いを吐露するシーン。また翔太が被害者の〈亡霊〉に悩まされていることを告白するシーン。さらには、ある人物が、愛する者を失う度に後悔を募らせるシーンなどからは、人は人との間にこそ償いや赦しを見出せる存在であってほしいという、著者の祈りすら感じさせる。
「自分の罪を本当に認め、悔い改められるかどうかは、自分自身の人間性が問われるのはもちろんのこと、誰と接し、どんな関係を築くかにもよると思います。
例えば森友問題で文書改竄を命じた人たちも、このままだんまりを決め込めば訴追は免れるかもしれない。でも何か不幸なことがある度に『あの時の報いだ』と思うなど、何らか自分に返ってくる感情はあるはずです。そういう、司法で贖えない罪のことを今作では書きたかったです。翔太が亡霊に苦しむということはまだ救われる余地はあります。自分の心を偽れないのは、心をまだ持っているという証拠ですから」
彼が人間に戻れるかどうかの瀬戸際に二三久や綾香がいて、亡き父の手紙まであったことに感謝したくなる。〈亡くなった人には何も伝えられない〉からこそ、今を偽らず、また逃げずに生きたいと思わせる、苦くて優しくて真っ直ぐな小説だ。
●構成/橋本紀子
●撮影/田中麻以
(週刊ポスト 2020年5.8/15号より)
初出:P+D MAGAZINE(2020/09/02)