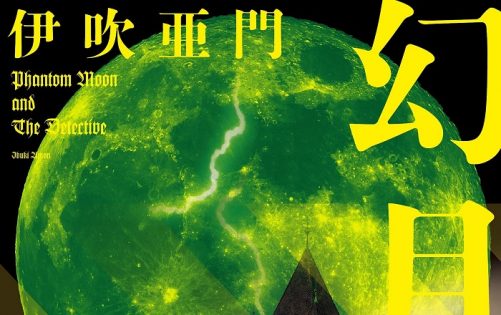【著者インタビュー】伊吹亜門『幻月と探偵』/昭和10年代の満州を舞台に、本格推理+近現代史を見事に融合
時は昭和13年。孤高の私立探偵・月寒三四郎は、国務院の役人から急逝した秘書の死の真相を究明するよう、直接依頼を受けるが……。いま注目のミステリ作家による、本格歴史推理小説!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
デビュー作で注目を集めた平成生まれの駿才による歴史本格ミステリの進化形!
『幻月と探偵』

KADOKAWA
1925円
装丁/坂野公一(welle design)
伊吹亜門

●いぶき・あもん 1991年名古屋市生まれ。同志社大学卒。在学中はミステリ研究会に所属。2015年、「監獄舎の殺人」で第12回ミステリーズ!新人賞を受賞。これを連作化した『刀と傘 明治京洛推理帖』で18年にデビュー。翌年第19回本格ミステリ大賞を受賞した他、「ミステリが読みたい!2020年版」国内篇第1位に。長編『雨と短銃』も好評。「岸信介を書いたのは満洲には欠かせない人物だからで、現政権を批判する度胸は私にはありません(笑い)」。171㌢、78㌔、B型。
人間の心理が剥きだしになるのは動乱期。満洲を書く以上、相応の知識や覚悟が要る
同志社大学ではミステリ研究会に所属し、4回生の時、「卒業記念に応募した」一作入魂の短編、「監獄舎の殺人」で第12回ミステリーズ!新人賞を受賞。同作を連作化した『刀と傘』では幕末〜明治初期の京都を、最新作『幻月と探偵』では昭和10年代の満洲を舞台に、本格推理+近現代史を見事融合させた点に、平成3年生まれの俊英、伊吹亜門氏の手柄はあるといえよう。
主人公は
*
「私はミステリ用語でいうところのホワイダニット、つまり動機や
特に歴史好きというわけではないんですが、子供の頃は阿川弘之先生の海軍提督三部作を読んだり、抵抗感は少ない方だと思う。世代的に太平洋戦争や満洲に関しては『
時は昭和13年。協和会の甘粕正彦が推すこの探偵が、要はお眼鏡に適ったということだろう。椎名から特急あじあ号の切符を手渡され、新京に飛んだ月寒は、先頃急逝した秘書〈瀧山秀一〉の死の真相を究明するよう、国務院の役人である岸から直接依頼を受ける。
瀧山は奉天会戦の元英雄〈
しかも小柳津家には〈三つの
「私も以前は閃き型の超人探偵が好きだったんですが、最近は自分が実社会で働いている影響もあるのか、月寒はそれとはかなり異なりますよね。今後の関係もあることだし、無理な捜査はやめとこうみたいな(笑い)。
実は今年出た初長編『雨と短銃』を書く前に、国内外のハードボイルドを一通り猛勉強したんです。なかでも影響を受けたのがロス・マクドナルドのリュウ・アーチャー物で、別名観察者とも言われるくらい、足を使って人に話を聞き、少しずつ真相に近づく名探偵も面白いなあって。
そのロス・マク熱が未だ冷めなくて、天才肌というよりは相手に寄り添い、大小様々な事情を聞き出す、聞き上手で人間臭い月寒を書こうと。そうした造形が満洲の功罪から人々の日常まで、多面的に書き込める効果を生んだ気もします」
そもそも自分は昭和も知らない
晩餐会には義稙の義弟で哈爾浜高等工業学校教授の〈
そして毒は料理ではなく、食後に供された〈
ちなみに岸や椎名以外はほぼ架空の人物だが、背後に漂う空気感は全て本物。
「例えば岸や関東軍が阿片の利権に関与していたのはほぼ事実らしいんですが、本人は当然否定しますよね。義稙のような元長州軍閥の英雄が絡んだ証拠もありません。でも何があってもおかしくないのが、盧溝橋事件から1年が経ち、事態が泥沼化しつつあった、当時の満洲だと思う。
『3つの太阳』というのも大陸進出後、満鉄の敷設も担った鹿島建設の作業員が、上からの日差しと下からの照り返しに灼かれ、熱中症に苦しんだと、記述が残っているんですね。そんなふうに、あ、これは使えると思ったトピックを積み重ねた中に謎を構成し、あと、私は哈爾浜どころか日本から一歩も出たことがないので、当時の街路図を国会図書館で手に入れたり、小柳津邸に関しては三宮の異人館を見に行ったりして、何とかそれらしい街並みや間取りを再現しました」
そもそも昭和も知らない自分が、満洲というただでさえセンシティブな問題をエンタメにしていいのかという葛藤は、執筆中、常にあったという。
「この頃の満洲はギリギリまだ平和でしたけど、書く以上は調べうる限りを調べ、相応の知識や覚悟が要る。そこまでさせる磁場や魅力が満洲にはありましたし、いずれは戦争やその痛みを書くことにも挑めるよう、確固たる実力や実績を積み上げることが、今の私の目標なんです」
あくまで作話的興味から歴史を知り、知見を深める、彼なりの関わり方を誰が否定できよう。表題が示す通り幻と現のあわいをゆき、〈
●構成/橋本紀子
●撮影/朝岡吾郎
(週刊ポスト 2021年10.1号より)
初出:P+D MAGAZINE(2021/09/28)